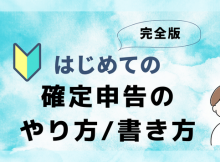控除とは?節税に活かせる方法は?所得控除と税額控除の違いなどわかりやすく解説!
控除の種類や申告方法、節税の仕方をご紹介

控除は、税額計算と節税を考える上で大切な仕組みです。税金を計算する際に課税所得や税額から一定の金額を差し引くと、納税する金額を抑えられます。
控除は、年末調整や確定申告などで自己申告しないと受けられないため、仕組みをしっかり理解して、申告したいものです。
適切に控除を受け、節税につなげて手取り収入を増やしましょう。
創業手帳では、「税金チェックシート」を配布しております。手元に残るお金が変わってくる税金の支払いや経費のコツなどを分かりやすく解説しています。無料ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
控除とは?意味や目的について

控除とは、税の計算を行う際に登場する考え方で、節税に生かせる仕組みです。控除を利用すれば、納付する税金の額を抑えられます。
控除の基本的な仕組みを理解できると、税額が決まる流れやルールも分かり、税額計算もしやすくなりそうです。
控除とはどんなものか、その概念や目的について解説します。
控除の意味
控除とは、「一定の金額を差し引く」という意味の言葉です。
税金について使われる場合には、課税対象となる所得金額や納付すべき税金の額から一定の金額を引く制度を示します。
具体的には、年末調整や確定申告で所得税を計算する際に使いますが、その書類をもとに計算される住民税にも関係するものです。
所得税や住民税などの税金の計算では、収入から必要経費を引いた「所得」と呼ばれる金額がもとになります。
その金額が低ければ低いほど納税額も低くなり、高ければ高いほど納税額も高くなります。しかし、自分勝手な判断では必要経費を差し引かれません。
そこで、必要経費として認められる出費の種類を限定し、一定の金額を引いて良い制度を作りました。それが控除です。
所得から差し引いても良いものを「所得控除」、さらに、税額から直接差し引いても良いものを「税額控除」として認められています。
現金が手元に戻ってくるわけではない
控除は納税額を抑えられる制度ですが、たまに「控除で現金(税金)が戻ってくる」と表現する人がいます。
確かに、所得税の年末調整などでは、控除を受けたことで還付金が得られる場合もありますが、厳密には控除は「税金が戻ってくる」ことを示しているわけではありません。
還付金が戻ってきたのは結果であり、そもそも還付金は、自分の給料から天引きされていた税額の一部です。
控除を受けると課税される所得や納めるべき納税額は減りますが、それによって現金が手元に入るとは限りません。
控除の目的
控除の目的は、納税者の事情を考慮して税金の負担を調整することにあります。
生活や労働のために使う(であろう)金額を、個々の事情に合わせて差し引いて負担を軽減するのが控除の役割です。
同じ金額を稼いだ人同士でも、個々の生活の仕方や家族構成によって経済事情は異なります。
独身の人と配偶者や子どもを持った既婚者では、後者のほうが必要経費は多くなると想像できます。
そのため、2人とも同じ金額の税金を徴収されたら、後者の生活への負担は大きくなるでしょう。
そこで、一人ひとりの事情に応じて配偶者控除や扶養控除といった控除を行い、負担を抑えます。
控除で生活が大変な人の税金を抑えて、個々の事情ベースで公平に税負担を課すことができます。
控除の種類は所得控除と税額控除の2種類

控除には、所得控除と税額控除の2種類があり、この2つを使い分けるとより高い節税効果が望めます。
それぞれの控除の項目について意味や目的、どんな時に使えるかを理解しましょう。
所得控除とは
所得控除は、税額を計算するベースとなる所得から差し引ける控除です。項目は多く、全部で14種類もありますが、全部の項目に当てはまることはありません。
それぞれ、自分が適用となる項目の控除だけを選んで控除を受けます。
サラリーマンの給与所得は年末調整で控除を受けられますが、所得控除の中には別途確定申告が必要となるものもあります。
控除は自己申告制なので、申告をしないと控除は受けられません。
税額控除とは
所得控除とは違って、課税所得を元に算出した所得税から直接控除できるのが税額控除です。
税額控除はその金額がそのまま差し引かれるため、所得控除よりも節税効果が大きいと言われています。
【一覧表】所得控除の種類
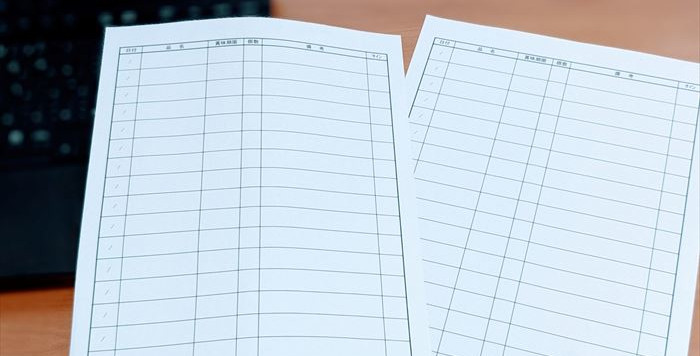
所得控除は、全部で15種類あります。税金がかかる所得金額を小さくするための控除で、所得から控除額を差し引けるのが特徴です。
それぞれの所得控除の対象者と控除額について、詳しく見ていきましょう。
人的控除と物的控除がある
所得控除は、人的控除と物的控除の2種類に分けられます。
人的控除とは、人に対する控除のことです。人とは、納税者本人やその家族を示します。人的控除には、以下の8種類があります。
| 基礎控除 | すべての人が対象。 |
| 配偶者控除 | 生計を一にする配偶者の所得が48万円以下。かつ納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下。 |
| 配偶者特別控除 | 生計を一にする配偶者の所得が48万円~133万円以下。かつ納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下。 |
| 扶養控除 | 生計を一にする16歳以上の親族の所得が48万円以下。 |
| 障害者控除 | 障害者の納税者本人・生計を一にする障害者の配偶者・障害者の親族。 |
| 寡婦控除 | 合計所得金額500万円以下の納税者が配偶者と死別または離婚。 |
| ひとり親控除 | 合計所得金額500万円以下の納税者が、生計を一にする子どもがいるひとり親。 |
| 勤労学生控除 | 合計所得金額75万円以下の勤労学生。 |
物的控除とは、社会政策的な配慮から設けられている控除のことです。以下の7種類があります。
| 雑損控除 | 災害、盗難などの損失。 |
| 医療費控除 | 1年間の医療費が10万円以上の場合。 |
| 寄附金控除 | ふるさと納税などの寄附金。 |
| 社会保険料控除 | 納税者の社会保険料、同一生計の親族の社会保険料。 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 確定拠出年金、小規模企業共済などの掛け金。 |
| 生命保険料控除 | 生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料。 |
| 地震保険料控除 | 地震保険の保険料。 |
基礎控除
基礎控除とは、所得が2,500万円以下の人すべてに適用となる控除です。
以前は誰でも無条件に受けられる控除でしたが、2020年から所得要件が加えられました。金額も、一律で控除されていたところ、所得金額に応じて段階的に金額が定められています。基礎控除の金額は以下の通りです。
| 合計所得金額 | 控除額 |
| 2,400万円以下 | 48万円(住民税43万円) |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円(住民税29万円) |
| 2,450万円超 2,500万円以 | 16万円(住民税15万円) |
合計所得金額とは、事業所得や給与所得、雑所得などを合計した金額です。
配偶者控除
合計所得が48万円以下の配偶者がいる人が対象です。
ただし、2018年から納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されないことになりました。
控除額は本人の合計所得金額によって違いますが、配偶者が69歳以下の場合、最高で38万円、70歳以上の場合、最高で48万円となります。
配偶者特別控除
配偶者の年間合計所得金額が給与所得控除後48万円超133万円以下の場合、給与収入103万円超約201万円以下の場合、対象となります。
配偶者控除と同じく、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されません。
扶養控除
合計所得金額が48万円以下の子どもや両親、兄弟姉妹などが控除対象扶養親族の場合、適用されます。生計を一にしている家族で、16歳以上が対象です。
| 年齢 | 控除額 |
| 16歳以上18歳以下 | 38万円 |
| 19歳以上22歳以下 | 63万円 |
| 23歳以上69歳以下 | 38万円 |
| 70歳以上 | 48万円 |
| 70歳以上 | 58万円 |
雑損控除
災害、盗難、横領などによる被害にあった時に受けられる控除です。通常の生活に必要な財産が対象となります。恐喝や詐欺などは対象となりません。
また、ぜいたく品や事業用の資産も対象外です。下記の計算後、高い方が控除額となります。
- 雑損控除額の算出方法
-
- (損害額+災害関連の支出額-損害により受け取った保険金額)-総所得金額の10%
- (災害関連の支出のうち、盗難・横領被害の原状回復を除く費用-損害により受け取った保険金額)-5万円
※上記は災害を想定して記載していますが、盗難・横領などの場合も同様です
医療費控除
1年間に10万円を超える医療費を払った人が受けられる控除です。生計を一にする配偶者や親族の医療費は対象となりますが、健康診断や美容整形、栄養ドリンクなどの費用は対象となりません。
- 医療費控除額の算出方法
-
- 総所得が200万円以上:1年間の医療費の合計-10万円
- 総所得が200万円以下:1年間の医療費の合計-総所得の5%
1年間とは、申告する年の1月1日~12月31日を意味します。
控除額の計算のベースは、医療費全額から保険金などで補填される金額を引いたもので、そこから10万円を引いたもの、もしくは総所得金額の5%のうち多いほうが控除されます。なお、控除額の上限は200万円です。
なお、2026年12月31日までは「セルフメディケーション税制」も利用できます。こちらは健康診断や予防接種など健康促進の取り組みを一定程度行っている人およびその家族が、薬局で特定一般用医薬品等(指定の風邪薬など)を購入した費用が一定の条件で所得控除となる制度です。
年間12,000円以上該当する医薬品を購入した人が対象で、控除額は以下の様に計算します。
- セルフメディケーション税制の算出方法
-
- 1年間の特定一般用医薬品等購入額-12,000円
※上限88,000円
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択制なので、どちらか控除額が大きくなる方で申告しましょう。
寄附金控除
寄付金控除は、国や公益法人などに特定の寄附金を払った人のための控除です。ふるさと納税などもこれに含まれます。
寄付金控除は、「特定寄附金の額-2,000円」もしくは「総所得金額等×40%-2,000円」の多いほうが控除額となります。
寄付金控除は、税額控除にも寄附金特別控除があります。
寄付金特別控除に当たるのは、政党や政治資金団体、認定NPO法人、公益社団法人などに対する寄付金の控除です。これらの寄付をした場合には、どちらかを選べます。
社会保険料控除
社会保険料を支払った金額が、全額所得から控除されます。次の通り、該当する保険料は多岐にわたります。
-
- 国民年金保険料
- 厚生年金保険料
- 健康保険料(健康保険税)
- 後期高齢者医療制度の保険料
- 船員保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 国民年金基金の掛金
- 農業者年金保険料
- 厚生年金基金の掛金
- 労働者災害補償保険の特別加入者が支払う保険料
生計を一にする配偶者や扶養親族の保険料を支払っている場合も控除が可能です。控除できる項目が多いので、支払った社会保険料を正確に把握し、控除忘れが出ないように注意しましょう。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金や確定拠出年金などを支払っている人が受けられる控除です。次の掛金が控除されます。
-
- 自営業者向けの小規模企業共済
- 企業型確定拠出年金
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
- 心身障害者扶養共済
小規模企業共済は個人事業主の退職金制度のようなもので、サラリーマンには関係ありません。一方で、個人型確定拠出年金(iDeCo)はサラリーマンの加入者も多い制度です。加入している方は忘れずに所得控除を受けてください。
なお、控除金額は1年間に払った全額ですが、控除対象は加入者の掛金のみで扶養者などの掛金は控除できません。
生命保険料控除
生命保険・個人年金・介護医療の保険料を支払っている人が受けられる控除です。
控除額の最高は生命保険が「新契約」が含まれる場合は、各項目4万円ずつの12万円です。旧契約のみの場合は生命保険・個人年金は各項目5万円まで控除できますが、3項目の控除総額の最高額は同様に12万円となります。
新契約(2012年1月1日以降の契約)の生命保険料・個人年金保険料控除
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| 2万円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万円超~4万円以下 | 支払保険料等×1/2+1万円 |
| 4万円超~8万円以下 | 支払保険料等×1/4+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
旧契約(2012年1月1日より前の契約)の生命保険料・個人年金保険料控除
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| 2万5,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万5,000円超~5万円以下 | 支払保険料等×1/2+1万2,500円 |
| 5万円超~10万円以下 | 支払保険料等×1/4+2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律5万円 |
なお、新旧双方に加入している場合は、いずれか控除額の大きな方を任意で選択できます。
介護保険料控除
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| 2万円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万円超~4万円以下 | 支払保険料等×1/2+1万円 |
| 4万円超~8万円以下 | 支払保険料等×1/4+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
また、個人年金保険料については、保険料の払込期間および年金受取期間が10年以上(もしくは終身)の契約が対象です。生命保険料控除は、支払い人が本人であれば家族名義でも申告できます。ただし、受取人が本人・配偶者・親族でなければなりません。
地震保険料控除
地震保険などの損害保険料を払っている人が受けられる控除です。次に該当する住宅・家財の地震保険契約が控除の対象となります。
-
- 所得税の確定申告/年末調整をする本人が所有・居住している自宅
- 生計を一にする親族が所有・居住家
- 本人/生計を一にする親族が保有する家財
地震保険には「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の2種類があり、どちらに該当するかによって計算式が異なります。なお、旧長期損害保険は2006年12月31日以前に契約して、その後契約変更がない保険が対象です。
控除額は以下の要領で計算します。
- 地震保険料:
-
- 年間に支払った保険料の全額(上限5万円)
- 旧長期損害保険料:
-
- 年間の保険料額が1万円以下の場合:全額
- 年間の保険料額が1万円超2万円以下:支払った金額×1/2+5,000円
- 年間の保険料額が2万円超:一律15,000円
二つの控除は併用できないため、二つの保険に加入している場合は控除額が多い方で申請しましょう。
寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除
配偶者と死別した人、死別や離婚をして扶養親族のいる人、未婚で子どもがいる人が対象となる控除です。
ひとり親の控除は35万円、それ以外の寡婦(寡夫)は27万円となっています。
子どものある単身者、子以外の扶養親族を持つ寡婦には合計所得金額500万年以下の所得制限があります。
障害者控除
納税者本人や控除対象配偶者、扶養家族が障害者の場合に受けられる控除です。
控除額は、ひとりにつき27万円、特別障害者はひとりにつき40万円、同居特別障害者はひとりにつき75万円となっています。
勤労学生控除
納税者が勤労学生の場合に適用となります。
条件は、アルバイトなどの勤労の所得で、合計所得金金額が75万円以下、さらに不動産所得など給与所得以外の所得が10万円以下です。控除額は一律27万円となります。
【一覧表】税額控除の種類

税額控除は、7種類があります。納めるべき税額から控除額を差し引けるのが特徴です。それぞれの控除対象者や、控除額について詳しく見ていきましょう。
住宅ローン控除
住宅ローンを組んでマイホームを新築、購入した人、家の増改築をした人が受けられる控除です。住宅ローンの残高をもとに控除額を計算します。
住宅ローン控除を受けるための条件は以下の通りです。
-
- 合計所得金額が3,000万円以下
- ローン返済期間が10年以上
- 住宅取得後6カ月以内に住む
- 住宅の床面積が50㎡以上
- 中古住宅の場合は建築後20年以内、中古マンションの場合は建築後25年以内の物件(一定の新耐震基準等の適用あり)
- 増改築の場合は100万円を超える費用がかかっている
- 店舗とは住宅の併用物件の場合、床面積の半分以上が居住用に使われている
会社に勤めるサラリーマンも、最初の年は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整で控除できます。
住宅特定改修特別税額控除
個人所有の居住用家屋で、一定の要件を満たす一般省エネ改修工事をした場合に適用となる控除です。
住宅特定改修特別税額控除を受けるための要件は、以下の通りです。
-
- 平成26年4月1日~令和5年12月31日までに居住
- 一般省エネ改修工事の日から6カ月以内に居住
- 一年の合計所得金額が3,000万円以下
- 床面積50平方メートル以上、かつ床面積の2分の1以上を居住
- 2以上の住宅を所有する場合は、主の居住であること
- 一般省エネ改修工事が50万円を超える
- 工事費用の2分の1以上の額が自己居住部分の費用である
なお、一般改修工事には、居室の断熱工事の他、一体となって効用を果たす太陽熱利用冷温熱装置、太陽光発電装置などの取り換えや取り付け工事も含まれます。
控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額までです。
住宅耐震改修特別控除
個人所有の居住用家屋で、住宅耐震改修をした場合に適用となる控除です。
住宅耐震改修特別控除を受けるための要件は、以下の通りです。
-
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
- 平成26年4月1日~令和5年12月31日までに居住
- 2以上の住宅を所有する場合は、主の居住であること
- 耐震改修した家屋は、現行の耐震基準に適合していること
控除額は、住宅耐震工事の標準的な費用の額までです。
配当控除
配当所得のある人のための控除です。法人から受ける利益の配当、基金利息、証券投資信託の利益の分配が対象となります。
控除金額は課税総所得1,000万円以下の場合で、配当所得×10%(一定のものは5%)です。
外国税額控除
国際的な二重課税を防止するための控除で、外国所得税などがある人が対象となります。
その年の外国所得税、もしくは、その年の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)の多いほうが控除金額です。
源泉徴収税額
源泉徴収税額は、給与から天引きして、会社が支払った税金です。すでに払っているものなので、控除できます。
災害減免額
自然災害や火災で住宅や家財に損害を受けた人のための控除です。損害金額が時価の2分の1以上の場合に対象となります。
ただし、災害にあった年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には対象となりません。その際には、所得控除の雑損控除が利用できます。
控除を受けるための申告方法とは

サラリーマンや個人事業主が控除を受けるためには、主に年末調整や確定申告の際に申告を行います。
タイミングを逃してしまうと、控除が受けられなくなったり、二度手間になったりするため、慎重に準備を進めましょう。
特に、個人事業主は全ての手続きを自分で行う必要があるので、抜けのないように控除の手続きをしましょう。
サラリーマンの場合には、個人事業主のように自分で収入と控除の計算をしたり、税務署に書類を持って行ったりしなくても良い人が多いです。ほとんどの控除を年末調整で行い、一部の控除のみ自分で確定申告することが必要になります。
所得税の控除の手続きを行うと、翌年の住民税にも反映されます。
所得控除と税額控除の流れ
控除の流れは、2段階になっています。はじめに所得控除を引かれた後、税率がかけられて納税額が決まり、さらにそこから税額控除が引かれる流れです。
所得控除は、課税される所得から控除されるもので、税率控除は税金から直接控除されます。同じ控除でも差し引くタイミングが異なるため、最終的な節税効果が違います。
所得10万円で1万円分の控除ができた場合でも、所得控除では9万円×税率(5%)=4500円を差し引けますが、税額控除では丸々1万円を引くことが可能です。
※税率は課税所得によって異なります。
基本的に自己申告が必要
基本的には所得控除も税額控除も自己申告が必要です。
ただし、サラリーマンの場合には、個人事業主のように自分で収入と控除の計算をしたり、税務署に書類を持って行ったりしなくても良い人が多くなります。
サラリーマンの場合には、ほとんどの控除は年末調整で行い、一部の控除のみ自分で確定申告することが必要です。
サラリーマンは、年末調整で申告
サラリーマンの控除は、多くが年末調整で行えます。年末調整は、会社が控除の手続きを代行してくれるため、自分で行うのは簡単な書類記入と提出だけです。
年末調整の書類とともに控除証明書などを提出すると、会社が税計算をして、還付金などの対応をしてくれます。
ただし、控除しても天引きされた所得税が余らなければ、還付金はないので注意してください。
個人事業主や一部のサラリーマンは、確定申告で申告
個人事業主だけでなく、サラリーマンも一部の控除を受けるためには確定申告が必要となる場合があります。
サラリーマンで確定申告が必要な所得控除は、主に雑損控除・医療費控除・寄附金控除などです。
また、税額控除では寄附金特別控除・外国税額控除・配当控除が確定申告をしないと受けられません。住宅ローン控除の開始の年も、確定申告が必要です。
控除に必要な書類
所得控除と税額控除、年末調整と確定申告、それぞれのために必要な書類は違います。確定申告に使う書類を年末調整に提出しないように注意しましょう。
- 年末調整で必要な書類
-
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書
- 年末調整に使う主な証明書類
-
- 保険会社などが発行する支払額などの証明書
- 住宅取得資金などに係る借入金の年末残高等証明書(2年目以降)
- 個人事業主の確定申告で必要な書類
-
- 確定申告書B
- 青色申告決算書
- 個人事業主の確定申告に使う主な証明書類
-
- 保険会社などが発行する支払額などの証明書
- 住宅取得資金などに係る借入金の年末残高等証明書(2年目以降)
- 所得控除の確定申告に使う主な証明書類
-
- 災害関連支出の金額の領収を証する書
- 医療費・薬代等の領収書
- 寄附した団体などから交付を受けた領収書など
- 税額控除の確定申告に使う主な証明書類
-
- 配当金支払計算書
- 外国所得税を課されたことを証する書類
- 寄附金(税額)控除のための書類
- 住宅取得資金等に係る借入金の年末残高等証明書(初年)
ワンストップ特例制度で控除とは
ふるさと納税のワンストップ特例制度を使う場合には、控除の方法が少し異なります。
ワンストップ特例では、所得税が還付されるのではなく、翌年の住民税が減額される形で控除されます。
まとめ・控除を上手に活用して節税につなげよう
控除は所得税などを節税する際に使える便利な制度です。控除の目的も税徴収の公平性にあるため、可能な控除は全て活用し、節税しましょう。
手続きの方法は、控除の種類やその人の状況によって異なるため、注意してください。また、控除のためには必要書類を整えることも必要となります。
毎年の年末調整や確定申告では忘れずに控除を活用し、納税額を抑えましょう。
創業手帳では、税金で損をしないために「税金チェックシート」を作成しました。税金の支払いだけでなく、経費の使い方、税金をできるかぎり安くする方法など、わかりやすく解説しています。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。