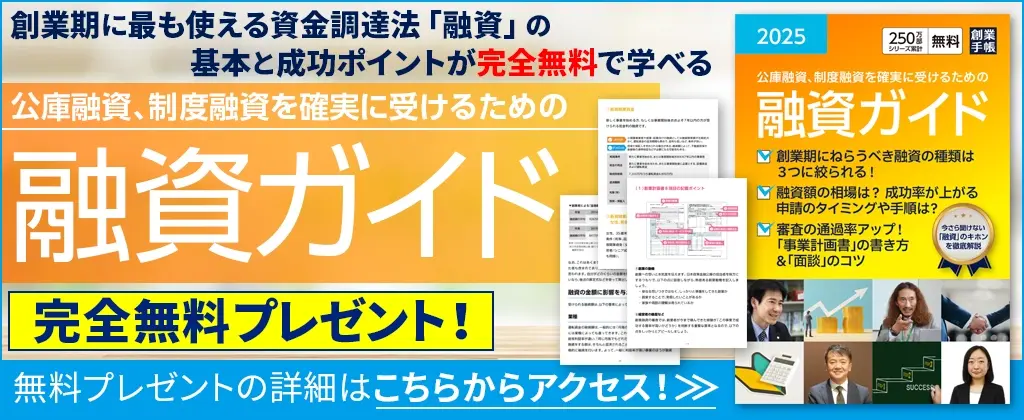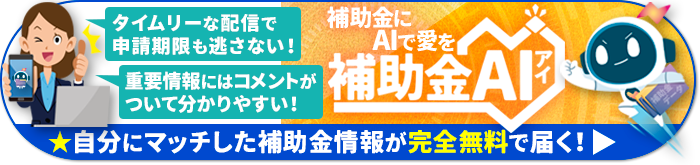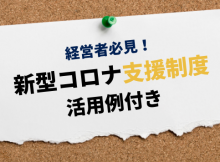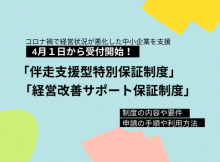早期経営改善計画策定支援とは?補助対象や補助額を解説
早期経営改善計画策定支援を活用すれば中小企業支援の専門家と相談しながら経済的援助を受けられる

早期経営改善計画策定支援を活用すれば、税理士や公認会計士をはじめとした専門家から社会情勢の変化に対応するためのアドバイスを受けられます。また、専門家との相談費用や具体的な計画を策定する際の必要経費に対して、一定の補助金を受給できるメリットもあります。
新型コロナウイルスは一段落したものの、原材料価格の高騰や円安などの経済状況・環境の変化に十分対応できていない中小事業主の方もいるのではないでしょうか。
漠然とした課題や問題を抱えつつも、どのように着手すべきか悩んでいる事業主の方にとって、早期経営改善計画策定支援は利用を検討すべき制度です。
こちらの記事では、中小企業支援の専門家と相談しながら経済的援助を受けられる早期経営改善計画策定支援の具体的な内容を解説します。利用を検討すべき事業主の特徴も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
創業手帳では、融資を検討中の方へ、融資の基本をまとめた「融資ガイド」を無料配布しています。融資の成功率をあげるために、ぜひご利用ださい。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
早期経営改善計画策定支援の概要

早期経営改善計画策定支援とは、資金繰りの安定や収益力の改善を目指す中小企業事業主と専門家の取り組みを支援する制度です。
中小事業主が、国から認定を受けた税理士や公認会計士などの専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けたとき、費用(専門家に対して支払う費用やモニタリング費用)の2/3が補助されます。なお、認定経営革新等支援機関は中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム」から行えます。
経済的補助を受けながら外部専門家による経営に関する質の高いアドバイスをもらえる点は、早期経営改善計画策定支援を利用するメリットです。
日本国内にある企業の99%は中小企業と言われており、中小企業は日本経済を支える存在です。経済状況・環境の変化に対応できず事業を閉鎖してしまうのは、雇用が失われるだけでなく取引先にも悪影響を及ぼすなど、経済全体に悪影響を及ぼしてしまいます。
そこで、政府としても中小企業の財政基盤の強化や収益力の向上を目指す仕組みを作り、経営をサポートしているのです。
早期経営改善計画策定支援で受けられる支援

早期経営改善計画策定支援で受けられる、具体的な支援内容は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| ビジネスモデル俯瞰図の策定 | 事実を俯瞰して収益の仕組みや商流などを見える化する |
| 経営課題の内容と解決に向けた基本方針の立案 | 現状分析を踏まえた経営課題と解決策を検討 |
| アクションプランの策定 | 見える化された課題を行動計画に落とし込む |
| 損益計画の立案 | アクションプランの改善計画を数値化して計画を策定 |
| 資金繰表(実績・計画)の策定 | 過去の資金繰り実績を分析、将来の資金計画を策定 |
上記のように、専門家と共に経営課題を発見・分析すれば、自社の状況や構造的な問題を客観的に把握できます。また、資金繰表(実績・計画)の策定を通じて事業主自身が財務状況を把握でき、事業の現況や将来に向けた課題を金融機関が把握しやすくなるでしょう。
上記の計画を専門家と共に策定したあとは、実際に経営改善に取り組みます。計画に取り組むときも、専門家が伴走支援してくれるため安心です。
伴走支援では、策定した計画の進捗状況の確認や、計画と実績の乖離が生じたときにおける対応策の検討をサポートしてくれます。計画を実行する中で「スムーズにいかない」「進捗が思わしくない」という事態に陥っても、専門家に相談できる点は早期経営改善計画策定支援の魅力です。
早期経営改善計画策定支援の補助対象と補助額
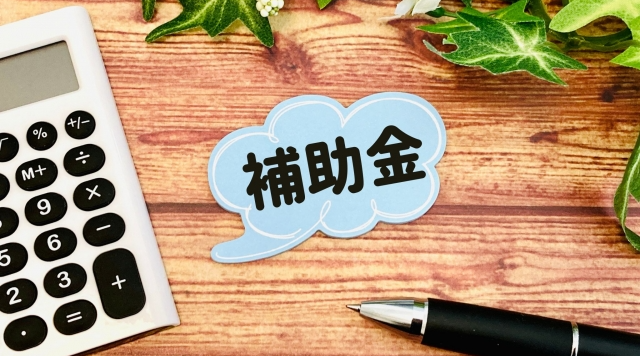
早期経営改善計画策定支援の補助対象と補助額は、以下のとおりです。
| 補助対象経費 | 補助率 |
| 計画策定支援費用 | 2/3(上限15万円) |
| 伴走支援費用(事業者の希望に応じて実施) | 2/3(上限5万円) |
| 伴走支援費用(決算期) | 2/3(上限5万円) |
※金融機関交渉に係る費用は10万円を上限として加算できる
サポートをした専門家に対して支払う費用の内、2/3(上限25万円)の補助を受けられます。経済的な補助を受けながら専門家から経営に関するアドバイスを受けられるため、経営に関する悩みや不安をお持ちの方は有効活用しましょう。
早期経営改善計画策定支援を受けるのがおすすめの中小事業主

早期経営改善計画策定支援の概要やコンセプトを踏まえて、支援を受けるのがおすすめの中小事業主の特徴を解説します。
自社の状況を客観的に知りたい事業主
自社の状況を客観的に知りたい事業主にとって、早期経営改善計画策定支援は活用すべき制度です。
認定経営革新等支援機関の専門家は、財務や組織管理に関する専門的な知識を有しています。さまざまな角度から自社の状況を分析し、事業主自身では気付きにくい課題や改善点を明らかにしてくれるでしょう。
ビジネスモデル俯瞰図の作成を通じて、事業主は自社のビジネスモデルを見える化でき、強みと弱みを理解できます。どのように事業展開をするか、どのような問題に向き合うべきか把握するうえで、有意義な相談となるはずです。
事業の継続性に不安を感じている事業主
事業の継続性に不安を感じている事業主は、早期経営改善計画策定支援を利用する意義が大きいでしょう。
資金繰りや財務状況に不安があると、安心して事業を継続できません。しかし、税理士や公認会計士をはじめとした財務会計の専門家から、自社の経営状況に応じたアドバイスを受ければ改善すべき課題を把握できます。
効果的な経営改善策を立てつつ、資金繰り計画を立てることで資金繰りの管理を適切に行えます。事業投資に振り向ける資金を把握し、資金を効率的に活用することも、将来的に事業を継続するうえで欠かせません。
資金繰りの管理方法をアドバイスしてほしい事業主
早期経営改善計画策定支援は、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの経営改善に取り組む事業主を支援する制度です。資金繰りの管理方法について、専門家からアドバイスしてほしいと考えている事業主は、早期経営改善計画策定支援を活用しましょう。
税理士や公認会計士は、財務管理や税務に関する専門的な知識と豊富な経験を持っています。相談者の状況を踏まえて的確なアドバイスを提供し、最適な資金繰りの方法を考えてくれるでしょう。
事業主が資金繰りを考えるうえでは、現在の財務状況だけでなく借入金の返済や将来の資金需要を予測する必要があります。現状分析に加えて、売掛金の管理や在庫管理なども考えなければなりません。
資金繰りの管理方法について多角的にアドバイスを受けたいときは、早期経営改善計画策定支援を活用して税理士や公認会計士からアドバイスを受けるとよいでしょう。
経営改善について専門家に伴走してほしい事業主
早期経営改善計画策定支援を利用すれば、経営改善に着手する際だけでなく、伴走しながら専門家がサポートしてくれます。定期的なモニタリングを通じて計画の進捗状況を確認してもらい、必要なアドバイスを受けられる点がメリットです。
もし計画を策定しても、当初の計画通りに実行できず終わってしまうと意味がありません。財務状況が改善せず、経営が行き詰まってしまうリスクが高まるでしょう。
早期経営改善計画策定支援を活用すれば、計画が進んでいない場合でも専門家が原因を確認し、対応策を検討してくれます。速やかに軌道修正を図れば、着実に経営改善を進められるでしょう。
内部管理体制の整備が不十分な事業主
内部管理体制の整備が不十分で、改善の必要性を感じている事業主は早期経営改善計画策定支援を利用しましょう。持続的・安定的な事業継続や事業投資を行うためには、内部管理体制や経営の透明性確保に向けたガバナンス体制の整備が欠かせません。
専門家からアドバイスを受けることで、自社の内部管理体制の問題点を把握できます。経営改善計画やアクションプランの策定を通じて、問題を改善するための具体的な方法を立てられるでしょう。
内部管理体制の整備が不十分だと、社内のコミュニケーションや意思疎通が停滞し、社会情勢の変化に脆弱となってしまう恐れがあります。専門家のノウハウを活用し、内部管理体制の整備に関するアドバイスを受けられれば、社内の意思疎通がスムーズになる期待が持てます。
早期経営改善計画策定支援を利用する際の流れ
早期経営改善計画策定支援を利用する際の流れは以下のとおりです。
- 認定支援機関(外部専門家)へ問い合わせて利用申請する
- 金融機関と相談する
- 早期経営改善計画の策定を行い提出する
- 早期経営改善計画を実行して金融機関と相談する
- 補助金の申請を行う
まずは認定支援機関へ問い合わせを行い、早期経営改善計画策定支援の利用申請を行います。早期経営改善計画策定支援事業利用申請書をはじめとした必要書類を用意し、外部専門家と連名で中小企業活性化協議会へ提出します。
書類の作成にあたっては金融機関の「事前相談書」が必要です。事前に金融機関に早期経営改善計画を策定する旨を伝え、相談を済ませておきましょう。
早期経営改善計画の提出が済んだら、外部専門家のアドバイスを仰ぎながらビジネスモデル俯瞰図やアクションプランなどの早期経営改善計画を策定します。早期経営改善計画が完成したら、外部専門家とともに金融機関に提出します。
金融機関から早期経営改善計画を提出したことを確認できる書面を受け取ったら、外部専門家と連名で中小企業活性化協議会へ提出しましょう。申請が通過したら外部専門家に通知され、中小企業活性化協議会から外部専門家に対して計画策定費用の2/3が支払われます。
さらに、早期経営改善計画の策定から1年後の最初の決算時にモニタリングを受けます。必要に応じて、事業全般や経営に関するアドバイスを受けることが可能です。
その後、外部専門家が計画の実施状況を金融機関と共有し、中小企業活性化協議会にモニタリング報告書を提出します(事業主は申請不要)。中小企業活性化協議会による審査が行われ、申請が通過したら中小企業活性化協議会から外部専門家に対してモニタリング費用の2/3が支払われます。
早期経営改善計画策定支援の必要書類

早期経営改善計画策定支援の申請にあたって、以下の必要書類を用意する必要があります。
【利用申請時】
- 早期経営改善計画策定支援事業利用申請書
- 申請者の概要(早期経営改善計画策定支援)
- 業務別見積明細書(早期経営改善計画策定支援)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
- 認定経営革新等支援機関であることを証する認定通知書等の写し
- 事業者に対する認定経営革新等支援機関の見積書及び単価表
- 金融機関(メイン行又は準メイン行)の事前相談書
- 申請者の直近3年分の申告書
【支払申請時】
- 早期経営改善計画策定支援事業費用支払申請書
- 早期経営改善計画書
- 業務別請求明細書(早期経営改善計画策定支援)
- 従事時間管理表(業務日誌)(早期経営改善計画策定支援)
- 《計画策定支援》実務指針に基づく実施確認表
- 認定経営革新等支援機関の請求書類(中小企業活性化協議会宛)
- 申請者と認定経営革新等支援機関が締結する早期経営改善計画策定支援に係る契約書の写し
- 申請者による費用負担額(1/3)の支払を示す書類の写し
- 金融機関に早期経営改善計画を提出したことが確認できる書面
スムーズに申請を進めるためにも、早い段階で準備を進めておくとよいでしょう。
まとめ
早期経営改善計画策定支援を活用すれば、専門家から資金繰りの改善や経営課題を解決するための具体的なアドバイスを受けられます。専門家へ支払う費用のうち、2/3が補助されるため、自己負担を抑えられるメリットがあります。
自社の状況を客観的に知りたい事業主や、事業の継続性に不安を感じている事業主は利用を検討してみてください。専門家からアドバイスを受ければ、抱えている悩みや不安を解消するヒントを得られるでしょう。
創業手帳別冊版「補助金ガイド」では、中小事業主に役立つ補助金や助成金に関する情報を発信しています。経営支援や資金調達に関する有益な情報も発信しているため、ぜひ参考にしてみてください。
また創業手帳では、融資をご検討中の方向けに融資の基本的な仕組みをわかりやすくまとめた「融資ガイド」も無料で配布しています。審査で通るためのコツなども解説していますので是非ご参考ください。
(編集:創業手帳編集部)