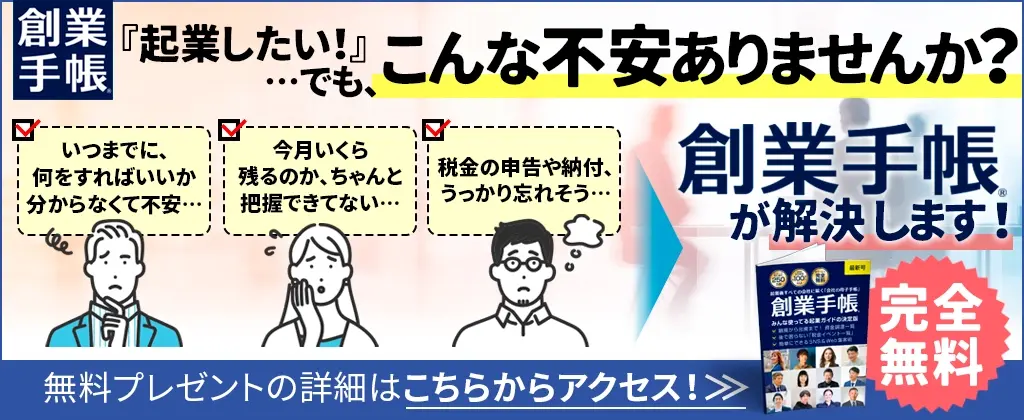シニア起業はやってはいけない?シニア起業の成功率や成功事例などをご紹介
シニア起業でやってはいけないこと、成功する人・失敗する人の違い、活用できる補助金・助成金などご紹介

定年後の新たな挑戦として注目を集める「シニア起業」。豊富な経験とネットワークを武器に事業を立ち上げるシニア世代が増えている一方で、「今さら起業なんて無謀では?」「失敗したら老後資金がなくなる」といった不安の声も少なくありません。
実際のところ、シニア起業は本当にリスクが高いのでしょうか。それとも、人生100年時代における新たな可能性を秘めているのでしょうか。本記事では、シニア企業に成功する人・失敗する人の違い、活用できる補助金・助成金などをまとめてご紹介します。
創業手帳(冊子版)は、起業に必要なノウハウを一つの冊子にまとめた「起業のためのガイドブック」です。資金調達方法から資金繰りの基礎や、税金の知識などがこの一冊でおさえられます。
また、起業のために必要な準備としてわかりやすいのが「創業カレンダー」です。起業予定日を記入すると、その予定日を起点に前後1年間のやることがカレンダー形式で把握することができます。どちらもあわせてご活用ください。
この記事の目次 日本政策金融公庫が実施した調査「2024年度新規開業実態調査」によると、開業時の年齢は「40歳代」の割合が37.4%と最も高いです。しかし、「50歳代」の割合20.8%で「30歳代」に次いで3位になっていて、シニア起業の割合は決して低くありません。 また、開業時の年齢は上昇傾向にあり、2024年度の平均年齢は43.6歳となったといいます。ということは、シニア世代の起業は増えている傾向にあるといえるのではないでしょうか。 また、アメリカの名門大学MITなどの研究者が行った調査「AGE AND HIGH-GROWTH ENTREPRENEURSHIP」によると、若いときに起業するよりも、40〜50代で起業した起業家の方が成功率が高いことがわかっています。 シニア起業の成功率は決して低くない、といえそうです。 シニア起業でやってはいけない8つのことをご説明します。 シニア起業では家族の理解と協力が不可欠です。配偶者や子どもたちの反対を押し切って始めると、家庭内の関係が悪化し、精神的な支えを失ってしまいます。特に退職後の起業では、家計への影響や将来の不安について家族も心配しています。 事前に起業の目的、事業内容、リスク、収支見通しを丁寧に説明し、家族の不安を解消することが重要です。また、万が一事業が失敗した場合の対応策も含めて話し合っておくことで、家族の理解を得やすくなります。家族の協力があれば、事務作業の手伝いや精神的な支援を受けられ、事業の成功確率も高まります。 長年のサラリーマン経験で培ったスキルや人脈を活用せず、全く新しい分野に挑戦するのは非常にリスクが高い選択です。若い世代と比べて学習能力や適応力が劣る傾向にあるため、新分野での競争は不利になりがちです。 これまでの職歴で身につけた専門知識、業界の人脈、培ったノウハウこそがシニア起業の最大の武器です。例えば、営業経験があるなら営業代行やコンサルティング、技術職なら技術指導や顧問業務など、既存のスキルを活かせる分野で起業することが成功への近道です。全く新しい分野に挑戦したい場合も、まずは副業として始めて経験を積んでから本格的に取り組むことをお勧めします。 退職金や長年の貯蓄は老後の生活資金として確保しておくべき大切な資産です。これらを事業資金として一気に投入してしまうと、事業が失敗した際に生活基盤を失ってしまいます。シニア世代は再就職が困難で、収入を回復する手段が限られているため、この失敗は致命的です。 事業資金は生活費を除いた余剰資金の範囲内で調達し、段階的に投資することが重要です。最初は小規模から始めて、事業が軌道に乗ってから徐々に投資額を増やしていく方法が安全です。また、事業用資金と生活資金は明確に分けて管理し、最低でも2-3年分の生活費は確保しておくことが必要です。 シニアになると体力や集中力の低下は避けられない現実です。若い頃と同じような長時間労働や肉体的に負担の大きい仕事を選ぶと、健康を害したり継続が困難になったりします。特に飲食店や小売業など、長時間の立ち仕事や重い物の運搬が必要な業種は慎重に検討する必要があります。 年齢に適した事業を選ぶことが重要で、これまでの経験や知識を活かせるコンサルティング、教育・指導業、軽作業での製造業などが適しています。また、体調管理にも十分注意を払い、定期的な健康診断を受けながら無理のない範囲で事業を進めることが大切です。体力的な限界を認識し、それを補う工夫や仕組みづくりも必要です。 市場や競合他社の分析を十分に行わずに参入すると、既に飽和状態の市場で苦戦することになります。特に同様のサービスを提供する競合が多い場合、価格競争に巻き込まれて収益性が悪化し、結果的に事業継続が困難になります。 事前に徹底的な市場調査を行い、競合他社の強み・弱み、価格設定、サービス内容を分析することが不可欠です。その上で自社の差別化ポイントを明確にし、競合にはない独自の価値を提供できる事業モデルを構築する必要があります。また、定期的に市場動向をチェックし、変化に応じて戦略を調整していく柔軟性も重要です。 現代のビジネスにおいて、インターネットやデジタル技術の活用は必須となっています。シニア世代の中にはITに苦手意識を持つ方も多いですが、オンラインでの情報発信や顧客とのコミュニケーションを怠ると、競合他社に大きく遅れを取ってしまいます。 ホームページやSNSでの情報発信、オンライン広告の活用、電子決済の導入など、基本的なIT活用は避けて通れません。自分でできない場合は、家族や専門家に協力を求めたり、外部業者に委託したりする方法もあります。また、ITスキル向上のための研修を受講することで、事業の幅を広げることができます。 起業当初から大きな成功を目指して急激な事業拡大を図ると、人員管理、資金管理、品質管理などが追いつかずに経営破綻を招く危険性があります。シニア起業では「スモールスタート」が基本原則です。 最初は一人または少数精鋭で始め、事業が安定してから段階的に規模を拡大していく方法が安全です。無理な成長を追求せず、持続可能な事業運営を心がけることが重要です。また、事業規模に応じた適切な管理体制を整備し、自分の管理能力を超えない範囲での運営を維持することが成功の鍵となります。 事業開始直後から安定した収入を得られることは稀です。多くの場合、売上が軌道に乗るまでには半年から数年の時間がかかります。この期間の生活費や事業運営費を十分に見込んでいないと、キャッシュ不足に陥って事業継続が困難になります。 詳細な収支計画を作成し、最悪のシナリオも含めて資金計画を立てることが必要です。売上の見込みは控えめに、支出は多めに見積もることが安全です。また、予備資金として計画額の1.5倍程度の資金を準備しておくことをお勧めします。定期的に収支実績と計画を比較し、必要に応じて計画を見直すことも重要です。 シニア起業で成功する人と失敗する人の特徴をまとめました。それぞれの対比を理解して、自らの起業に落とし込んでみてください。 シニア年代の方が起業するのに向いているおすすめの業種をご紹介します。シニアならではの視点や経験を活かせる業種はたくさんありますので、ぜひ参考にしてみてください。 シニア起業の成功事例をご紹介します。 ブルーベリーファームおかざきを経営する畔柳氏は、従来の農業の課題を逆転の発想で解決しました。ブルーベリー栽培の最大のデメリットである「収穫の手間」を、お客様による「ブルーベリー狩り体験」として提供する観光農園を展開しています。 この業態により、農園側は収穫に関わる人件費を削減でき、お客様は高価なブルーベリーを安価で楽しみながら収穫できるという双方にメリットのあるビジネスモデルを確立しました。主な客層は女性や家族連れで、地域の気軽なレジャーとして好評を得ています。 同農園は夏場の60日間のみの営業で年収2,000万円を達成しています。営業期間が限定されているため、空き時間を活用してオンラインセミナーでのノウハウ提供、カフェ経営、ジャムなどの加工品販売も展開しています。オンラインセミナーには台湾やタイからも引き合いがあり、今後はハーブ農園への挑戦も計画しています。 畔柳氏は自動車部品メーカー・デンソーで年収1,000万円のサラリーマンでしたが、対人関係のストレスと将来への不安から起業を決意しました。現在は「起業して大正解だった」と振り返っています。 起業後は対人関係のストレスがほぼ解消され、収入が大幅に増加し、定年がない安心感を得られました。また、顧客に直接価値を提供する実感がやりがいとモチベーションにつながっています。 今では著名なネット生命保険となっているライフネット生命保険株式会社も、シニア起業が始まりでした。 創業者の出口治明氏は、30年以上にわたって日本生命で勤務し、ロンドン事務所長や国際業務部長などの要職を歴任していました。しかし、グローバル展開に関する会社との方向性の違いから、系列のビル管理会社への出向を命じられました。一般的には左遷と呼ばれる人事異動でした。 出口氏は、この逆境を挫折とは捉えませんでした。出口氏が勤めていた会社では、子会社に出向になって本社に戻ってきた人は過去一人もいませんでした。55歳という年齢もあり、30年以上携わってきた生命保険業界から身を引く潮時だと考え、”遺書”として『生命保険入門』を執筆しました。 その後、東京大学の総長室アドバイザーを務めている際に、「保険会社を作ってみないか」という提案を受けました。出口氏はその場で思わず「はい」と答え、これが起業のきっかけとなりました。 若い世代が経済的に厳しい状況にある日本で、新しく生保を起業する意味は「保険料を半分にして安心して赤ちゃんを産める社会を創りたい」という一点に集約されていました。『生命保険入門』で展開した持論である「保険料を下げるには営業費を下げるしかなく、そのためにはネットの活用が有効である」という考えが事業の基盤となりました。 ライフネット生命の成長の要因は、優秀な社員に恵まれたことに尽きると出口氏は語っています。 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」は、特定の属性を持つ起業家を対象とした優遇融資制度です。 この制度を利用できるのは、新しく事業を始める方または事業開始から7年以内の事業者で、女性の方か、35歳未満または55歳以上の方が対象となります。35歳から54歳までの男性は対象外です。 融資限度額は7,200万円で、そのうち運転資金は4,800万円までです。資金の使途は設備購入や店舗改装などの設備資金と、仕入れや人件費などの運転資金に分かれます。 返済期間は設備資金が20年以内、運転資金が10年以内となっています。どちらも最長5年間の据置期間を設けることができ、この期間中は利息のみの支払いで元本返済が猶予されます。これにより事業が軌道に乗るまでの資金繰りに配慮されています。 担保や保証人については個別相談が可能で、柔軟な対応が期待できます。また、経営者保証免除特例制度や各種金利優遇制度との併用により、さらに有利な条件での融資を受けることも可能です。 ものづくり補助金は、正式には「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と呼ばれる制度で、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を支援することを目的としています。 この補助金制度は、企業が直面する様々な制度変更への対応を支援するために設けられています。対象となる制度変更には、働き方改革の実施、被保険者の適用拡大、賃上げの実施、インボイス制度の導入などが含まれます。これらの制度変更により、中小企業は新たな対応コストや業務負担が発生するため、それに対応するための生産性向上が急務となっています。 補助の対象となるのは、生産性向上に資する革新的な取り組みです。具体的には、新しいサービスの開発、革新的な試作品の開発、既存の生産プロセスを改善するための設備投資などが支援されます。これらの投資により、企業は制度変更に伴う負担を軽減しながら、同時に競争力の強化を図ることができます。 この制度は、単なる設備購入への助成ではなく、企業の持続的な成長と競争力向上を目指した戦略的な投資を後押しすることで、日本の中小企業全体の生産性向上に寄与することを狙いとしています。 関連記事:【2025年最新版】ものづくり補助金をわかりやすく解説!補助上限4,000万円・最低賃金賃上げ特例など変更点についても解説 小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓を支援することを目的とした補助金制度です。この制度では、小規模事業者が自ら経営計画を策定し、商工会や商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓の取り組みに対して補助が行われます。 補助の対象となる経費は幅広く設定されており、販路開拓に関連する様々な活動に活用できます。具体的には、チラシやパンフレットの作成、ホームページの制作、ウェブ広告の実施、店舗の改装工事、展示会への出展費用、新商品の開発費用などが含まれます。これらの経費はいずれも「販路開拓のため」という条件が付きますが、実際の事業活動においては多くの投資がこの条件に該当するため、比較的柔軟に活用することができます。 さらに、この基本的な枠組みに加えて、国の政策目的に合わせた特別枠も設置されています。特別枠では、通常の補助率や補助上限額よりも優遇された条件で補助を受けることができる場合があり、該当する事業者にとってはより魅力的な制度となっています。 この補助金は、販路開拓という条件はあるものの、小規模事業者にとって非常に使い勝手の良い制度として評価されています。法人・個人を問わず利用でき、商工会や商工会議所のサポートを受けながら申請できるため、補助金申請に不慣れな事業者でも取り組みやすい制度といえるでしょう。 関連記事:【2025年最新版】小規模事業者持続化補助金とは?概要や変更点などを解説 IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的とした補助金制度です。この制度は、業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に向けて、ITツールの導入を支援することを目的としています。 補助の対象となるITツールには、ソフトウェアやサービス等が含まれますが、どのようなツールでも対象となるわけではありません。対象となるITツールは、事前に事務局による審査を受け、補助金の公式ホームページに登録・公開されているもののみが対象となります。この仕組みにより、一定の品質や効果が見込まれるツールのみが補助対象として認められています。 補助対象経費には、ITツール本体の導入費用だけでなく、導入時の相談対応やサポート費用、クラウドサービスの利用料等も含まれます。これにより、単なるツールの購入だけでなく、導入から運用開始までのトータルなサポートに必要な費用についても補助を受けることができます。 この制度は、ITに詳しくない中小企業でも安心してデジタル化に取り組めるよう設計されており、日本全体の生産性向上とデジタル化推進に寄与することを目的としています。事前登録制により品質が担保されたツールから選択できるため、導入失敗のリスクを軽減しながらIT化を進めることが可能です。 関連記事:【2025年最新版】IT導入補助金とは?わかりやすく解説 創業手帳では、経営者の中でよく使われる補助金をランキング形式で紹介した『補助金ガイド』を無料でお配りしています。ぜひこちらもあわせてご活用ください。 シニア起業でよくある10の質問をご紹介します。 はい、年金受給者でも起業は可能です。ただし、注意すべき点がいくつかあります。 厚生年金を受給している65歳未満の方が起業して法人を設立し、自分に給与を支払うと在職老齢年金制度が適用され、年金額が減額される場合があります。月額給与と年金の合計が28万円を超えると減額対象となります。個人事業主の場合は基本的に対象外ですが、事業所得が多額になると国民年金保険料や国民健康保険料に影響する可能性があります。 年金は雑所得、事業所得は事業所得として確定申告が必要です。事業が赤字の場合、年金所得と損益通算できる場合もあります。また、65歳以上の場合、公的年金控除が適用され税負担が軽減されます。 事前に年金事務所や税務署、税理士などの専門家に相談し、自分のケースではどのような影響があるかを具体的に確認することをおすすめします。 体力面での不安を考慮した事業選択が重要です。 在宅でできるコンサルティング業、オンライン講師、Webライティング、ネット販売などは体力的な負担が少なく続けやすい分野です。また、自分のペースで時間調整ができる業種(占い師、カウンセラー、家庭教師など)も適しています。 長時間の立ち仕事が必要な小売業、重い物を扱う運送業、深夜営業の飲食業などは体力的な負担が大きく、継続が困難になる可能性があります。 定期的な健康診断を受け、無理のないスケジュールを組むことが大切です。繁忙期と閑散期を意図的に作り、休息期間を確保する事業設計も効果的です。また、将来的に体力が衰えても継続できるよう、システム化や外注化を視野に入れた事業構築を心がけましょう。 家族の理解は事業成功の重要な要素です。感情論ではなく、論理的なアプローチで説得することが効果的です。 まず、起業の動機と目的を明確に説明しましょう。「生きがいを求めて」「社会貢献したい」「経験を活かしたい」など、家族が共感できる理由を伝えます。次に、詳細な事業計画書を作成し、市場調査結果、収支見通し、リスク分析を数字で示します。 家族が最も心配するのは経済的リスクです。生活資金は確保すること、事業資金は余剰資金の範囲内で行うこと、失敗した場合の対応策も含めて説明しましょう。また、段階的なスタート(まずは副業から始める)を提案することで、リスクを軽減できることを伝えます。 家族にも何らかの形で参加してもらえるよう提案することで、反対から協力へと気持ちを変える効果があります。事務作業の手伝い、意見やアドバイス、精神的な支援など、家族それぞれができる範囲での協力を求めましょう。 年齢だけを理由に融資を断られることはありませんが、審査では様々な要素が考慮されます。 返済能力が最重要視されます。事業計画の妥当性、過去の信用履歴、担保や保証人の有無、そして事業の継続性が評価されます。高齢者の場合、事業承継計画や後継者の存在も重要な判断材料となります。 日本政策金融公庫の「シニア起業家支援資金」や自治体の制度融資など、高齢者向けの優遇制度があります。また、信用保証協会の保証付き融資なら、金融機関も比較的融資しやすくなります。 自己資金の充実が最も確実です。また、国や自治体の助成金・補助金、クラウドファンディング、親族からの借入なども検討しましょう。特に助成金は返済不要なため、条件に合致するものがあれば積極的に活用すべきです。 この不安は多くのシニア起業希望者が抱く問題です。適切なリスク管理で対処できます。 生活資金と事業資金は明確に分けて管理しましょう。最低でも3年分の生活費は手をつけない資金として確保し、事業には余剰資金のみを投入します。「失っても生活に支障のない範囲」という原則を徹底することが重要です。 最初から大きな投資をせず、事業の成長に合わせて段階的に資金を投入する方法が安全です。まずは最小限の投資で事業を開始し、売上が安定してから追加投資を行います。これにより、失敗時の損失を最小限に抑えられます。 万が一の場合に備えて、元の職場での嘱託雇用の可能性、アルバイトやパートでの収入確保、公的支援制度の活用などを事前に調べておきましょう。また、健康保険や年金などの社会保障制度は継続して加入することが大切です。 IT技術に不安があっても起業は可能ですが、現代のビジネス環境では最低限の対応が必要です。 完璧を求める必要はありません。ホームページ作成、メール対応、SNSでの情報発信、オンライン決済など、事業に不可欠な部分から少しずつ習得していきましょう。最近は直感的に操作できるツールも多く、基本的な機能であれば短期間で習得可能です。 すべてを自分で行う必要はありません。ホームページ制作は専門業者に依頼し、SNS運用は若い世代の家族や知人に協力してもらう、経理ソフトの操作は税理士に任せるなど、得意な人に任せる方法も効果的です。 自治体や商工会議所が開催するシニア向けIT講座、パソコン教室での個別指導、オンライン学習サービスなど、年齢に配慮した学習機会が多数あります。同世代の仲間と一緒に学ぶことで、不安も軽減され継続しやすくなります。 シニア起業家向けの支援環境は充実しており、様々な場所で仲間や支援を得ることができます。 各都道府県の産業振興センター、市区町村の創業支援センター、商工会議所、中小企業診断士協会などで、シニア向けの起業セミナーや相談会が定期的に開催されています。これらの場では同じ境遇の仲間と出会え、情報交換も活発に行われています。 シニア起業家のネットワーク組織、異業種交流会、ビジネスマッチング団体などがあります。また、元の職場のOB・OG会や業界団体なども貴重な人脈の場となります。 FacebookグループやLinkedInなどのSNS上には、シニア起業家のコミュニティが存在します。地理的制約なく全国の同世代起業家と交流でき、経験談の共有や相談ができます。コワーキングスペースでも年齢を問わず起業家同士の交流が生まれます。 多くのシニアは豊富な経験を持ちながら、それをビジネスに結び付ける方法が分からないケースがあります。 職務経歴、担当した業務、身につけたスキル、人脈、資格、趣味、特技などを詳細にリストアップしましょう。その際、「当たり前」だと思っていることも含めて書き出すことが重要です。長年の経験で身についた知識やノウハウは、他の人にとって貴重な価値がある場合が多いのです。 自分の経験と市場のニーズを照らし合わせて、事業化できる領域を見つけます。例えば、営業経験があれば中小企業向けの営業代行、経理経験があれば個人事業主向けの記帳代行、子育て経験があれば育児相談やベビーシッターなど、様々な可能性があります。 単独の経験だけでなく、複数の経験を組み合わせることで独自性の高いサービスを創出できます。例えば、「IT経験×介護経験=高齢者向けIT支援」「海外勤務経験×語学力=中小企業の海外進出支援」など、ユニークなビジネスモデルが生まれます。 起業に年齢制限はなく、何歳から始めても遅すぎることはありません。 実際に70代、80代で起業して成功している事例は数多くあります。カーネル・サンダーズは65歳でKFCを創業し、世界的企業に育て上げました。日本でも60代後半から70代で起業し、地域に根ざした事業を展開している方々が多数います。 年齢よりも「健康状態」「やる気」「準備の充実度」「明確な目的意識」が成功の鍵となります。体力的に無理のない事業選択、十分な市場調査、資金計画の策定などがしっかりしていれば、何歳でも成功の可能性があります。 高齢であることをハンディキャップと考えず、長年の経験、人生の知恵、落ち着いた判断力、豊富な人脈などの強みとして活用する発想が重要です。特に信頼性や安心感を重視する業界では、年齢が大きなアドバンテージになります。 シニア起業の大きな魅力の一つは、働き方の自由度の高さです。 「週3日だけ」「午前中のみ」「季節限定」「予約制」など、自分のライフスタイルに合わせた働き方が可能です。事業設計の段階から、どの程度の時間を仕事に割くかを明確にし、それに応じた事業規模や運営方法を計画しましょう。 将来的に労働時間を減らせるよう、事業の仕組み化を進めることが重要です。オンライン販売システムの構築、定期的な収入源の確保、アシスタントの雇用などを通じて、自分が直接働く時間を段階的に減らしていくことができます。 完全に引退する時期や、事業承継の方法についても事前に考えておきましょう。家族への承継、従業員への譲渡、廃業時の手続きなど、出口戦略を明確にしておくことで、安心して事業に取り組めます。また、健康状態に応じて事業規模を縮小していく柔軟性も大切です。 以上、シニア起業についてご紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。 創業手帳の冊子版では、起業に役立つ知識やノウハウを豊富に掲載しています。無料なのでぜひ、お気軽に資料請求してみてください。 (編集:創業手帳編集部)

 【完全無料】今やるべきことがすぐわかる!『創業カレンダー』
【完全無料】今やるべきことがすぐわかる!『創業カレンダー』
シニア起業の成功率は?
 【完全無料】今やるべきことがすぐわかる!『創業カレンダー』
【完全無料】今やるべきことがすぐわかる!『創業カレンダー』シニア起業でやってはいけない8つのこと

1. 家族に相談せずに進める
2. スキルや経験のない分野で始める
3. 退職金や貯蓄を一気に投資する
4. 体力を過信した事業選択
5. 競合調査を怠る
6. IT・ネット活用を軽視する
7. 過度な拡大志向
8. 収支計画の甘さ
 【完全無料】今やるべきことがすぐわかる!『創業カレンダー』
【完全無料】今やるべきことがすぐわかる!『創業カレンダー』シニア起業で失敗する人・成功する人の違いとは?

失敗する人
成功する人
自己流に走る
周囲と情報共有し助言を得る
勢いだけで起業
経験や専門性を活かす
家族の反対を無視する
家族の理解と協力を得る
全財産を一気に投入
段階的に資金投入し生活資金を確保
体力を過信して無理をする
年齢に適した事業選択をする
競合調査をしない
市場分析と差別化戦略を立てる
IT・デジタル活用を避ける
積極的にIT技術を取り入れる
最初から大きく展開したがる
スモールスタートで着実に成長
楽観的な収支計画
現実的で詳細な事業計画を策定
一人で全てやろうとする
外部専門家や協力者を活用する
過去の成功体験に固執
時代の変化に柔軟に対応する
顧客ニーズを推測で判断
顧客の声を直接聞いて改善する
健康管理を軽視する
定期的な健康チェックと体調管理
学習意欲が低い
新しい知識やスキル習得に積極的
失敗を恐れて行動しない
小さな失敗から学んで改善する
プライドが高く修正を嫌う
謙虚に意見を受け入れ軌道修正する
短期的な利益ばかり追求
長期的な視点で事業を構築する
ネットワークを活用しない
人脈や業界の繋がりを最大活用
資金繰りを軽視する
キャッシュフロー管理を徹底する
品質より量を重視
高品質なサービス・商品を提供
シニアが起業に向いているおすすめの業種一覧
業種
おすすめポイント
コンサルティング業
長年培った専門知識と経験が最大の武器。初期投資が少なく、自宅をオフィスにできるため低リスクで始められる。人脈を活かした営業展開が可能。
教育・研修業
豊富な実務経験を教える側として活用できる。オンライン講座なら全国対応可能で、資格取得支援など継続的な収入源を構築しやすい。
介護・福祉関連サービス
高齢化社会で需要拡大中の成長分野。同世代への共感力が高く、訪問介護や介護相談など比較的参入しやすいサービスから始められる。
地域密着型サービス
地域の人脈と信頼関係を活用できる。高齢者向けの買い物代行、家事代行、ペットの世話など、地域ニーズに応じたきめ細かいサービス提供が可能。
手工芸・クリエイティブ業
趣味を収益化できる理想的な分野。オンライン販売で全国展開でき、教室運営と作品販売の両方で収入を得られる。初期投資も材料費程度で済む。
農業・園芸業
健康的で生きがいのある仕事。直売や加工品販売で付加価値をつけやすく、体験農園や農業指導など多角化も可能。定年後の健康維持にも効果的。
不動産関連業
宅建士などの資格があれば信頼性が高い。仲介手数料収入は単価が大きく、地域の土地勘や人脈を活かした営業が展開できる。
小規模な飲食業
家庭料理の腕を活かせる身近な分野。テイクアウト専門やケータリングなら設備投資を抑えられ、地域の常連客づくりで安定経営を目指せる。
リペア・メンテナンス業
技術系の経験を活かせる分野。出張修理なら店舗不要で、物を大切にする価値観が評価される時代。専門技術があれば競合が少ない。
整体・マッサージ業
資格取得で差別化でき、高齢者の健康ニーズに応えられる。訪問型なら設備投資が少なく、リピート客による安定収入が期待できる。
イベント・冠婚葬祭業
人生経験の豊富さが活かせる分野。司会業や式典プロデュースなど、落ち着いた対応力が重宝される。地域の信頼関係がそのまま営業力になる。
アンティーク・リサイクル業
目利き力と趣味性を活かせる。オンライン販売で販路拡大でき、買取から販売まで一貫して行える。環境意識の高まりで社会的意義もある分野。
シニア起業の成功事例

ブルーベリーファームおかざき
ライフネット生命
 【完全無料】今やるべきことがすぐわかる!『創業カレンダー』
【完全無料】今やるべきことがすぐわかる!『創業カレンダー』シニア起業で活用できる代表的な補助金・助成金

新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)
ものづくり補助金
小規模事業者持続化補助金
IT導入補助金
シニア起業のよくある10の質問

Q1. 年金を受け取りながらでも起業できますか?
Q2. 体力的に不安があるのですが、どんな仕事なら続けやすいですか?
Q3.家族に反対されています。どう説得すればよいでしょうか?
Q4. 高齢でも融資を受けられますか?
Q5. 起業に失敗したら老後資金が尽きてしまうのでは?
Q6. ITやネットが苦手でも起業できますか?
Q7.同年代の仲間や支援を受けられる場所はありますか?
Q8. 過去の経験をどう活かせばいいかわかりません
Q9. 何歳までなら起業しても遅くないのでしょうか?
Q10. 起業したら働き続けなければいけませんか?
シニア起業は準備してから挑戦しましょう