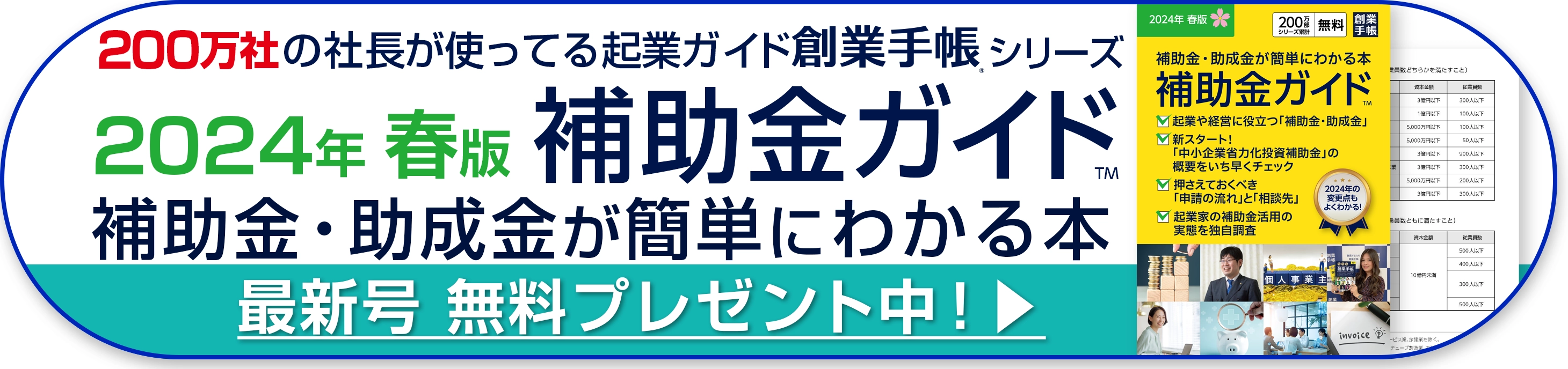【国が支援強化を発表!】最低賃金引上げで一部の補助金要件緩和と中小企業支援策が充実化
最低賃金の引上げでIT導入補助金などいくつかの補助金の要件が緩和

2025年度の最低賃金は全国加重平均で1,121円となり、前年度から66円引き上げられる予定です。この引き上げにより、中小企業の人件費負担は大幅に増加すると見込まれます。
そこで、政府は賃上げを実現する企業を後押しするため、補助金の要件緩和や支援策の拡充を打ち出しました。たとえば、IT導入補助金やものづくり補助金の要件が緩和され、より多くの企業が活用できるようになります。
本記事では、最低賃金引き上げに対応するための具体的な支援策と、その活用方法について詳しく解説します。
補助金は予算や募集枠に限りがあり、早めの情報収集が欠かせません。
創業手帳の無料でお配りしている「補助金ガイド」では、IT導入補助金やものづくり補助金など最新の制度をまとめています。今すぐチェックして、自社に合った制度を逃さず活用しましょう。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
経産省が打ち出す中小企業への主な支援策

経済産業省は2025年9月、最低賃金引き上げに対応する中小企業向けの支援策を発表しました。この支援策は、主に「価格転嫁の促進」「補助金による直接支援」「生産性向上支援」という3つの柱で構成されています。
単なる資金援助にとどまらず、企業の収益力そのものを高める総合的な支援となっている点が特徴です。
注目ポイント1:一部補助金の要件が緩和
生産性向上を支援するために、ものづくり補助金・IT導入補助金・省力化投資補助金(一般型)に設けられている「最低賃金引上げ特例」の要件が緩和されます。以下の要件を満たす場合に、「最低賃金引上げ特例」で、通常より高い補助率(1/2から2/3に引上げ)が適用されます。
| 区分 | 従来の要件 | 改正後の要件 |
| 対象期間 | 指定する一定期間(R5.10~R6.9) | 指定する一定期間 |
| 雇用条件 | 地域別最賃+50円以内で雇用している従業員 | 改定後の地域別最賃未満で雇用している従業員 |
| 雇用期間 | 3ヶ月以上 | 3ヶ月以上 |
| 従業員割合 | 全従業員数の30%以上 | 全従業員数の30%以上 |
具体的には、指定する一定期間において、3か月以上にわたり改定後の最低賃金未満で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いる事業者が優遇の対象です。
さらに、一定期間において事業場内最低賃金を「全国目安で示された最低賃金の引上げ額(63円)」以上にする事業者に対しては、採択審査においてさらに加点されます。
これにより、ものづくり補助金・IT導入補助金・省力化投資補助金(一般型)に採択される可能性が高まります。補助金の受給を通じて、DX推進や省人化をはじめとした事業投資をする際に、実質的な自己負担を抑えることが可能です。
なお、実際に要件緩和が実施される時期については未定です(2025年9月現在)。申請予定の方は、各補助金のホームページをチェックしておきましょう。
注目ポイント2:補助金や税制等による支援
補助金による支援では、持続化補助金をはじめとした補助金事業を通じて、小規模事業者に対して販路開拓を支援します。商工会・商工会議所の伴走支援を受けながら販路開拓に取り組むことで、ビジネスチャンスを増やせるでしょう。
また賃金引上げ特例の要件を満たしていれば、通常補助上限額が50万円のところ、150万円を上乗せすることができます。
ほかにも、賃上げ促進税制による賃上げ支援や100億企業等に対する成長加速化支援なども盛り込まれています。賃上げと企業の生産性向上を通じて、輸出による外需獲得や地域内の仕入れ増加など、地域経済を活性化させる効果も期待されています。
賃上げ促進税制の活用により、大企業・中堅企業は全雇用者の給与等支給額の増加額の最大35%、中小企業は最大45%を税額控除を受けられます。これにより、実質的な賃上げ負担を軽減することが可能です(税額控除額の上限は法人税額または所得税額の20%)。
たとえば、中小企業が年間給与総額を300万円増やした場合、最大135万円の税額控除を受けられるため、実質的な負担は165万円まで圧縮されます。
これにより、賃上げに踏み切りやすくなるうえ、従業員のモチベーション向上による生産性アップも期待できるでしょう。昨今は人材不足に悩まされる企業も多いため、人材確保の面でも賃上げは効果的な取り組みです。
日本政策金融公庫は、従業員の賃上げに取り組む事業者に対して「賃上げ支援特別貸付」を行っています。給与支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある事業者に対して、基準金利から0.5%引き下げた(貸付日から2年間)特別金利で融資を実施する制度です。
このように、賃上げを通じて融資を受ける際の優遇制度も用意されています。事業投資を検討している方は、あわせて活用を検討するとよいでしょう。
注目ポイント3:価格転嫁対策の強化
賃上げに伴うコスト増の影響を軽減するためには、価格転嫁が求められます。経済産業省は、価格転嫁対策の強化として、以下の支援を行う予定です。
- 改正下請法(取適法)・振興法の着実な執行
- 発注側企業等における取引慣行の改善
- 幅広い業界での取引適正化の要請・働きかけの継続
一般的な企業間取引では、発注側企業が強い立場にあります。そこで、経済産業省が取引適正化の推進に向けた積極的な周知・広報を行う予定です。
改正下請法(取適法)では、サプライチェーン全体での価格転嫁や支払期間の短縮などの課題に対し、協議に応じない一方的な価格設定を禁止します。また、手形払いの禁止も設けられる予定です。
また、評価が芳しくない発注側企業や地方公共団体などに対して指導・助言を行ったり、発注側企業に取引慣行の改善を促したりする行政指導を強化する方針です。
また、政府は価格転嫁対策を進めるために「パートナーシップ構築宣言」の拡大を進めています。「パートナーシップ構築宣言」とは、サプライチェーン全体の付加価値向上や、大企業と中小企業の共存共栄を目指す宣言です。
宣言企業は、「下請企業との望ましい取引慣行(「振興基準」)の遵守」の一環で適正な価格転嫁に協力する必要があります。中小企業としては、宣言企業が増えれば、値上げ交渉がしやすくなるでしょう。
価格転嫁が実現すれば、最低賃金引き上げによる人件費増加分を売上でカバーすることが可能です。これにより、コスト増による廃業や倒産を回避できるでしょう。
注目ポイント4:厚労省との連携強化
経済産業省と厚生労働省の連携が強化され、全国の労働局・働き方改革推進支援センター(全国47か所)や労働基準監督署で補助金制度に関する説明を受けられます。
センターでは、社会保険労務士をはじめとした専門家と無料で相談が可能です。賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用など、事業経営に関するアドバイスを受けられます。
また、中小企業庁の「よろず支援拠点」でも、経営に関する相談が何度でも無料で可能です。企業の経営課題に合わせて、専門家が対応してくれるため、有効活用できる場面があるでしょう。
なお、2026年度にはより専門性の高い支援組織を「よろず支援拠点」の中に設ける予定です。具体的には、工場での生産管理の経験がある専門家や技術者の派遣などを通じて、企業の生産性向上やデジタル化を後押しする狙いがあります。
業務改善助成金の対象も拡大

厚生労働省が所管である「業務改善助成金」の拡充も発表されました。
これまで業務改善助成金の対象は、事業場内最低賃金が地域別最低賃金プラス50円以内の事業者に限定されていました。しかし2025年度からは、「事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満まで」に拡大されています。なお、助成率は事業場内最低賃金が1,000円以上の場合3/4、1,000円未満の場合は4/5です。
また、従来の制度では賃金引上げ後の申請はできませんでした。申請前に賃金引上げ計画を立て、申請後に賃金を引き上げる必要がありました。
しかし、2025年9月5日から当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金の引き上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要です。手続きの負担が軽減され、より使いやすい制度となっています。
まとめ:賃上げと生産性向上を両立するチャンス
2025年度の最低賃金引き上げは、全国加重平均で66円という過去最大の上げ幅となり、中小企業にとって大きな転換点となっています。
しかし、政府が打ち出した包括的な支援策を活用すれば、この課題を成長の機会に変えることが可能です。賃上げによる人材確保と、生産性向上による競争力強化を同時に実現する手段が用意されているため、有効活用できる場面があるはずです。
経済産業省や厚生労働省が用意している支援を活用し、生産性の向上や人材確保、業務効率化などを推進しましょう。
創業手帳では、最新の補助金や助成金などの情報を無料でお届けしています。「補助金ガイド」や、補助金の最新情報がリアルタイムで届く「補助金AI(ほじょアイ)」などを無料で利用できるため、ぜひ経営にお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)