個人事業主が知っておくべき勘定科目一覧|経費になる・ならない事例
個人事業主がよく使う勘定科目は覚えておいて損はなし!
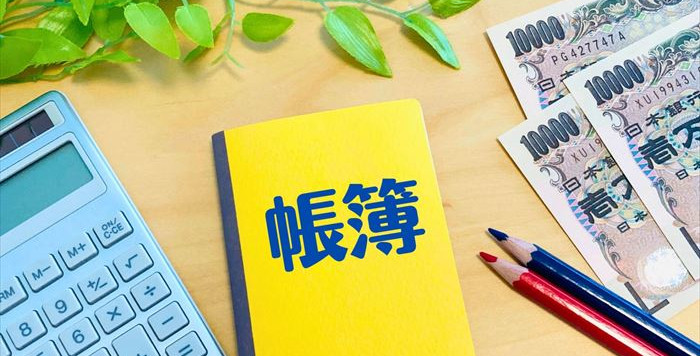
個人事業主が帳簿付けで悩みやすい「勘定科目」。適当に仕訳してしまうと確定申告の際に手間が増えたり、税務署から不審に思われたりする可能性もあります。
この記事では、個人事業主がよく使う勘定科目の使い方について、確定申告で提出する決算書に沿って概要をまとめました。特に活用頻度の多い費用の勘定科目(経費)を中心に、グレーゾーンの考え方なども解説しています。
仕訳で迷った際は曖昧に判断せず、お金の流れが発生した経緯や目的などから適切に勘定科目を使い分けましょう。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
勘定科目の基本となる5つの区分

勘定科目とは、帳簿付けの際に取引の内容をわかりやすく類別するための科目の総称です。取引を勘定科目ごとに振り分ける作業を「仕訳」と呼びます。
勘定科目は、以下5つのグループに分類されます。
| 区分 | 概要 | 主な勘定科目の例 |
|---|---|---|
| 資産 | パソコンや車など、取得価額が一定以上のものや将来お金になるもの | 現金、預金、売掛金、商品、土地、建物、車両、工具器具備品など |
| 負債 | 銀行からの借り入れなど、将来支払いが必要なもの | 借入金、未払金、未払費用、前受金など |
| 純資産 | 事業主自身の出資や、事業用と私用のお金のやりとり | 元入金、事業主貸、事業主借など |
| 収益 | 商品販売やサービス提供による収入全般 | 売上高、雑収入、受取利息など |
| 費用 | 事業を行うためにかかる支出全般 | 仕入高、旅費交通費、通信費、広告宣伝費、接待交際費、水道光熱費、消耗品費、修繕費、減価償却費、福利厚生費など |
取引が発生したら、5つのうちのどの区分に属するかから考えると、適切な勘定科目を選びやすくなります。
例えば同じ支出を伴う取引でも、高額で売ったらお金になる可能性があるものを買った場合は「資産」、事業に使う細かな事務用品を買った場合は「費用」です。
区分を判断したあとに、その区分に応じた勘定科目で仕訳することで、お金の動きが正しく把握できる帳簿や決算書が作成でき、健全な経営にもつなげられます。
【一覧】個人事業主がよく使う経費の勘定科目とは?

個人事業主がよく使う勘定科目といえば費用の区分、いわゆる「経費」です。
勘定科目は「絶対にこの名称にすべき」というルールはないものの、確定申告書の様式に合わせて作っておくことで、経理の作業負担を軽減できます。
国税庁の青色申告決算書にもある勘定科目のうち、個人事業主が把握しておきたい主な経費の科目を以下にまとめました。
| 勘定科目 | 概要 | 主な経費例 |
|---|---|---|
| 租税公課 | 税金や公的費用 | 印紙税、事業税、自動車税 |
| 水道光熱費 | インフラ費用 | 水道代、ガス代、電気代 |
| 荷造運賃 | 商品発送や配送に関わる費用 | 梱包資材代、宅配便料金 |
| 通信費 | 通信サービスに関する費用 | 電話代、インターネット代 |
| 旅費交通費 | 移動や出張に関する費用 | 電車代、バス代、宿泊費 |
| 広告宣伝費 | 顧客獲得のための宣伝費用 | チラシの印刷代、広告掲載料 |
| 接待交際費 | 取引先との関係維持に使う費用 | 接待飲食費、贈答品代 |
| 消耗品費 | 少額・短期利用の備品購入 | 文房具代、10万円未満の備品代 |
| 損害保険料 | 保険契約にかかる費用 | 火災保険、賠償責任保険 |
| 修繕費 | 設備や建物の修理にかかる費用 | 事務所の修理代、備品修繕費 |
| 減価償却費 | 資産を耐用年数で経費化するための科目 | パソコン・車など高額資産の購入費 |
| 給料賃金 | 従業員への給与 | アルバイト・社員の給与 |
| 福利厚生費 | 従業員向けの厚生関連費用 | 健康診断費、飲料代 |
| 外注工賃 | 業務を外部に委託した費用 | デザイン費、ライティング費 |
| 地代家賃 | 事務所や店舗などの使用料 | オフィス賃料、駐車場代 |
| 雑費 | 他の科目に当てはまらない少額の支出 | 慶弔費、新聞図書代 |
経費になるのは「事業に使うもの、事業に関係のあるもの」のみで、私的な費用は一切経費になりません。
それぞれの勘定科目に当てはまる事例と、経費になるもの・ならないものを具体的に解説します。
租税公課
租税公課は、税金や公的団体に収める費用を仕訳する際に使う勘定科目です。
| 租税公課(経費)になるもの | 租税公課(経費)にならないもの |
|---|---|
| 収入印紙代 登録免許税 事業用の固定資産税・都市計画税 事業税(個人事業税) 事業用の不動産にかかる不動産取得税 自動車税など、事業用車両にかかる税金 行政サービス利用の手数料(登記簿謄本、住民票など) 商工会や同業者団体への会費 税込経理方式の場合の消費税 |
事業主の所得税・住民税・相続税・贈与税 税抜経理方式の場合の消費税 延滞税、不納付加算税、過怠税などの罰則的な税金 事業主の交通違反の反則金・罰金 |
事業主個人の税金のほか、懲罰的な特性を持つ費用は経費にはできません。
水道光熱費
水道光熱費は、事業用の水道・ガス・電気といったインフラ費用の勘定科目です。
水道代、電気代などと分けて計上しても、水道光熱費としてまとめて計上しても問題ありません。
| 水道光熱費(経費)になるもの | 水道光熱費(経費)にならないもの |
|---|---|
| 事務所や店舗で使う水道代・電気代・ガス代 事業用の倉庫の電気代 自宅のうち、事業専用スペースで使った分の光熱費 |
自宅兼事務所の生活スペース分の光熱費 |
自宅兼事務所などで事業をしている個人事業主の場合、家事按分をして事業用の水道光熱費のみを経費計上します。
プライベートと共用するものは、水道光熱費に限らず家事按分が必須です。
荷造運賃
荷造運賃は、製品や商品の梱包や運送にかかる費用を処理するための勘定科目です。
| 荷造運賃(経費)になるもの | 荷造運賃(経費)にならないもの |
|---|---|
| 包装紙、段ボール、ガムテープ、緩衝材などの梱包資材代 荷札、伝票などの発送に必要な備品代 宅配便・小包郵便・書留などの配送料 梱包・発送作業を外注した場合の委託費用 運送業者への運賃(トラック・鉄道・船便など) 店舗やオフィス移転に伴う引越し費用 |
個人的な荷物を送るための送料 |
梱包や荷造での使用が大半を占めるのであれば荷造運賃、梱包・発送以外にも使う10万円未満の消耗品(ガムテープなど)は消耗品費とするなど、主な利用目的で使い分けるといいでしょう。
通信費
通信費は、インターネット関連の費用や携帯の通話料金など通信手段に関する費用を処理するための勘定科目です。
| 通信費(経費)になるもの | 通信費(経費)にならないもの |
|---|---|
| 固定電話・携帯電話の通信料 インターネット回線料、プロバイダ料 サーバー利用料、ドメイン取得料 すぐ使う切手・はがき・封筒代 電報代 |
プライベート利用の携帯の通信料 プライベート利用のインターネット回線料 |
切手をまとめて購入して備蓄する場合、通信費ではなく貯蔵品として処理し、実際に使用した際に通信費を使います。
通信費と荷造運賃は混同しやすいですが、通信費は連絡目的、荷造運賃は商品発送を目的としたときで使い分けましょう。
また、インターネット回線や携帯電話をプライベートでも使用している場合、水道光熱費と同様に按分して計上します。
使用割合を求め、プライベートの支出は事業主貸で仕訳をしてください。
旅費交通費
旅費交通費は、業務を行う中で発生する交通費や旅費、宿泊費などを処理するための勘定科目です。
| 旅費交通費(経費)になるもの | 旅費交通費(経費)にならないもの |
|---|---|
| 電車・バス・タクシー代 交通系ICカードのチャージ代 定期券代 飛行機代、レンタカー代 出張時の宿泊費、旅費 出張中の食事代 |
事業主の通勤代 プライベート旅行の交通費・宿泊費 |
旅費や交通費の領収書は適切に保管し、万が一なくした場合は日付・目的・行先・出費額を記録した書類を作って保管します。
法人カードや事業用に使う交通系ICカードを取得しておくと、プライベートと混同せずに済み、管理が楽になるのでおすすめです。
出張費を前払いしている場合は仮払金として計上しておき、精算した際に旅費交通費で処理します。
広告宣伝費
広告宣伝費は、事業の宣伝や販促、広告に使う費用を計上する際に使用する勘定科目です。
| 広告宣伝費(経費)になるもの | 広告宣伝費(経費)にならないもの |
|---|---|
| ポスター・チラシ・カタログなど印刷物の制作費 社名入りノベルティ(ボールペン・カレンダーなど)の作成費 看板の作成・設置費用(取得価額10万円未満) テレビ・ラジオ・インターネット広告の掲載料 DM代(切手・はがき代など含む) イベントのための出展料や装飾費用 |
事業外の私的な広告出稿 |
広告宣伝費は通信費と似ているケースがありますが、不特定多数へのPR目的なら広告宣伝費、特定の相手とのやりとりが目的なら通信費になります。
看板など取得価額が10万円以上になると固定資産となり、減価償却費での計上が必要です。
接待交際費
接待交際費は、取引先や仕入先など事業に関わりがある人に対して使用する費用を処理するための勘定科目です。
接待には様々な形があるため、経費として計上できる費用も多岐にわたります。
| 接待交際費(経費)になるもの | 接待交際費(経費)にならないもの |
|---|---|
| 取引先との飲食代 贈答品(お中元・お歳暮・記念品・お土産など) 取引先を接待するための送迎費(タクシー代・ハイヤー代など) 取引先を招待するイベントの費用(ゴルフ場利用料、観劇招待費など) ロータリークラブの会費 取引先への祝い金、香典、せんべつ代 |
事業外の友人・家族との飲食代 私的な贈り物や趣味の会合の費用 税法上「社会通念上相当」と認められないほど高額な接待費 |
接待交際費は、事業と関係のある接待が対象となるため、個人的な会食やプレゼントにかかる費用は計上できません。
また、1人10,000円以下の会食を行った場合、それを証明できる書類が残っていれば会議費として計上可能です。
消耗品費
消耗品費は取得価額が10万円以下、または法定耐用年数が1年未満のものの購入代金を処理するための勘定科目です
| 消耗品費(経費)になるもの | 消耗品費(経費)にならないもの |
|---|---|
| 文房具(筆記用具・ファイルなど) 電球・洗剤・食器などの消耗品 10万円未満の応接用テーブルと椅子のセット 10万円未満の備品(机・椅子・本棚、コピー機など) 10万円未満のソフトウェア代 |
プライベート用の家具や日用品 |
椅子とテーブルのセット商品の場合、1セットあたり10万円未満であれば消耗品費として処理可能です。
損害保険料
損害保険料は、安全に事業を行うことを目的に加入した各種保険にかかる保険料を経費と計上するために使う勘定科目です。
| 損害保険料(経費)になるもの | 損害保険料(経費)にならないもの |
|---|---|
| 事務所や店舗にかける火災保険料、地震保険料 自動車保険料(対人・対物・車両保険など) 兼用の建物や車のうち、事業用に使っている分だけの損害保険料 |
事業主の生命保険料 自家用車の自動車保険料 自宅兼事務所の生活スペース分の保険料 |
事業とは無関係の生命保険や自家用車、自宅の火災保険の保険料は経費にならないので注意してください。
ただし、事業を行う場所が自宅であったり、自動車を事業でも使っていたりする場合は、按分することで保険料の一部を経費に計上できます。
修繕費
修繕費は、固定資産の修理や現状維持などにかかった費用に対する勘定科目です。
金額が20万円未満、または3年以内の周期で行われる修繕などが対象の目安になります。
| 修繕費(経費)になるもの | 修繕費(経費)にならないもの |
|---|---|
| 建物・設備の故障部分の修理費 業者による保守点検費用 設備や車両の定期メンテナンス費用 原状回復費(賃貸契約終了時の修繕など) 建物の小規模な壁や窓の補修費 |
自宅兼事務所の生活スペース分の修繕費 自宅のリフォーム代 |
固定資産の価値を向上させる目的や使用期間を延長するために支払う費用は、修繕費(費用)ではなく資本的支出で処理します。
資本的支出は、費用の科目のように一括での処理はできません。
建物や車両運搬具などの固定資産の勘定科目で計上したのち減価償却していきます。
減価償却費
減価償却費は、取得価額が10万円以上で長年使用する固定資産の購入費を計上するための勘定科目です。
一旦資産の勘定科目で計上した固定資産を、毎年少しずつ減価償却費で処理していきます。
| 減価償却費(経費)になるもの※ | 減価償却費(経費)にならないもの |
|---|---|
| 事業用パソコンやソフトウェア 事業用の机・椅子 機械装置・工具類 エアコン、冷暖房設備などの建物付属設備 事業用の自動車・バイク・自転車 事業用の建物の購入費 看板や大型設備 店舗の増改築に伴う解体費用 引っ越し時に新設した設備代 事業とプライベートで兼用する設備の事業用分の費用 |
プライベート用に購入したパソコン・家具・車両 装飾用の絵画や骨とう品、美術品(時間の経過で価値が減らないと認められる資産) |
※購入時にそのまま減価償却費(経費)になるのではなく、毎年の振替時に減価償却費として経費化するという意味
高価な固定資産の購入代は、一括ではなく数年に分けて経費に計上しなければなりません。
何年かけて計上するのかは、品目ごとに定められた法定耐用年数を確認してください。
給料賃金
給料賃金は、従業員に支払う給与や手当を処理するための勘定科目です。
個人事業主でも従業員を雇うことがあれば、給与を支払ったことを帳簿に記録する必要があります。
| 給料賃金(経費)になるもの | 給料賃金(経費)にならないもの |
|---|---|
| 基本給 時間外手当 住宅手当・家族手当・資格手当などの諸手当 現物支給(会社負担で支給する食事・制服など給与課税対象となるもの) |
事業主の報酬 白色申告者が家族に支払う給与 |
なお、給料賃金を帳簿に記録する際は、借方には源泉所得税や社会保険料も含んだ総支給額で記載してください。
従業員に振り込んだ金額や源泉所得税など細かな内訳は、貸方に記録します。
福利厚生費
福利厚生費は、従業員の労働環境の改善などに対して発生する費用を処理するための勘定科目です。
| 福利厚生費(経費)になるもの | 福利厚生費(経費)にならないもの |
|---|---|
| 社員旅行やレクリエーション費用(従業員全体を対象とする場合) 忘年会・新年会など社内行事の費用 従業員への祝い金(結婚・出産など) 研修代、セミナー参加費 親睦活動費 職場に備える常備薬やお茶代 |
事業主や家族だけの旅行・飲食 事業主の健康診断料 事業主の国民年金、国民健康保険料 事業主のスポーツクラブの会費 特定の一部の従業員だけを優遇するような支出(公平性がない場合) |
労働環境の改善等を目的とした費用であり、従業員全体を対象としている場合には福利厚生費に該当します。
個人事業主の福利厚生のための費用は該当せず、経費にもなりません。
外注工賃
外注工賃は、外部の業者に仕事の依頼や注文を行った際に支払う報酬を計上するための勘定科目です。
| 外注工賃(経費)になるもの | 外注工賃(経費)にならないもの |
|---|---|
| ホームページの制作や運営を外部に委託した費用 記事執筆やデザイン制作をフリーランスに依頼した費用 部品加工や印刷業務を外部工場に委託した費用 システム開発やアプリ制作の委託費 |
事業と関係のない私的な依頼 |
外注先が個人の場合、支払い内容によって源泉徴収が必要です。源泉徴収義務者(給与や報酬を支払う会社や個人)は源泉徴収を行いましょう。
地代家賃
地代家賃は、事業で使用している不動産の賃借料などを処理するための勘定科目です。
| 地代家賃(経費)になるもの | 地代家賃(経費)にならないもの |
|---|---|
| 事務所や店舗の家賃、管理費、共益費 土地の賃借料 事務所や店舗の更新料(20万円以下) 月極駐車場の利用料 倉庫の賃借料 |
自宅兼事務所の生活スペース分の家賃 住宅ローンの元本(負債) 土地の購入費(資産) |
住宅ローンの元本は「借入金の返済」にあたるため、費用ではなく負債の減少として処理します。
経費になるのは利息部分だけで、勘定科目は利子割引料です。
土地の購入費は資産の取得にあたりますが、土地は減価償却の対象外となる(時間経過で価値が減る資産と認めらない)ため、経費にはできません。
雑費
雑費は、少額かつ他の勘定科目には該当しない経費を計上する際に使う勘定科目です。
| 雑費(経費)になるもの | 雑費(経費)にならないもの |
|---|---|
| 少額の引越し費用 作業着や備品のクリーニング費用 ゴミ処理代、粗大ゴミの処分費 事業の分野の専門書 市区町村の区費・組合費など少額の負担金 |
事業と関係のない個人的な支出 スーツや靴など私用もできる衣装類 日常でも使えるメイク道具 事業主の飲食代(接待や会議などを伴わないもの) |
雑費にできる経費の総額に上限はありません。しかし、雑費ばかりになると正確に経費の動きを把握できず、信頼性の低い決算書ができてしまいます。
税務調査の対象になる恐れもあるので、雑費は多用しないように気をつけてください。目安は、経費全体の5~10%程度です。
個人事業主が勘定科目の使い分けで注意すべき点
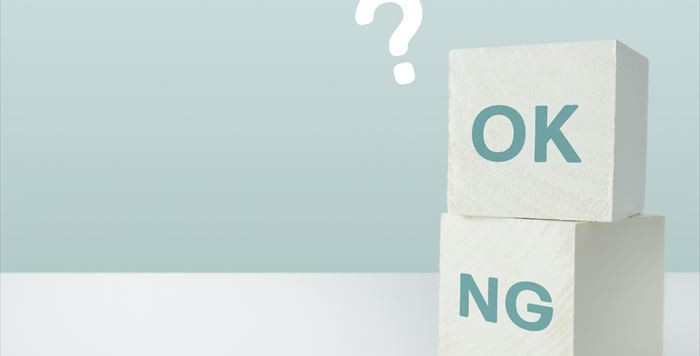
支出や収入の性質によって勘定科目を使い分けることが大切ですが、中には判断に迷う取引もあります。
ここからは、個人事業主が判断に迷いやすいシーンや知っておくべき科目および使い方を解説します。
経費のグレーゾーン
個人事業主の支出のうち、経費として計上していいか迷う「グレーゾーン」があります。
以下に、迷いやすいシーン例をまとめました。
| シーン例 | なぜグレーゾーン? |
|---|---|
| エステ、マッサージ、ジムの費用 | 業務に直接的に必要かの線引きが難しい。モデルや俳優業など外見を整える必要性が高い職業以外は通常認められない |
| 美術展、コンサートの鑑賞費用 | デザイナーが知見を深めるために活用した場合などは経費になり得るが、趣味の延長とみなされれば否認されてしまう |
| ビジネス関連の書籍代 | 単なるビジネス書や自己啓発の本などは、事業との関連性を客観的に証明するのが難しい場合がある |
基本的には、プライベートな用途とは明確に線引きでき、事業に必要と客観的に認められる費用が経費になり得ます。
グレーゾーンの支出が多いと否認のリスクが高まる可能性があるので、できるだけしっかりと線引きをしておきましょう。
資産や負債になる支出の区別
帳簿上でよく使うのは費用(経費)の勘定科目ですが、中には資産や負債の支出に該当する取引もあります。
支出=必ず経費になるわけではないので、次のように性質ごとの使い分けが不可欠です。
| 区分 | 特徴 | 主な勘定科目 |
|---|---|---|
| 資産 | 長期的に価値があるもの。購入時は経費にならず、減価償却で少しずつ経費化する(土地は減価償却不可) | 建物、車両運搬具、工具器具備品、建物付属設備、土地など |
| 負債 | 将来支払う義務があるもの(元本部分のみ) | 借入金、未払金、未払費用、前受金など |
| 経費 | その年度の費用として直接処理できる | 水道光熱費、通信費、旅費交通費など |
区分に迷う代表的な支出が「敷金・礼金」です。
敷金は最終的に返還されるものなので、原則は繰延資産の区分になり、敷金などの勘定科目で処理します。
礼金は返還のない謝礼金であるため、20万円未満であればそのまま地代家賃になりますが、20万円以上であれば長期前払費用(資産)で一旦計上し、あとから地代家賃や支払手数料などで処理するのが一般的です。
事業主貸・事業主借の活用
個人事業主ならではの勘定科目として「事業主貸」「事業主借」があります。
個人事業主は、事業と個人のお金が法律上区別されないため、事業用口座から生活費を出したり、逆にプライベート口座から経費を立て替えたりすることが可能です。
そのような際には、事業主貸または事業主借で処理します。
| 事業主貸の主な例 | 事業主借の主な例 |
|---|---|
| 生活費を事業用口座から引き出したとき 事業用口座から私的な買い物代を支払ったとき 事業のお金で個人の税金(住民税、所得税など)を支払ったとき |
事業の経費を個人のお金で立て替えたとき 個人カードで事業用の備品を買ったとき 個人のお金を事業用口座に入金したとき |
事業主貸と事業主借は、経費などになるお金を計上するのではなく、事業とプライベートのお金の動きを見える化するための勘定科目といえます。
帳簿付けに活用することで、事業とプライベートの支払いが混在しやすい個人事業主でも、口座や現金の残高に矛盾が出にくくなるでしょう。
まとめ・個人事業主として勘定科目を正しく理解しておこう
個人事業主が使う勘定科目に決まった名称はないものの、確定申告時に作成する決算書や収支内訳書と同様の科目を使うことで、経理の負担が軽くなります。
お金の流れの性質ごとに5つの区分に整理し、どんな目的で使った支出か、どんな内容の収入かに応じて適切な勘定科目で処理しましょう。
会計には専門知識が求められるので、税理士に相談や依頼して、適切に会計処理をしていくのも選択肢のひとつになります。
「経費で損しないためのチェックリスト(無料)」では、経費削減や節税のためのヒントを掲載しています!詳しくは以下のバナーから!

創業手帳・編集部のコメント
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。



































勘定科目は、個人事業主の方にとって帳簿付けの際など必ず知っておく必要がありますよね。
こちらの記事では、勘定科目の「費用」に分類される「経費」に絞って詳しく説明しました。
個人事業主の方にとって、経費を正しく把握し、帳簿を付ける=間違いない納税を行う=節税へと繋がる基本かつ必須作業です!
確定申告の期限直前で慌ててしまい、日頃の業務が滞ってしまった…というお声もお聞きします。
個人事業主の方は、メインの業務に加え、あらゆる業務を同時進行で行っていく必要があるため、慌ただしい毎日を送っているかと思います。
どうしても経理作業などは後回しになってしまいがちですが、一度にまとめてやろうとすることはおすすめできません。数日で理解しようとするより、日々のルーティンとして取り入れて勘定科目を知識として身につけましょう!
日頃から費用(経費)の勘定科目は何なのかを常に意識することが、業務の継続に直結します。
実際に個人事業主の方のお話を聞くと、最初は、簿記や経理の知識がなくても、費用(経費)を勘定科目に振り分ける=仕訳作業を行っていると、段々と事業のお金の流れを肌感覚で掴めてくるそうです。
資金管理は事業を継続していく上で、無視できない業務です。
まずは、ぜひ以下の創業手帳の記事を参考にしながら、実際に仕訳作業を行ってみてくださいね!
帳簿に関する記事はこちら
創業手帳の冊子版(無料)の第1章では、資金調達やキャッシュフローについて基本から学べ、キャッシュフロー改善チェックシートを活用していただくことで、より資金の管理を確実にすることができます。ぜひお気軽に読んでみてください!