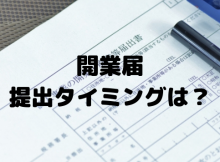個人事業主に向いている人の特徴は?メリット・デメリットや開業の流れも解説
個人事業主が向いている人と向いていない人の違いは?

個人事業主としての仕事は、人によって向き不向きが存在します。
向いている人は個人事業主として成功する可能性がありますが、向いていない人は働き方が合わず失敗する可能性が高いです。
そのため、双方にはどのような違いがあるのか理解してから、独立するかどうか判断することをおすすめします。
今回は、個人事業主に向いている人と向いていない人の特徴を紹介します。
個人事業主になるメリット・デメリット、平均年収、必要なスキル、開業の流れも解説しているので、独立を検討している人は参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
個人事業主が向いている人の特徴

個人事業主が向いている人には、共通の特徴があります。主な特徴は以下のとおりです。
決断力があり主体的に取り組める
個人事業主に向いているのは、決断力があり、主体的に行動できる人です。個人事業は様々な判断を行う必要があり、適切に物事を判断できる力が欠かせません。
また、ビジネスではスピードも重視されます。
決断が遅れてしまうと、同業者に仕事を奪われてビジネスチャンスを逃してしまう可能性があるので、迅速かつ的確な決断力が必要です。
さらに、個人事業主として成功するには、業務改善や新規事業の企画・構築など積極的に取り組んでいくことが求められます。
主体的かつ自発的に行動できる人も成功しやすいです。
責任感を持って行動ができる
責任感を持って行動できる人も個人事業主に向いています。ビジネスに関する決定を自分で行うことになるので、その決定に責任が生じます。
成功も失敗もすべて自分次第であるため、責任を負う覚悟がなければ個人事業を続けていくのは困難です。
責任感を持って仕事をやり抜く人は、顧客やクライアントからも信頼を得られやすいメリットがあります。
長期的な関係性を築いたり、人脈が拡大したりすることで、事業の発展につながります。
自己管理が得意
自己管理が得意な人も個人事業主に向いています。個人事業主は自分の裁量で仕事を進めることが可能です。
労働時間や日数に特に制限はなく、仕事の量も自分で決められるので、働き方の自由度に魅力があります。
ただし、スケジュールや体調、お金などのあらゆることを自分で管理しなければなりません。
複数の案件を同時に進行する場合には、それぞれの納期に注意しながらスケジュールを組んで仕事を行う必要があります。
また、仕事が滞らないように体調面にも気をつけたり、事業資金や経費、支払期限などを適切に管理したりしなければなりません。
自己管理ができる人であれば効率良く仕事を進められるので、個人事業主になっても苦労することは少ないといえます。
営業力やコミュニケーション力が高い
個人事業主には、営業力やコミュニケーション力も求められます。
個人事業主になれば自分で仕事を獲得しなければなりません。営業力があれば仕事を獲得しやすく、安定的に案件を受注できます。
また、顧客や取引先とのやりとりも発生します。今後も仕事を受注してもらうためには信頼関係を構築する必要があり、そのためにはコミュニケーションスキルが欠かせません。
相手の話を聞いて適切な言葉を返せる人は信頼関係を築きやすく、継続的に仕事を獲得できます。
自己研鑽を怠らない
自己研鑽できる人も個人事業主に向いています。社会の状況は変化が早く、臨機応変に対応しなければなりません。
変化する状況に対応したり新しいことを始めたりするには、新しい知識や技術を身につける必要性が出てくることもあります。
普段から知識やスキルを向上する努力ができる人は、変化に対して柔軟に対応できるので、長期的にビジネスで成功を収められる可能性が高いです。
専門的な知識や技術が豊富な人は同業者との差別化を図れるため、高単価の仕事を受注しやすいメリットもあります。
モチベーションを維持できる
モチベーションを維持しながら仕事ができる人も個人事業主に向いています。
すべての責任を持ってことになる個人事業主は、自分を奮い立たせて仕事に取り組んでいかなければなりません。
目標ややりがいなど自分を動かし続ける力がないと、個人事業を長く続けることは困難です。
仕事に対する情熱や目標を持ち、困難を乗り越えられるだけの高いモチベーションを維持できる人は挫折のリスクが低く、個人事業主を続けられます。
個人事業主に向いていない人の特徴

以下の特徴に当てはまる人は、個人事業主に向いていない可能性があるので注意してください。
安定志向を求めている
安定志向を求める人は、個人事業主に向いていないといえます。
個人事業主は、自分で仕事を受注して収入を得る働き方です。案件によって単価は異なりますが、仕事を受注できなければ収入を得られません。
そのため、毎月給与が出る会社員と比べて、収入面で不安定になりやすい傾向があります。
決まった給与を受け取れる働き方のほうが好みという人は、個人事業主の働き方はストレスに感じて長続きしない可能性が高いです。
主体性や決断力がない
主体性や決断力がない人も個人事業主に向いていません。
個人事業主として仕事を得て続けていくためには、主体的に行動することが求められます。
失敗を恐れて主体的に行動ができなければ仕事を獲得できず、収入を得られない可能性があります。
また、不確実な状況の中で、リスクを考慮しながら最善の選択をしなければなりません。
人の意見に流されやすい人や思い付きで行動する人は判断を誤り、事業が失敗してしまうリスクがあります。
行動力が低く、迅速かつ的確な決断ができない人はビジネスチャンスを掴みにくく挫折する可能性があるので、個人事業主に向かないといえます。
責任感や向上心がない
責任感や向上心が足りなければ個人事業主を続けていくのは困難です。
会社員には組織の一員としての責任がともないますが、その範囲は限定されています。しかし、個人事業主になればあらゆることの責任を背負わなければなりません。
また、ビジネスを取り巻く環境は変動が激しいので、学び続けていくことも大切です。
向上心が足りないと新しい知識や技術が身に付かず、同業者に後れをとってしまうことで事業が停滞するリスクが高まります。
自己管理ができない
自己管理が苦手な人も個人事業主には不向きです。
個人事業主は複数の案件を同時進行することがあります。また、書類作成や財務管理など本業以外の作業にも対応しなければなりません。
あらゆることに自分で対応する必要があるため、スケジュールや体調などの管理に徹底することが求められます。
自己管理が苦手な人は、仕事に遅延が発生したり、安定した案件を確保できず収入が不安定になりやすかったりするリスクがあります。
コミュニケーションをとるのが苦手
コミュニケーションをとることが苦手な人は、個人事業主を続けるのが難しいといえます。
個人事業主の場合、自分で案件を獲得し、顧客や取引先とやりとりをしながら仕事を進めていく必要があります。
案件獲得や顧客・取引先との円滑なやりとりを実現するためには、コミュニケーションスキルが欠かせません。
人と話すことが苦手な人は、顧客やクライアントと信頼関係を築くのが難しく、仕事を得る機会を逃してしまう可能性があります。
個人事業主になるメリット・デメリット

個人事業主になることを考えている人は、独立するメリットとデメリットを理解しておくことも大切です。
ここで、個人事業主になることのメリットとデメリットを紹介します。
メリット
個人事業主のメリットは以下のとおりです。
-
- 法人設立よりも開業手続きが簡単
- 経理などの事務負担がかかりにくい
- 利益が少ないうちは税負担がかからない
個人事業主の開業手続きは、税務署や都道府県税事務所、市町村に開業届を提出するのみと、定款の作成や法人登記などが必要な法人設立よりも簡単です。
また、法人であれば、給与計算や所得税・住民税の源泉徴収などの事務負担が発生します。
一方、国民年金と国民健康保険の加入が一般的の個人事業主であれば、このような事務負担がありません。
個人事業で得た利益には所得税が発生しますが、利益が少ないうちは法人税よりも税率が低く税負担が少ないこともメリットです。
今後事業が軌道に乗って収益が増えるようであれば、法人化するという選択肢もあります。
なお、開業時に青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告が行えます。青色申告の場合、要件を満たせば最大65万円の特別控除が適用され、節税効果によって税負担を減らすことが可能です。
デメリット
個人事業主になるデメリットは以下のとおりです。
-
- 社会的な信頼が得られにくい
- 確定申告が必要になる
- 社会保険料が全額自己負担になる
個人事業主は、収入が不安定になりやすく、会社員よりも社会的な信頼を得られにくい傾向にあります。
そのため、金融機関から融資を受ける際やクレジットカードを作成する際に不利になる可能性が高いです。
また、年末調整がある会社員とは異なり、個人事業主は確定申告をしなければなりません。
毎年自分で所得税の計算を行い、書類を作成して期限内に税務署への申告と納税が必要になります。消費税の課税事業者であれば、その分の確定申告と納税も必要です。
なお、年金や健康保険の社会保険料が全額自己負担となる点にも注意してください。
会社員は会社が社会保険料の半額を負担してくれますが、個人事業主は全額自分で支払うことになるので、金銭的な負担が大きくなる傾向にあります。
個人事業主の平均年収

個人事業主の平均年収は、業種や地域、経験年数、顧客基盤などの要因によって大きく異なります。
国税庁の調査によると、日本の個人事業主全体の平均所得は約300万円程度とされていますが、この数字だけで実態を把握することは難しいといえるでしょう。
IT・Web関連の個人事業主はプログラミングやデザイン、マーケティングなどの専門スキルを活かし、比較的高収入を得ている傾向があります。
年収500万円から1,000万円以上を稼ぐフリーランスも珍しくありません。
一方、小売業や飲食業などは固定費や仕入れコストがかかる上に競争も激しく、年収200万円前後の事業主も多く存在します。
また、開業初年度は顧客基盤の構築や設備投資などにコストがかかるため収入が低くなりがちですが、事業が軌道に乗るにつれて収入が安定する傾向です。
個人事業主は売上げから必要経費を差し引いた所得に対して課税されるため、同じ売上高でも経費率によって手取り収入は大きく変動します。
安定した収入を確保するためには、特定分野での専門性を高めることや、固定客や継続案件の獲得、複数の収入源を持つことなどが重要です。
なお、繁忙期と閑散期の収入格差を埋めるための資金計画や、将来的な事業拡大の方向性を考えることも、個人事業主として長期的に安定した収入を得るためには欠かせない要素といえます。
個人事業主に必要なスキルとは

個人事業主として成功するためには、専門技術だけでなく経営者としての多面的なスキルが求められます。
専門分野のスキル
個人事業主として成功するためには、自身の事業の核となる専門スキルが最も重要です。プログラミング、デザイン、ライティング、コンサルティングなど、顧客に提供する価値の源泉となるスキルを常に磨き続ける必要があります。
市場の変化や競合の動向を見据えながら、継続的な学習を怠らないことが成功への第一歩です。
営業力
どれほど優れたスキルを持っていても、それを必要とする顧客と出会い、仕事を獲得できなければ収入には結びつきません。
自分の価値を効果的に伝え、信頼関係を構築する能力が重要です。営業活動は苦手意識を持つ方も多いですが、個人事業主にとっては避けて通れない重要なスキルです。
経営者視点
事業を継続させるためには、経営者としての視点も不可欠です。売上・経費管理、税務、資金繰りなどの財務スキルは事業継続の基盤となります。
特に確定申告や経費計上のルールを理解し、適切に対応することは個人事業主にとって必須です。
時間管理能力
締め切りが異なる複数の案件を同時に進行させる場合も多く、効率的なスケジュール管理ができなければ機会損失や信用低下につながります。
優先順位の設定や集中力の維持など、時間を味方につける工夫が求められます。
変化対応力
市場ニーズや技術トレンドの変化を敏感に察知し、自分のサービスや価格設定を適宜調整できる判断力も必要です。
固定観念にとらわれず、常に新しい可能性を探る柔軟性が長期的な成功につながります。
メンタル管理
不安定な収入や孤独な労働環境など、個人事業主特有のストレス要因に対処しながらモチベーションを維持し続ける精神力は、長期的な成功には欠かせません。
自己管理とセルフケアのバランスを保ちながら、持続可能な働き方を確立することが重要です。
個人事業主になるためのステップ

個人事業主となって事業を始めるのであれば、開業までの流れを知って準備をすることが大切です。
ここで、個人事業主になるためのステップについて紹介します。
1.業種や開業場所などを決める
開業の手続きを行う前に、業種や開業場所などを決めなければなりません。
個人事業で始められる仕事はいろいろあるため、まずはどのような業種で開業するのかを決めます。
業種によっては、専門知識・スキルや資格、免許などが必要です。自分のやりたい事業を始めるためには、何が必要なのか把握しておくことが求められます。
すでに実績や経験がある業種で開業するのもおすすめです。
また、ビジネスを展開していくためには、拠点も必要です。
自宅を職場として活用できるケースもあれば、専用の事務所や店舗が必要になるケースもあります。
ただし、立地によって客層は異なります。自分の事業と客層がマッチする場所を選ぶ必要があるので、事前にどこで開業するのか決めておくことも大切です。
2.事業の目的や資金計画などの事業計画を立てる
次に、業種や開業場所が決まれば事業計画を立てます。
事業計画とは、事業の目的な内容、展開方法、資金計画、マーケティング戦略などをまとめた計画のことです。
具体的な目的や運営方法、収益の見込みなどを明確にしておくことで、事業で直面するリスクを把握し、対策を講じられます。
無計画なまま開業しても、思い描いた結果を得ることは困難です。
具体的かつ実現可能な事業計画を立てて事業を進めていくことで、運営方針がぶれるリスクが減り、円滑に展開できます。
なお、事業計画書は事業の全体像や収益の見込みなどを客観的に把握できるものであるため、金融機関からの資金調達などでも必要になります。
3.クレジットカードや社会保険などの手続きを行う
開業手続きを行う前に、クレジットカードやローン契約、社会保険などの手続きを行うことをおすすめします。
個人事業主になると社会的信用が下がりやすく、クレジットカードの新規作成やローン契約が不利になる可能性があります。
そのため、事業用のクレジットカードを作成したりローン契約したりする場合には、開業前に契約しておくと安心です。
また、会社を辞めて個人事業主になる時は、国民年金や国民健康保険への加入が必要となります。退職後は速やかに手続きを行ってください。
4.開業に関する手続きを行う
事業計画を立てたり、開業資金を確保できたりすれば、いよいよ開業手続きの段階に入ります。
開業日を決めて、その日から1カ月以内に管轄の税務署に開業届を提出してください。
開業届には、事業主の情報や事業内容、開業日などを記載します。
土地や建物を使って事業を行う際は、所在地図や賃貸契約書の写しも必要になるので、事前に用意してください。
また、開業届を提出する時に青色申告承認申請書を提出するかどうかを検討してください。
白色申告の場合、比較的簡単に確定申告ができますが、税制優遇措置を受けられません。
今後、収益の上昇によって所得税の負担が増える可能性があれば、最大65万円までの特別控除が適用できる青色申告を検討することをおすすめします。
まとめ・個人事業主に向いているなら開業の準備を始めよう
主体性や決断力、営業力、自己管理能力など、事業を展開していく素質があれば個人事業主に向いており、ビジネスで成功しやすいです。
反対に、安定志向を好む人や向上心がない人は、個人事業主よりも会社員の働き方のほうが向いているかもしれません。
個人事業主として働きたいのであれば、必要な知識・技術・ノウハウを身につけた上で検討してみてください。
この記事を読んで「個人事業主としてやっていきたい」と思われた方は、次なるステップとして「どのような準備が必要か」を把握しましょう。その際にぜひこちらの「創業カレンダー」をご活用ください。起業予定日の前後1年間のやることリストがカレンダー形式で把握することができます。まだ具体的に日程が決まっていなくとも、どんな準備が必要なのかを把握するために使うこともできます。無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)