起業と独立、向いてるのはどっち?判断ポイントをチェックリストで解説
働き方や目的を確認しよう

「独立と起業って、どう違うの?」「自分にはどちらが向いているのだろう?」そのような疑問を感じている方に向けて、この記事では「独立」と「起業」の違いをわかりやすく整理し、それぞれの特徴や向いている人のタイプを解説します。
最後にはチェックリストもご用意していますので、自分に合った選択肢を見つける参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
そもそも「独立」と「起業」の違いとは?

自分の向いている働き方を理解するためにも、まずは独立と起業の違いから解説していきます。
独立=既存スキルを活かして「ひとりで稼ぐ」
独り立ちと言い換えられるように、独立とは所属していた組織から離れて自分の力のみで生計を立てることを意味します。
個人事業主に転身する時に使われる用語で、以下のような自営的な働き方を指します。
-
- フリーランス
- 業務委託
- 代理店
起業=新しい仕組み・ビジネスモデルを「ゼロから作る」
新しく事業をスタートさせることを起業と意味し、主に法人設立をともなう独立を指す用語です。
新しい仕組みやビジネスモデルをゼロから作ることで、「起業=法人化」と考えるとわかりやすいでしょう。
近年ではスタートアップ企業やベンチャービジネスなど、起業をする若者が増えています。
ただし、起業したからといってすぐに安定した収入が得られるとは限りません。
クライアントを得るためにこまめに営業活動を実施し、事業が失敗したとしても経済的に困らないよう、余裕を持って資金を用意しておくことが起業する上で大切です。
「独立」と「起業」の共通点と違い
独立と起業の共通点と違いをまとめると、以下の表のようになっています。
| 共通点 | ・新しく事業を始めること ・自分の力で生計を立てる ・自由度の高い働き方ができる |
| 違い | ・独立:勤めていた会社などから離れて開業すること ・起業:新規の事業を始める、法人設立をともなう独立 |
どちらも新しく事業をスタートし、自分の力で生計を立てることは共通している箇所です。
企業のもとで働いているわけではないので、出社時間や退社時間、休日などを比較的自由に決められる点も共通点といえます。
しかし、前述したように独立は勤めていた会社から離れて個人事業主として開業することを意味していますが、起業は法人設立をともなう独立を指します。
個人事業主になるプロセスを経ないことが特徴となり、新しいビジネスを立ち上げて市場に新しいものをもたらす働き方です。
独立と起業の例

ここからは、独立と起業それぞれの働き方について、例を挙げて解説していきます。どういった働き方ができるのか理解するためにも参考にしてください。
独立の例
まずは、自分が持っているスキルを活かして企業や組織から独立する場合に考えられる働き方の例を紹介します。
営業職からフリーランス営業代行に
企業で働いて培った営業スキルを活かして独立したいと考える人もいるかもしれません。そんな時には営業代行としてフリーランスで働くことを検討してみてください。
「営業人材が足りない」と悩む企業は多いですが、人材を雇用するとなれば時間やコストがかかり、スキルを持っていなければ教育も必要です。
しかし、業務委託としてフリーランスの営業代行を活用すれば、時間をかけずに売上拡大に貢献してくれます。
多くのメリットを受けられるので、営業活動を業務委託する企業も増えています。そのため、独立をすればすぐに仕事を獲得できる可能性も高いです。
フリーランスの営業代行の主な業務内容は以下の通りです。
-
- 見込み客へのアプローチ
- 既存客へのフォロー
- セミナーやイベント時の集客サポート
- リファラル営業を実施し、商品の販売
- 営業戦略の考案
美容師が店舗から独立して自分のサロンを開業
美容師の資格があり、現在店舗に勤めている場合は独立をして自分のサロンを立ち上げることが可能です。
現在持っているスキルを独立後もそのまま活かすことができます。
自分のサロンを開業する場合は、従業員として一定年数勤務し続け、キャリアを積んでから独立するケースが一般的です。
店舗を開業するには初期費用がかかりますが、自宅の一部をサロンにするほか、シェアサロンという選択肢もあります。
独立となれば、自分が思い描いているコンセプトに沿ってお店作りができるます。
内装やインテリアのデザインだけではなく、提供するメニューやターゲットとなる客層まで自分の好みやビジョンに沿って決められる点がメリットです。
ITエンジニアの業務委託化
ITエンジニアとして働いている人が独立したいと考えるきっかけは以下の通りです。
-
- 収入や残業が多いなど、待遇に不満がある
- 時間や場所に捉われずに働きたい想いがある
- 仕事に対するやりがいを求めている
勤めている企業に対して何らかの不満があると、独立を考えるITエンジニアは多いです。
独立をすれば、クライアントとなる企業と業務委託契約を結んで働くことで、受託報酬や相談料を受け取って稼ぐことが可能になります。
ITエンジニアであれば、パソコンやネット環境があればどこでも仕事ができるので初期費用を抑えて独立できる点が魅力です。
営業や経理業務など、雑務が増える部分に注意が必要ですが、培ったスキルを活用して働くことができ、働く時間や休日も自分の好きなように選べます。
クライアントを獲得して安定した収入を確保するためにも、専門性を高め、実績を増やして信頼性アップを図ってください。
デジタルコンテンツの販売
自分で制作したデジタル形式のコンテンツをオンライン上で販売するビジネスモデルをデジタルコンテンツ販売といいます。
ダウンロードが可能なデータやオンライン上で利用できるサービスとなり、以下のようなものが代表的なデジタルコンテンツです。
-
- オンライン講座
- Eブック
- 写真素材
- イラスト素材
- 動画
- 音楽やサウンド素材
- テンプレートやツール
特殊な機材を使用せずに技術さえあれば、普段使用しているスマートフォンやパソコンでもコンテンツを作成できます。
生産や発送といった業務も必要なく、在庫を抱える心配もありません。一度制作すれば繰り返し販売できるので、スケールメリットが期待できるビジネスです。
デジタルコンテンツの販売では、専用のプラットフォームを活用するのが一般的です。
手数料や販売形態、集客など、様々な点を考慮して、自分に合う方法を選んで販売を目指してみてください。
起業の例
次に起業して働く場合の例を紹介していきます。
Webサービスを立ち上げて法人化
Webやインターネットを利用して提供するサービスを総称してWebサービスといいます。
自分でWebサービスを立ち上げて法人化する方法もあり、低予算でスタートできる点がメリットです。
パソコンやネット環境があればスタートできるので、起業のハードルが低いです。無形の商材を取り扱うので、在庫リスクがない点も魅力になります。
Webサービスを立ち上げて起業する際の収益化方法は以下の通りです。
-
- 広告収入
- サブスクリプション
- 電子商取引
- 課金制
Webサービス内に広告を載せれば、表示された回数やアクション回数によって報酬を受け取ることが可能です。
また、サブスクリプションサービスを提供すれば、1カ月や半年、1年など、ユーザーに対して一定期間ごとのサービス利用料を請求し、解約されない限りは安定した収入を確保できます。
電子商取引はEコマースのことを指し、Web上で商品の取引場所を提供することを指します。
出展料や手数料で収益を得る仕組みです。課金制のサービスを提供すれば、サービス内の機能を有料化して収入を得ることもできます。
商品開発・クラファンからのブランド立ち上げ
商品開発やブランドの立ち上げを検討していても、資金調達に問題があればクラウドファンディングの活用を検討してみてください。
商品開発やブランド展開にかかる資金を、インターネットを通じて募れる仕組みをクラウドファンディングといい、購入型や寄付型、ファンド型や融資型といった種類があります。
多くの支援者から出資を受けられれば、自己資金がない状態でも起業することが可能です。
マーケティングとしても活用でき、商品やブランドの魅力をアピールでき、宣伝にもなります。
インフルエンサー
趣味のSNSや動画投稿で広告収益が大きくなった時は、インフルエンサーとして法人化することが可能です。
法人化すれば、税額を大幅に下げることができるだけではなく、社会的信用も得られやすくなります。経費にできる幅も広がるので、様々なメリットを受け取れます。
安定した収入を確保するためにも、質の高いコンテンツを制作し続けるだけではなく、フォロワー数を増やすためにもコラボやキャンペーンの実施、関連性の高いグループやコミュニティへの参加などを積極的に行ってみてください。
副業の事業規模が拡大して法人化(週末起業)
起業となれば会社を退職する必要があると考える人もいますが、実際には副業として週末起業をする人も一定数います。
週末の空いた時間を使って起業する方法となり、リスクを抑えた起業が可能です。
副業の事業規模が大きくなると、法人化したほうが税金面のメリットがある点を理解しておいてください。
年間利益が600万円以下だと法人化しても税金面でのメリットが少ないです。
しかし、600万円以上の利益が生まれたら、法人化をして給与所得控除を利用したほうが所得税を抑えられます。
また、本業と両立できる業種を選び、目標を立てながら計画的に業務を進めることで、心身に負担をかけずに業務を遂行できます。
独立と起業のメリット・デメリット
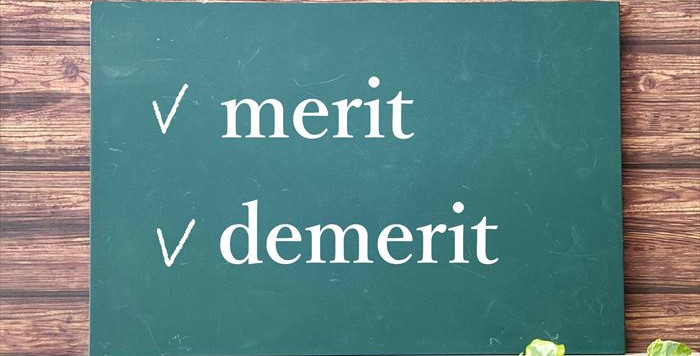
ここからは、独立と起業それぞれのメリット・デメリットを解説していきます。
独立のメリット・デメリット
まずは、企業を退職して独立した場合のメリット・デメリットです。
メリット
企業から独立し、個人事業主になるのは法人化に比べると手続きが簡単な点が魅力です。
法人化の場合は、定款の作成や登記をするまでに早ければ1週間、長ければ1カ月程度かかってしまいます。
しかし、個人事業主であれば都道府県税事務所や税務署、市町村に開業届を提出するだけで開業できるので手軽です。
また、自由度が高い点も魅力です。
独立すれば企業に在籍しているわけではないので、自分の好きな時間に仕事をスタートできます。
定年も決まっていないので、仕事が受注できれば年齢を問わず長く働き続けられる点もメリットです。
デメリット
独立した場合は、社会保障が少ない点に注意してください。
病気や怪我をした場合、傷病手当や出産時の手当もないため、自分で貯蓄をしておかないと生活面で困ることがあります。余裕を持って資金を確保することが大切です。
また、所得が増えると税額が増える点にも注意してください。累進課税となるため、所得額が増えると税率も上がっていきます。
個人事業税が課せられる点も覚えておいてください。
起業のメリット・デメリット
次に、起業する際のメリット・デメリットです。
メリット
起業をすれば、会社員時代にはない税制優遇が受けられるようになります。
青色申告を行えば、赤字分を翌期以降に繰り越せるだけではなく、青色申告特別控除によって最大で65万円を所得から差し引けるので節税も可能です。
前述したように600万円以上の利益が出れば、節税メリットも得られます。
会社員として働く場合と比較すると、収入が高くなる可能性がある点も魅力です。
会社員の場合、成果を出しても昇給の上限があるので思っていたよりも収入が得られない可能性があります。
しかし、起業をすれば利益を出した分だけ青天井で還元されるので、会社員時代よりも収入アップする可能性があります。
利益は自分の収入に直結するので、モチベーションを維持しながら働き続けることが可能です。
デメリット
起業する場合、法人登記するための費用がかかります。事業年度ごとに決算を行う必要もあり、会社をたたむ際には清算の手間がかかります。
あらゆる面で会社員時代や個人事業主と比較すると、手間がかかる点に注意してください。
税制や行政上の手続きが多くなるので、税理士や経理担当として働く人材を雇う必要も出てくるため、コストがかかる点もデメリットです。
【チェックリスト】独立と起業のどちらが自分に向いている?

最後に、独立と起業のどちらが自分に向いているか判断するために役立つチェックリストを紹介していきます。
当てはまる項目をチェックし、自分に合う働き方を見出すために役立ててください。
まずは、独立に向いているタイプは以下の通りです。
-
- 安定した収入よりも自由を重視する
- 今すぐ商品化できるスキルがある
- チームで働くより一人が好き
- 個人で完結できる範囲で広げたい
- 自分の専門スキルや資格を活かして、顧客に価値を提供したい
次に、起業に向いているタイプは以下の通りです。
-
- 社会課題の解決やイノベーションなど、より大きなビジョンを掲げたい
- ゼロから新しい商品・サービスを作り、事業として大きく育てたい
- チームを作って仲間と一緒に大きな挑戦をしたい
- 将来的に資金調達や組織化を考え、ビジネスモデルを拡張したい
まとめ|独立も起業も「目的とスタイル」で選ぶのが正解
独立が向いているのか起業が向いているのかわからずに悩んでいる人もいるでしょう。
しかし、「どちらが正しいか」ではなく、「自分に合っているかどうか」を考えることが大切です。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを把握し、判断してみてください。
「起業したい」「独立を考えている」という方の中には、「何をどう進めたらいいかわからないから先に進めない」という方も多いのでは。そんな方はぜひ『創業手帳』をお読みください。起業に必要な最低限のノウハウをこの一冊にまとめています。無料でお届けしますので、ぜひご活用ください。
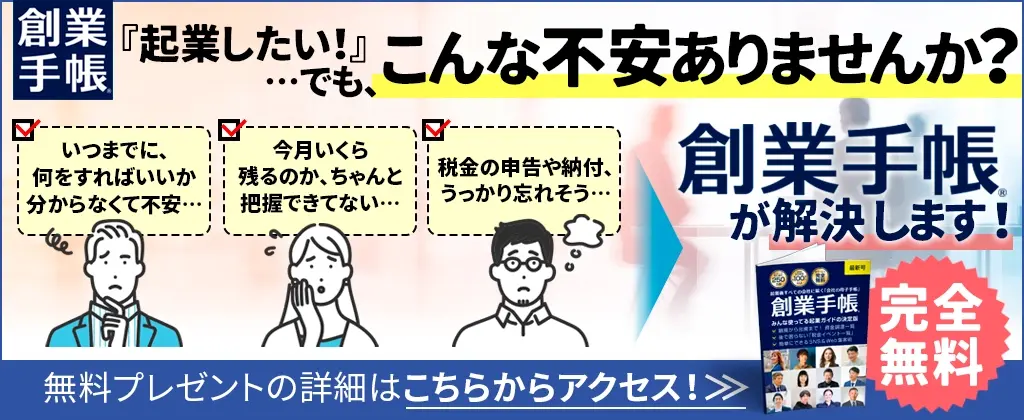
(編集:創業手帳編集部)




































