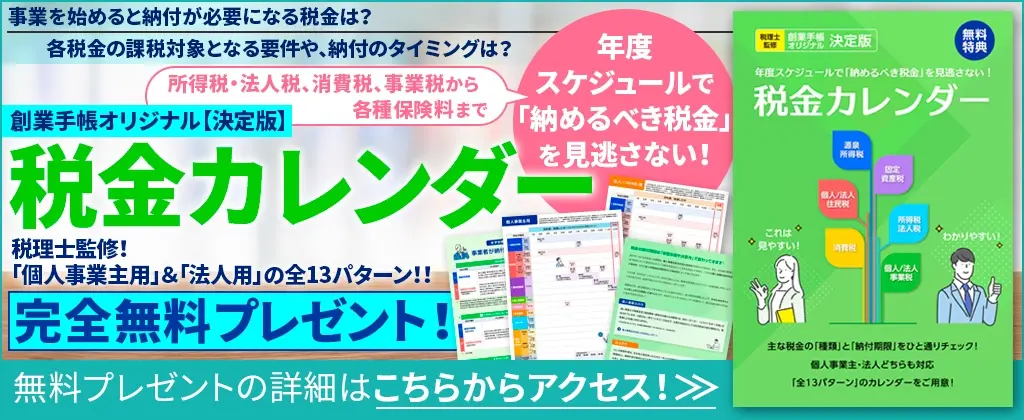会社を相続すると税金がかかる!納める税金の種類と税負担を抑える方法について解説
相続で会社の株式にかかる税金を事前に把握して対策しよう

会社を経営していた親が亡くなり、その会社を引き継ぐことになった場合、会社の相続によって税金が発生するのか不安に感じてしまうものです。
結論からいえば、会社を相続することによって様々な税金が発生する可能性があります。
そこで今回は、会社を相続した場合に納める税金の種類と、税負担を少しでも抑える方法について解説していきます。
現在会社を相続して悩んでいる方はもちろん、将来的に会社を相続する可能性がある方も、ぜひ参考にしてみてください。
税金については相続税以外にも様々な税金があり、いつ支払えばいいのか忘れがち。税金の支払いを忘れてしまうと、延滞税が更にかかってしまうケースもあります。それを防ぐために創業手帳では「税金カレンダー」を作成しました。様々な税金について、いつ発生するのかをカレンダー形式で確認することができるアイテムです。無料でお配りしていますので、是非お役立てください。
この記事の目次
会社の相続とは?

そもそも会社の相続とは、株式(経営権)を後継者に渡すことを指します。
会社が所有する財産はあくまで会社のものであり、経営者個人が所有する財産とは異なるため相続されません。
また、被相続人が社長や取締役などに就いていた場合、後継者がそのまま地位を相続することもできません。
後継者に渡す株式は、株主総会における議決権でもあります。株式を3分の2以上持っていれば、会社経営に関するほとんどの事項に対して決定権を持てるようになります。
株式を集める方法
後継者は株式を相続することになりますが、相続人が複数いる場合は株式の分散によって後継者の経営支配力を失わせないために、株式を集めておく必要があります。
株式を集める方法としては、以下の3点が挙げられます。
株式を買い取る
後継者以外の相続人や株主が3分の1以上の株式を保有している場合、後継者に集中させるために株式の買い取りを行うこともあります。
買い取りによって株式の割合を増やせますが、その分コストがかかってしまいます。
遺言書を作成する
遺言書を事前に作成しておくことで、遺産分割時に発生しやすい争いを防ぐことも可能です。
遺言書を作成する際は、後継者に株式を集中させること、もしほかに相続人がいる場合は株式ではない別の財産を渡すようにすることで、遺留分の配慮も可能となります。
生前贈与で後継者に事業承継させる
株式を3分の2以上後継者に集中させるために、生前贈与を行っておくという方法もあります。贈与契約書を結び、経営権と共に自社株式の引き継ぎも行ってもらいます。
会社の株式を生前贈与で後継者に渡しておけば、確実に経営権を得るために必要な株式を渡すことも可能です。
会社を相続する際に発生する税金

会社を相続する際、以下の税金が発生します。それぞれの税金について詳しく解説します。
相続税
相続税は、被相続人から財産を相続した際、受け取った分の財産に発生する税金です。株式を相続した場合、相続税の対象になるのは相続時の取得金額です。
相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)を基準に評価額を算定します。
評価額を算定したら、相続税の速算表に当てはめて税率と控除額を確認しておきます。
もし、正味の遺産額(不動産や預金などの財産から借入れ金・未払い金などの債務を差し引いたもの)が基礎控除額を下回っていた場合、相続税はかかりません。
贈与税
贈与税は、個人から無償で財産の贈与を受けた場合にかかる税金です。贈与税を納めるのは財産を受け取った側です。
贈与税額は1年間(1月1日~12月31日)で贈与として受け取った財産の合計から、基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率をかけて計算します。
18歳以上の人が直系尊属から受けた財産の場合は「特例贈与財産」、それ以外の贈与財産には「一般贈与財産」に区分され、該当する区分の税率をかけて算出することになります。
不動産の所有権移転にかかる税金
相続税・贈与税以外にも、会社を相続した際に不動産の所有権を移転することになった場合は、登録免許税や不動産取得税の課税対象です。
登録免許税は所有権の登記を行う際に納める税金です。対象の土地・建物の固定資産税評価額に、税率をかけて計算します。
不動産取得税は土地や建物の購入・建築などを行った場合、登記の有無を問わず納めなくてはならない税金です。
基本的に相続では発生しないものの、生前贈与を受けた際には課税されることになります。
相続で法人税・消費税はかからない
会社を相続または贈与を受けた際には上記の税金がかかってきますが、法人税や消費税などは発生しません。
ただし、事業譲渡で譲渡価額と譲渡対象の資産・負債に差額が生じている場合は法人税がかかってしまいます。
また、消費税の場合も事業譲渡や現物出資だと個々の資産を譲渡したものと判断され、課税される可能性が高いです。
株式の相続税評価額を計算する方法

株式にかかる相続税・贈与税は、株式の相続税評価額を求めた上で納める税額を算出していきます。
ここでは、上場企業と非上場企業別に相続税評価額を求める方法についてご紹介します。
上場企業の株式を相続する場合
上場企業の株式を相続した場合、毎日の株価変動が考慮され、以下4つの金額のうち最も低いものが適用されます。
-
- 相続開始日の終値(取引所の営業日ではなかった場合、最も近い日の終値を採用)
- 相続開始月の毎日の終値をもとに計算した平均額
- 相続開始日の前月で毎日の終値をもとに計算した平均額
- 相続開始日の前々月で毎日の終値をもとに計算した平均額
過去の株価はインターネットから確認できるのはもちろん、証券会社から残高証明書を発行してもらう方法もあります。
非上場企業の株式を相続する場合
非上場企業の株式を相続する場合、会社の規模や経営権を持つかどうかによって評価方法も異なります。主な評価方法は以下の3つです。
それぞれの評価方法について解説します。
1.純資産価額方式
純資産価額方式とは、主に中小企業の株式を評価する際に用いる方式です。会社の清算(解散)時に純資産はいくらになるかで評価していきます。
計算式は以下のとおりです。
1株あたりの純資産価額=(相続開始時に会社を売却した場合の利益-法人税相当額)÷相続開始時の発行済み株式数
会社の総資産から負債や清算で生じた含み益にかかる法人税を差し引き、発行済み株式数で割ることで、1株あたりの純資産価額を割り出せます。
2.類似業種比準方式
類似業種比準方式とは、類似する業種の中で上場する企業の株価を参考に、1株あたりの評価額を決める方式です。
比較する上場企業の規模的に、類似業種比準方式は大手企業に用いられる傾向にあります。
非上場企業の株式を評価する際には、利益・純資産・配当を比較して株価を計算します。計算式は以下のとおりです。
1株あたりの評価額=類似業種における株価×(配当比準割合+利益比準割合+純資産比準割合)÷3×斟酌率
斟酌率とは、会社の規模に応じて調整するためのものです。大会社は0.7、中会社は0.5、小会社は0.5が適用されます。
3.配当還元方式
配当還元方式とは、過去2年間の配当金を10%で割り戻し、非上場企業の株式価額を求める方式です。同族株主以外の株主が株式を取得した場合、配当還元方式が採用されます。
配当還元方式の計算式は以下のとおりです。
配当還元価額=(株式にかかる年配当金額÷10%)×(株式1株あたりの資金額÷50円)
配当還元方式は株価の評価方法として例外的なものであり、通常は純資産評価方式または類似業種比準価額方式で計算します。
また、配当還元方式で計算すると、株価は低くなるように設定されています。少数株主だと非上場株式を持っていた場合でも、経営支配力がないためです。
会社の相続にかかる税金を抑える方法は?
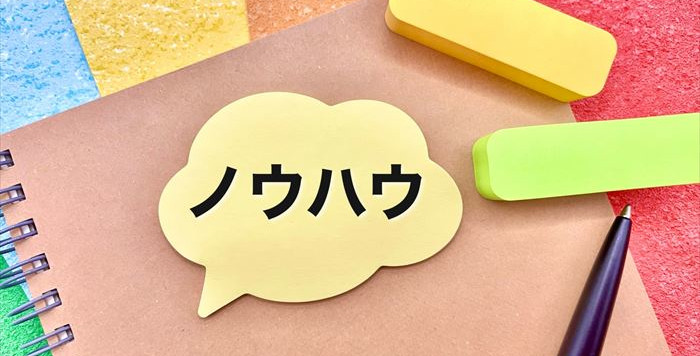
株式の相続によって多額の税金が発生してしまうと、後継者の資産状況が悪化し、会社にも悪い影響を与えてしまう恐れがあります。
このような事態を回避するためにも、税金対策は必須です。
そこで、会社の相続にかかる税金を少しでも抑える方法について解説していきます。
株式の評価額を下げて対策する
相続税の負担を抑えたい場合、財産の額に応じて納める税額も上がっていくため、課税される財産の評価額を下げることで節税につながります。
株式の評価額を下げる具体的な対策方法は、以下の4つです。
先代経営者に死亡退職金を支払う
死亡退職金とは、本来亡くなった人に支給されるはずだった退職金を、家族などが受け取れる制度です。
先代経営者が亡くなった際に数千万円規模の死亡退職金を支給することで、会社の純資産を減らすことができ、財産の評価額を下げられます。
ただし、死亡退職金はみなし財産に該当し、受け取った家族が相続税を納めることになるので注意が必要です。
含み損のある資産を売却する
会社が保有する資産のうち、含み損のある資産を売却することでも財産の評価額を下げられます。
例えば会社が利用していない土地に帳簿上5,000万円の価値があった場合、2,000万円で売却すれば3,000万円分の純資産が減ることになります。
ただし、購入してから3年以内に売却しようとすると、帳簿価額のままで計算しなくてはなりません。
投資用の不動産を購入する
金融機関から借入れた資金を使って投資用の不動産を購入した場合、負債の借入れ金は額面のまま評価されますが、不動産の相続税評価額に関しては実際に購入した金額よりも下がるのが一般的です。
そのため、双方の差額分が純資産価額の評価額から減らせることになります。
なお、こちらも購入してから3年以内は実際に購入した金額で計算することになります。
3年が経過すると土地は路線価・倍率方式など、建物は固定資産税評価額の相続税評価額で評価されます。
さらに土地は貸家建付地、建物は貸家としての評価減が適用され、さらに評価額を減らすことが可能です。
減価償却費を計上する
減価償却とは、時間が経つにつれて資産の価値が減少するとみなし、その資産の耐用年数にわたって購入費用を毎期均等に配分することを指します。
例えば、オフィスで使用するPCやコピー機などです。
減価償却の対象となる資産は購入時に全額経費計上されず、毎期配分することになるためその分利益が減って節税につながります。
会社の設備入れ替えを検討している際は、会社の相続が行われる前に減価償却費を計上しておくと、税額を抑えることも可能です。
株式配当金の引き下げを行う
未公開株だと自社株の配当率が高い傾向にあるため、配当金の引き下げによって株式の評価額も下げられます。
特に経営者がすべての株式を保有していた場合、配当金の引き下げは容易に行うことが可能です。
ただし、配当金の引き下げを行わなくてもすでに配当金が低かった場合、高い効果は見込めないのでほかの方法を試してみてください。
会社の相続をスムーズにするためにできること

会社の相続にはトラブルも付き物です。お金や譲渡割合などのトラブルを回避しつつ、スムーズに相続するためには、どのような対策を行っておくと良いのでしょうか。
最後に、会社の相続をスムーズに行うための方法をご紹介します。
経営承継円滑化法を活用する
経営承継円滑化法とは、中小企業のスムーズな事業承継を支援する目的で施行された法律です。
例えば後継者が会社を相続する際に、遺留分や会社の資産に対する税負担などによって、相続が困難になる可能性もあります。
こうした問題に対応するために、経営承継円滑化法では3つの支援措置を設けています。
-
- 事業承継税制
- 民法の特例
- 金融支援
経営承継円滑化法を活用することで、中小企業の株式が遺留分などで分散してしまうことを防ぐことも可能です。
なお、遺留分の特例を受けるためには、推定相続人全員から合意を得た上で、経済産業大臣の確認と家庭裁判所から許可を得る必要があります。
税制や補助金を活用する
会社を相続する場合、相続税や贈与税などの税金に加えて手数料なども発生していきます。
また、一般的な親族・従業員が事業を承継するとなると資金調達が難しくなるなどの問題も起こり得ます。
そこで、事業承継に活用できる税制や補助金について知っておくことも大切です。
例えば中小企業庁が創設した「事業承継補助金」は、事業承継を機に経営革新・事業転換などを行う中小企業に対して、経費の一部を補助してくれる制度です。
申請期間が限られているものの、毎年応募することができます。
また、日本政策金融公庫でも中小企業向けの融資制度や再建資金(企業再生貸付)、事業再生支援資金などが活用できます。
相続をするまでに会社で税金やトラブルの対策をしておこう
会社を相続する場合、相続税や贈与税などの税金がかかることになります。また、後継者が安定した経営権を引き継ぐために、決定権が持てる3分の2以上の株式取得が必要です。
税金対策やトラブルを回避するには、経営者が存命している間に対策を進めておくことが重要となります。
相続開始後でも対策は可能ですが、できることが限られてしまうので、なるべく早めに対策を練っておくと良いです。
(編集:創業手帳編集部)