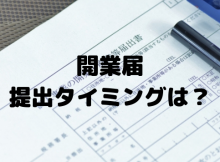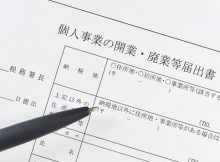開業届の出し方がよくわかる!必要な書類やよくある質問も解説
開業届の出し方を確認しておこう

個人事業をはじめるにあたって、税務署に開業届を提出する必要があります。
提出しなくても特に罰則はありませんが、青色申告などが利用できない可能性があるので、事業を開始する際は開業届を忘れず提出してください。
開業届の出し方は複数あり、自分に合った方法で提出できます。そこで今回は、開業届の出し方や必要な書類、同時に提出しておくとよい書類について紹介します。
開業届に関するよくある質問も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
開業届の3つの出し方

開業届は、個人事業主の納税地にある税務署に提出することになります。出し方は3パターンあるので、それぞれの提出方法について解説します。
税務署の窓口
近くに税務署があれば、窓口に直接持って行って提出できます。近くの税務署がどこにあるかは、国税庁の公式サイトから検索可能です。
窓口の場合、提出時に記入漏れやわからない部分があったとしても、職員の人に確認しながらその場で直すことができるので、ミスを抑えられます。
デメリットは、開庁時間に合わせて窓口に行かないといけないことです。税務署は平日8時30分~17時まで開庁しています。
平日の日中に行けない人は窓口提出が難しいかもしれません。
ただし、税務署には時間外収受箱が設置されているので、そこに投函すれば時間外や休日も提出が可能です。
郵送代がかからないので、近くに税務署がある時は時間外収受箱の活用をおすすめします。
郵送
窓口に行けない場合、郵送で税務署に提出する方法もあります。
後述するe-Taxでの提出ではマイナンバーカードが必要ですが、郵送はマイナンバーを確認できる書類があれば提出可能です。
ただし、郵送代が発生する点に注意が必要です。
切手を貼った返信用封筒を同封することで、開業届の控えを返送してもらえます。今までは控えに税務署の収受日付印の捺印がありましたが、2025年1月1日から廃止されました。
当分の間は、返信用封筒を同封すれば収受した日付と税務署名が記載されたリーフレットを同封されます。
e-Tax
e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、国税に関する各種手続きをインターネットから行えるシステムです。
開業届だけではなく、所得税や消費税などの申告や法定調書の提出などにも活用できます。
この方法で開業届を提出するためには、マイナンバーカードとそれを読み取るためのICカードリーダライタ、もしくは読み取りに対応したスマートフォンが必要です。
また、手続きにマイナンバーカードを発行する際に登録した利用者証明用電子証明書パスワードと券面事項入力補助用暗証番号も必要になります。
e-Taxの場合、ソフトから開業届の作成・提出が可能です。
郵送と違って郵送代がかからず、本人確認書類の添付も不要なため、マイナンバーカードと読み取る機器があればおすすめの提出方法です。
開業届の提出時に必要な書類

開業届を提出するにあたって、いくつか書類の準備が必要です。ここで、提出時に必要な書類を紹介します。
個人事業の開業・廃業等届出書
開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。税務署や市区町村役場の窓口、国税庁のホームページで入手できます。
税務署の窓口や郵送で提出する場合、手書きした届出書やPCで作成し、印刷した届出書を用意してください。
e-Taxで申請する場合、電子化した開業届が必要です。e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーで、必要事項を入力するだけで簡単に届出書の作成できます。
マイナンバーカードやマイナンバーがわかる書類
開業届にはマイナンバーを記載する項目があります。そのため、マイナンバーカードやマイナンバーがわかる書類が必要です。
マイナンバーがわかる書類には、通知カードや番号が記載された住民票などが挙げられます。
また、e-Taxで提出する場合はマイナンバーカードが必須です。まだ持っていない人は事前に発行しておいてください。
本人確認ができる書類
開業届を提出する際に本人確認が発生するので、身分を確認できる書類が必要です。
マイナンバーカードがあれば、顔写真や氏名、住所などの身元を確認できる情報が掲載されているので、1点で本人確認ができます。
しかし、マイナンバーカードを所持していない時は、マイナンバーを証明できる通知カードや住民票などの書類に加えて、運転免許書・パスポートといった身元を確認できる書類の計2点が必要です。
窓口では2点を提示し、郵送の場合はコピーして同封してください。e-Taxから提出する時はマイナンバーカードを使用するため、本人確認書類の添付は不要です。
開業届と同時に提出しておくとよい書類

ビジネスをはじめるにあたって、状況によっては開業届以外の書類も提出する必要があります。
書類によっては提出期限が定められているものもあるので、開業届と一緒に提出しておけば、提出忘れや二度手間を防ぐことが可能です。
ここで、開業届と同時に提出しておくとよい書類を紹介します。
事業開始等申告書
事業開始等申告書は、都道府県に個人事業を開始する旨を通知するための書類です。
自治体によっては、個人事業開業届書や事業開始届などの名称になっていることもあります。
この書類は都道府県税である個人事業税に関わる書類になります。青色申告特別控除を適用する前の事業所得が290万円以上の場合、個人事業税の納税が必要です。
提出の対象は開業する個人事業主全員であり、提出先は各都道府県の税事務所です。一部自治体では市区町村に提出するケースもあります。
また、提出期限は自治体ごとに異なるので、Webサイトを確認してください。
青色申告承認申請書
所得税の青色申告承認申請書は、確定申告を青色申告で行う場合に提出が必要です。
青色申告を行う年の3月15日までに税務署に提出してください。ただし、開業日がその年の1月16日以降に開業する場合、開業日から2カ月以内が提出期限です。
青色申告では、特別控除を適用できるので、それを活用することで所得税の節税につながります。
他にも赤字を翌年以降に最長3年間繰り越せる、家族に支給する給与を経費にできるなどのメリットもあります。
開業時期によっては提出期限に余裕がありますが、提出忘れによって青色申告ができないという事態を回避するためにも、開業届と一緒に出しましょう。
青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与に関する届出書は、青色申告を行う事業主と生計を一にする配偶者や親族を従業員として雇用し、労働の対価として給与を支払う場合に提出します。
税務署にこの届出書を提出することで、親族に支払った給与を必要経費に算入することが可能です。
提出期限は、給与を経費に算入する年の3月15日までです。開業が申告する年の1月16日以降であれば、2カ月以内に提出してください。
また、新しく専従者を追加した際にも2カ月以内に届出書の提出が必要です。
さらに、青色事業専従給与を経費にするためには、その年の12月31日の時点で15歳以上であること、6カ月以上の期間で事業を従事していることも条件となっています。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、従業員を雇用する場合に税務署に提出する書類です。
従業員を雇用すると、毎月支給する給与から所得税や住民税を源泉徴収し、事業主が納税を行うことになります。
この届出書を提出することで、源泉徴収した所得税の納付書などが送付されるようになります。
ただし、開業届に「給与等の支払いの状況」の欄に必要事項を記載している場合、この書類の提出は不要です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、10人未満の従業員を雇用し、源泉徴収に関する特例を受けたい時に税務署に提出する書類です。
従業員を雇用して給与を支給する場合、源泉徴収の義務が発生します。
通常は源泉徴収した月の翌月10日までに納税が必要です。しかし、この申請を行うことで年2回に分割してまとめて納税できる特例制度を適用できます。
提出期限は特にありませんが、特例は提出した日の翌月に支払う給与から適用されます。
そのため、10人未満の従業員を雇用することを前提に開業する際は、開業届と一緒に提出しておけば提出忘れを防ぐことが可能です。
適格請求書発行事業者の登録申請書
適格請求書発行事業者の登録申請書は、インボイス制度に対応する場合に税務署に提出する書類です。
インボイス制度がスタートして以降、事業者が商品・サービスを購入する際に支払う消費税額を納付税から差し引く仕入税額控除を適用するには、適格請求書が必要になりました。
適格申請書は、発行事業者として登録される事業所しか発行できません。
取引先が消費税の納税事業者である場合、適格申請書を発行してもらえないと仕入税額控除が使えなくなり、困ってしまう可能性があります。
取引きの中止や取引数量・金額が減るなどのリスクが発生するため、必要であれば開業と同時に適格請求書発行事業者に登録しておくと安心です。
なお、適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者となっているので、課税事業者になるリスクも理解して登録手続きを行ってください。
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書は、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を指定するために税務署に提出する書類です。
棚卸資産とは、事業によって仕入れた商品が年末までに売れず残った在庫のことです。
この棚卸資産の金額を確定するための評価方法には、原価法と低価法があり、届け出を提出することでどちらの方法で評価するか自分で選出できます。
届出書を提出しなかった場合、最終仕入原価法によって棚卸資産を評価することになります。
機械や自動車など時間の経過によって価値が下がる資産が、減価償却資産です。
この減価償却資産の償却方法は、定額法となるのが原則ですが、届け出を提出すれば資産を取得した年に減価償却費を多く形状できる定率法を選択できます。
棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法は、どちらの方法を選ぶかによって税負担が軽くなる可能性があります。
そのため、自分の状況に合わせて届け出を提出して、方法を指定してください。
開業届の提出に関するよくある質問

ここからは、開業届の提出に関するよくある質問を紹介します。
開業届は絶対に提出が必要?提出期限はいつ?
開業届の提出が必要かどうかは、ケースバイケースです。
所得税法では、事業を開始するにあたって、その事実があった日(開業日)から1カ月以内の提出と定められています。
期限内に提出していなかったからといって、特に罰則があるわけではありません。
しかし、法律で提出が定められているので、個人事業を始める際は開業届を提出してください。
例外を挙げるとすれば、副業として個人事業を始める場合です。副業の収入がそれほど多くなければ、開業届を出さなくても問題はありません。
ただし、事業と認められる規模で仕事を続けていくのであれば、開業届の提出をするのが無難です。
開業届を提出するメリットは?
開業届を提出することには、以下のメリットがあります。
-
- 青色申告特別控除を適用できる
- 屋号で銀行口座を開設できる
- 創業融資の申請やオフィスの契約が可能になる
- 小規模企業共済に加入できる
大きな節税効果のある青色申告特別控除を適用するためには、青色申告を利用できるように承認申請書の提出が必要です。
開業届を提出していないと青色申告承認申請書を出すことができないので注意してください。
また開業届には、「○○商店」などビジネスで使える名称(屋号)を記入する項目があります。
そのため、提出した開業届の控えがあれば、屋号名義での銀行口座を作成し、ビジネス用の口座として活用することが可能です。
ほかにも、創業融資の申請やオフィスなどの事業を行う拠点を契約する際、中小企業経営者・個人事業主の退職金制度である小規模企業共済に加入する際にも、開業届の控えを活用できます。
開業届を出す場合の注意点は?
開業届を出すと個人事業主としてビジネスを始めることになるので、注意点もあります。
例えば、配偶者の扶養に入っている人が個人事業主になって一定以上の収入を稼ぐと、配偶者控除や配偶者特別控除が適用できなくなります。
控除が利用できなくなると、配偶者の税負担が大きくなることに注意してください。
また、会社員などを辞めると、失業中は再就職活動をすることを条件に一定金額の失業手当が支給されます。
しかし、離職後に個人事業主になると失業保険が適用されず、手当を受け取れません。
ただし、「2022年7月から事業開始等による需給期間の特例」が新設されたので、要件を満たしていれば再就職手当が支給されるようになりました。
利用できるかどうか、厚生労働省のホームページやハローワークに確認することをおすすめします。
開業届の控えは保管するべき?
開業届の控えは保管することをおすすめします。開業届の控えは、屋号で銀行口座を開設したり、小規模企業共済の加入手続きに使ったり、何かと使用する機会があります。
窓口提出であればその場で受け取れますが、郵送提出をする時は返信用封筒を同封して、返送してもらってください。
万が一紛失した場合、税務署で「保有個人情報開示請求書」を提出することで再発行できます。
e-Taxからの申請では控えが発行されません。その代わり、送信時のデータや受信通知の控えで代用できるので、データを保管しておいてください。
まとめ・個人事業を始めるなら開業届を忘れず出そう
開業届を出さなくても罰則はありませんが、開業届を出すことで青色申告ができたり、事業用の銀行口座が開設できたりするなどのメリットがあります。
所得税法でも提出が定められているので、個人事業を始めるなら必要な書類や出し方を確認し、忘れず提出しましょう。
必要に応じて青色申告承認申請書や事業開始等申告書などの書類も同時に提出すれば、何度も税務署を行き来するという手間を省け、提出忘れも防げるのでおすすめです。
創業手帳では、起業、開業の準備をどのように進めていいのかわからない方のために『創業カレンダー』をご用意致しました。やることが書かれたTODOカレンダーを無料でお届けしますので、そちらに起業予定日を記入すれば、前後1年間のやることを見える化!ぜひあわせてご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)