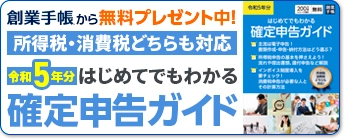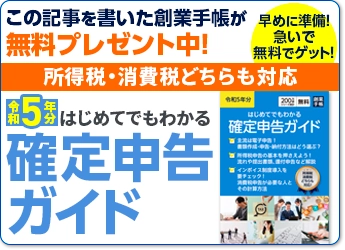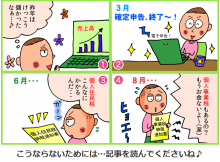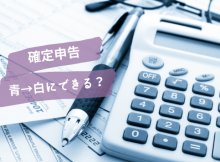複式簿記の書き方とは?記帳例から単式簿記との違いまで解説
複式簿記の書き方がわかると節税につながる!

個人事業主が青色申告で最大65万円の特別控除を受けるには、複式簿記による記帳が必要です。
一般的に簿記は単式簿記と複式簿記の2種類に分かれますが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
そこで今回は、複式簿記について解説しつつ、実際の書き方例を紹介します。
複式簿記についていまいち理解できていない、どのような点に注意すればいいかわからない人は、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
複式簿記とは

複式簿記とは、日常的に発生するひとつの取引きについて、原因と結果の2つから記録する記帳方式です。
例えば現金1,000円から交通費700円を使ったとします。この時、複式簿記には原因として「交通費として700円使ったこと」と、結果として「現金が700円減ったこと」を記録します。
複式簿記は企業会計原則に含まれる「正規の簿記の原則」の要件をすべて満たしており、正確性の高い記帳方式として認められているのです。
-
- 網羅性:全取引きの記録を漏れなく記帳している
- 秩序性:秩序立ったルールに則って記帳している
- 検証可能性:事後に検証できる資料に基づいて記帳している
単式簿記との違い
複式簿記と単式簿記の大きな違いとして、記帳の難しさが挙げられます。
単式簿記はひとつの勘定科目に対してその増減を記録する記帳方式です。現金出納帳などは単式簿記によって記録していきます。
例えば前日の現金残高が10万円で、その日の売上げが2万円、仕入れに5万円、電気代に1万円、残高から1万円を預金に預け入れした場合、その日の現金残高は5万円になることがわかります。
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
| 1月1日 | 繰越 | 100,000 | ||
| 〃 | 売上 | 20,000 | 120,000 | |
| 〃 | 仕入れ | 50,000 | 70,000 | |
| 〃 | 電気代 | 10,000 | 60,000 | |
| 〃 | 預金 | 10,000 | 50,000 |
単式簿記でも現金の流れはわかるものの、一定期間の売上額や経費を集計するのには適していません。
また、現金の変動を記録することが可能ですが、取引きによって増減した資産を記録するのは難しく、貸借対照表を作成できない点も単式簿記の特徴になります。
複式簿記の書き方で知っておきたい「借方・貸方」

複式簿記の書き方として、まずは借方・貸方について理解することが大切です。ここでは、借方・貸方の特徴や各取引項目と仕訳のルールについて説明します。
借方・貸方とは?
ひとつの取引きを借方と貸方の2つに分けて記帳することで、2つの側面からお金の動きを把握できるようにします。
記帳する際は左側に借方、右側に貸方を記入するのが基本です。
あくまでひとつの取引きを2つの側面から記録しているだけなので、借方と貸方に記載する金額は必ず一致します。
もし一致していなかった場合は、どこかで仕訳ミスが発生している可能性が高いです。
5つの取引項目と仕訳のルール
日々の取引きは大きく5つの項目に分類されます。5つの取引項目はそれぞれ借方・貸方に振り分けられます。
| 借方 | 貸方 | |
|---|---|---|
| 資産 | 増加 | 減少 |
| 負債 | 減少 | 増加 |
| 純資産 | 減少 | 増加 |
| 費用 | 増加 | 減少 |
| 収益 | 減少 | 増加 |
資産と費用が増加した際には借方に記載しますが、負債や純資産、収益が増加した場合は貸方に記載が必要です。
仕訳の際にどちらに記載するべきか迷ってしまう人もいますが、何が増えて何が減ったのかを確認することで、正しく振り分けられるようになります。
資産
資産は会社が所有する財産を指しており、主に以下の3つに分類されます。
-
- 流動資産:1年以内に現金化が可能な流動性の高い資産(預金、売掛金など)
- 固定資産:長期間にわたり使用されている資産(不動産、営業権など)
- 繰延資産:将来的に収益がもたらされると予測される資産(開業費など)
例えば現金が1万円増えた場合、記帳する際には借方に「現金 10,000」と記入します。
負債
負債は、会社がいずれ支払わなくてはならないもので、主に流動負債と固定負債に分類できます。
流動負債は1年以内に返済しなくてはならない負債です。主に買掛金や支払手形、未払金などが流動負債に分類されます。
固定負債は返済期日が1年以上先の負債です。長期借入金や社債などは固定負債となります。
純資産
純資産とは、会社の資産から負債を差し引いて手元に残る金額です。返済義務のない資産であり、主に株主資本と株主資本以外で分けられます。
株主資本は株主から出資してもらったもので、資本金や資本剰余金、自己株式などです。
一方、株主資産以外は株主に帰属していない資産が当てはまります。例えば評価・換算差額等や新株予約権などです。
費用
費用は、事業者が収益を得る際にかかった金額になります。例えば商品を製造するために必要な原材料の仕入れにかかった金額は費用に分類されます。
仕入れにかかった金額以外にも、従業員に支払う給与やボーナス、広告宣伝費、通信費、水道光熱費なども費用です。
収益
収益は、事業によって得た収入などです。取引きで受け取った金額や、受取が確定している金額などが該当します。
収益を大きく3つの分類に区分すると、売上げ・営業外収益・特別利益です。
売上高(事業で生み出した収入)は売上げに分類されますが、預金や貸付金などから発生した受取利息や、株式などの受取配当金、手数料収入や補助金など重要性の低い雑収入などは営業外利益に分類されます。
複式簿記の書き方例
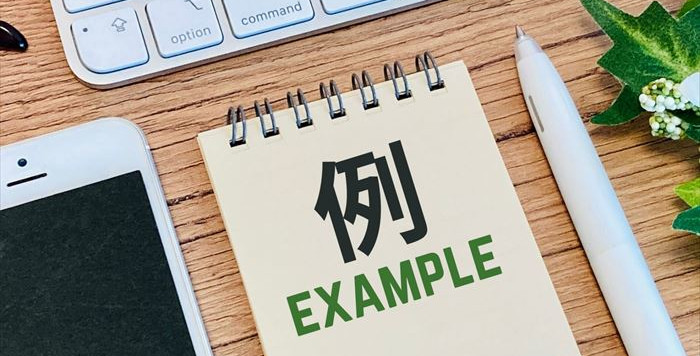
実際に複式簿記で記帳する際には、どのような書き方になるのでしょう。ここでは、様々なケースをもとに複式簿記の書き方例を紹介します。
商品の代金を現金で受け取った場合
1万円の商品が売れて、その代金を現金で受け取った場合、現金(資産)が増加したことと売上げ(収益)が増加したことを記入します。
| 借方(勘定科目) | 金額 | 貸方(勘定科目) | 金額 |
| 現金 | 10,000 | 売上 | 10,000 |
資産の増加は借方に、収益の増加は貸方に記入していきます。この記帳によって、会社の資産が増加したのは収益が増加したからということがわかるでしょう。
取引先と掛取引をした場合
掛取引は、商品を引き渡したタイミングではなく後日支払う取引きを指します。
多くの会社での取引きで行われており、月末など定められている締め日に1カ月分をまとめて支払うのが一般的です。
掛取引の場合、売掛金(後で支払われる代金)が未回収の時点で借方に計上し、代金を回収できたら貸方に計上することになります。
【掛取引で20万円の商品を販売し、月末にまとめて支払われる場合】
| 借方(勘定科目) | 金額 | 貸方(勘定科目) | 金額 |
| 売掛金 | 200,000 | 売上 | 200,000 |
【前月に販売した商品の代金20万円が預金口座に振り込まれた場合】
| 借方(勘定科目) | 金額 | 貸方(勘定科目) | 金額 |
| 普通預金 | 200,000 | 売掛金 | 200,000 |
銀行から現金を借入れた場合
銀行から現金を借入れた場合、現金(資産)は増加したので借方に記入し、借入金(負債)は増加したので貸方に記入します。
この仕訳によって、会社が使える現金は増加したものの、会社が銀行に返済しなくてはいけない負債が増えていることがわかります。
| 借方(勘定科目) | 金額 | 貸方(勘定科目) | 金額 |
| 現金 | 500,000 | 借入金 | 500,000 |
現金で借入金を返済した場合
銀行から借入れていた借入金50万円を現金で返済した場合、借入金(負債)が減少したことと、現金(資産)が減少したことを記録します。
負債の減少は借方に、資産の減少は貸方に記録してください。
| 借方(勘定科目) | 金額 | 貸方(勘定科目) | 金額 |
| 借入金 | 500,000 | 現金 | 500,000 |
商品を掛けで仕入れた場合
商品を掛けで仕入れた場合は、仕入れ先から商品を仕入れた日と実際に代金を支払う日の2回記帳します。
商品を仕入れた日は、仕入れ(費用)が増加して買掛金(負債)が増加したため、仕入れは借方に、買掛金は貸方に記録してください。
一方、商品の代金を支払う場合には、買掛金(負債)が減少して現金(資産)も減少するため、買掛金を借方、現金を貸方に記録します。
【商品を10万円で仕入れた場合】
| 借方(勘定科目) | 金額 | 貸方(勘定科目) | 金額 |
| 仕入れ | 100,000 | 買掛金 | 100,000 |
【10万円の買掛金を現金で支払った場合】
| 借方(勘定科目) | 金額 | 貸方(勘定科目) | 金額 |
| 買掛金 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
複式簿記を使って作成する決算書
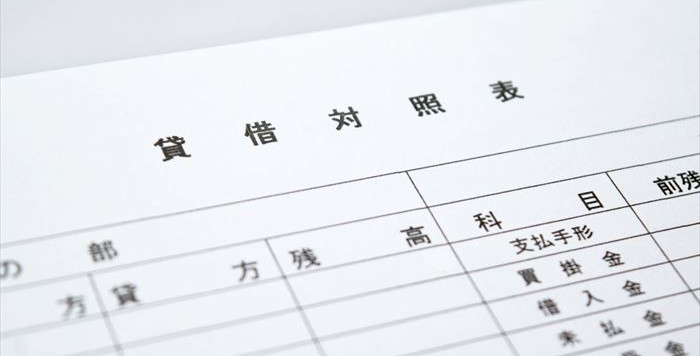
複式簿記は決算書を作成する上で必要な記帳方法になります。特に貸借対照表と損益計算書は複式簿記による個々の取引きでの仕訳が必要です。
貸借対照表
貸借対照表は、特定の時点における会社の資産や負債、純資産を示すための財務諸表です。
複式簿記は5つの取引項目に分類して仕訳が行われますが、そのうち資産・負債・純資産は貸借対照表によって表示されます。
貸借対照表を作成する際には、左側の借方に資産、右側の貸方に負債と純資産を振り分けて記載します。
借方の資産と、貸方の負債・純資産の合計が一致していなくてはなりません。
この貸借対照表を見ることで、単式簿記だとわからない現金や売掛金、借入金の残高まで把握できるようになります。
損益計算書
損益計算書は、会社に出た儲けや損失を計算するための財務諸表で、一定期間における経営成績を表しています。
事業年度中にどれくらい稼げて経費をどれだけ使い、最終的にどれだけの儲けがあったのかがわかるため、事業の収益性や成長性を図ることが可能です。
損益計算書を作成する際には、左側の借方に費用、右側の貸方に収益を振り分けて記載します。
ただし、収益から費用を差し引いて利益が出ている場合、借方側に利益の項目を追記し、費用+利益の合計が収益と一致するようにします。
複式簿記を書く際に気を付けたいこと

ここまで複式簿記の書き方について説明してきましたが、さらに気を付けておきたいポイントもあります。以下の点に注意しつつ、複式簿記を書いてください。
間違いがないように注意する
複式簿記で記帳する際には、いかなる取引きも漏れなく、間違えずに記帳することが大切です。
特に複式簿記は借方と貸方が一致していることで金額の正確性を示しているため、帳簿に記載する際には数字を間違えないように転記してください。
特に同じ数字が並んでいる場合や、桁数が多くなっている場合には注意が必要です。
もし金額を間違えたまま記帳してしまうと、帳簿の内容が正確ではないとして不正経理を疑われてしまう可能性もあります。
自分ひとりだと確認しても間違いを見逃してしまいやすいため、複数人からチェックを受けるようにしたほうが良いです。
借方と貸方の金額を必ず合わせる
仕訳の際には借方と貸方の金額が合っているか、必ず確認しておくことも大切です。
仕訳を1回行うごとに合計額が間違っていないかチェックするのが望ましいとされています。
借方と貸方の金額が一致していない場合、数字を間違えて記入していたり、記入漏れがあったりする可能性が高いです。
また、取引きによっては借方と貸方の勘定科目が2つ以上になる場合もあります。この時も合計金額に間違いがないかチェックしてください。
適切な勘定科目に振り分ける
複式簿記で仕訳を行う際には、適切な勘定科目に振り分けることも重要です。
取引項目は資産・負債・純資産・費用・収益の5つに分類されますが、そこからさらに適切な勘定科目に振り分ける必要があります。
適切に振り分けられると、現在の経営状況を正確に把握できたり、経営での意思決定もしやすくなったりします。
なお、勘定科目は一度設定したものを継続して使うようにしてください。
また、外部の人にも伝わりやすいよう、内部書類との統一やわかりやすい用語を活用することもポイントです。
複数の勘定科目がある場合
ひとつの取引きでありながら、複数の勘定科目に振り分けることもあります。この場合、2行以上に分けて勘定科目ごとに記載してください。
例えば15万円で商品を現金で購入した際に、2,000円の振込手数料も支払った場合は、以下のように記入します。
| 借方(勘定科目) | 金額 | 貸方(勘定科目) | 金額 |
| 商品購入 | 150,000 | 現金 | 150,000 |
| 振込手数料 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
領収書・レシートなどは整理しておく
会計帳簿を正確に付けるためには、領収書やレシートなどの証憑類も必要です。
記帳した後も仕訳伝票の裏側に証憑を貼り付けておくことで、後から確認する際にも見やすくなります。
なお、電子帳簿保存法によって領収書などの紙媒体の書類は、タイムスタンプを付与するなどの条件を満たすことで、PDFでの保存も可能となりました。
紙媒体を保管しているとどうしても場所を取るようになってくるため、PDFでの保存も検討してみてください。
保存期間を把握しておく
複式簿記によって作成した帳簿や領収書・レシートなどの証憑類は、一定期間保存しておく必要があります。
青色申告を申請している個人事業主の場合、確定申告の期限日翌日から7年間は帳簿類の保存が必要です。領収書などの関係書類も7年間保存しなくてはなりません。
白色申告の場合、同じく確定申告の期限日翌日から7年間保存する必要があります。ただし、それ以外の任意帳簿や領収書、請求書などは5年間の保存です。
適格請求書発行事業者は自社が発行する適格請求書の控えに加え、受け取った適格請求書を7年間保存します。
まとめ・複式簿記の書き方を覚えて決算書を作成してみよう
複式簿記は単式簿記に比べて記帳する内容が複雑になってきます。しかし、経営指標を把握したり、経営判断を見極めたりするのに役立ちます。
貸借対照表や損益計算書を作成する際にも、複式簿記による仕訳が必要です。
青色申告で特別控除などを活用したい方は、複式簿記の書き方を覚えて決算書を作成してみてください。
創業手帳では、確定申告において「青色申告と白色申告とで何が違うの?」「どのような控除があるの?」と疑問に思われている方々にわかりやすくまとめた「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。ぜひこちらもあわせてご利用ください。
(編集:創業手帳編集部)