GEOとは?検索エンジンの現状やGEOの重要性、具体策を紹介
SEOからGEOへの転換期が訪れている
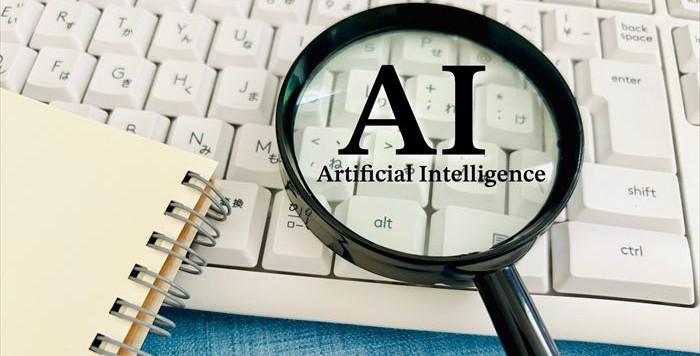
近年、検索エンジンのあり方が大きく変わりつつあります。
従来のSEO(検索エンジン最適化)は、Googleなどの検索結果で上位表示されることを目的とした対策を講じてきました。
しかし、生成AIによる検索に最適化を図ることが重要視されています。
そこで注目されているのが、GEOです。生成AIが搭載された検索エンジンから、最適なコンテンツが表示・引用されるために工夫する取組みを指します。
今回は、GEOについてわかりやすく解説しながら、GEOが必要な理由やSEOに対する影響、GEO対策の具体例などを紹介します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
GEOとは

GEO(Generative Engine Optimization)とは、Google AI OverviewsやChatGPT、Geminiなど、生成AIを搭載した検索エンジンで視認性を高めるためにコンテンツを最適化させる手法です。
現在、Googleなどの検索エンジンでは、検索結果のページの一番上に表示されるのは、関連性の高いWebページではなく「AIによる概要」です。
このAIによる概要の中で引用されることで、自社サイトの露出を増やすことができ、認知度の向上にもつながります。
検索エンジンの歴史
従来は、ユーザーが疑問に感じたこと・知りたいことを検索エンジンで入力し、その結果として関連性の高いWebページが表示されていました。
検索結果の上位に表示されることでユーザーのクリック率が高まり、ブランドの認知度向上や商品・サービスの購買率が向上します。
キーワード配置や被リンクの獲得、ページの読み込み速度の向上など、SEO対策を実施することでユーザーの目に触れる機会を増やしていきました。
しかし、現在の検索エンジンには生成AIが搭載されるようになり、検索結果の一番上に入力したキーワードに答える形のテキストが表示されています。
その結果、Webページをわざわざ閲覧しなくても、情報を取得できるようになりました。
GEOが必要な理由

WebマーケティングでSEO対策を実施する企業は多いですが、今後はGEO対策が必要になってくるといわれています。ここからは、GEO対策が必要な理由について解説します。
オーガニック検索への対応
生成AIを搭載した検索エンジンの登場によって、オーガニック検索に大きな変化が起きています。
オーガニック検索とは、リスティング広告などの広告枠を除いて表示される部分を指します。
従来は、わからないことがあればGoogleなどの検索エンジンにキーワードを入力し、表示されたオーガニック検索部分を見て、自分が知りたいことが書かれていそうなサイトを探してクリックしていました。
しかし、生成AIを搭載した検索エンジンを利用すれば、AIによる概要を見て納得したユーザーはそこで行動を完結してしまいます。
つまり、従来のSEO対策だけではオーガニック検索に十分な対応ができないといえます。
生成AIを搭載した検索エンジンでユーザーの関心を高めるためにはGEOが不可欠です。
ユーザーの検索行動変化への対応
生成AIの登場によって、ユーザーの検索行動に変化が見られています。これまではわからないことがあれば、GoogleやMicrosoft edgeなどを使って調べていました。
しかし、近年は多くのユーザーがChatGPTなどの生成AIを活用して、情報の収集や購入の検討をするようになっています。
生成AIのプラットフォームを活用すれば、検索エンジンを使わなくても気になることやわからないことを調べられます。
生成AIは検索エンジンの膨大な情報の中から、ピックアップして情報を提供しています。
つまり、AIに選ばれやすい表現や記事構成などを自社サイトに取り入れることが重要です。
GEOによるSEOへの影響

ここからは、GEOによるSEOへの影響について解説します。
クリック率の低下
検索結果の上位にAIによる概要が表示されるため、欲しい情報はすぐに得られ、そこで検索を終える人も少なくありません。
そうなると、SEO対策によって上位表示されていたとしてもクリックしてもらいにくくなります。
検索結果だけを閲覧してユーザーが離脱する「ゼロクリック検索」も徐々に増えていることから、企業側でクリック率を高める対策を講じる必要があります。
クリック率を高めるためには、主にキーワードを中心に対策をしてきたSEOから、ユーザーの検索意図をより的確に捉えた、質の高いコンテンツの制作が必要です。
トラフィックへの影響
AIによる概要はトラフィック(サイトに訪問したユーザーの数やアクセス数、セッション数など)にも影響をもたらしています。
AIは複数のWebサイトの情報を参照しており、検索上位に表示されていないサイトの情報も見つけます。
そのため、上位表示されていてもAIによる概要に反映されていない場合は、トラフィックが低下する可能性が高いです。
また、AIプラットフォームを経由してWebサイトを訪れたユーザーは、さらなる深い知識や情報を求めていることが考えられます。
ユーザーに対して、確実に知識や情報を伝えられるようになると、エンゲージメントやCV率の高いトラフィックになることが期待できます。
トラフィックを評価する際には従来の量に加え、AIによる回答全般で露出度は高くなっているか、トラフィックの質は高いか、流入経路は多様化されているかなど、総合的に評価することが重要です。
ユーザー行動に対する影響
ユーザーの検索行動には様々な変化が見られています。検索エンジンだけでなく、AIプラットフォームを活用して調べることが増えています。
また、これまで検索する際にはキーワードでの入力を基本としていました。しかし、AIの活用によって自然な話し言葉で検索できるようになっています。
さらに、テキストで入力するだけでなく、音声検索や画像検索などの利用も今後は増えていくと考えられます。
そのため、ユーザーが求めていることを明確に捉え、画像にalt属性の付与や構造化データの実装、会話型コンテンツの作成など、様々な検索方法での最適化が必要です。
意図しない形での表示
AIに誤った情報が学習されていた場合、そのまま誤情報が表示されたり拡散されたりする可能性が高まります。
特に専門的な分野では大きな問題に発展する可能性や、炎上を招いてしまうリスクがあることに注意しなくてはなりません。
AIに引用されたくない情報がある場合は、事前に対策を講じる必要があります。
例えば、AI Overviewに引用されないようにする場合は、robots metaタグの「nosnippet」を設定することで、AIによる概要の直接入力に使われないようにできます。
GEOに取り組むメリットとは

GEOに取組むことで企業が得られるメリットとして、以下の4点が挙げられます。
-
- リーチが拡大しやすい
- ユーザーからの信頼性が高まる
- ユーザーエクスペリエンスが向上する
- 先行者利益として競合優位性が高まる
AIによる概要などの引用元セクションに自社サイトが表示されると、キーワード検索の枠を超えてリーチを拡大できるようになります。
リーチが拡大すれば、より幅広いユーザーの流入や認知度向上も期待できるかもしれません。
また、AIにピックアップされた情報は、ユーザー側が「質の高い情報」「わかりやすい情報」と認識するようになり、信頼性の向上につながります。
ほかにも、GEOによってコンテンツを最適化することで、迅速かつ関連性の高い情報が表示されることから、ユーザーの満足度に加えロイヤリティの向上も期待できます。
まだGEOに着手できていない企業は多くあるため、早めに対策を講じることで競合優位性を高めることが可能です。
GEO対策の具体例

GEOには様々な対策方法があります。ここからはGEO対策の具体例を挙げて、対策を講じたほうが良い理由について解説します。
E-E-A-Tを強化する
E-E-A-Tとは、Googleがサイトやコンテンツを評価する際に用いられる基準です。E-E-A-Tは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取っています。
SEO対策でもE-E-A-Tを意識して制作したコンテンツが上位表示されやすくなる傾向にありましたが、GEOではその重要性がさらに増しています。
AIはコンテンツをピックアップする際の判断材料として、E-E-A-Tを基準にする可能性が高いです。
そのため、AIに信頼性を示すためには、コンテンツのE-E-A-Tを強化していく必要があります。
例えば、コンテンツ制作者の経歴や専門的な資格を明示したり、具体的な数値・統計データなどを出す時は根拠となる情報源を記載したり、実体験をもとにしたケーススタディを提供するなどです。
情報の鮮度を示すためには、最終更新日の表示も欠かせません。
正確で最新な情報を維持する
GEOにおいて基本的かつ重要な対策のひとつに、「正確で最新な情報を維持すること」が挙げられます。
生成AIは、インターネット上の膨大な情報を学習・参照して回答を作成します。
そのため、古い・誤った情報や曖昧な表現が含まれるコンテンツは信頼性の低い情報源とみなされ、引用や参照の対象から外れるかもしれません。
例えば、自社サービスの価格や機能に変更があったにもかかわらず、Webサイトを更新していない場合、生成AIが誤った情報を提示してしまうリスクがあります。
これはユーザー体験の損失だけでなく、ブランドイメージにも悪影響を与える恐れがあります。
そのため、GEOを意識したコンテンツ運営では、業界動向や制度変更などをいち早く反映させることや、定期的なコンテンツの見直し、古くなった情報の更新などが有効です。
AIが優先的に参照するのは「信頼できる一次情報」であり、「鮮度の高いコンテンツ」です。
単に情報を蓄積するだけでなく、常にユーザー視点で最新性と正確性を維持することが、GEO成功への第一歩になります。
質問応答型コンテンツを設計する
質問応答型コンテンツを設計することも、GEO対策に有効な方法のひとつです。ユーザーが質問形式で検索した際に、AIはその質問に回答する形でコンテンツを生成します。
キーワードのみを入力すると検索意図を読み取るのが難しく、質問形式で入力するほうがAIが回答しやすい傾向です。
つまり、AIにピックアップされやすいコンテンツにするためには、同じように質問応答型のコンテンツを設計することで、採用される可能性が高まります。
質問応答型コンテンツを設計するには、まずターゲットとなるユーザー層が抱きやすい疑問・課題などを分析します。
そして、Googleサーチコンソールや関連の質問サイトに投稿された内容などを参考にして、具体的な質問のパターンを想定しなければなりません。
質問を設定する際には単純に「はい・いいえ」で回答できる質問ではなく、5W1Hのように詳しい説明が必要となる質問が重視されます。
質問に対する回答に含まれる情報が多いと、AIがコンテンツを引用する価値が高まることが理由です。
なお、質問に対する回答を複数の視点で作成することで、包括性が高まりAIからの評価も上がりやすくなります。
構造化データを活用する
構造化データとは、Webページに記載されている内容をよりわかりやすくするために、HTMLにマークアップする専用コードを指します。
SEOでは検索エンジンのクローラーが巡回しやすいように構造化データを活用していました。
しかし、AIに関しても正確にコンテンツ内容を理解し、引用しやすくするために構造化データを活用することが必要といえます。
例えば、FAQやハウツーガイド、製品情報ページ、会社の営業時間・所在地などの情報に対して適切な構造化データのマークアップを実装させれば、「このページには何が書かれているか」をAIに明確に伝えられます。
FAQは質問応答型コンテンツとの相性も良く、AIの引用率向上が期待できるでしょう。
まとめ・AI時代においてはSEOだけではなくGEO戦略も不可欠
すでにAI検索の需要は高まっていますが、今後はさらにその需要も向上していくことが考えられます。
従来のSEO対策は重要な取組みではあるものの、今後はGEO戦略も必要不可欠な取組みになってきます。
AI時代に合わせてユーザーのニーズや行動の変化にも柔軟に対応しつつ、GEO戦略を取り入れてみてください。
創業手帳では、様々なジャンルに特化した生成AIを比較してわかりやすく解説した「ChatGPT生成AIガイド」を無料でお配りしています。ビジネスにAIを活用しようと検討されている方は、ぜひこちらもあわせてご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)





































