フリーランスが経費にできる費用とできない費用は?経費に使われる勘定科目や経費割合の上限も解説
フリーランスは経費計上で節税につなげよう!

フリーランスになったら、経費や売上げなどの管理をすべて自分で行わなければいけません。
これまでは会社がやってくれていたことをやらなければいけないことが、大きな負担だと感じてしまう方もいると考えられます。
特に会計の知識がなかったり、数字が苦手だったりすると、より憂鬱に感じてしまう作業です。
しかし、経費に関する知識はそこまで難しいものではなく、ポイントを押さえておけば問題ありません。
そこで今回は、フリーランスにおける経費の重要性や経費にできる費用と勘定科目、経費計上できない費用、経費の上限、経費計上するための領収書・レシートの保管方法といった基本的な内容について解説していきます。
会社経営者にとって税金の支払いは重要な義務ですが、多種多様な税金が存在し、どの税金をいつ支払うかが複雑に感じられることもあります。そのため、創業手帳では個人事業主や法人向けに「税金カレンダー」を用意しました。このカレンダーでは、支払うべき税金とその支払い月がカレンダー形式で一覧表示され、解説も付いています。無料で利用できますので、ぜひこの機会に活用してください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
フリーランスにおける経費の重要性

フリーランスにおける経費は、仕事で使用したお金のことです。仕事でパソコンを使っている方であれば、パソコンの購入費用や各種ソフトの利用料金などが当てはまります。
また、自宅兼事務所で仕事をしている方であれば、仕事に使用している割合なら家賃も経費として認められます。
仕事関連のセミナー受講料なども経費計上できる可能性があることを覚えておいてください。
経費を正しく理解しておくと、翌年支払う税金を減らせる場合があります。
支払う税金を決めるために行うのが確定申告ですが、その際に必要経費と控除を1年間の総収入から差し引き、所得を計算します。
その所得額に応じて納税金額が決まるため、経費を正しく把握することは重要です。
フリーランスが経費にできる費用と勘定科目

フリーランスが経費にできる費用と勘定科目は以下のとおりです。
| 勘定科目 | 内容 |
| 開業準備費 | Webサイトの制作費用や広告費用など開業にかかった費用 |
| 租税公課 | 個人事業税や事業利用資産の固定資産税、自動車税、登録免許税、印紙税 |
| 水道光熱費 | 事務所で使う水道代やガス代、電気代、灯油代 |
| 旅費交通費 | 事業で使用する交通費や出先で利用したコインパーキング代 |
| 通信費 | 事業で使用する郵便、電話、インターネット料金 |
| 広告宣伝費 | 事業や商品の広告に関する費用 |
| 接待交際費 | 取引き先への接待や贈答にかかる費用(プライベートは除く) |
| 損害保険料 | 事故や火災などの損害保険料 |
| 消耗品費 | 文房具や伝票、名刺、作業用デスク、10万円未満のパソコンなど |
| 修繕費 | 建物や機械などの修理代 |
| 減価償却費 | 建物や車、コピー機、オフィス家具、機械(法定耐用年数に従って一部を経費計上する) |
| 外注工賃 | 外部に業務を委託し、支払った費用 |
| 地代家賃 | 事務所などの家賃や使用料 |
| 利子割引料 | 借入れの支払利息や分割払いの手数料 |
| 貸倒金 | 取引き先の経営悪化や倒産で、回収できなくなった損害金額 |
| 車両費 | ガソリン代や車検費用など |
| 福利厚生費 | 従業員の社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)、法定外福利費(食事代、慶弔見舞金、健康診断、社員旅行) |
| 給与賃金 | 従業員に対して支払う給与や手当 |
| 雑費 | 事業に関わる引越し代や書籍代、クリーニング代、年会費、銀行の振込手数料など |
創業手帳では、科目ごとに経費を分かりやすく解説した「経費で損しないためのチェックリスト」を無料配布しています。すぐに実践できる具体的な事例を掲載しています。

フリーランスの経費は「家事按分」できる
家事按分は、フリーランスなどが自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費などの一部を「事業を行う上で必要な支出」として計上できることです。
プライベートの生活費と事業費が混在している費用をルールに則って計算し、事業に使った分を算出するのが家事按分です。
ここでは、家賃が10万円で居住スペースが60㎡、事業で使用しているスペースが15㎡の場合はどうなるのか解説していきます。
按分率は15㎡÷ 60㎡=0.25(25%)、経費計上できる額は100,000円(1カ月の家賃)× 25%(按分率)= 25,000円となります。
フリーランスが経費計上できない費用とは?

フリーランスとして仕事をしている中で発生した費用であっても、経費計上できないものもあります。続いては、経費計上できない費用について解説していきます。
プライベート関連の支出
プライベート関連の支出は、経費として計上できないこととなっています。
プライベートで使用する備品や趣味を極めるための書籍などは、事業と関係がないので経費として認められません。
経費として計上できるかの基準は、事業に必要な支出かどうかです。私的な支出を経費として計上してしまうと、税務トラブルの原因になりかねないため、注意が必要です。
生計を共にする家族・親族への給料
フリーランスと生計を一にする家族や存続は、事業主と家計が同じだとみなされます。そのため、事業に従事してもらい給料を支払ったとしても経費計上はできません。
ただし、青色申告で事業専従者給与の届け出をしていて、以下の条件を満たす場合は経費計上が可能となります。
-
- 生計を一にする配偶者または15歳以上の家族や親族である
- その年の6カ月を超える期間従事している
- あらかじめ届け出を行っている
所得税・住民税
税金は租税公課として経費計上できると思われがちですが、所得税や住民税は計上できません。
フリーランスが確定申告を行った結果として支払うものだからです。帳簿では、事業主貸となります。
また、相続税や復興特別所得税、贈与税、延滞税、加算税も経費には計上できません。これらはあくまでも個人に課されるものであり、事業に関係するとはいえないためです。
ただし、事業で自宅を使用している場合は、家事按分した固定資産税を経費に計上できるなどの例外もあります。
借入れ・住宅ローンの元本
借入れや住宅ローンの元本も、経費に計上できません。
借入れ金は設備投資など事業に関する用途も含まれると思われがちですが、経費に計上できるのは借入れ金を使用した支出です。
返済自体は計上できないので注意してください。
ただし、利息に関しては借りたお金ではないので、経費計上が可能です。
借入れや住宅ローンがある場合は利息のみ経費計上できることを把握しておかないと、自分が痛い目を見ることになってしまいます。
取得価額10万円以上の備品
事業用に10万円以上で購入したパソコンなどの備品で、特例の適用を受けないものに関しては、固定資産扱いになります。
そのため、法定耐用年数に応じた減価償却費にしなければいけません。
このような場合、耐用年数から購入費用を分割して経費計上するため、1年で全額経費にすることは不可能です。
耐用年数は、パソコンが4年、金属製の事務机・イス・キャビネットは15年、時計は10年といったように定められています。
例えば16万円のパソコンを購入した場合は、4年かけて4万円ずつ計上するという仕組みです。耐用年数に従い、減価償却費として計上することが原則となります。
罰金・違反金
罰金や反則金は、個人に課されるものです。そのため、事業主貸で処理しなければいけません。
仕事中に交通違反をしてしまい、反則金を取られた場合などは、経費にあたるのではないかと考える方もいます。
確かにそのような考え方もできますが、罰金や違反金で節税できるのはおかしいので経費には計上できません。
ただし、レッカー移動された時のレッカー代は罰金や違反金ではないので、経費として認められるケースがあります。
敷金・保証金
敷金や保証金は、退去時に返金されるものです。そのため、資産として処理され、経費計上はされません。勘定科目は、敷金・保証金となります。
退去する時に敷金から原状回復費を差し引いた残金があれば戻ってきます。その時に差し引かれた原状回復費は、修繕費として経費計上可能です。
また、敷金と一緒に支払う礼金や更新する時に支払う更新料は、経費計上できます。
20万円未満なら地代家賃として仕訳し、20万円以上の場合は資産として処理します。
賃貸期間または5年間での減価償却となり、勘定科目は長期前払費用となることも覚えておくべきポイントです。
福利厚生費
健康診断や人間ドック、スポーツジムの利用費などは福利厚生費に該当します。
これらの費用は従業員への支出なら経費計上できますが、フリーランス自身には福利厚生費が認められていません。そのため、経費として計上することは不可能です。
また、青色事業専従者として働く家族に退位する福利厚生費も、経費にはできません。
このことから、フリーランスの場合は基本的に福利厚生費を経費として計上できないことを把握しておく必要があります。
スーツ代
スーツは、取引先に足を運ぶ際などに身に付けるものなので、プライベートで着る機会はほとんどありません。そのため、スーツ代は事業に必要な支出だと考えられます。
しかし、スーツ代は経費として認められにくいのが実態です。
過去には「スーツは個人の好みに左右されるものであり、誰もが利用するものなので、個人的な消費に当たる」と判断され、経費として認められなかった判例もあります。
ただし、明らかに業務で必要であり、プライベート用の衣服と区分が明らかになっていれば、経費として認められる可能性もないとはいい切れません。
また、業務時にのみ使用する作業着やユニフォームであれば、経費として認められます。
二次会に使った飲食費
フリーランスとして活動する中で発生する取引き先などとの飲食費は接待交際費、従業員との飲食費は福利厚生費として経費計上できます。
しかし、二次会に使った飲食費に関しては注意が必要です。なぜかというと、接待交際費として認められるのは、一次会までとなっているからです。
二次会や三次会を行ったとしても、その時にかかった飲食費は経費計上できないので、混同しないようにしてください。
忘年会や新年会など、従業員以外の取引き先といった第三者が参加する場合は、接待交際費として経費計上しなければいけない点にも注意が必要です。
フリーランスの経費の割合に上限はある?

フリーランスの経費に上限は定められていませんが、60%を超えるのはリスクが大きいといわれています。
経費率が60%を超えてしまった場合、税務調査の対象になる可能性が高まるためです。
税務署は、売上げと経費のバランスをチェックし、売上げの計上漏れや架空経費の計上、本来経費として認められていないかなどを確認しています。
そのため、経費率が高くなると怪しまれてしまい、税務調査の対象になるリスクが高まります。
ただし、事業に必要な経費が正しく計上されていれば問題ないので、必ず60%以内に収めなければいけないというわけではありません。
経費率は業種や経費の種類によっても変動する(卸売業は90%、小売業は80%、サービス業は50%など)ので、バランスが崩れていないか定期的なチェックを怠らないようにしまてください。
フリーランスが経費計上するための領収書・レシートの保管方法3つ
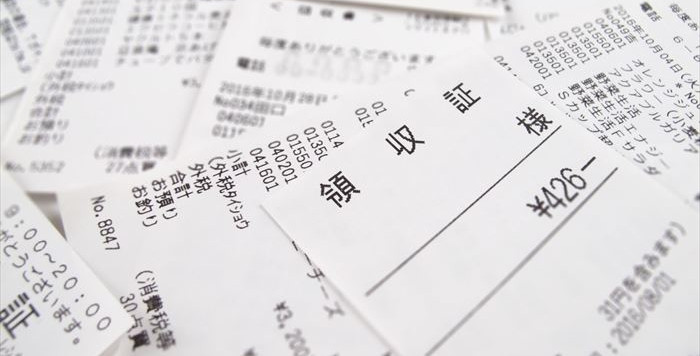
経費計上するためには、領収書やレシートを保管する必要があります。最後に、どのような保管方法があるかのご紹介です。
月ごとの封筒に入れる
月ごとの封筒に入れるというのは、オーソドックスな保管方法になります。
「1月」や「2月」などと書いた封筒を用意し、経費関連のレシートを入れておくだけなので非常に簡単です。
封筒とペンを用意できればすぐにスタートできる手軽さが魅力的な方法です。
しかし、レシートをそのまま封筒に入れるので、バラバラになってしまいます。ファイルなどに保管する場合と比較すると、確認しにくくなってしまうのはデメリットです。
ほかの書類と間違えて処分してしまう可能性もあります。
封筒に入れて保管する場合は、1年分をまとめて入れておける入れ物を用意し、紛失対策を徹底的に行うようにしてください。
そうすることで、必要になった時に焦らずに済みます。
ノートに貼り付ける
ノートに貼り付けて保管するという方法もあります。封筒に入れておくよりも確認がしやすいので、こちらの方法を選択する方もいるでしょう。
本棚にしまっておけば整理整頓もでき、封筒よりも紛失しにくいといったメリットもあります。
ただし、領収書やレシートの枚数が多いと、1冊に収まりきらなくなるかもしれません。
作業の手間がかかったり、ノリが剥がれて紛失してしまったりするなどのデメリットも考えられます。
ノートを使って保管する場合は、ページ数が多いノートまたは大判のノートを使用したり、テープとノリで貼り付けたりするなどの対策を講じるのがおすすめです。
スキャンして画像で保管する
2022年1月の電子帳簿保存法改正で、電子データの保存が承認なしでできるようになりました。そのため、デジタルで経費書類を保存しやすくなりました。
さらに2024年1月からは電子取引きのデータ保存が義務化されています。
真実性や可視性の確保も重要になります。
タイムスタンプが付されていることや、正当な理由なしで訂正や削除ができないようにルールを定めてそれに基づく運用を行うことなどが、真実性の確保を担保するために重要です。
また、可視性を確保するには、保存場所のマニュアルを設けたり、検索機能を使えるようにしたりしなければいけません。
「適格請求書発行事業者」の場合の取り扱い方法とは
インボイス制度における領収書やレシートの取り扱いは、適格請求書を簡易的にした書類として認められています。これは、適格簡易請求書と呼ばれています。
ただし、適格簡易請求書を発行できるのは特定の業種のみとなっているので注意が必要です。
発行できるのは、以下の業種です。
-
- 小売業者
- 飲食店業者
- 写真業者
- 旅行業者
- タクシー業者
- 駐車場業者
また、以下の項目が盛り込まれている必要があります。
-
- 適格請求書発行事業者の氏名もしくは名称、登録番号
- 取引き年月日
- 軽減税率の対象品目である旨を示す取引き内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
- 税率ごとに区分した消費税額等もしくは適用税率
まとめ・経費計上できる費用を正しく理解して円滑に経費計上をしよう
フリーランスとして仕事をする場合、確定申告をしなければいけません。そのためには、経費に計上できるものとできないものを正しく理解しておくことが重要です。
正しい知識があれば、円滑に経費計上が可能となります。
また、経費計上しやすくするために、領収書やレシートはきちんと保管しておきましょう。
適切に経費を管理することで税負担を軽減できるため、どの税金をいつ支払うかだけでなく、どの経費が税金の計算にどう影響するかも把握する必要があります。そこで、創業手帳では個人事業主や法人向けに「税金カレンダー」を用意しました。このカレンダーは、支払うべき税金とその支払い月をカレンダー形式で示し、各税金に対する経費の効果的な使い方の解説も含んでいます。無料で利用できますので、経費管理と税金の計画にぜひご活用ください。
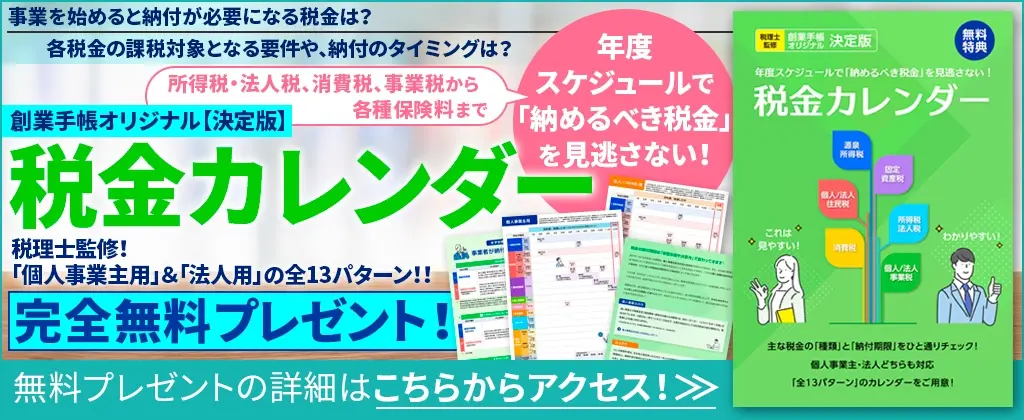
経費の基本を知りたい方は、「経費で損しないためのチェックリスト」をご活用ください。「経費を削減すると、なぜ利益がアップする?」「経費が節税に繋がる仕組みとは?」などの質問にお答えしています。ぜひご一緒にご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)







































