粗利率が低い原因と改善方法やほかの利益との違いを解説
利益を出すためにも粗利率が低い原因を探ろう

粗利率は会社の経営状態を示す指標になるため、経営者や財務担当者は認識しておく必要があります。
しかし、中には粗利の意味や粗利率の計算方法、低くなってしまう要因など、詳細を理解していない人もいるでしょう。
そこで今回は、粗利率の基本的な概要について解説するとともに、粗利率が低い原因や改善するための方法などを紹介していきます。
ほかの利益との違いについても解説していくので、粗利率が低い要因を知りたい人や利益を出したい人、経営状態を把握したい場合には、ぜひ参考にしてみてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
粗利率とは

粗利率について知るためにも、まずは粗利について解説していきます。
粗利とは、商品やサービスを販売して得た収益の一部で、売上高から売上原価を差し引いた額です。
売上原価とは仕入れや製造などで必要になった費用を指し、損益計算書では「売上総利益」となり、粗利益とも呼ばれています。
粗利の計算方法は、「売上げ-商品やサービスの売上原価」です。そのため、100円で仕入れたノートを200円で販売した場合の粗利は200円-100円=100円となります。
「1年間の売上高-売上原価」の計算式では、企業全体の1年間の粗利を計算できます。
次は粗利率についてです。粗利率とは、企業が得た粗利が売上高に対してどの程度の割合を占めているのかを示す指標となります。
粗利率が高いほど、商品やサービスに付加価値を付けられるため、粗利率を求めれば企業の収益性評価に役立ちます。
粗利率の計算方法・計算式
粗利率を求める計算式は以下の通りです。
「粗利(売上総利益)÷売上高×100%=粗利率」
例えば、売上高が1,000万円で売上原価が400万円、粗利が600万円だった場合の粗利率は「600万円÷1,000万円×100%」と計算できるので、粗利率は60%です。
粗利率の平均は業界によって違いがあります。
同業他社と比較することで、効率良く稼げているかを把握でき、商品やサービス状況を知るために役立ちます。
業界別の平均粗利率
粗利率を求めれば商品やサービスの利益率を把握でき、粗利率が高ければ効率の良い経営ができていると考えられます。
しかし、適切な粗利率は業種や経営方針によって変わるので注意が必要です。
例えば、卸売業は仕入れをした商品をそのまま売るので粗利益が低いです。製造原価が高くなる製造業でも粗利率は低くなります。
一方で、人件費が多く必要となる飲食サービス業や宿泊業では、粗利率が高くなりがちです。
しかし、工夫によって人件費が抑えられている場合には営業利益の割合が大きくなるため、粗利益が低いからといって一概に利益水準が低いとは言い切れません。
総務省で発表された「中小企業実態基本調査(令和4年度決算実績)」による粗利率は以下の通りです。
| 業種 | 粗利率 |
|---|---|
| 建設業 | 23.87% |
| 製造業 | 20.73% |
| 運送業・輸送業 | 23.49% |
| 情報通信業 | 47.60% |
| 小売業 | 30.42% |
| 卸売業 | 15.12% |
| 不動産業・物品賃貸業 | 46.34% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 63.32% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 41.33% |
| 学術研究・専門、技術サービス業 | 56.83% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 41.66% |
上記の粗利益は平均となっており、前述したように同業種でも経営戦略などによって粗利率には違いがあります。
粗利率のみでは企業経営の良し悪しを判断することは難しいため、ほかの指標と併せて分析するようにしてください。
粗利率が低い原因

粗利率が低いからといって売上げが少ないとは言い切れません。
売上高も顧客数も順調に伸ばしている企業でも、粗利がマイナスになっているケースもあります。粗利率が低くなる主な要因は以下の通りです。
変動費率が増加している
変動費率とは、売上高に対する変動費の割合を指しています。変動費率が増加する要因としては、仕入原価が高い時と販売価格が下がる時です。
例えば、これまで1個100円で仕入れて200円で販売していた商品があったとします。その場合の粗利は100円です。
しかし、仕入価格が120円に上がった場合、販売価格を200円に据え置きすれば、粗利は80円に減ってしまいます。
また、仕入価格が100円のままでも販売価格を180円に下げれば粗利は80円になり、元の100円と比較すると20円の減少です。
変動費が高くなるのは付加価値率の低下を意味します。
仕入価格が上昇した際には、顧客に納得してもらえるように付加価値を高めて販売価格に原価の上昇分を反映させるようにしてください。
販売価格が適正でない
販売価格を低く設定し過ぎると粗利を回収できなくなります。商品やサービスを提供する際には、原価に人件費や運搬費といった費用と利益をプラスして販売を行います。
しかし、これらの費用や回収予定の利益をしっかりと計算せずに価格を決定してしまうと、原価に対して販売価格が低くなってしまうかもしれません。
販売価格が低すぎれば「薄利多売」になるため、売上げを伸ばせたとしても得られる粗利が僅かとなってしまいます。
販売価格をあまりにも低く設定してしまえば、人件費や原材料が大きく高騰した場合に販売をすればするほど赤字になる「逆ザヤ」と呼ばれる現象に陥る可能性も高いので注意が必要です。
積み上げ原価型の価格設定になっている
積み上げ原価型の価格設定になっている点も粗利率が低い要因の1つです。原価に利益を上乗せして販売価格を決定する考えを積み上げ原価といいます。
原価が上がった場合、販売価格を維持するためには利益を削る選択肢をとりがちですが、「多く売ってもなかなか利益が出ない」といった状態になりかねません。
販売価格から利益を差し引いた価格を目標原価と定め、利益の確保を優先することが重要なポイントです。
粗利率を改善させる方法
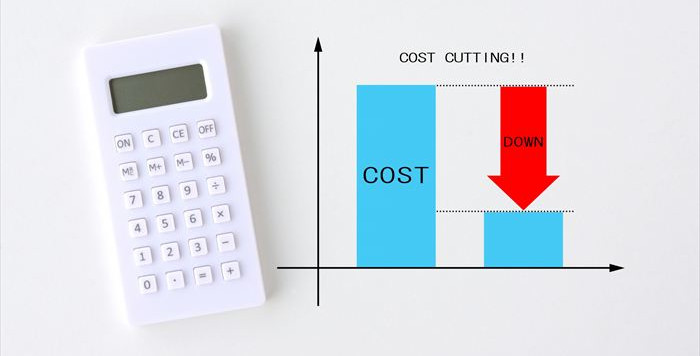
売上げが伸びているのに粗利益が少ない場合や赤字になった場合には粗利率も低くなります。
利益改善を目指すためにも、粗利率が低くなった場合の対応方法を把握しておくと安心です。
変動費の削減
変動費を削減して変動費率を下げれば粗利率に影響を与えます。
ただし、変動費は売上げを作るためのコストでもあるため、売上げの確保を優先し、無理のない対策を講じる必要があります。
以下を参考に施策を検討してみてください。
-
- 現金仕入れを行い、仕入単価を下げる
- 大量購入で仕入単価を下げる
- 支払いサイトを短縮し、仕入単価を下げる
- 余剰在庫の処分をする
- 返品率を下げる
大量購入や現金仕入れ、支払いサイトの短縮といった対処法は、キャッシュフローの悪化につながるので注意してください。
余剰在庫が減らず、返品率も下がらないようであれば、根本的な経営課題を抱えている可能性もあります。あらゆる点に着目して施策を打ち出していってください。
販売価格の見直し
粗利率が低い場合、最も効果的な対策といえるのが「販売価格の見直し」です。商品やサービスの提供価格を上げればその分粗利は多くなります。
例えば、これまで200円で販売していたものを220円で販売すれば20円分粗利が高くなります。
しかし、すでに消費者に対して根付いている価格を上げることで、消費者離れを引き起こす可能性が考えられるでしょう。
安易に価格を上げてしまえば消費者が離れていき、結果的に以前よりも状態が悪くなる可能性もあるので、販売価格の変更は慎重に行う必要があります。
販売価格を高くした場合でも、販売数をキープしたいなら付加価値をプラスして競合との差別化を図ってみてください。効果的な対策は以下の通りです。
-
- 顧客へのヒアリングを実施して、より魅力的な商品に改良して販売する
- 顧客の悩みを解決できる商品やサービスを生み出す
- アフターサービスを充実させて顧客満足度の上昇を図る
「価格が高くてもこの会社の商品を購入したい」「価格が高くなってもサービスを利用し続けたい」と感じてもらえるような商品づくりやサービスの提供を心がけることが重要です。
原価の見える化・構造の最適化を行う
「どこにコストがかかっているか」を可視化して、高粗利商品へのシフトや、原価構造自体の見直しを図ることで、粗利率の底上げが可能です。
粗利を定期的に記録しておけば、売上原価の管理がしやすくなります。その結果、効率的なコスト管理を行えます。
粗利は、販売価格が変わらなければ製造にかかった原価のみに左右されるため、粗利の変動を分析すれば原材料費の増減をスムーズに察知できるでしょう。
問題点を早期発見すれば、仕入れの価格交渉や仕入先の見直しなどの具体策を実行することで経営への影響を減らすことに役立ちます。
粗利率とほかの利益の違い

企業の収益を把握するには、粗利(売上総利益)のみ把握しても意味がありません。
損益決算書には、そのほかにも様々な利益が記載されており、併せて把握することで、財務状態の理解もしやすくなります。
経営戦略の軌道修正もしやすくなるため、粗利や粗利率だけではなく、ほかの利益についても深く理解することが大切です。
・営業利益
企業の本業における営業力で稼ぎ得た利益を営業利益といいます。飲食店を経営している場合は、提供している飲み物や食べ物を売って稼いだ利益が営業利益です。
粗利を見れば本業の利益がわかると考える人もいますが、商品の販売やサービスを提供する際には、原価のほかにも様々な費用がかかります。
商品をPRするための広告宣伝費や営業活動による費用が当てはまるだけではなく、企業を運営するための総務や経理などの間接部門によるサポート費も含まれます。
これらの活動に必要な経費をまとめて「販売費および一般管理」と呼び、営業利益は売上総利益から差し引くことで求められる仕組みです。
計算式は、以下のようになっています。
「粗利(売上総利益)-販売費および一般管理費=営業利益」
営業利益を算出できれば、本業でどの程度稼いでいるのかを把握できます。売上高や総資本、従業員数などと営業利益のバランスから経営状態の分析も可能です。
粗利が高くても商品を販売するために多くの広告費をかけていたり、無駄に人件費をかけたりしていれば、販売管理費が膨らむので営業利益を圧迫する要因となります。
また、売上高に対する営業利益の割合を売上高営業利益率と呼び、高いほど本業によって十分な利益が出ている証だとわかります。
自社の収益性を判断する目安になるので、以下の計算式を用いて求めてみてください。
「営業利益÷売上高×100=売上高営業利益率(%)」
・経常利益
営業利益に営業外収益を合算した利益を経常利益といいます。営業外収益とは、以下のものが含まれます。
-
- 投資による利益
- 株式の配当金
- 預貯金や貸付金による利子
- 不動産賃貸料
- 為替差益
計算式は以下の通りです。
「営業利益+営業外収益-営業外費用=経常利益」
営業外費用は、借入金に対する支払い利息や為替差損、社債利息や投資による損失などです。
経常利益では、運用利益や本業以外の活動を含めた通常可動時に、企業が1年間でどの程度の利益または損失を出したのかが判明します。
営業利益と比較をすれば、本業と本業以外の利益のバランスを把握するためにも役立ちます。
・税引前当期純利益
税金を納める前の利益額を税引前当期純利益といいます。
経常利益に特別利益をプラスして特別損失を差し引いた利益となり、特別利益は本業以外で得たイレギュラーな高額収入を指すため、イレギュラーな収支を含めてどの程度儲けたかを判断できます。
算出方法は以下の通りです。
「経常利益+特別利益-特別損失=税引前当期純利益」
特別利益の例を挙げると以下のようになっています。
-
- 土地や建物などの固定資産の売却で得た利益
- 株式の売却によって得た利益
- 貸倒れ処理した債権の回収によって得た利益
特別損失に関しては、本業以外によるイレギュラーな支出となり、以下のものが当てはまります。
-
- 固定資産の売却による損失
- 株式の売却による損失
- 災害による損失
・当期純利益
税引前当期純利益から税金を差し引いたものを当期純利益といいます。純利益ともいわれており、一会計期間の最終的な経営成績となります。
当期純利益がプラスとなれば黒字になり、反対にマイナスとなれば赤字の状態です。
特別損失による影響によって前年度と比較すると当期純利益が著しく減ってしまうケースもあります。
売上ダウンと考える人もいますが、営業利益や経常利益が右肩上がりであれば問題ないといえます。
当期純利益を計算する際には、そのほかの利益と併せてチェックしなければなりません。当期純利益の計算式は以下の通りです。
「税引前当期純利益-税金=当期純利益」
当期純利益が増加すれば、株主への配当や自己資本の蓄積が期待できるので、株主や取引先などのステークホルダーから注目されやすい指標だと考えられます。
まとめ・事業の発展を目指すためにも粗利率向上を目指そう
変動費率の増加や販売価格などが要因となって粗利率が低下してしまいます。
低いからといって一概に利益水準が低いとは言い切れませんが、粗利率をチェックすれば売上げに対してどの程度の利益を得ているのかを把握できます。
適切に分析を行えば無駄なコストや収益向上のポイントを把握するためにも役立つので、経営判断をするためにも本記事を参考にしてみてください。
創業手帳(冊子版)では、事業発展に必要な情報を多数掲載しています。どれも役立つ内容となっているので、知識を増やすためにも活用を検討してみてください。
(編集:創業手帳編集部)



































