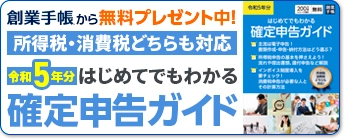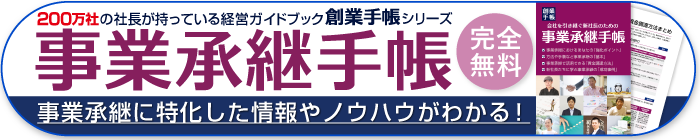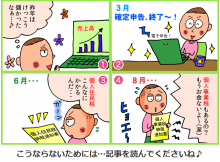【2026年最新】個人事業主は赤字廃業でも確定申告すべき?基礎控除58万円の新基準も解説
廃業した年の所得額で確定申告の必要性が変わる!

個人事業の廃業で迷うのが、廃業した年の確定申告をすべきかどうかです。
確定申告の必要性は所得額によって変わるほか、必要がなくてもあえて確定申告するメリットもあります。
そこで今回は、廃業後の確定申告のポイントや費用事情を解説します。廃業する際の手続きや必要な書類もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
廃業時を含め、毎年必要な確定申告の流れを「確定申告ガイド(無料)」にまとめました。悩む人が多い消費税の申告についても取り上げています。
この記事の目次 2025年(令和7年)分以降の所得税から、基礎控除額が引き上げられました。これにより、申告の要否を決める基準が以下の通り変更されています。 ※ただし、事業所得が赤字であっても、給与所得など他の所得がある場合は、「損益通算」による税金の還付を受けるために申告した方が有利になります。 所得税(赤字廃業)とは別に考えなければならないのが消費税です。インボイス制度(適格請求書発行事業者)に登録していた場合、所得が赤字であっても以下の手続きが必須となります。 2025年1月より、税務署の窓口で申告書の控えに受領印(収受日付印)を押してもらう運用が廃止されました。廃業後に融資の精算や各種証明で申告書の控えが必要な場合は、以下の方法で対応します。 廃業した年に確定申告をする場合、通常の確定申告とは違うポイントがあります。 廃業年度の確定申告ならではとなる、仕訳や経費の計上方法についてまとめました。 廃業から確定申告を行うまでの間に必要費用が発生した場合、「事業を廃止した場合の必要経費の特例」により、費用を計上できます。 例えば、廃業後に設備や在庫の処分、事務所の清掃などの費用がかかれば、確定申告の際に経費として計上することが可能です。 特例を使える主な条件は以下になります。 対象となる費用は経営が続いた場合に計上できる必要経費かつ、事業・山林・不動産所得のいずれかに関連した費用です。 経費と認定される基準は管轄の税務署によって異なるので、廃業時に問い合わせて確認することをおすすめします。 個人事業主が廃業する場合、その事業年度の減価償却費は年度初めから廃業する月の分まで計上が可能です。 例えば廃業した月が10月であれば、確定申告時に1月から10月分の減価償却費を計上できます。 廃業年度に10万円以上の固定資産を購入した際には、減価償却費の計上方法を踏まえて確定申告の準備をしましょう。 廃業した年度に減価償却が計上しきれない場合、帳簿に未償却分が残ります。未償却分は、固定資産をどう処理したかによって扱いが変わるので注意してください。 未償却分の固定資産を廃業後も引き続き使用するのであれば、会計上の処理が発生しないので確定申告にも影響を与えません。 資産を破棄した場合は固定資産除去損として扱われ、確定申告時の経費に損失として参入できます。 固定資産を売却した場合は、譲渡所得の取得費として計上してください。 法定業種を営む個人事業主が納める個人事業税は、年度の途中の廃業の場合、廃業日から1カ月以内に申告と納税を行わなければなりません。 申告・納税を行うことで、確定申告の際に経費として計上できるので、忘れずに手続きをしましょう。 廃業届の提出によって、事業に関係する納税義務や源泉徴収義務がなくなったことを通知しなければいけません。 廃業手続きで提出する書類は多岐にわたり、提出期限も設けられています。必要な書類や手続きを確認して前もって準備しておくことが大切です。 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)は、所轄の税務署に提出する書類です。廃業日より1カ月以内に提出します。 廃業届を提出しなくても、何かペナルティを受けるわけではありません。しかし、税務書に廃業の事実を伝えるために必要な手続きなので、期限内に忘れず提出してください。 入手先は税務署の窓口や国税庁のホームページとなります。ホームページから入手する場合、印刷して手書きするか、PDFに直接入力して印刷してください。 青色申告の承認を受けている場合、所轄の税務署に青色申告の取りやめ届出書を提出してください。期限は廃業する年の翌年3月15日までです。 提出先が同じであるため、一般的には廃業届と同時に提出します。 別々に出しても問題はありませんが、ついうっかり忘れてしまう可能性もあるので同時に提出するのがおすすめです。 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書は、専従者(家族従業員)や従業員を雇用していて給料を支払っている場合、所轄の税務署に提出が必要です。 廃業に伴い源泉徴収する義務がなくなるので、提出しなければなりません。 こちらも廃業日から1カ月以内が提出期限となるため、廃業届と同時に提出がおすすめです。なお、廃業時に給料から差し引いた源泉徴収税は、廃業日の翌月10日までに納付してください。 個人事業主が消費税の課税事業者であれば、廃業と同時に課税事業者でなくなることを所轄の税務署に通知しなければなりません。そこで提出するのが、消費税の事業廃止届出書です。 事業廃止届出書の提出期限は特に設けられていませんが、提出忘れを防ぐために、廃業届とともに提出するのがおすすめです。 また、廃業までの課税期間(個人事業主なら1月1日~12月31日)の消費税は、所得税と同じく確定申告が必要になります。 事業の廃止等届出書は、都道府県税事務所に提出する書類で、個人事業税に関わります。個人事業税は都道府県に納めているので、廃業する旨を通知するために提出しなければなりません。 この書類は都道府県によって書類の名称や形式、提出期限が異なります。そのため、事前に提出先の都道府県税事務所のホームページで確認してください。 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書は、事前に所得税の一部を支払う予定納税を行っており、申告する納税額が予定納税額より少なく見積もられる場合に提出します。 この書類を所轄の税務署に提出することで、予定納税額の減税や免除を受けることが可能です。減額申請書の提出期限は以下の2パターンがあります。 未提出の場合は通常通りに予定納税額を納付することになりますが、確定申告によって納め過ぎた分は還付されます。 廃業の理由はさまざまです。経営不振が理由の場合もあれば、個人事業主が法人成りするために一旦廃業するケースもあります。 どういった理由であれ、廃業した途端に事業に関するお金が全くかからなくなるわけではありません。 廃業後に発生する可能性があるお金について、以下にまとめました。 廃業しても、事業年度内に発生した税金は支払いが必要です。 税金は基本的に翌年度に支払いしたり、1月1日時点の情報をもとに決定したりします。そのため廃業日以降に当年分の各税金を支払うケースは珍しくありません。 所得税は赤字廃業でなければ所得に対してかかり、消費税も課税取引があれば納税します。 固定資産税はその年の1月1日に所有している固定資産にかかるので、廃業日が1月1日以降なら当年分は支払いが必要です。 廃業するにしても、納税しなくてはならない金額はあらかじめ見当をつけておいたほうがいいでしょう。 個人事業主の場合、廃業手続き自体に必要な費用はありません。法人と違って登記していないので、廃業手続きは書類の提出さえすれば完了します。 廃業日以降にかかる可能性がある費用は、基本的には税金です。ほかにあるとすれば、個々に発生する費用となります。従業員への退職金や資材の処分費用などが例です。 赤字廃業であれば資金繰りを考えなくてはならず、計画的に行う必要があります。 具体的に申告したほうがいいケースやメリットは以下のとおりです。 個人事業主の場合、事業に直接関係のない控除についても確定申告の際に手続きします。以下の控除は、確定申告することでしか受けられません。 個人事業主は個人的な控除と事業所得の申告を一緒に行うため混乱しがちですが、事業とは関係のない控除の申告は引き続き行いましょう。 赤字や廃業を理由に確定申告をやめてしまうと、これらの控除が適用されなくなるので注意してください。 株取引で損失が出ている場合、確定申告をすることで繰越控除が可能です。 上場株式の売却で出た譲渡損失は、利益との相殺による損益通算が認められます。損益通算後も控除しきれない損失があれば、翌年以降3年間まで繰越控除ができるのです。 確定申告によって損失を繰り越せば、株取引で利益が出た年に控除され、節税になります。損失が生じた年と、繰越期間である3年間は確定申告が必要です。 赤字の状態で廃業した場合は所得がないため、確定申告をすると払い過ぎている所得税が返ってくる可能性があります。 還付を受けられるのは、取引先から源泉徴収されている個人事業主です。源泉徴収されていれば所得税を先に納めた状態になりますが、赤字であれば所得税の納税は免除されるため、確定申告により還付を受けられます。 ただし、預金の利子といった源泉分離課税は還付されないので注意してください。 確定申告を行えば、確定申告書の控えを所得証明として利用できます。 所得の証明が必要になるシーンは、住宅ローンや事業資金といった融資を受ける時です。融資審査では返済能力を確認する所得の証明書類として、過去数年分の確定申告書類の提出を求められることがあります。 赤字廃業した直後に融資を受ける気はなくても、万が一に備えて確定申告をし、所得の証拠を残しておくのがおすすめです。 赤字廃業後に確定申告をすると、国民健康保険(国保)を軽減できる可能性があります。 国民健康保険料の一部は、総所得金額が基準以下だと減額される仕組みです。保険料は、確定申告などを通じて所得状況を通達することで決まります。そのため、廃業しても確定申告は行いましょう。 確定申告で所得が基準以下と証明されれば減額が適用され、支払う保険料が安くなる可能性があります。 確定申告をすれば、住民税が非課税であることを証明する非課税所得証明書の発行が可能です。 非課税所得証明書は、保育園の入園申請や児童手当の申請などで必要になります。証明書は地方自治体で発行されますが、確定申告または住民税申告をしなければ発行できません。 子供がいる個人事業主は特に注意し、廃業年の確定申告をしておきましょう。 個人事業主が廃業した場合、その年の所得額に応じて確定申告すべきかが決まります。所得48万円超なら必要、赤字廃業なら不要です。 しかし、赤字であっても確定申告を行うことで、繰越控除や源泉徴収の還付を受けられるなどのメリットがあります。 また所得の証明にもなるので、今後のためにも廃業後も確定申告をすることをおすすめします。確定申告の流れが簡単にわかる「確定申告ガイド(無料)」も活用してください。 (編集:創業手帳編集部)
 【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」
廃業したら確定申告はする?しない?

結論から言うと、廃業した年の所得が一定額以下であれば、所得税の確定申告は法的には不要です。しかし、2025年(令和7年)からの税制改正やインボイス制度の影響により、判断基準が以前とは変わっています。1. 所得税の申告が必要なボーダーライン
2. 【重要】インボイス登録者は赤字でも「消費税」の申告が必要
3. 2025年から「受領印」が廃止に
廃業した年の確定申告のポイント
廃業後の費用は計上できる
減価償却費は廃業する月まで計上する
未償却分は資産をどうするかで変わる
未償却分の固定資産の処理方法
帳簿上の処理
廃業後に使う場合
会計上の処理はない
廃業を機に破棄する場合
固定資産除却損として計上する
廃業を機に売却する場合
譲渡所得の取得費として計上する
個人事業税を納税しておけば計上できる
 【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」個人事業主の廃業に必要な書類と手続き

廃業手続きとは、国や都道府県に個人事業を辞めることを通知する「廃業届」を提出することです。個人事業の開業・廃業等届出書
青色申告の取りやめ届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
事業廃止届出書
事業の廃止等届出書(個人事業税)
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
個人事業主の廃業にお金はかかる?
廃業しても支払いが必要な税金
税金
概要
所得税
当年の所得に対して支払いが必要
消費税
当年の課税期間に発生した消費税の支払いが必要
個人事業税
当年の1月1日から廃業日までの支払いが必要(事業主控除額は事業月数に応じた月割)
固定資産税(償却資産税)
当年の1月1日時点で所有している固定資産があれば支払いが必要
源泉徴収した所得税
従業員から源泉徴収している場合、納付期限までに支払いが必要
廃業時に支払いが必要な費用
 【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」メリットは?個人事業主が赤字廃業でも確定申告したほうがいいケース

赤字廃業した場合、個人事業主の所得はマイナスになるので、確定申告は不要です。一方、あえて申告したほうがいいケースや、することで得られるメリットがあります。控除を受けたいとき
株取引の損失を繰越控除したいとき
所得税の還付の可能性があるとき
所得の証明をしたいとき
国民健康保険料の軽減措置を受けたいとき
非課税所得証明書を発行したいとき
まとめ・赤字廃業なら確定申告は不要だがやるメリットもある!

確定申告について更に詳しく知りたい方は無料で配布中の「確定申告ガイド」をあわせてお読みください。詳細は上のバナーをクリック!