【中小企業向け】メールセキュリティ対策の種類・取り組み方などを解説
中小企業こそメールセキュリティ対策が必要!

現在、ビジネスシーンではビジネスチャットツールを活用し、リアルタイムでのやり取りが可能となりました。
それでも依然としてメールは重要なコミュニケーションツールとして活用されています。
そんなビジネスに欠かせないメールですが、近年は企業を狙ったランサムウェアやフィッシングメールなど、外部から攻撃を受けてしまうことも少なくありません。
また、これまでは大手企業や府省庁などが狙われてきましたが、現在は中小企業や地方公共団体などもターゲットにされる傾向にあります。
そこで今回は、中小企業向けにメールセキュリティ対策の種類や取り組み方について解説します。
メールセキュリティ対策のツールを選ぶ際のポイントなどもまとめているので、導入を検討されている人はぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
メールセキュリティ対策とは?

メールセキュリティ対策とは、メールによる情報漏洩やウイルス感染、フィッシング詐欺、なりすましなどの脅威から、メールの内容だけでなく企業・従業員を守るための取り組みを指します。
ビジネスシーンではメールを使った業務連絡や取引に関する連絡をすることも多く、企業の機密情報が含まれている場合もあります。
もし外部から攻撃を受けて機密情報が流出すると、自社だけでなく取引先にも深刻な影響をもたらしてしまう可能性が高いです。
そのため、企業におけるメールセキュリティ対策の重要性は非常に高いといえます。
企業の規模や取り扱う情報の機密性などによっても異なりますが、メールの暗号化やスパム・ウイルスの検知、誤送信防止、従業員のセキュリティ教育は必須です。
どこまでやれば安心という明確なゴールはないため、脅威の変化に合わせて継続的に見直すことが重要となります。
ランサムウェア被害は今や中小企業が中心
警察庁サイバー警察局による「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」では、ランサムウェアの被害に関する統計にて、被害企業・団体などの規模別報告件数を紹介しています。
令和6年の被害件数222件のうち、大企業は61件、中小企業は140件、団体などは21件という内訳でした。
令和5年のデータと比較すると、大企業の被害件数は減少しているものの、中小企業の被害件数は37%も増加しており、今や中小企業を中心に狙われていることがわかります。
中小企業の被害が増えている要因としては、十分なセキュリティ体制が整備されていないことが挙げられます。
IPAによる「2024年度中小企業等実態調査結果」で貴社の情報セキュリティ対策はどのような体制で行われているかという質問に対し、「専門部署(担当者)がある」と回答したのは9.3%、「兼務だが、担当者が任命されている」が21.0%、「組織的には行っていない(各自の対応)」が69.7%と、7割近い企業が組織的にセキュリティ体制を整備していないことがわかっています。
メールセキュリティ対策を講じていなかった場合のリスク
メールセキュリティ対策を講じていなかった場合、外部からの脅威にさらされていることになりますが、具体的にどのようなリスクがあるのでしょうか。
IPAによる「2024年度中小企業等実態調査結果」でサイバーインシデントによる影響で生じた被害に関する質問では、「データの破壊」が35.7%と最も多く、次いで「個人情報の漏洩」が35.1%、「ウイルスメールなどの発信」が21.5%、「業務情報(営業秘密を除く)の漏洩」が21.3%でした。
このような被害を受けることで顧客・取引先からの信用が低下し、これまで築いてきた信頼関係が破綻する恐れもあります。
企業を狙うメール攻撃の主な種類・手口

メールによるセキュリティ被害は外部からの攻撃によるものと、内部からの情報漏洩によるものの2つに分けられます。
特に外部からの攻撃は標的型攻撃とばらまき型攻撃に分けることが可能です。それぞれの手口について解説します。
標的型攻撃(ランサムウェア)
特定の企業または個人を狙ったもので、メールに添付されているファイルを開いたり、メール本文にあるURLにアクセスしたりすると、ランサムウェアに感染してしまいます。
詐取したメールデータやSNS、自社のホームページで公開されている情報などを悪用しているため、上司や同僚、取引先、顧客など、実在する組織・人物になりすましてメールを送り、偽の請求書や振り込み口座を通知して金銭を奪おうとするケースもあります。
ランサムウェアに感染すると、機密情報や重要情報を窃取されるリスクだけでなく、暗号化やデータを人質に身代金を要求してくるので注意が必要です。
ばらまき型攻撃(フィッシングメール)
ばらまき型攻撃は不特定多数を狙ったメール攻撃です。
例えばフィッシングメールは、第三者が企業や個人になりすましたメールを送り、送られた人が個人情報などを入力・送信することで不正アクセスなどの被害に発展します。
金融機関を装って個人にフィッシングメールを送り、口座情報を入力させようとする事例が多いです。
また、ビジネスでも利用するサービスに偽り従業員が騙されてしまうケースもあります。
内部からの情報漏洩リスク
メールは外部からの攻撃だけでなく、内部からの情報漏洩リスクもあります。
従業員が意図的に情報を持ち出すリスクや、取引先に送信したつもりが全く関係ない企業・個人に誤送信したことで、機密情報の流出につながる可能性が高いです。
また、メールを一斉送信する際に「Cc(全受信者のメールアドレスを表示)」を誤って設定してしまい、送信したメールアドレスが他の人に流出するトラブルもあります。
中小企業が取り組むべきメールセキュリティ対策

機密情報を保護するためにも、メールセキュリティ対策として企業はどのような取り組みを行っていけば良いのでしょう。
ここで、受信メール・送信メール別の対策方法から、人的・運用セキュリティ対策まで解説します。
受信メールの対策方法
まずは怪しいメールを受け取らないための対策方法について紹介します。
受信メールに対するルールの設定
毎日取引先やDMなどから、たくさんのメールが届くこともあるでしょう。
知らないメールアドレスであるにも関わらず、添付ファイルを開いたりURLにアクセスしたりすると、マルウェアに感染する恐れがあります。
このような被害を受けないためにも、事前に社内で受信メールに対するルールを設定しておくことが大切です。
例えば、メールの本文に不自然な日本語が使われていたり、普段のやり取りでは送られてこないような形式のファイルが添付されたりしている場合、上司や担当者など他の人に相談するといったルールを決めておいてください。
また、メール攻撃の手口や最新の事例などを知ってもらうために、定期的に勉強会を開催して周知させる方法もあります。
スパムメールのブロック設定
不要な広告が含まれるメールや詐欺メールなどをスパムメールとして検出し、受信しないようブロック設定することも可能です。
また、フィルターの設定によって迷惑メールフォルダに振り分けられ、邪魔なメールを受信メールから排除できます。
ブロックを設定する方法は各プロバイダによって異なりますが、主に送信者のメールアドレスを確認し、拒否リストに登録することで可能になります。
ウイルス対策ソフトの導入
ウイルス対策ソフトの中には、メールスキャンを実施してくれるソフトもあります。
受信したメールをスキャンすることで、自分がそのメールを開く前にマルウェアがあるか検知します。
マルウェアを検知した場合、普通のメールとは隔離させて対処することが多いです。
メールセキュリティ対策専用のツールと組み合わせて導入すれば、受信メールによるリスクを大幅に低減させられるでしょう。
認証技術(SPF・DKIM・DMARC)を用いたなりすまし対策
受信メールの信頼性を確かめられる認証技術を導入することで、フィッシングメールや詐欺メールなどのなりすまし対策につながります。
例えばメール送信元のドメインを認証する方法では、送信者を検証し、認証に失敗したメールをすべて排除します。
この方法には、IPアドレスを使ったSPFや電子署名を用いるDKIM、認証に失敗したメールを隔離・拒否するDMARCなどの仕組みが活用されています。
ファイル送受信ルール(PPAP対策・自動スキャン等)の整備
メールを使ってファイルを送受信することも多いため、事前にファイルの送受信ルールを整備することも重要です。
例えば、PPAPと呼ばれるパスワード付きzipファイルと別送でパスワードを送る方法が行われてきました。
しかし、この方法はセキュリティ面で脆弱性が高いとされており、PPAPの使用を廃止する動きが進んでいます。
それでもPPAPファイルが送られてくる場合があるため、クラウド上で暗号を解除・スキャンを行い、PPAPファイルを経由してウイルス感染を防ぐ対策も必要です。
テキスト形式での受信の活用
受信したメールの中にはHTML形式も含まれますが、HTML形式のメールはプログラミングによってスクリプトを埋め込むことができ、開封した人のPCで悪意ある動作を起こさせることもできてしまいます。
そのため、HTML形式をそのまま受信するのではなく、テキスト形式に変換してから受信できるように設定することも大切です。
また、HTML形式でもメール内の画像を非表示にする設定をしておくことで、ウイルスに感染する被害を抑えられます。
送信メールの対策方法
次に、送信メールの対策方法について解説します。
送信メールの暗号化
送信メールのセキュリティ性を高めるには、通信の暗号化が効果的です。
TLSやSSLといったネット上でデータを暗号化し、送受信する仕組みを取り入れることで、万が一第三者が不正にアクセスしたとしてもメール内容の露見を防げます。
また、S/MMEという暗号化方式を採用すると、暗号化だけでなくメールへの電子署名もできるようになり、受信者がなりすましメールかどうかを区別しやすくなります。
送信前チェック体制の構築(自己承認・二重チェック・BCC強制)
送信者によるメールの誤送信や、Ccの状態で送信するなどのトラブルを防ぐために、送信前のチェック体制を構築することも重要です。
例えば、送信者がメールを送信する際に、承認画面を設けて内容の再確認を行ってもらう自己承認機能を取り入れれば、誤送信を未然に防げるようになります。
また、メールを送信すると上司などの第三者に確認依頼のメールが届き、承認されることでメールが送信される二重チェック機能も誤送信の抑制につながります。
メールアドレスの情報漏洩を防ぐなら、メールの宛先をCcからBCCへ強制的に変換する機能が効果的です。
人的・運用セキュリティ対策方法
メールセキュリティ対策というと、ウイルス対策ソフトやフィルタリングシステムなどの「技術的対策」に注目が集まりがちです。
しかし実際には、メールの誤送信や不審メールの開封など、人的ミスが原因で情報漏洩が発生するケースも少なくありません。
どれほど高度なセキュリティシステムを導入しても、従業員一人ひとりの意識が低ければ防御の穴が生じます。企業全体で「人」を中心とした対策を整えることも重要です。
従業員教育と意識向上の重要性
まず取り組むべきは、全従業員を対象にしたセキュリティ教育の実施です。
フィッシングメールの特徴や、不審なリンク・添付ファイルの扱い方などを具体的に学ぶことで、日常的なリスク回避能力を高められます。
定期的に「疑似フィッシング訓練」を行えば、どの程度注意が行き届いているかを可視化でき、教育効果も持続します。
教育内容は最新の脅威動向に合わせて更新し、繰り返し啓発することがポイントです。
メール運用ルール・ポリシーの整備
人的ミスを防ぐには、個人の意識だけでなく「仕組み」としてのルール整備が欠かせません。
例えば、外部宛てメールの送信時に上長の承認を必須とする、添付ファイルはクラウド共有リンクで送る、機密情報を含むメールは暗号化を義務化するなど、実務に即したポリシーを定めましょう。
また、ルールは作るだけでなく、定期的に見直しと周知を行うことが大切です。
全社員が同じ基準で運用できる環境を整えることで、ヒューマンエラーによるリスクを最小限に抑えられます。
導入コスト・運用コストの目安

メールセキュリティ対策は「費用が高い」という印象を持たれがちですが、近年は中小企業でも導入しやすいクラウド型サービスが増えています。
クラウド型はサーバーや専任の管理者を必要とせず、初期費用を抑えて短期間で導入できるのが特徴です。
1ユーザーあたり月数百円〜と比較的安価で、スパム対策・ウイルス検知・誤送信防止などの基本機能をまとめて利用できます。
一方で、費用対効果を高めるためには、自社に必要な機能を見極め、リスクの高い部署から段階的に導入するのがポイントです。
複数サービスを契約するよりも、メール・ウイルス・情報漏洩対策を一元管理できる統合型ソリューションを選ぶことで、運用コストの削減にもつながります。
定期的に利用状況を見直し、不要な機能を削るなど、柔軟な運用体制を整えることが大切です。
中小企業がメールセキュリティ製品・ツールを選ぶ際のポイントと比較基準
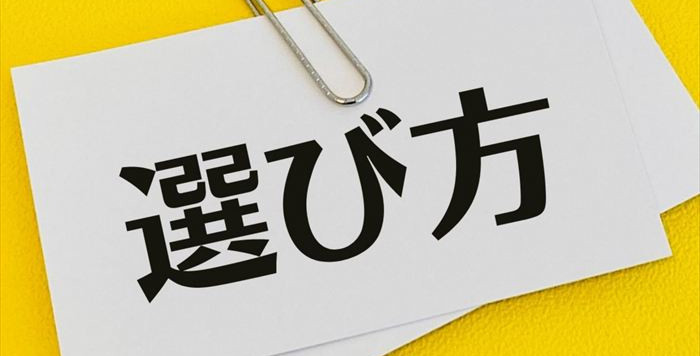
メール攻撃から大切な情報を守るためにも、メールセキュリティ製品や専用ツールの導入が有効です。
中小企業がメールセキュリティ製品・ツールを選ぶ場合、どのようなポイントに注目し、比較していけば良いのでしょうか。
ここで、製品・ツールを選ぶポイントと比較基準について解説します。
自社に必要な機能が揃っているか
メールセキュリティ製品やツールといっても、それぞれ備わっている機能は異なります。
例えばランサムウェアに対抗できるツールを導入したい場合、安全な仮想環境下でファイルを開き中身を確認できる「サンドボックス」が備わっていると安心です。
また、メールを無害化できる機能を持つ製品・ツールなら、怪しいメールはすべて無害化されてから受信メールに届くので、リスクだけでなく従業員の負担も軽減されます。
メールセキュリティ製品やツールを選ぶ前に、まず自社にどんな機能が必要なのかを洗い出してから、必要な機能が揃っているかチェックしてみてください。
自社の規模・業務内容に合っているか
中小企業の規模や業務内容によっては、求められる機能が異なってきます。
例えば一般的な業種かつ小規模であれば、ウイルス対策と迷惑メールのフィルタリング機能だけでも十分なセキュリティ効果が得られる場合もあります。
一方で、医療系や金融系など個人情報を多く取り扱う企業の場合、最低限の機能だけでは不十分であり、より高度なセキュリティ対策が必要です。
高度なセキュリティ機能が備わった製品・ツールは、その分費用もかかってくることから、自社の規模や業務内容に合わせて選ぶことが大切です。
無料版または無料期間で動作確認はできるか
メールセキュリティ製品やツールを導入したことで、業務に使用するPCに悪影響を及ぼし、通常の動作ができなくなってしまうケースもあります。
動作不良を起こさせないためにも、本格導入をする前に無料版または無料期間を活用して、動作確認を行っておくことも重要です。
ただし、メールセキュリティ製品やツールによっては無料版や無料期間が設けられていない場合もあります。
本業に支障をきたさないためにも、できるだけ動作確認が行える製品・ツールを選ぶようにしましょう。
クラウド型とオンプレ型のどちらにするか
メールセキュリティ製品・ツールは、クラウド型とオンプレ型の2つに分類できます。
クラウド型はクラウド上から提供されるサービスを活用し、メールを保護するシステムです。
送受信されるメールはすべてクラウド環境を通過するようになっているため、ウイルスやスパム、フィッシングメールなどを検知すると隔離させ、無害化させてから社内のメールサーバーや端末に送られます。
オンプレ型は、自社の施設内にサーバーやネットワーク機器などを設置し、自社でメールを保護するタイプです。
自社内に設置したメールサーバーや専用のアプライアンスを経由して、検査やフィルタリングが行われます。
ただし、オンプレ型は運用や保守にかかるコストと人的負担が大きいことから、中小企業はクラウド型から選ぶのがおすすめです。
まとめ・自社に適したメールセキュリティ対策を導入しよう
サイバー攻撃を受けるのは大企業というイメージを持つ人もいますが、近年は矛先が中小企業になっており、すでに多くの中小企業がメール攻撃を受けています。
メール攻撃を受けてランサムウェアの感染やアカウントの乗っ取り、個人情報の漏洩などが発覚すると、会社としての信用度が下がってしまうことから、早急な対策が必要です。
今回紹介した内容を参考にしつつ、自社に適したメールセキュリティ対策を導入し、大切な情報を保護しましょう。
創業手帳(冊子版)では、経営やビジネスに役立つ情報を公開しています。個人事業主やフリーランス、中小企業など、規模ごとに最適なサービスも紹介しているため、ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)





































