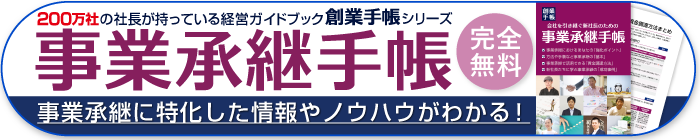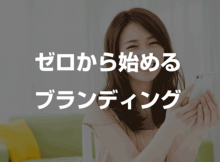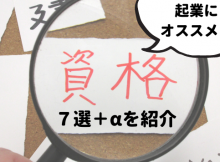会社を10年存続させるには?長く続く企業に共通するポイント
10年存続する会社には共通点がある

会社を設立したものの、10年後も存続している企業は決して多くありません。実際に統計では、多くの中小企業が数年以内に廃業や倒産に追い込まれているのが現実です。
その一方で、厳しい競争や景気の波を乗り越え、10年以上継続している会社には、必ずと言っていいほど共通する特徴や工夫があります。
この記事では、会社を10年続けることの現実や必要な経営基盤、存続させるのに必要な要素などを解説します。
成功につながるポイントや、会社を10年存続させるために今からできることなども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
▶▶▶10年続く会社づくりのヒントは『創業手帳』に掲載。無料の資料請求はこちらから。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
会社を10年続けることの現実

会社を創業してから10年後も存続している企業は6~7割程度だと言われています。これは中小企業庁のデータから推計しました。
業界別で見てみると医療・福祉は比較的低い廃業率ですが、飲食業は高い傾向です。
創業からわずか10年程度で多くの会社が廃業してしまうため、起業をしても廃業を意識して危機感を持たなければ事業存続は難しいと言えます。
廃業する理由として考えられるものの1つが「販売不振」です。商品やサービスを開発しても、思うように売れなければ利益を確保できないため、会社の存続が危ぶまれます。
また、「資金繰りの悪化」も要因の1つです。不景気だけではなく、資金配分のミスや資金調達のタイミングのミスなど、内的要因によって資金繰りが悪化するケースもあります。
これは、経営者が財務の知識に疎いことが要因です。知識を持っていなければ誤った方向で経営判断や資金調達が実施されるため、資金繰りが悪化して会社の存続にも影響を与えてしまいます。
その他にも、後継者不足や人材不足などが、廃業の理由として考えられます。創業直後から長期存続を意識した経営戦略が大切です。
▶▶▶10年続く会社づくりのヒントは『創業手帳』に掲載。無料の資料請求はこちらから。
会社を続けるために必要な経営基盤

会社を長く続けるために必要な経営基盤について解説していきます。
資金繰りと利益確保
前述のとおり、「資金繰りの悪化」は廃業する理由の1つに挙げられます。
赤字経営や資金繰り難が会社の経営に悪影響を与えるため、早い段階からキャッシュフロー管理を行うことが重要です。
資金繰りを改善するためには資金繰り表の活用がおすすめです。会社のお金の出入りを管理する表で、お金の流れを可視化できるので現状の把握や改善点の検討に役立ちます。
金融機関から融資を受ける際の資料としても活用できるため、融資を受けやすくするためにも活用を検討してみてください。
また、自己資本比率の改善を図る必要もあります。
企業の財務安全性を分析する指標として用いられるのが自己資本比率で、数値が高い方が負債に大きく依存しておらず、財務健全性が高いと言われています。
そのためにも、利益を生み出して借入金の返済を行い、自己資本を増やすことを目指してください。
その他、不要な固定資産の売却や所有している株式やリゾート会員権の売却も自己資本比率の改善に役立ちます。
短期利益と中長期的な投資のバランスを取り、安定した利益確保を続けることが存続の鍵です。
顧客基盤の安定化
顧客基盤は、ビジネスの成長を支えるための重要な資産となり、新しいビジネスの創出にも役立ちます。
企業が長期的に存続して事業拡大を図っていく上で不可欠な要素となるため、顧客基盤の安定化についても考える必要があります。
新規顧客を取り込むことも大切ですが、安定化を図るためにはリピーターを作ることも重要です。
リピーターを育成するためには、アフターサービスや顧客満足度の向上が重要です。
迅速な対応や丁寧なコミュニケーションを心がけ、「また利用したい」「この会社なら安心できる」と思われれば、リピーターになってもらいやすくなります。
また、市場調査や顧客データ分析を行い、変化するニーズに合致した商品やサービスを提供する必要もあります。
ニーズは時代によって変わっていくため、市場調査や顧客データの分析は定期的に行うことが肝心です。
さらにリスク分散を図るためにも、複数の販売チャネルを確保し、顧客接点を多様化することを検討してください。
人材・チーム作り
中小企業庁の調査によれば人材不足は廃業理由の上位にあるため、企業は採用と定着が重要課題と言えます。
就労条件の改善は、新しい人材を確保するためだけではなく、既存の従業員にとっても魅力となり、定着につながります。
給与や賞与を上げる他、休暇制度や福利厚生制度の充実など、働きやすい会社作りを目指していきましょう。
また、適切な評価制度やスキルアップ支援も効果的です。
目標の達成度合いで評価する目標管理や従業員の行動による結果を客観的に判断する評価制度のコンピテンシー評価、上司だけではなく複数の人から評価を受ける360度評価など、業種や経営環境、戦略などによって最適な評価方法を採用してみてください。
成果を生み出す組織になるためにも、チーム作りも大切です。外部の専門家や顧問を活用し、社内にない知見を補うことで組織力を高められます。
▶▶▶10年続く会社づくりのヒントは『創業手帳』に掲載。無料の資料請求はこちらから。
会社を存続するために必要な要素

会社を存続するためには、様々な要素が必要です。要素について具体的に解説していくので参考にしてください。
1.変化に対応できる柔軟性
市場や消費者のニーズに柔軟に対応できる企業は存続しやすいと言えます。市場や消費者のニーズは変化していくため、その変化に対応できなければ存続できません。
そのため、外部環境の変化を常にモニタリングし、戦略の修正や新規事業の検討を継続していってください。
競合の状況や規制変更にも柔軟に対応していくことで、長期的な企業存続が可能になります。
2.経営者の姿勢とリーダーシップ
経営者の姿勢やリーダーシップも会社の経営にとって重要な要素です。会社が軌道にのったタイミングで、経営者が会社を私物化していけば従業員離れが加速してしまいます。
成長を急ぐあまりに既存事業の強化ではなく新規事業に手を出すなど、経営者による判断ミスで会社に致命的な損害を与えてしまえば、最悪の場合倒産する可能性もあります。
経営者は意思決定の迅速さと一貫性を維持し、組織全体に明確な方向性を示すことが必要です。
社員とのコミュニケーションを密に取り、経営方針や理念を浸透させることで組織力を高めていきましょう。
そのためにも、経営者自身が学び続けることが大切です。最新情報や経営手法を積極的に取り入れる姿勢が長期存続に不可欠です。
3.健全な財務体質とリスク分散
返済義務のない自己資本を多く持ち、資金繰りが安定している状態を健全な財務体質と言います。
具体的には、自己資本比率が高く、当座比率や流動比率が良好で、キャッシュフローも安定していることが指標として挙げられます。
また、固定費を抑えて変動費化することで、売上変動による経営リスクを軽減することが可能です。
複数の資金調達ルートを確保し、緊急時の資金繰りに対応できる体制を整える方法も重要です。
4.組織文化とガバナンスの確立
組織文化とガバナンスの確立も会社を存続させるために必要な要素です。
企業として目指すべきミッションを明確にし、組織全体で共有することで従業員のエンゲージメント向上や生産性アップを図れます。
従業員が成長を目指せる文化を醸成し、経営層が率先して実施し、なおかつ従業員とのコミュニケーションも促進させれば、ビジョンへの共感を得られ、定着や強化が可能です。
また、ガバナンスに関しては不正や不祥事の防止、ステークホルダーからの信頼、持続的な成長を目指すためにも重要です。
社内規程やマニュアルを整備し、透明性の高い経営体制を確立することがポイントとなります。
コンプライアンスを遵守し、法令違反や不正行為を防止する仕組みを社内に浸透させることも大切です。
5.ブランド力と差別化戦略
企業や商品が持つ独自の価値をブランド力と言いますが、ブランド力も会社の存続には重要です。
高いブランド力を持つことができれば、商品やサービスを選ぶ際の第一候補となり、収益性アップや市場シェアの拡大につながります。
ブランド力が構築されれば、競合他社との差別化も図りやすくなります。
市場内で優位性を維持できるよう、自社の強みや独自価値を明確化し、競合との差別化を図ってみてください。
中長期的にブランド価値を高めるためには、品質管理や顧客体験の改善が重要です。
口コミや紹介を通じた信頼獲得を重視すれば、顧客のロイヤルティ向上につなげられます。
6.デジタル活用と業務改善
会社の存続を促すためにはデジタルの活用や業務改善も重要です。バックオフィス業務をデジタル化すれば、効率的な経営管理と人的リソースの最適化の実現を目指せます。
デジタル化によるデータ分析を活用すれば、経営判断の精度を高め、戦略やマーケティングに反映させることも可能です。
また、オンライン販路やデジタルマーケティングを導入すれば、新規顧客獲得や売上拡大を図ることもできます。
7.後継者問題と事業承継の準備
後継者不足によって廃業する企業も多いため、長期に亘って会社を存続させるためにも、後継者問題や事業継承の準備は早い段階から検討することが重要です。
そのためにも、事業承継計画を策定し、後継者教育や引き継ぎの体制を整備していきましょう。
また、外部人材の登用やM&Aも選択肢として検討すれば、将来の経営安定につながります。
事業承継税制などの優遇制度を活用し、財務負担を抑えながら円滑な承継の実現を目指してみてください。
8.外部パートナーとの連携と協働
会社の存続を促すためには、外部パートナーとの連携も視野に入れましょう。行政や金融機関との連携によって、支援制度や資金調達の機会を有効に活用できます。
また、取引先や同業他社との協力関係を築き、情報共有や共同事業の機会を増やす策もあります。
企業の社会的信頼とブランド価値を高めるためには、地域社会や団体との共創関係を構築することも検討してみてください。
▶▶▶10年続く会社づくりのヒントは『創業手帳』に掲載。無料の資料請求はこちらから。
長寿企業に学ぶ成功のポイント

ここからは、長寿企業に学ぶ成功のポイントを解説していきます。会社の存続を促すためにも成功している企業を参考にして、事業経営を行ってみてください。
経営理念の浸透と社員共有
理念を全従業員に浸透させ、日々の意思決定や行動指針に反映させている長寿企業は多いです。
理念共有のためには、朝礼や研修、社内報などを活用することで、従業員の共通理解を深められます。
また、会社がどの方向を目指しているのか、どんな人材が必要なのかなど、理念に沿った評価制度を導入することで、従業員の行動と企業目標を一貫させられます。
地域社会・顧客との信頼関係構築
長寿企業を目指すためにも、地域社会や顧客との信頼関係の構築は大切です。
長寿企業は、地域密着型の活動や社会貢献を通じて、地域住民や顧客との信頼関係を長期的に維持しています。
そのためにも、顧客の声を定期的に収集し、改善策を迅速に反映させることで信頼度を高めています。
地元企業や団体との協働を行い、コミュニティ内での存在感を高める取り組みを継続している企業も多いです。
継続的な事業革新と改善
事業の品質改善や効率化を行わなければ事業継続は難しいです。長寿企業は既存事業の品質改善や効率化を定期的に行い、競争力を維持している特徴があります。
新規事業やサービスについては少しずつ試験的に導入することで、リスクを抑えつつ成長の可能性を探ることができます。
また、技術や制度の変化には柔軟に対応し、時代に合わせた改善を組織的に実施することも大切です。
▶▶▶10年続く会社づくりのヒントは『創業手帳』に掲載。無料の資料請求はこちらから。
会社を10年続けるために今からできること

会社を10年存続させるには、経営戦略の定期見直しや社内外ネットワークの活用、内部統制や業務効率化の整備などが当てはまります。
以下を参考に、10年後も経営を続けている企業を目指してみてください。
経営戦略の定期見直し
経営戦略は定期的に見直しを図ってください。事業計画や中期戦略は、年に1回以上見直しを行い、達成状況と課題を明確化させます。
市場環境や競合状況を分析し、必要に応じて戦略の方向性を修正することも大切です。
また、KPIや数値目標を社内で共有し、計画と実行のギャップを早期に修正することも重要です。
社内外ネットワークの活用
10年後も会社を存続させるためには、社内外ネットワークの活用も欠かせません。
そのためにも、商工会議所や業界団体に参加し、最新情報や支援制度を活用できる体制を整えましょう。
また、経営判断の相談先として信頼できる専門家やコンサルタントとの関係を構築し、随時不安点や問題点を相談してみてください。
異業種交流や勉強会を通じて、新しい知見や協力関係を得ることで事業拡張の可能性を広げることができます。
内部統制と業務効率化の整備
会社の長期存続には社内運営の効率化が不可欠です。そのため、業務フローの標準化やマニュアル化を進めることで効率化を図れます。
経理・労務・在庫管理などの重要業務においては、内部統制を整備し、不正やミスの防止に努めてください。
ITツールや自動化を活用すれば、従業員の負担を減らすことができ、組織全体のパフォーマンス向上を目指せます。
▶▶▶10年続く会社づくりのヒントは『創業手帳』に掲載。無料の資料請求はこちらから。
ポイントを押さえて会社を10年存続させよう
会社を10年続けるには、資金・顧客・人材の基盤作りと変化への対応力が欠かせません。
理念と利益を両立し、地域や顧客との信頼関係を築くことが存続企業の共通点です。
長く成長できる会社を目指すためにも、計画の見直しや支援制度の活用を検討していきましょう。
創業手帳(冊子版)では、事業を継続させるために役立つ情報を豊富に紹介しています。大切な会社を10年以上存続させるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
(編集:創業手帳編集部)