監査役には誰がなる?選任の条件や方法、適した人物の特徴を解説
健全な経営の実現のため監査役を選任しよう

会社の健全な経営のためには、監査役を正しく選任する必要があります。
企業の業務執行が適切に行われているかどうかを監視、監督する役割を持つ監査役は、経営陣から独立性を確保する存在でなければなりません。
この記事では、健全な経営を実現するために、監査役を選ぶ方法や監査役の仕事内容をはじめ、監査役に必要な資格と条件について解説します。
監査役の選任方法を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
監査役の役割と仕事内容

監査役は、企業の業務執行が適切に行われているか監督、監視する役割を持つ人を意味します。
会社法381条1項にあるように、監査役は職務の執行を監査する権限を持つ存在です。
また、独立した立場で監視しなければならず、会社の透明性を保つために欠かせない存在といえます。ここでは、監査役の役割や仕事内容について解説します。
監査役の役割
監査役の役割は、企業が健全で適切な業務執行や経営判断をしているか第三者的な立場で監査することです。
持続的な成長を確保して、社会的信頼に応えられる良質な企業体制を確立する義務を負っているかを判断します。
監査役がいることで株主や投資家からの信頼を得やすく、監査役がいる企業は適正な企業統治体制や法令遵守が担保されることにも期待されます。
監査役の仕事内容
監査役の主な仕事内容は、業務監査と会計監査です。業務監査は、取締役の業務執行や定款や法令を確実に守り、これらに違法性がないかをチェックします。
業務監査では、取締役会への出席や取締役が作成した書類の閲覧、取締役などとの意思疎通なども業務監査に含まれ、監査結果の報告によって発表されます。
会計監査では、企業や公共団体などの組織が作成した計算書類や財務諸表に誤った部分がないかを監査し、経理上の計算書類に法的な不正がされていないかなどをチェックしまなければなりません。
会計監査とは、企業や公共団体などの組織によって作成された計算種類などを第三者が監視することです。
会社の経営判断においても誤りがないかを確認して、株主、取引先、従業員に不利益が被らないようにします。
監査役が必要な企業・設置できない企業
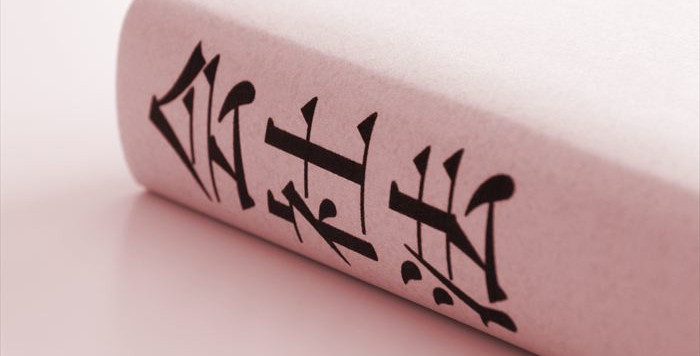
すべての会社に監査役の設置義務があるわけではありません。監査役を設置できない場合もあります。ここでは、その違いを紹介します。
監査役の設置が必要な企業
すべての会社が監査役を設置しなければならないわけではありません。監査役が必要な企業は、「会計監査人設置会社」と「取締役会設置会社」のみです。
会計監査人設置会社は会社法第327条第3項で監査役を設けることが決められていて、監査役が義務となるのは大会社となります。
会社法で大会社に該当するのは、資本金5億円以上または負債額200億円以下いずれかの条件を満たす会社です。
一方の取締役会設置会社は、取締役会を設置する会社、会社法によって取締役会設置義務の会社です。
これらの会社に該当する場合、会社法327条第2項で監査役の設置が定義されています。
監査役を設置する理由は、取締役会の意思決定の公正性を確認して企業の透明性や法令遵守がされている状態を保つためです。
ただし、公開会社ではなく会計参与を置いている株式会社は、例外として監査役設置の義務が生じることに注意してください。
監査役を設置できない企業
一方で監査役を設置できない企業もあります。
「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」は監査役の権限が重複することを避けるため、監査役を設置できません。
監査等委員会設置会社は、社外取締役を新たに活用した監査体制で、取締役会に監査等委員会を置き、3人以上の体制で監査を担う形となります。
指名委員会等設置会社は、取締役会の下に報酬、指名、監査それぞれ3名以上の取締役で構成された委員会により、業務を監査する流れです。
ただし、監査の対象は取締役の業務執行です。こちらの場合も監査役は設置できません。
監査役に就任できる人の資格・条件

監査役になるために特別な資格は不要です。ここでは、監査役に就任できる就任できる人の資格・条件について解説します。
監査役になれない人の条件
会社法では、特定の条件に当てはまる人材は監査役にできないことが定められています。会社法第331条と会社法第335条で決められた内容に記載されているので確認してください。
会社法第331条と会社法第335条では、監査役になれない人の具体的な条件として以下の項目を挙げています。
-
- 法人
- 監査を実施する会社の取締役・支配人・使用人、または子会社の取締役・支配人・使用人・会計参与・執行役員
- 会社法などの規定違反を行い刑に処せられた後に執行を終えた、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない人
- 法令違反によって禁固刑以上の刑に処せられてからその執行を終えていない、もしくは執行を受けることがなくなっていない人
社外監査役になる条件は厳しい
監査役には、社内監査役と社外監査役がありますが、社外監査役には厳しい要件が定められています。会社法第2条16項で定められていますが、簡単に解説します。
-
- 就任前の10年間で当該会社および子会社の取締役・会計参与・執行役員・支配人・その他使用人になっていない
- 就任前の10年間で当該会社および子会社の監査役だった場合、当該監査役に就任する前の10年間で当該会社および子会社の取締役・会計参与・執行役員・支配人・その他使用人になっていない
- 当該会社の親会社などで取締役・監査役・執行役員・支配人・その他使用人ではない
- 当該会社の親会社・子会社などで業務執行取締役などに就任していない
- 当該会社の取締役・支配人・その他重要な使用人や、親会社などの配偶者や二親等以内の親族ではない
監査役に適した人の特徴

監査役にどのような人が適しているのかわからない人もいるかもしれません。ここでは、監査役に適した人の特徴について解説します。
弁護士
業務監査では、法律に従って運営しているかを監査します。
監査役が弁護士であれば、法律違反を見抜いたり、消費者の安全確保のために責任を持って取り組んでくれたりします。
弁護士は法律の専門家であり、業務において法律違反がされていないか正しくチェックできるからです。
近年は産地偽装などで法律違反を行うケースもあります。
このような事件が明るみに出てしまえば企業の信頼が崩れるだけでなく、株価の暴落や利益を害する可能性も高いです。
これらの要因によって当然株価の大暴落、売上低下、従業員の倒産などにも影響が出てしまえば立て直すことに時間もかかりますが、未然に防げる可能性もあります。
公認会計士や税理士
公認会計士や税理士も社内監査役に適しています。決算書類などの作り方を知っているだけでなく、不正が起こりやすい部分も熟知しているからです。
また、監査および会計の専門家であれば、企業会計の監査役としても適任です。
とくに、税理士は税務の専門家で、企業会計に詳しいだけでなく、税務ルールや法律にも熟知しています。
これらの資格者を監査役にすれば、粉飾決済の防止や会社のダメージとなる損害を未然に防いで利害関係も守れます。
元税務署職員や元銀行員
元税務署職員や元銀行員も社内監査役に適しています。
税務署職員は、企業が不正や脱税をしていないかを確認できるため、業の会計書類のチェックや粉飾決算の有無を見分ける力に長けているのです。
また、脱税のリスクを熟知しているので監査役に適任です。
なお、銀行員は日常的に企業の財務分析を行い信用力について調査しています。
銀行としても貸したお金が返ってこなければ、大きな損失を抱えてしまうため、このように企業の決算状況を常に確認しています。銀行員も会計監査の適任者です。
CFO(最高財務責任者)
CFO(最高財務責任者)も監査役に適した人材です。CFOは、組織内で最高位の財務専門家であり、常に財務状態を監視しています。
一般的な企業財務の専門家ではなく、欧米などではCEO(最高経営責任者)と同じステータスが確保されています。
企業の財務戦略の策定を行うのみでなく、それを実行する重要な役割を担う存在です。資金調達や財務報告の監督、投資分析、リスク管理などを含めた業務を担当します。
高度な分析力があり、企業の財務データを正確に分析して予測を立てられると、資金の流れから持続的な成長について対応できる能力があります。
内部監査を経験したことがある人
過去に内部監査を経験した人も監査役に適しています。監査役は、企業が適切に事業を運営、経営、管理、監視しているかを見極める重要な役割です。
業務内容や権限を理解して信頼している内部監査経験者は、業務上の不正防止や業務改善において気づきにくい問題点を見つけてくれます。
観察眼に優れていて関連する法律や会計に関する知識もあり、コンプライアンス意識も高い傾向です。
監査役を選任する方法

ここからは、監査役を選任する方法を解説します。
1.監査役候補者に打診する
監査役になるためには、上記で解説したような人材を選出して事前に打診します。監査役は重要な職務であり、その分責任も重大です。
口約束やその時の気分で簡単に返事ができるものではないかもしれませんので、候補者には内容を十分に理解してもらい、覚悟を持って就任してもらう必要があります。
なお、監査役会設置会社の場合は3人以上の監査役を設置します。そのうちの半数以上は社外監査役であり、常勤監査役は1名です。
この場合は社内と社外での監査役を選任しなければならず、欠員が出た場合のことも考えて複数人の人材を選ぶと安心です。
2.現任の監査役または監査役会から同意を得る
監査役候補者が就任する意思を固めた場合、監査役または監査役員会から同意を得なければなりません。
ただし、監査役員会設置会社では、監査役員会から過半数の同意が必要です。
監査役員または監査役員会では、候補者に対して経験、経歴、適性などを審査して同意を決定する流れです。
3.株主総会で選任議案を提出する
監査役を選任したあとは、株主総会に選任議案を提出します。
株主総会では、普通決議によって選任される流れです。会社法329条1項で定められている流れで、必ず行う必要があります。
株主総会出席者の過半数の同意を得れば、監査役が選任されます。
4.役員変更登記の申請をする
監査役決定後は登記手続きが必要です。株主総会の翌日を起算日として2週間以内に管轄の法務局に申請を行います。
必要な書類は「株主総会議事録」「株式会社変更登記申請書」「株主リスト」「本人確認書類」「委任状(司法書士に依頼した場合)」です。
手続きには、印鑑証明代や登録免許税などがかかります。登記を怠った場合には罰金が科せられる可能性もあるので忘れずに申請してください。
監査役の任期はいつまで?

監査役になった場合、取締役の職務執行監査を行いますが、解任されなければ任期が続くわけではありません。
監査役の任期は原則4年で、選任後4年以内に終了する事業年度で最終のものに関する定時株主総会が終結するまで続きます。
独立性の観点から、原則として任期短縮はできません。
ただし、補欠監査役では定款の決まりがある場合、ある監査役や退任後にその補欠として選任された監査役は、退任した監査役の任期満了にともなって退任します。
まとめ・監査役に誰がなるのか、適任者を見極めよう
会社は取締役の業務執行の独立性を確保しながら、監督、監視する役割として監査役を選任します。健全な経営のためには、適した人材を監査役に選任しなければなりません。
本記事を参考にしながら適した人材を監査役にすることで、業務執行や組織運営の健全性が保てます。
監査役の設置をはじめ、会社を運営していくうえではさまざまな法務・登記の知識が必要です。
『創業手帳』には、会社設立の手順から経営体制づくり、資本金・税務・届出まで、起業時に知っておくべき実務を一冊にまとめています。
これから会社運営の基盤を整えたい方は、ぜひ手に取ってみてください。
(編集:創業手帳編集部)




































