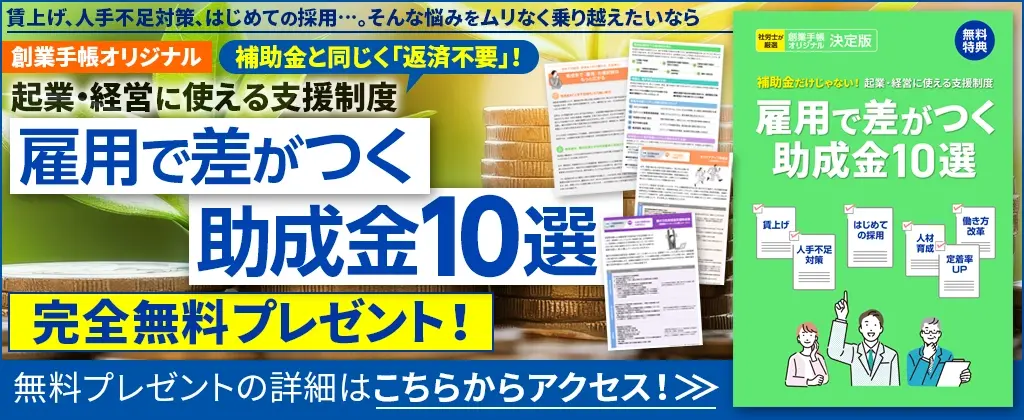所定労働時間とは?定義・雇用形態別の違い・明示義務をわかりやすく解説
就業規則・契約書の明示に役立つ「所定労働時間」の基本知識

従業員を雇う側は、労働時間に対する確実な把握が重要です。また、所定労働時間は会社によってルールが異なることに注意が必要です。
今回は、所定労働時間の基本知識について解説していきます。
定義や雇用勤務形態別の定め方、関連制度や明示に関する事項まで、幅広い内容となっているので、知識を補うためにも参考にしてみてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
所定労働時間とは?定義について

労働契約や就業規則などであらかじめ定める労働時間を所定労働時間といいます。
休憩時間を除いた始業時刻から終業時刻までの時間を指し、労働基準法で定められている1日8時間、週40時間の範囲内で企業が自由に設定することが可能です。
あらかじめ労働させることを約束した時間で、労働契約書に「毎週月~木、始業8時 就業17時 休憩1時間」と記載があれば、1日の所定労働時間は8時間、1週間の所定労働時間は32時間です。
法定労働時間との違い
法定労働時間の「法」は、労働基準法を指しています。労働基準法第32条では、定めら1日8時間、1週間40時間の労働時間の上限が定められています。
原則として、法定労働時間を超えた労働をさせてはいけないことになっており、法定労働時間を超えて労働させる場合には36協定を締結し、労働基準監督署に届け出しなけばれなりません。
また、割増賃金の支払いも必要です。
所定労働時間は、法定労働時間の範囲の中であれば自由に設定できます。
所定労働時間が1日6時間であれば、その時間を越えて1時間残業しても法定労働時間の1日8時間を超過していないため、36協定の締結も必要なければ割増賃金の支払いも必要ありません。
実労働時間との違い
従業員が実際に働いた時間のことを実労働時間といいます。
所定労働時間は法定労働時間内で定められた労働時間のことですが、実労働時間は、所定労働時間に時間外労働時間を加えた時間が当てはまります。
所定労働時間が6時間で時間外労働が1時間であれば、実労働時間は7時間です。
労働基準法では、実労働に基づいて賃金が支払われます。両者に差異があれば、実労働時間を基準にして残業代が掲載される仕組みです。
企業は労働時間を客観的に把握する責務があるため、タイムカードやPCログなど、客観的な記録による勤怠管理をしなければなりません。
企業が所定労働時間を定める方法とよくある設定例
所定労働時間は、就業規則や雇用契約書で明示されることが一般的です。
設定の際には、業種や業務の特性、従業員の働き方を考慮し、始業・終業時刻、休憩時間なども含めて総合的に決定します。
オフィス勤務でよく見られるのが「9時〜18時(休憩1時間)」、時短勤務では「10時〜16時(休憩1時間)」といった設定です。
企業側には、労働基準法に違反しない範囲で、従業員の働きやすさを考慮した労働時間の設定が求められます。
【雇用・勤務形態別】所定労働時間の決め方
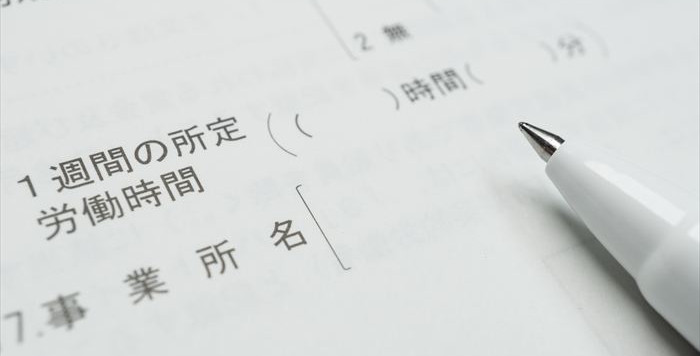
近年、働き方や契約内容が多様化しており、雇用形態や勤務形態によって、所定労働時間には違いが生じています。
ここからは、時短勤務、派遣社員、パート・アルバイトなど、雇用形態や勤務形態別の所定労働時間について解説していきます。
時短勤務(短時間正社員)
1日の労働時間を通常よりも短くして働くことを時短勤務といいます。所定労働時間が8時間と定められた会社で6時間や7時間で働く場合は時短勤務です。
勤務時間は、本人の事情や業務ニーズによって通常の正社員の範囲内で設けられます。
育児介護休業法によって2012年7月からすべての事業主に短時間勤務制度の導入が定められています。
そのため、企業が任意で導入するものではなく、原則導入が義務付いている労働者の権利です。
ただし、時短勤務は育児や介護といった理由がある場合のみに適用される制度です。
育児は3歳に満たない子どもを養育している労働者が対象で、1日の所定労働時間が6時間以下や入社1年未満といった労働者は対象外となります。
介護では要介護状態にある対象家族を介護する労働者が対象となり、日雇いや週の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外です。
派遣社員
派遣会社と雇用契約を結んで別の会社で働く人を派遣社員といいます。派遣先企業の指揮命令で業務に従事しますが、雇用主は派遣元となる派遣会社です。
派遣社員にも法定労働時間の上限が適用されるため、1日8時間、週40時間以内で所定労働時間が決められます。
所定労働時間を超過した場合には、割増賃金の支払い義務も発生します。
ただし、実際の勤務時間は派遣先の指揮命令下で実施されるため、両者の間で労働時間管理の連携が必要です。
パート・アルバイト
正社員よりも労働時間が短い労働者のことで、学生やフリーター、主婦などがパート社員やアルバイト社員として企業で従事しています。
パートやアルバイトの所定労働時間は、雇用契約書で個別に定められています。
1日8時間、週40時間の制限は正社員と同様です。しかし、正社員と比較すると所定労働時間は短く、例として以下のような時間が設定されます。
-
- 学生:始業17時 就業21時 週4日
- 主婦:始業9時 就業15時 週5日
これらの労働時間は、あらかじめ企業が定めて募集する以外にも、従業員が自分で決められる場合もあります。
フレックスタイム制
一定期間の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者がその範囲内で自由に始業時間や就業時間を決められる制度がフレックスタイム制です。
生活スタイルや業務状況によって柔軟に働く時間を決められるメリットがあります。
なお、1日8時間、週40時間以内の法定労働時間は適用されません。以下の方法によって所定労働時間を求められます。
清算期間の暦日数÷7日×40時間
所定労働時間が法定労働時間を越えた場合に割増賃金が発生する仕組みです。
変形労働時間制
繁忙期や閑散期に合わせて労働時間を調整できる制度が変形労働時間制です。
本来であれば、1日8時間、週40時間を超えて労働させることはできず、それ以上働かせる場合には残業代を支払う必要があります。
しかし、変形労働時間制であれば労働時間を調整でき、余計な残業代を支払う必要はありません。1週間単位、1カ月単位、1年単位の3種類があります。
・1週間単位
曜日の繁閑に合わせて労働時間を調整できます。平均して所定労働時間が週40時間に収まるように調整しなければなりません。
・1カ月単位
1カ月単位の平均労働時間を1日8時間・週40時間の所定労働時間内で調整できます。
1カ月単位で調整すれば、1日の労働時間や休日の制限はありません。
例えば、月の前半が閑散期、月の後半は繁忙期であれば、前半を9時~16時の実働6時間、後半を8時~19時の実働10時間と労働時間を柔軟に定められます。
・1年単位
繁忙期に労働時間を増やして閑散期に労働時間を減らすことで、年間の平均労働時間を所定労働時間に調整できます。
年間で繁忙期と閑散期がはっきりしている業種におすすめです。
業務量に応じて労働時間を調整できるため、従業員の負担を軽減しながら生産性向上を目指せます。
所定労働時間と関連制度|休憩・休日・有給の考え方

所定労働時間を深く理解するためには、知識を備えておく必要があります。休憩、休日、有給のそれぞれのルールや考え方について解説していきます。
休憩のルール
休憩時間には法律によって決められたルールがあります。
休憩時間を多く与える分には問題ありませんが、休憩時間が少ない場合や休憩時間を与えない場合には罰則が科せられる可能性もあることに注意してください。
労働基準法における休憩時間は以下のとおりです。
-
- 労働時間6時間以上:少なくとも45分
- 労働時間8時間以上:少なくとも1時間
労働時間が6時間以下の労働者に対して休憩時間を与えなくても問題ありません。
なお、休憩時間は労働時間に含まれていないため、休憩時間分の賃金を支払う必要はありません。
休日の種類と考え方
休日には、労働基準法で定められている法定休日と企業が独自に設定する所定休日の2つがあります。法定休日は週1日または4週4日です。
所定労働時間は週40時間以内で設定するため、多くの企業では完全週休2日制を採用し、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日に設定するのが一般的です。
年次有給休暇との関係
年次有給休暇には、労働基準法によって勤務年数に応じた日数の付与が義務付けられています。
正社員であれば入社6カ月後に10日間、以後1年ごとに1日ずつ(継続勤務3年6カ月以降は2日ずつ)増加していき、最大で20日まで毎年付与されます。
ただし、付与するためには条件があります。
-
- 6カ月間継続勤務している労働者
- 6カ月間の全労働日8割以上出勤している
上記要件を満たせばパートやアルバイトにも付与する必要がありますが、付与日数は正社員とは異なります。
所定労働時間は明示が義務|トラブルを防ぐためのポイント
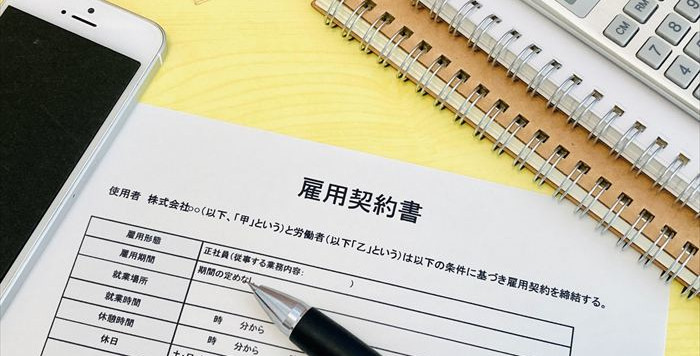
労働者を雇用した際には、企業は労働条件を明示する義務があります。トラブルを防ぐためにも重要なポイントなので、あらかじめ理解しておいてください。
雇用契約書・労働条件通知書での明示方法
明示は、雇用契約書や労働条件通知書を活用して行います。
・雇用契約書
企業と従業員の間における雇用契約を証明する書類です。始業時刻や終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無や休憩時間などを明示します。
雇用の際には内容確認や捺印を実施し、明確な契約として内容を共有します。
・労働条件通知書
従業員を採用する際に、労働条件などを記載して従業員に対して交付する書類を労働条件通知書といいます。
雇用契約書と同様に、始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無や休憩時間などを明示します。
ただし、あくまでも通知書類であり、内容を確認して互いが理解したという証明にはなりません。トラブルを避けたいのであれば、雇用契約書を活用してください。
明示しなかった場合の罰則
労働条件の明示をしなかった場合、以下のような罰則が科せられます。
-
- 明示義務違反:30万円以下の罰金
- パートや有期雇用労働者への明示義務違反:10万円以下の過料
罰則以外にも、労働基準監督署による行政指導の対象になる可能性があるほか、従業員から慰謝料の請求や労働契約の解除などを請求されるかもしれません。
悪質な場合には、企業名が公表されるため、イメージの低下につながります。
所定労働時間と残業の関係を簡単に理解しておこう
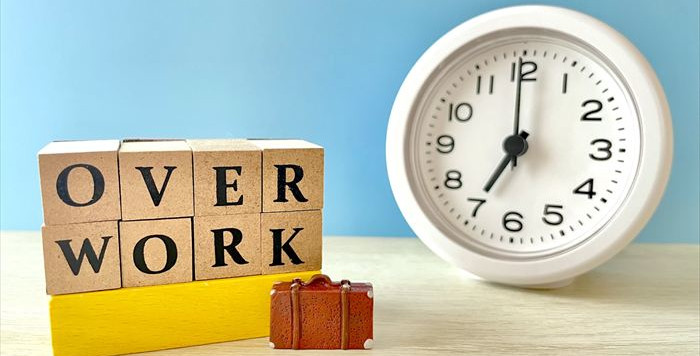
所定労働時間を超えた働き方は、必ずしも「残業=違法」ではありません。
「法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)」との関係性や、36協定の締結状況によって対応が異なります。
法定労働時間を超えて従業員を働かせたい場合には、労使協定を締結しなければなりません。「36協定」と呼ばれており、労働基準法第36条に基づく労使協定の略称です。
企業と従業員の双方が合意し、労働基準監督署に届け出をすれば、時間外労働として法定労働時間を超えて働けます。
ただし、月45時間(年間6カ月まで)、年間360時間が上限となり、臨時的で特別な事業がない限りは、上限を超えて労働できません。
臨時的な事情がある場合でも、年720時間、休日労働を含んだ複数月平均80時間以内、月100時間未満を越えた労働は禁止です。
まとめ・所定労働時間は正しく理解しよう
法定労働時間や休憩、休日や年次有給休暇など、それぞれのルールや関係性について理解していなければトラブルを招く可能性があります。
また、法改正を考慮すると定期的な見直しも不可欠です。それぞれの規定をはじめ、時間外労働や育児・介護休業制度など、関連する条項の定期的な確認が必要です。
社労士といった専門家に相談すれば、適切なアドバイスを受けられるため、不明な点があれば相談を検討してみてください。
従業員を雇ううえでは、契約内容の整備だけでなく、国の支援制度の活用も見逃せません。
創業手帳では、初めての採用や正社員化、育児・シニア雇用支援などに使える
「雇用で差がつく助成金10選」を無料で配布中です。
「人を雇いたいけど負担が不安…」という方にもわかりやすく、
支給額・要件・申請の流れを一覧表で整理しています。
制度を知るだけでも大きな一歩。ぜひあわせてご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)