なぜ”捨てられるはずのもの”が人気商品に?人気の裏に”廃材”あり!
ゴミのはずが…「捨てる」が「売れる」に変わる時代

大量生産、大量消費の時代は長く続いたものの、環境問題やSDGsといったキーワードが聞かれるようになりました。
SDGsや物価高の影響で、消費者の意識が「安く買う」から「意味のある買い物」へとシフトするようになりました。
そのひとつが廃材の利用です。廃材や端材は製造コストが低く、企業にとって利益率の高い商品開発も可能です。
従来の大量生産・大量消費から、ストーリー性のある少量生産品に価値を見出す時代となり、「捨てる」が「売れる」に変わる時代となりました。
様々な業界の事例からどういった廃材や端材がヒット商品となったのか見ていきます。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
廃材や端材がヒット商品になった事例

廃材や端材を活用したビジネスモデルは、すでに多様な業界で成功を収めています。
ここからは、具体的な事例を通じて、その成功要因を紹介します。
廃材や端材をコーヒーグッズやオブジェ、インテリア素材として活用
家具を製造する過程で発生する端材や家具にはできない短い木材はインテリア素材などに活用できます。
この事例では、家具メーカーとコーヒー会社がコラボして、廃材や端材からドリッパースタンドやフィルターケースを製造しました。
木の素材を生かしたシンプルデザインが採用され双方の会社名の印字が印象的です。
また、家具製作の端材を利用した干支オブジェを毎年発表している企業もあります。
3Dデータを用いて木材の切削を自動化する機器を導入したことで、滑らかで手になじむ表現が可能になりました。
廃材、端材の利用はストーリー性を持たせることもできます。インド洋でカヌーとして使われていた木材や線路の枕木として使われていた素材を使った家具が注目されています。
廃材を「味のある素材」として再定義し、ペンキ跡などの風情を残しながら自然素材の塗料でコーティング処理して新しく家具として利用した事例です。
大量生産の製品は品質が安定しているものの、無個性ともとらえられます。歴史や味わいを残した家具はそれぞれが異なる表情を見せてくれます。
自分だけのオリジナルの製品を持ちたいという消費者のニーズに応えたビジネスです。
規格外野菜や余剰野菜をスムージーに
SDGsのテーマとして、フードロスの削減も多くの人が関心を持つテーマです。
例えば野菜や果物は規格を外れていたり、納期が合わなければ出荷できずに廃棄されるものもたくさんあります。
見た目や納期の問題でだけで廃棄される野菜は、栄養価や味には問題がありません。そこで規格外野菜や余剰品野菜を加工品として活用するビジネスが注目されています。
これらの野菜をスムージーパックとしてオフィスに届けるほか、個人向けの冷凍スムージーのサブスクリプションサービスを提供しています。
テレワークやサテライトオフィスのように場所にとらわれない働き方も広がりました。
そこで、在宅時間の増加にともなって拡大余地がある宅食市場を開拓したサービスを提供しています。
規格外野菜や余剰野菜といった農業における長年の課題を解決するチャレンジです。
ビール製造副産物をお菓子や肥料に
フードロスは、食べられずに捨ててしまう食品だけではありません。食品の製造過程で発生する副産物も産業廃棄物として捨てられてしまいます。
麦芽粕(モルト粕)は、ビールの製造過程で発生します。そこでサステナブルジャンクをコンセプトにチョコチャンククッキーの製造にチャレンジしました。
ボリューミーでザクザクの食感、香ばしさが感じられます。
また、エコな商品と聞くとナチュラルテイストのものを思い浮かべがちですが、この製品ではポップで派手な色合いでテンションが上がるパッケージを採用しました。
リサイクルや再利用と聞くと、何かを我慢しなければならないようなイメージを持つ人もいるかもしれません。
この製品では、地球や身体のために我慢するのではなく、わくわくして楽しさを感じられるアイデアの創出を目指しています。
不要な衣類をリメイクファッションに
世界のファッション業界で発生するごみは9,000万トン以上です。
「服から服を作る」をコンセプトにしたこの企業では、不要な衣類の回収から新しい服への再生までを一貫して行っています。
連携しているブランドは200以上です。衣類を回収してケミカルリサイクル、Tシャツやパーカー、靴下などんを作っています。
もともとポリエステル素材のリサイクルに長けたメーカーであり、古着に含まれるポリエステルを使って、再度ポリエステル樹脂を製造する技術を開発しました。
古着となった服から再度服を作ることによって廃棄物になることなく循環します。サーキュラーエコノミーを社会に実装するブランドとして認知度が高まっています。
なぜ人は”余りもの”に惹かれるのか?

廃棄物や端材の再利用は、社会的な意義があるものです。しかし、これらの”余りもの”に人が魅力を感じるのは社会的意義だけではありません。
ここからは、消費者の心理的な変化と、廃材商品が持つ独特の魅力についての分析しました。
「もったいない」が「応援したい」に変わる
大量消費時代と比較して消費者の価値観は大きく変わってきています。消費者の価値観は「所有する喜び」から「社会貢献する喜び」へと変化してきています。
価値観が変化する一方で、逆に「もったいない」という日本古来の概念は、現代的な「エシカル消費」として再評価されるようになりました。
購買体験は、商品の価値だけではなくその背後のストーリーも重要です。
環境への配慮がある商品を購入することで環境保護に貢献できるという満足感が、購買意欲を高めています。
エシカル・サステナブル志向の拡大
SDGsやサステナビリティへの関心が高まり、環境配慮型商品への需要が増加しています。持続可能な社会の実現を目指す考え方は若年層を中心として広まりました。
倫理的な観点、環境配慮を考慮した商品選択、消費行動が求められ、企業の社会的責任を重視する傾向が強まっています。
価格だけでなく、商品の背景や製造プロセスを重視する消費者が増えたことで企業も応えるようにエシカル・サステナブルな商品開発、サービス提供に力を入れるようになりました。
「一点もの」と「背景ストーリー」への関心
大量生産品は基本的に無個性で多くの人が同じものを所有しています。
大量生産されたたくさんの商品に囲まれているからこそ唯一無二の商品価値が注目されるようになりました。
その商品を唯一無二にするのは背景になる物語です。商品の製造過程や素材の由来に興味を持つ消費者が増加しています。
廃材や端材を使用している商品はSNSで共感を集めやすい「ストーリー性のある商品」です。
「一点もの」と「背景ストーリー」があることによって購買後の満足度も高まります。
「購入=共感・応援」という新しい動機
今までの購買行動では実用性や機能性、価格などを重視していました。しかし、近年になって企業の理念や取組みへの共感が購買動機となっています。
それが明確に表れているのが「応援消費」です。応援消費とは、商品を購入することで、企業やプロジェクトを応援する行動です。
その商品を購入することによって消費者自身が社会問題解決の一部になれるという参加意識が購買を促進しています。
企業が仕掛ける”逆転マーケティング”のポイント

廃材や端材を使うからこそ、ほかにはない価値が生まれてそれが消費者に評価される逆転マーケティングの流れは多くの分野で成功しています。
ただし、廃材や端材を使っていれば必ず成功するわけではありません。
廃材や端材を活用したマーケティングの成功要因を、具体的な手法とともに解説します。
原価が低い
廃材や端材を使った商品が成功するためには、まず原価の問題をクリアしなければいけません。
原材料費が低ければ、小ロット生産でも採算が取れ、市場テストがしやすい傾向にあります。
また、原価が安ければ初期投資を抑えて新商品開発ができるので、スタートアップや中小企業でも参入しやすいでしょう。
廃材や端材を使ったビジネスは、思ったような商品が作れずに失敗してしまう可能性もあります。
失敗リスクが低く、多様な商品展開を試行錯誤できる環境を整備しておくことが重要です。
ストーリー性がある
廃材や端材を活用するというストーリーは、企業のブランドイメージ向上に直結します。
商品の背景に社会的意義があることで、消費者の記憶に残りやすく、購買後の満足度を高めるのです。
多くの企業が環境や社会問題に取り組んでいます。しかし、多くの企業が取り組んでいるからこそ、独自性がある取組みが求められています。
廃材や端材使った商品は、印象的であり消費者にアピールできる具体的な事例として活用可能です。
SNSと相性が良い
廃材や端材から作られた製品は希少性が高いものもあり、ほかの製品にはない意外性があります。
そのため、SNSでの拡散効果が高く、低コストで高い宣伝効果が期待できるのです。
木やガラスといった元の素材感を活かした商品であれば「before→after」のストーリーが視覚的に伝わりやすく、ビジュアル面での訴求が強いためシェアされやすい傾向があります。
エコやSDGsといったテーマは共感性が高く、インフルエンサーやメディアが取り上げやすいトピックとしてSNSでこれからも注目を集めていくでしょう。
販売より「体験」を売る
現代の消費者は、商品そのものだけでなく、購入体験や使用体験に価値を見出すケースが増えています。
そのため、工場見学やワークショップなど、廃材活用のプロセスを体験できる仕組みが効果的です。
顧客が商品の価値創造プロセスに参加することで、世界でここにしかない商品が生まれます。
その体験も含めた商品なので強い愛着が生まれ、口コミで誰かにおすすめしたりリピート購入したりといったアクションにもつながりやすくなります。
はじめるヒント|自社の”捨てているもの”を見直してみよう

廃材や端材を利用したビジネスは、アイデアさえあれば低コストからスタートできます。
実際に廃材活用ビジネスをはじめるための具体的なステップとポイントを紹介します。
「もしかしたら価値があるのかもしれない」と新しい視点で自社で捨てているものを見直してみてください。
廃材を「資源」として再評価する
廃材や端材について、そもそも利用するという視点を持ったことがない企業も多いかもしれません。
活用するスタートとして、製造工程で発生する端材や副産物を「コスト」ではなく「資源」として捉え直してください。
もしも資源として利用できれば廃棄コストを削減しながら、新たな収益源を創出できる可能性が生まれます。
どういった廃材、端材が生まれているかは現場で働いている従業員のほうが知っているかもしれません。
社内の各部署と連携し、どのような廃材や副産物が発生しているかを調査することがスタートです。
廃棄物に新しい価値を付与する
廃棄するものは見方を変えれば、新しい商品の素材になります。
副産物である食品からほかの食品を製造したり、端材からほかの商品を製造したりと既存の廃棄物に新しい意味や価値を付与することで、新たな収益源を発見できることがあります。
そのためには、消費者のニーズや市場動向の分析が欠かせません。消費者がどういったテーマに興味があるかを知って廃材の活用可能性を検討します。
また、廃材や端材を活用していても商品自体に魅力がなければ受け入れられないかもしれません。安っぽい、手抜きに見える商品では訴求はできません。
デザイナーやクリエイターと協力し、廃材を魅力的な商品に変える方法を模索てください。
共感を呼ぶストーリーを構築する
消費行動に価値をもたらすには、商品を開発する作り手がストーリーを構築して提供することが大切です。
捨てられるはずのものが新しい魅力を得て商品化するといった消費者の共感を得やすいストーリーを構築するプロダクトアウト的なアプローチが効果的です。
共感を呼ぶためには、説得力が必要です。商品の背景や製造プロセスを丁寧に説明し、消費者の理解と共感を促してください。
企業と商品のファンになってもらうためにはSNSやWebサイトを活用し、廃材活用の意義や効果を継続的に発信するようにおすすめします。
まとめ|”無価値”を”無限の価値”に変える発想力
従来であれば「廃棄物」として処理していたものも、発想を転換すれば新しいビジネスチャンスになります。
これには消費者の価値観の変化も関係していて、それに企業の創意工夫が組み合わさることで、持続可能な事業モデルが生まれるはずです。
捨てるしかないと思っているものに新しく価値を与えるのは人のアイデアです。
「捨てる前に売れるかも」という視点を持つことが、現代のマーケティング成功の鍵だといえます。
廃材がヒット商品になるように、ビジネスは発想次第で大きく広がります。
創業手帳では、起業・事業化に役立つ情報やノウハウを無料でまとめています。ぜひご活用ください。
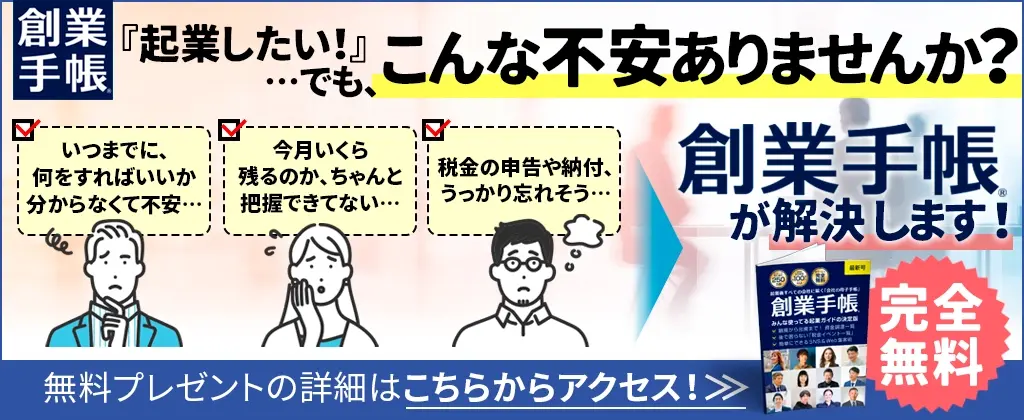
(編集:創業手帳編集部)




































