ファンマーケティングは何がすごい?手法やメリット、成功事例など解説
ファンマーケティングなら中長期的に売上を拡大できる!
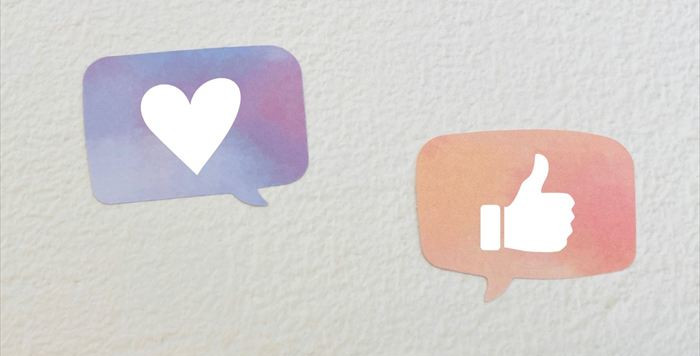
マーケティング戦略において新規顧客を増やすことも重要ですが、無条件で自社のブランドや商品・サービスを支持してくれる「ファン」を増やすことも大切です。
そのようなファンの存在を増やすには、ファンマーケティングが欠かせません。
ファンマーケティングを取り入れることで、中長期的な売上げの拡大も見込めます。
そこで今回は、ファンマーケティングの定義から代表的な施策、メリットや成功事例まで解説します。
ファンマーケティングを実践したいもののどのように計画を立て、運用すればいいかわからない人は、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
ファンマーケティングとは?定義・注目される背景について

ファンマーケティングとは、自社のブランドや商品・サービスに対して愛着を持つファンを増やし、中長期的な売上拡大を目指すマーケティング戦略です。
これまで行われてきたマーケティング戦略は、一般的にマスメディアの広告活用やクーポン配布、キャンペーンの実施など、企業から顧客に向けて一方通行による情報発信が中心でした。
しかし、ファンマーケティングはファン同士の交流会やミーティング、SNSなど企業と顧客が双方で、または顧客同士でコミュニケーションを図れる機会を設けます。
そうすることで顧客による口コミによって商品やサービスの認知度が高まったり、リピート率が向上するなど、多くのファンを生み出すことができます。
ファンが増えていけば、中長期的に安定的な売上にもつながるでしょう。
ファンマーケティングとファンベースの違い
ファンベースマーケティングはファンマーケティングと似ている言葉ですが、その目的が異なります。
ファンベースマーケティングも顧客との関係性を重視した手法になりますが、既存顧客との関係性を維持し、ロイヤルティを向上させることを目的としています。
一方、ファンマーケティングは顧客とのコミュニケーションを通じてファンをより増やしていき、売上を拡大させることが目的です。
新たな市場への参入や、ブランドの認知度をより高めたい場合にはファンマーケティング、既存顧客との関係性をより強化したい場合はファンベースマーケティングといったように、目的に合わせて適切な戦略を選択してください。
なぜファンマーケティングが注目されているのか?

近年ファンマーケティングの重要度が高まっており、多くの企業から注目を集めています。なぜファンマーケティングが注目されているのか、その理由について解説します。
新規顧客の獲得が難しくなっているため
ひとつ目の理由として、新規顧客の獲得が以前に比べて難しくなっている点が挙げられます。
現在日本国内では少子高齢化が進み、市場も徐々に縮小傾向です。特に消費者人口が全体的に減少するだけでなく、消費行動にも積極的な若い人たちが減っています。
新規顧客の獲得が難しくなっている中で、既存顧客から自社のブランドや商品・サービスに愛着を持ってもらい、ファンを増やしていくファンマーケティングが注目されています。
ファンが増えれば新規顧客数が減ったとしても、売上の拡大につながるでしょう。
口コミやSNSの影響力が大きくなっているため
インターネットが普及し、多くの人がSNSを使うようになったことで、消費行動にも大きな変化が現れました。
これまで商品を購入する際には、マスメディアなどから得た情報をもとに購入を決めるのが一般的でした。
しかし、SNSが普及したことで実際にその商品を購入した人の口コミが見られるようになり、その口コミも商品を購入する判断材料に用いられるようになっています。
つまり好意的な口コミが増えれば、それを見た消費者が商品を購入する可能性も高まります。
ファンマーケティングによって着実にファンを増やしていけば、口コミやSNSで自社の商品・サービスについて積極的に発信してもらえるでしょう。
ほかの手法の難易度が上がっているため
インターネットの普及にともない、企業でもWebマーケティングが取り入れられるようになりました。
大手企業はもちろん、多くの中小企業でもWebマーケティングを取り入れ、認知度の向上を目指しています。しかし、その結果競争が激化しているのも事実です。
例えばユーザーが検索したキーワードをもとに広告が配信される「リスティング広告」は、参入企業が増加したことでクリック単価が高まり、狙いたいキーワードによってはコストが高くなってしまいます。
一方、ファンマーケティングは無料で利用できるSNSを中心とした施策を行うことも可能です。
ファンマーケティングの代表的な施策

ファンマーケティングを成功させるためには、ファンと中長期的に関係性を構築していく必要があります。ファンとの関係性を構築するための代表的な施策は以下のとおりです。
コミュニティの立ち上げ・運営
ファンと継続的に接点を持てるだけでなく、顧客同士で商品・サービスの価値を共感できる場をつくるために、コミュニティの立ち上げ・運営がおすすめです。
コミュニティはオンライン・オフラインを問わず、顧客同士が交流できる場として活用されることで仲間意識が高まり、さらにブランドへの愛着を深めてもらうこともできます。
例えばコミュニティとしてLINEオープンチャットなどで専用のSNSグループをつくったり、オフラインでのファンミーティングや限定イベントを実施したりするなどです。
コミュニティの運営により、顧客同士で積極的に情報共有を行ってくれたり、直接商品などに対する意見をもらったりすることもできます。
UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用
UGCとは、ユーザーが主体となって生成したコンテンツです。例えばSNSでの投稿や口コミサイトに書き込んだレビューなどが挙げられます。
UGCは好意的な口コミだったとしても、企業が発信する情報より信頼性が高く、新規顧客の呼び込みにもつながります。
そのため、ファンマーケティングの施策としてUGCを活用するのがおすすめです。
具体的な活用方法としては、例えばSNS投稿キャンペーンを実施してUGCを促したり、ユーザーから許可をもらい公式サイトやSNSで紹介したりするなどです。
こうした施策を取り入れることによって、SNS上でのブランド想起率を高めたり、ECサイトの購入率を向上させたりできます。
SNSを活用したエンゲージメント強化
ファンマーケティングでは、ファンと日常的に接点が持てるSNSが重要なチャネルです。
SNSの運用によってフォロワーからの「いいね」やコメント、シェアなどのエンゲージメントを強化し、顧客とのつながりをより強固なものにできます。
また、エンゲージメントの強化によって投稿が広く拡散されれば、さらに新規顧客の増加も期待できます。
そのためには、SNSを単に企業が情報を発信する場として活用するのではなく、ファンと交流できる場として活用するのがおすすめです。
例えば、ユーザーの投稿に対して「いいね」などのリアクションを送ったり、コメントやDMなどで来た質問に答えたりするなどが挙げられます。
創業手帳ではSNSの運用について、あまり慣れていない方向けに基本的な部分から解説した「SNS運用ガイド」を無料でお配りしています。業界ごとに相性がいいSNSを表でまとめていたり、それぞれの投稿方法などについても解説。ぜひご活用ください。

ファンマーケティングを実践するメリット

ファンマーケティングを実際に取り入れた場合、企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
継続的な売上の拡大が見込める
ファンマーケティングによってファンが増えていけば、競合他社の製品と並べた時に愛着のある自社の商品を手に取ってもらいやすくなるため、価格競争に巻き込まれにくくなります。
また、ファンは一度だけでなく2回、3回と継続して購入してくれる可能性が高く、LTV(ライフタイムバリュー)の底上げも可能です。
価格競争に巻き込まれにくく、なおかつLTVの底上げも可能になることから、中長期的に売上の拡大が見込まれます。
広告費の削減につながる
これまで新規顧客を増やすためには、マスメディアなども広告を活用して認知度を高めることが重視されてきました。しかし、その分広告費はかさんでしまうものです。
一方、ファンマーケティングによってファンが増えるとUGCが増え、広告費用をかけなくても集客しやすくなります。
しかもUGCは企業が出稿した広告とは異なり、ファンでも第三者の意見として捉えられるので、信頼性が高いです。
商品・サービスのフィードバックが受け取れる
ファンマーケティングでは企業とファンの接点が増えるため、商品やサービスを愛用しているファンからのフィードバックも受け取りやすくなります。
フィードバックを受け取ることにより、企業は顧客が抱えるニーズを把握できるようになり、新たな商品の開発や品質を向上させることも可能です。
新規顧客を獲得できる
ファンマーケティングは、すでにファンになったユーザーを増やすだけでなく、新規顧客の獲得も可能です。
特に口コミを参考にして購入を検討する人も多く、ファンが商品について投稿した内容をもとに、これまで自社の商品を購入したことがない層からも購入してもらえる可能性が高まります。
新規顧客が増えれば、そこからファンになってくれる人を増やすこともできます。
ファンマーケティングにおける注意点

ファンマーケティングを実践する際には、メリットだけでなく注意点についても把握しておく必要があります。ここからは、ファンマーケティングにおける注意点の解説です。
ファンの育成に時間がかかる
ファンマーケティングでは、一般的な顧客から自社に対して愛着を持つファンに育てていく必要があります。
しかし、一般的な顧客から愛着を持つファンに育てるまで、ある程度の時間がかかってしまうことも念頭に置かなくてはなりません。
ファンを育てるためには、愛着が持てるようになるための施策を実践することも大切です。
例えば、会社の歴史や商品・サービスが誕生した経緯に関する情報の発信や、特別なイベントを開催するといったことが考えられます。
コミュニティの管理が必要になる
いくら企業と顧客、または顧客同士で交流できる場をつくったとしても、管理がしっかりと行われていなければ意味がありません。
例えばよく起こりやすいのが、新規顧客が初めてコミュニティに参加した際に、ほかのファンから高圧的な態度を取られたり、排他的なことをいわれたりするなどです。
このような態度・コメントがコミュニティに存在すると、ネガティブな方向に進んでしまいます。
コミュニティを管理する際にはガイドラインや投稿時のルールも最初に策定しておき、多くのユーザーが参加しやすいコミュニティを形成することが大切です。
想定外のファンがつくことがある
ファンマーケティングは基本的にファンが育成されるまで時間がかかってしまうものの、時には想定していた以上にファン数が増えたり、トラブルを引き起こすような熱狂的なファンが現れたりすることもあります。
過熱化したファンは企業に対して過剰な要求をしてきたり、ほかのファンや関係のない消費者も巻き込んでトラブルに発展したりする場合もあるかもしれません。
このような事態を回避するためにも、あえて熱量を冷ます必要があります。ファンの熱量に関係なく、ファン全員に対して公平に対応することが大切です。
炎上対策が欠かせない
ファンが大きな信頼や愛着を持っている分、期待値が高くなる傾向にあります。
もし期待値よりも下回ってしまった場合、大きく失望した結果、炎上に発展する恐れもあるので注意が必要です。
炎上対策として、例えばSNSやコミュニティのルールを策定したり、炎上リスクを従業員が理解できるよう研修を行ったりするなどが挙げられます。
ファンマーケティングの成功事例
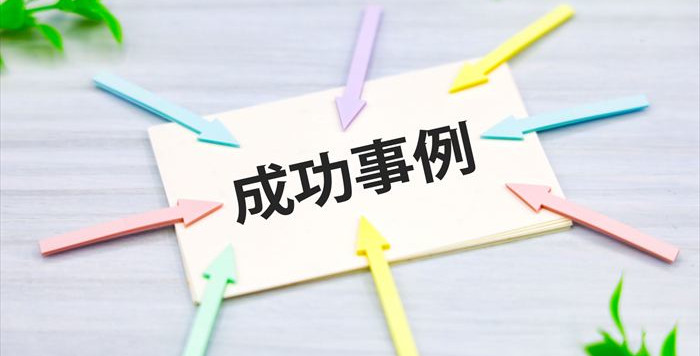
ファンマーケティングを実践したことで成功した企業も増えています。ここでは、ファンマーケティングの成功事例の紹介します。
ワークマン
作業服や安全靴などを取り扱うワークマンは、公式アンバサダー制度を取り入れています。
アンバサダー制度はワークマンのアイテムを愛用し、SNSなどでも発信している人に対して声がけを行い、新商品の発信を依頼したり共同で商品開発に取り組んだりする制度です。
無償で協力をしてもらっているためコストはかかりません。
また、ファンもアンバサダーとして新商品の発表会やモニター体験ができるなど、嬉しい恩恵を受けられます。
公式アンバサダー制度によってUGCが多く形成されるようになり、ブランドや商品の認知度を高めることに成功しました。
スターバックスコーヒージャパン
世界的なコーヒーショップとして知られるスターバックスでもファンマーケティングが取り入れられています。
スターバックスでは「My Starbucks Idea」と呼ばれるコミュニティサイトを立ち上げており、スターバックスに対する意見やアイデアを募集しました。
すると、サイトの立ち上げからわずか2カ月で4万件以上のアイデアが送られてきました。
その中にはスターバックスに対する課題を指摘する声もあったため、改善に取り組んでいったのです。
顧客の意見に寄り添い、改善に努めたことでその誠意が顧客にも伝わり、信頼関係の構築につながっています。
無印良品
無印良品は新たなファンマーケティング戦略として、「ファンマーケティング2.0」に取り組んでいます。
ファンマーケティング2.0では、アンバサダープロジェクトを立ち上げています。アンバサダーを新商品の展示会に招き、動画やSNSで紹介してもらいました。
その結果、コンテンツの再生回数は累計で210万回を超え、認知度の向上につながっています。
また、アンバサダーと協力して新たな商品開発に取り組んだり、UGCを収集して自社サイトで活用したりするなど、積極的にファンマーケティングを行っています。
MAPPA
主にアニメの企画・制作や関連グッズの販売なども手がけるMAPPAは、劇場版アニメを制作するために、監督やプロデュース会社と共にクラウドファンディングでプロジェクトを立ち上げました。
クラウドファンディングの出資者に対する返礼品には、制作支援メンバーミーティングで一部先行上映を観ることや、制作過程の進捗報告などがありました。
特に進捗報告はファンがその都度映画に関する情報をSNSなどで拡散したため、映画自体の認知度も高まり、結果的に興行収入は27億円以上となっています。
ヤッホーブルーイング
クラフトビールのメーカーとして知られるヤッホーブルーイングは、顧客のロイヤリティやエンゲージメント向上を図るために、Facebookページの運営をしていました。
Facebookページではスタッフと顧客、双方の顔と名前がわかるようにと、名指しでコメントのやり取りを行っています。
さらに、忘年会のような感覚で参加できるファンミーティングや醸造所を紹介するツアーなど、ファンのみならず参加した誰もが楽しめるようなイベントを開催しました。
その結果、商品のファンから企業自体のファンを増やし、そのファンによるUGCによって認知度の向上や新規顧客の獲得につながっています。
まとめ・ファンマーケティングによる継続的な関係構築を成功させよう!
ファンマーケティングは既存顧客との信頼関係をより強固なものにするだけでなく、UGCによって新規顧客の獲得にも効果が期待できます。
熱烈なファンが育つまでに時間はかかってしまうものの、中長期的に売上を拡大していくためにはファンの存在は欠かせません。
そのため、ファンマーケティングを実施して継続的な関係構築に努めていってください。
創業手帳(冊子版)は、ファンマーケティングを含む様々な手法・戦略に関する情報をお届けしています。ビジネスの方針決めや問題解決などにぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)





































