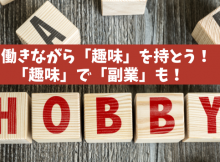経営者になるには?役割や方法、必要な知識・能力をわかりやすく紹介
経営者になるには手段や必要な能力などの理解が必要

経営者は、経営方針を決定して、事業を推進する役割です。リーダーとして事業、従業員が進むべき道を指し示すためには、どういった能力が必要になるのでしょうか。
ここでは、経営者になるために手段や求められる能力について解説しています。まだ事業の構想段階の人も、経営者になるまでの道筋を知っておいてください。
創業手帳は、経営者になるためのノウハウが詰まった一冊になっていますので、ぜひこちらの記事とあわせてお読みください。無料で差し上げています。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
経営者になるには? 5つの方法をわかりやすく解説
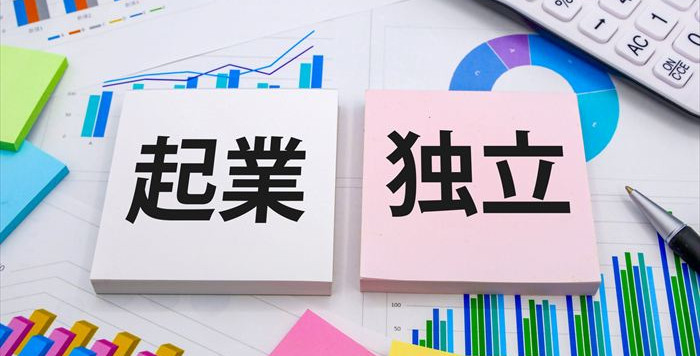
自分の力で道を切り拓く経営者の道は、苦労は多くてもやりがいがあります。やりたい仕事に取り組む、夢をかなえるために経営者を目指す人も多く存在します。
しかし、経営者になりたくても、そのためにどうすればいいのか具体的な方法がわからない人もいるでしょう。
ここでは、経営者になるための方法を5つ紹介していきます。
起業する
起業すれば、経営者となれます。ただし、起業するための資金や事業計画に不安があるかもしれません。
しかし、小規模であっても起業すれば経営者として事業をスタートできます。
いきなり店舗を構えるのではなく、オンラインショップからはじめる、事業が軌道に乗るまでは従業員を雇わずにひとりで仕事をするといった方法もあります。
誰かに雇用されるのではなく、一から自分で作った事業を育てていくことは経営者にとって大切な経験です。
フランチャイズで開業する
すべてを自分で計画して起業することができない時には、フランチャイズを利用した開業も検討してください。
フランチャイズとは、ほかの企業のブランド名や仕入れルートを使って起業する方法です。
起業するためのインフラを利用する対価としてロイヤリティを支払いますが、フランチャイズ本部の経営ノウハウを得られるのでビジネス経験が少なくてもチャレンジしやすい点が魅力になります。
本部が扱っている商品やサービスを販売できるので、自分だけで商品開発やマニュアル作成も不要です。実績や経験を積む一環としてスタートすることも検討してみてください。
従業員から昇級する 企業で昇格する
起業する方法は、自分で事業を一から立ち上げる以外にもあります。従業員として雇用されている会社で出世すれば、経営者になれる可能性があります。
すでにビジネスとして軌道に乗っているため、初めから自分で事業を興すよりもリスクが低く感じるかもしれません。
ただし、従業員から経営者まで出世するには、ほかの従業員やライバルよりも突出した能力が求められます。
企業規模が大きい場合には特にライバルとの競争は苛烈になるかもしれません。
すでに従業員として働いている場合には、これから経営者になれるかどうかも考慮して今後のキャリアパスを考えてみてください。
雇われ経営者になる
経営者とは、経営の最終判断を下すポストであり、オーナーとは限りません。
会社の所有権を保有する人に雇用されて経営者となるケースもあり、一般的に雇われ社長と呼ばれます。
しかし、経営者として雇用されるためには、それだけの能力や経歴が求められると考えられます。
経営者として選ばれるためにどういったスキルが必要なのかも考えて研鑽を積まなければいけません。
事業を承継する
すでに経営者として経営している人から事業を引き継ぐことでも経営者になれます。親から子に事業を引き継ぐようなケースです。
中小企業の後継者不足は全国で深刻化しています。そのため自分の子以外の第三者に事業を引き継ぐケースも少なくありません。
事業を引き継ぐ前に、従業員として業務を経験しておくことで事業承継がスムーズになるでしょう。
経営者の役割と資格・学歴の必要性とは?

経営者の経歴は多種多様です。学生時代に起業して経営者となるような事例では、社会人経験なしに経営者として働いています。
一方で、会社の経営をするためにはビジネス全般について幅広い知識が必要であり社会人経験が役立つケースもあります。
ここからは経営者の役割や経営者となるために必要な能力について解説しました。資格や学歴の必要性についても解説しているので参考にしてください。
経営者は企業における最高責任者
経営者は企業の最高意思決定機関として、業務の指揮監督を行う立場です。
単純にビジネスに集中すればいいのではなく、ステークホルダーへの還元や資金調達といった視点も求められます。
顧客ニーズや市場を把握した事業の立ち上げから、企業規模を拡大するためのスキームの検討といったタスクのほかに、人材の育成や社内環境整備にも取組みます。
幅広い業務をこなす経営者は、フットワークが軽くて行動力があるタイプも多いでしょう。予想外のトラブルに対応できるメンタルの強さも重要な資質です。
経営者になるには資格は必要なのか
経営者になるために、必ず取得しなければならない資格はありません。何も資格を持っていない人であっても経営者として就任できます。
ただし、経営者としての仕事に携わるためには幅広いジャンルの知識は不可欠です。
経営に役立つ資格としては、日商簿記や中小企業診断士、MBAなどが挙げられます。
日商簿記は、貸借対照表や孫永輝計算書を読み解いて、財務状況の判断をする基礎知識を身につけられます。
中小企業診断士は、取引先の経営状態を判断するにも役立つ資格です。MBAは、経営の全体像を把握して問題解決に取り組む知識を取得可能です。
どういった資格があるのか調べて自分に合うものを勉強してみてください。
経営者になるには学歴や社会人経験は必要なのか
経営者になるためには、学歴や社会人経験は必ずしも求められません。大学に行っていなくても働いた経験がなくても経営者にはなれます。
ただし、学歴や社会人経験自体ではなく、大学での勉強や社会人としての経験が経営に役立つ場面は多くあります。
加えて、大学や会社で得た仲間や人脈を活用して経営者になるといった方法も可能です。
経営者を多く輩出している大学で、卒業生や現役経営者とつながりを持つといった人もいるかもしれません。
創業支援のインキュベーション施設を設置するなど起業家支援を行っている大学もあるので、これから大学に進学して学ぶのであれば検討してみてください。
経営者が担う主な仕事内容

経営方針や戦略の決定は経営者の代表的な仕事です。しかし、実際にはより幅広く会社に携わる仕事をしています。
経営者がどういった仕事をしているのか、以下で紹介します。
経営方針や経営戦略の策定
経営者の経営方針や経営戦略の策定をより具体的にいうと、事業を展開する時の基本となる考え方、ワークフローなどを目標や方向性とともに示すものです。
従業員に企業が進むべき方向を指し示すためにも重要な意味を持ちます。
経営方針や経営戦略の軸となるのが経営理念です。
経営理念は、企業の存在や価値、ビジョンを言葉で表現したもので、経営方針や経営戦略は、経営理念をどうやって実現するかを前提に作られます。
経営方針や経営理念の策定は重要な仕事ではありますが、日々行うものではありません。事業の設立段階や、事業展開のステップで策定されます。
事業拡大に向けた事業推進
事業は、日々の基本的な営業、運用だけではありません。経営者は広い視野を持って事業を拡大するための事業推進を進めるよう求められます。
市場や顧客ニーズを調査するほか、事業拡大のための中長期的なゴール設定や共有も経営者の仕事です。
職場環境の整備
より円滑に事業を遂行する、現場の従業員が成果を上げられるようにするには、職場環境の整備が不可欠です。
職場環境の整備がされていないと、従業員が働きにくくなり仕事へのモチベーションが低下し、離職率の向上や生産性の悪化につながります。
職場環境の整備にはいろいろな手段があります。給与や福利厚生の充実はもちろん、オフィスの配置や冷暖房設備、備品の拡充といった環境もチェックします。
経営者になるとなかなか現場の声が届かないケースもあるので、定期的に従業員からヒアリングをし、実際に職場を視察するといった行動も有効です。
人材の雇用・育成・評価
事業が成長すれば企業の規模も大きくなります。会社が成長する時に欠かせないのが人材の雇用や育成です。
日々の業務の研修などは担当者や現場に任せられるものの、何を重視して教育するかを策定するのは経営者が取り組む部分も多くあります。
自社に必要な人材の募集や求める人物像を明確にして採用方針を決めるのも経営者の仕事です。
さらに、目標をもって業務に携わる従業員を正当に評価するための仕組み作りも求められます。
人材は企業を成長させるための貴重な経営資源です。採用した人材をどうやって活用するのかまで考えて、人材登用の方針を策定します。
資金繰り
企業経営に、資金繰りは欠かせません。資金繰りは、企業の収支を管理して過不足をコントロールすることをいいます。
例えば、商品の売上げが急伸したとしても、入金が遅れてしまえば新たな仕入れや従業員への給与支払いのお金が不足してしまうかもしれません。
売上げが大きくても資金繰りが悪化すれば支払いが滞って倒産リスクが大幅に高まってしまいます。
資金繰りは、従業員の雇用を守るため、企業が存続するために必要な仕事です。
経営者になるために必要な知識・能力
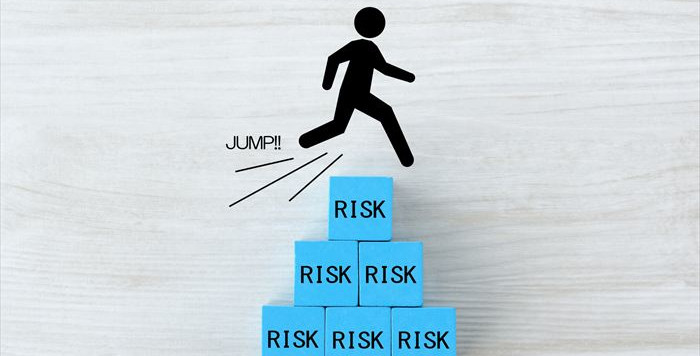
経営者になるために、資格や学歴、社会人経験は絶対に必要とはいえません。しかし、経営者になるために必要となる知識や能力は存在します。
どういった知識や能力が必要なのか。項目ごとに説明します。
リーダーシップ
経営者は、ひとりで事業を推進するだけでなく従業員や関係者とともに事業を成長させなければいけません。
会社のビジョンや理念を描き、会社の進むべき方向を示すにはリーダーシップが求められます。
ビジョンや経営理念を実現するために何をするべきなのかを打ち出して、従業員の意欲を引き出すためには発信力も必要です。
経営者がリーダーシップが取れていると周囲の能力を引き出せるとともに、より良い組織風土を作れます。
マネジメントとチームビルディング
組織をけん引するためにはマネジメントやチームビルティングの知識も必要です。経営理念やビジョンを実現するための戦略や仕組みづくり、組織運営がマネジメントです。
また、人材の特性や能力を見極めて、それぞれが最大のパフォーマンスを引き出せるような人材配置を行うチームビルディングも求められます。
財務・会計の基礎知識
経営者になるためには、ビジネスの基本知識に加えて、経理や財務、会計やマインドセットといった幅広い知識が求められます。
起業準備と並行して勉強していくこともできますが、必ず学んでおきたいのが財務や会計の基礎知識です。
会計の実務は担当者や専門家に依頼するかもしれません。
しかし、決算書類を正しく理解できていないと、経営状況を客観的に理解して自社や取引先の状態を判断できません。
起業するまでに貸借対照表と損益計算書、キャッシュフロー計算書の構造や読み方は理解しておくようにしてください。
マーケティングと顧客理解
経営者の仕事の中でも、事業戦略の決定は重要性が高い仕事です。マーケティングの知識や顧客理解は、戦略策定に役立ちます。
商品やサービスが売れる仕組みを理解しておけば、ターゲットに対して効率的にアプローチできるはずです。
マーケティングは、その対象によって区分分けされています。
WebマーケティングやSNSマーケティング、コンテンツやインフルエンサーマーケティングといった種類があり、さらに戦略選択のフレームワークも多くのものがあります。
自社の事業に適したマーケティングやフレームワークを優先して学ぶようにしてください。
問題解決力と決断力
経営判断を下す立場の経営者には、問題解決能力と決断力が必要です。課題を解決するには、物事を体系的に理解して論理的に考えてください。
ビジネスパーソンとして論理的に考える力と、迅速に決断する決断力の両方が欠かせません。
経営者には、状況や物事を冷静にとらえながら、どのような選択が必要か判断する決断力が求められます。
自己管理とストレス耐性
経営者は責任が重く、悩みを周囲に打ち明けにくい立場です。そのため、ストレスでの不調や自己管理の怠慢に陥るケースも頻発しています。
経営者として事業を存続させ続けるためには、会社だけでなく自分自身の管理やストレスのコントロールが必要です。
心身の不調が続けば意思決定力や思考能力にも影響します。経営者の不調は周囲に伝わってしまってしまう点も問題です。
経営者は、自分の感情を受け入れてケアすることが求められます。コーチングやカウンセリングといった第三者の力も借りながら取り組んでみてください。
まとめ・必要な知識・スキルを身に付けて経営者を目指そう
会社の経営は、決して簡単ではなく幅広い知識やスキルが求められます。さらに成功する経営者に共通しているのは、スキルや知識のアップデートを欠かさない点です。
資格取得を目指したり、人脈作りに交流会や勉強会に参加したりと経営者になるためにできることはたくさんあります。
従業員や取引先、顧客に信頼される会社を育てるためには、積極的に経験を獲得して知識を吸収してください。
将来経営者を目指すために、漠然とイメージするだけでなく行動に移すことが大切です。
創業手帳では、経営者になることを決めた方が具体的に準備すべきことをリスト化した「創業カレンダー」も無料でお配りしています。創業予定日を起点に前後1年間のやることリストがカレンダー形式で把握できるものになっています。ぜひこちらもご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)