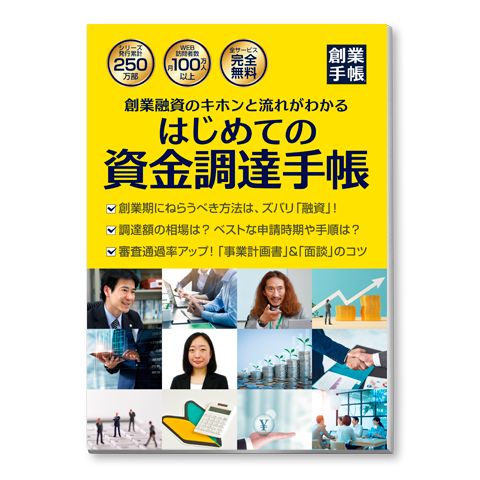個人事業主も福利厚生費を計上することは可能?条件や経費として認められる内容を解説
個人事業主も一定の条件を満たせば福利厚生費を計上できる!

法人と異なり、個人事業主は原則として福利厚生費を計上できません。しかし、従業員がいる場合など、一定の条件を満たした福利厚生費であれば経費として計上できます。
福利厚生費は、従業員のモチベーションやエンゲージメントにも貢献します。
従業員を雇用する時には、どういった福利厚生なら経費計上できるのかを把握して新しく導入を検討してみてください。
創業手帳では、福利厚生費を含む23の経費科目について『経費削減のポイント』と『節税のポイント』をまとめた『経費で損しないためのチェックリスト』を無料でお配りしています。こちらもあわせてご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
原則、個人事業主は福利厚生費を計上できない

福利厚生費は、企業が従業員に提供している福利厚生サービスにかかっている費用をいいます。
具体的には健康診断の費用補助や結婚祝い金、社内イベント費用など多くの施策が福利厚生費で処理されています。
福利厚生の目的は、従業員の生活やモチベーションを向上させたり、より働きやすい環境を整えたりすることです。
社会保険などの法律で定められている法定福利と会社が独自に設けている法定外福利があり、どちらも税法上は経費です。
法定福利費には、健康保険料や介護保険料、雇用保険料などが含まれます。法定外福利費には、社員旅行の費用や祝い金といった独自に設けた福利厚生が該当します。
福利厚生費は、従業員へのサービスとして事業主が負担する費用であり、原則として従業員がいない個人事業主は福利厚生費を計上できません。
しかし、一定要件を満たすことで福利厚生費の計上が認められます。どういった条件で福利厚生費の計上が認められるのかを以下で紹介します。
福利厚生費の条件
個人事業主であっても家族以外の従業員がいれば福利厚生費として経費計上可能です。
ただし、個人事業主だけの単独経営や家族以外の従業員がいない時は、経費計上できません。
また、福利厚生費として計上するには、一定の条件を満たすことが求められます。支払った費用の目的によっては、福利厚生費ではなく交際費と扱われます。
交際費も福利厚生費と同じように経費計上できるものの限度が設定されているため注意しなければいけません。
さらに、福利厚生費の条件を満たさない時には、給与として課税される場合もあります。
例えば、一部の従業員だけに提供されていたり、換金性が高いものを支給した時などは給与として扱われることがあります。
給与として扱われた場合、従業員の課税所得が増えるため、所得税や社会保険料の負担が重くなってしまうため注意が必要です。
以下では福利厚生費として認められるための条件について紹介します。これから福利厚生制度を導入する人も事前に確認しておくようにおすすめします。
賃金ではない
福利厚生として認められるのは、賃金ではなく換金性が欠けるもの、物品などの選択ができないものだけです。
具体的には社員食堂や忘年会のように賃金以外で利益を受けるものが福利厚生の要件です。
福利厚生をアウトソーシングするカフェテリアプランを導入する企業も増えていますが、選択制の場合、従業員の選択によって課税対象になる可能性があります。
すべての従業員が平等に適用されている
福利厚生は、機会の平等、つまりすべての従業員が平等に適用させることも要件です。
役員だけ、一部の社員だけが利用できる場合、正社員やアルバイトといった雇用形態で提供の有無が区別されてはいけません。
ただし、社内での役割や労働時間といった合理的な理由があれば福利厚生の内容が違っていても問題はないこととされています。
また、福利厚生を利用しない従業員に対して金銭で支給する場合には、その金額が給与として課税されることがあるので注意してください。
社会的に妥当な範囲の金額である
福利厚生の内容が、妥当な範囲を超えて高額な場合には福利厚生として認められないことがあります。社会通念上妥当な金額は国税庁の判断を参考にしてください。
具体的には、創業記念品の配布であれば1万円、4泊5日の社員旅行なら10万円が妥当と判断しています。
金額の妥当性は福利厚生の内容によって変わるので、判断に悩む時には税理士に確認してください。
家族従業員には適用される?
福利厚生費は、従業員の慰安を目的としているのでひとりで事業を営んでいる場合、家族経営の場合には基本的に経費計上できません。
しかし、家族以外の従業員以外には福利厚生が適用されます。
つまり、家族以外の従業員が入れば社員旅行や懇親会といった従業員の慰安を目的とした福利厚生を適用可能です。
社会通念上妥当と認められる費用であれば、個人事業主自身や家族の参加費も経費計上可能です。
福利厚生費として認められる内容

福利厚生は、従業員の慰安や労働意欲を向上させる費用であれば、様々なものが認められます。
どういった内容の福利厚生費として認められるのか以下で紹介します。
健康診断にかかる費用
従業員の健康管理に必要な健康診断に費用は、福利厚生費として計上可能です。
妥当である金額は、年1回の一般健康診断でひとり1万円~3万円程度が目安です。法定健康診断以外の人間ドックも全従業員が対象であれば福利厚生費として計上できます。
社員旅行代
従業員の慰安や親睦を目的にする旅行費用は、福利厚生費として計上可能です。具体的な上限額を定められておらず、宿泊かどうかによっても妥当な金額は違います。
ただし、過度に豪華な旅行は頻繁な実施は税務調査で指摘される可能性もあるので注意してください。
福利厚生として認められるためには、旅行の期間が4泊5日以内のものであり、その旅行には全社員の50%以上が参加している必要があります。
店舗や工場があると金額は、その店舗や工場ごとで50%以上の参加が条件です。
家賃補助
従業員に家賃補助を支払っている場合は福利厚生費として計上できます。家賃補助として一般的な金額は月額2万円~5万円程度です。
ただし、住んでいる地域や従業員の役職によっても妥当な金額は違います。
大切なのは、全従業員を対象として公平な制度設計です。特定の従業員だけ高額な補助を行うと給与所得とされる可能性もあります。
スポーツクラブ・マッサージの利用料金
従業員の健康を維持する目的の、スポーツクラブやマッサージの利用料金も福利厚生費として認められています。
金額の目安はスポーツクラブなら1カ月1万円程度、マッサージは月に一度5,000円~1万円程度です。
しかし、個人事業主や家族のスポーツクラブ、マッサージ費用は経費計上できません。また、特定の従業員だけが利用する場合は給与所得となる可能性があります。
慶弔の見舞金
結婚や出産の祝い金、死亡弔慰金のほか、疾病や災害の見舞金は福利厚生費として計上できます。
社会通念上妥当な範囲期の金額で全従業員が対象であることが経費計上の条件です。
また、見舞金は非課税になるので受け取る側の遺族には所得税が課税されることはありません。
国税庁の判断では、業務上の死亡である時は死亡当時の普通給与の3年分に相当する額、業務上の死亡でない時は死亡当時の普通給与の半年分に相当する額が弔慰金等に相当する金額としています。
飲食代
従業員に提供する飲食代は、1日当たりで3,500円(税抜き金額)を上限として福利厚生費として計上可能です。
具体的には、仕事中の従業員に弁当やデリバリーで食事を提供した場合や外食をふるまった時が挙げられます。
さらに、社員食堂の運営費や外食チケットの配布といった形でも経費計上可能です。
ただし、従業員が食事代の50%以上を負担していることが条件です。この金額を超えた時には給与所得として扱われる可能性があります。
新年会・忘年会などの費用
従業員全体を対象にした新年会や忘年会の費用も福利厚生費として計上可能です。
忘年会費用はひとり当たり5,000円~1万円程度が一般的ですが、上限が設けられているわけではありません。
特定の従業員のみを対象にした飲食の場合は、交際費として扱われる可能性もあります。
全員に参加資格があって、相当数の人数が参加していることがわかるように利用した店の領収書とともに社内案内を行った時の案内文書を保存しておくようにしてください。
生命保険料
従業員を被保険者とする生命保険の保険料は、福利厚生費として認められています。
妥当とされる金額は、ひとり当たり月額5,000円~1万円程度が目安ですが、明確な上限額は決められていません。
特定の従業員のみを対象にした高額の保険は給与所得になるので注意してください。
交通費
通勤に使う交通費を通勤手当として支給する場合は、定められた限度額の範囲であれば福利厚生費として扱われます。
また、自動車や自転車での通勤に対しても、相当額を支給可能です。
交通費の限度額は国税庁で規定されていて、公共交通機関による通勤であれば1カ月15万円まで、自転車や自動車であれば通勤距離に応じた上限額が適用されます。
最大額は片道の通勤距離が55キロメートル以上の場合で、31,600円です。
出張手当
業務のための出張については、出張手当を支給できます。日当は社会通念上相当な金額で明確に上限が定められていません。
出張手当を支給するには、出張旅費規程を作成している必要があります。税務調査でも必ず確認される部分なので、必ず作成しておいてください。
福利厚生費として認められない費用の具体例

従業員のために支出した費用であったとしても福利厚生費として認められないものも多数あります。具体的には以下のものです。
・特定の社員だけが受け取る補助
一部の社員だけ住宅手当や通勤手当、食事補助が受けられる場合は福利厚生費として認められず給与として扱われます。
・記念品とともに渡す現金や商品券
創業祝いや勤続祝いで記念品を贈呈する時、条件を満たせば記念品費用を経費計上できます。しかし、一緒に支給する現金や商品券は福利厚生費にはなりません。
・貸付金の利息
従業員が災害や病気で生活資金を必要としている時、合理的な利率であれば会社が貸付をおこなえます。
しかし、無利息や低利息での貸し付けをした時は、利息の差額分は給与として扱われることがあります。
・高額な人間ドック
健康維持のための人間ドックは福利厚生費として計上可能です。しかし、著しく高額な人間ドックは福利厚生費として認められません。
一般的でない検査項目を含んでいたり、オプション付きであったりする時は福利厚生費として認められないことがあります。
福利厚生費の仕訳方法

今まで福利厚生費を計上したことがないと、どのように処理すればいいのかわからないかもしれません。
福利厚生費を支払った場合、法定福利であれば法定福利費です。法定外福利費には福利厚生費の勘定科目を使用します。
以下の具体例で福利厚生の仕訳方法についてみていきます。
社員旅行代を支払った場合の仕訳例
〈例〉社員全員が参加した慰安旅行を開催し、費用100万円を支払った。
| 借方 | 貸方 | ||
| 福利厚生費 | 100万円 | 普通預金 | 100万円 |
健康診断の費用を支払った場合の仕訳例
〈例〉
全従業員を対象にした健康診断を実施して、健康診断費用10万円を支払った。
| 借方 | 貸方 | ||
| 福利厚生費 | 10万円 | 普通預金 | 10万円 |
社会保険料を負担した場合の仕訳例
社会保険料の従業員負担分は、預り金か法定福利費として計上することが認められています。
従業員負担分は、預り金の科目を使うと従業員分と事業主分が区別しやすくなります。
〈給与支払い時〉
給与30万円を支払った。うち2万円は社会保険料である。
| 借方 | 貸方 | ||
| 給与 | 30万円 | 現金 | 28万円 |
| 預り金 | 2万円 | ||
〈社会保険料納付時〉
従業員負担分の社会保険料2万円を事業主負担分とともに年金事務所に納付した。
| 借方 | 貸方 | ||
| 法定福利費 | 2万円 | 普通預金 | 4万円 |
| 預り金 | 2万円 | ||
上記では、事業主負担分の法定福利費と従業員から預かっている社会保険料をまとめて普通預金から支出しています。現金で納付した時には、貸方を現金で処理します。
従業員負担分の社会保険料を法定福利費で計上する場合でも基本的な流れは同じです。
従業員の給与から徴収した社会保険料を法定福利費として、納付時には事業主負担分と合算して納付します。
まとめ・従業員を雇用する個人事業主は福利厚生の導入を検討してみよう
個人事業主が、福利厚生費を計上するためには、従業員が平等に受けられて妥当な金額の福利厚生を導入しなければいけません。
例えば、通勤手当や住宅手当といった福利厚生は、従業員の手取り金額にも影響する福利厚生です。
より優秀な人材を確保して事業を成長させるためにも福利厚生費の整備は有効な手段です。
これから従業員を雇用する個人事業主は、どのような福利厚生費が必要か検討するとともに福利厚生の規定の作成をはじめてください。
経費をうまくコントロールできれば、利益も税金も変わります。
創業手帳では、23の経費科目を整理した『経費で損しないためのチェックリスト』を無料でご提供中!
明日から使える実践的なヒントが満載です。ぜひご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)