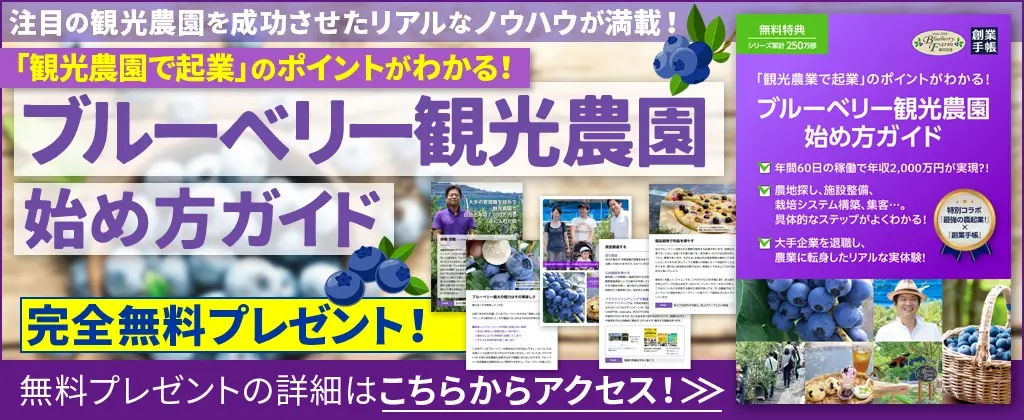貸し農園経営とは?経営スタイルや開業方法、成功のポイントなどを解説
貸し農園経営のメリット・デメリットも確認しよう

農業ビジネスに参入するのであれば、貸し農園経営という手段があります。
使っていない土地を農園として活用してもらえるため、土地を有効活用しながら収益を得ることが可能です。
ただし、貸し農園経営にはデメリットもあるため、メリットと共に理解することが大切です。
今回は、貸し農園経営の経営形態の特徴やメリット・デメリット、経営を成功させるポイントについて紹介します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
貸し農園とは?3つの経営形態の特徴

まずは、貸し農園がどのようなビジネスなのか、その概要と経営形態の特徴を紹介します。
貸し農園とは他者に農地を貸し出すビジネス
貸し農園は、農業を経営したい人や民間の人に向けて農地を貸し出し、その対価として家賃収入を得るビジネスです。
農業を始めるためには、農作物を育てるための土地が欠かせません。農地を持っていない人でも貸し農園を利用することで、気軽に農業経営を始められます。
また、農園を貸し出すオーナーは、使っていない土地を活用して収益を得ることが可能です。年間契約する借主が多いため、うまくいけば安定した収入を確保できます。
貸し農園の経営形態は3つ
貸し農園の経営形態は、大きく以下の3つに分かれます。詳しくは後述しますが、経営形態によって開業方法が変わることに注意が必要です。
ここで、各経営形態の特徴を紹介します。
1.体験型農園
体験型農園は、区切られた農地で種まき・苗の植え付けから収穫まで体験できる経営形態です。
農業従事者から直接指導を受けられ、利用者は本格的な農業体験が可能です。ただし、育てる農作物はオーナーが選ぶため、利用者は自由に作付けできません。
この経営形態は、農地の貸し借りではなく、利用者が支払う利用料がオーナーの収入源となります。
なお、農園で収穫した収穫物はオーナーに帰属します。利用料に収穫物代金を含むことで持ち帰ってもらうことが可能です。
2.市民農園(シェア畑)
市民農園はシェア畑とも呼ばれており、自治体や農家、民間企業などがオーナーとなって農園区画を利用者に貸し出す農園形態です。
利用者はオーナーに農園区画の賃借料を支払いますが、作物は利用者に帰属するのが基本となっています。
民営の貸し農園では、農業で必要な道具を用意しているケースが多いです。化学農薬や化学肥料を使用せず、有機栽培で野菜を育てられます。
市民農業では、日帰り型と滞在型があります。日帰り型は、自宅から通って農園を利用するタイプです。農園の近くに住む民間向けの貸し農園といえます。
一方の滞在型は、宿泊施設が併設されているため、遠方の人でも利用することが可能です。
3.営農者に農地として貸す
区切った農地を営農者に貸し出す経営形態では、オーナーは土地だけを貸し出し、農具や種・苗などの道具は利用者が用意します。
定期的な農園管理が必要ですが、農園の貸し出しにより収益を得られることが魅力です。農園では借主の計画どおりに好きな農作物を作付け・栽培できます。
貸し農園経営を始めるメリット

使っていない農園を貸し農園として経営することには、様々なメリットがあります。そのメリットは、以下のとおりです。
少ない初期費用で収益化できる
貸し農園経営は少ない初期費用で始められます。アパートやマンションとして土地を活用する場合、高額な建築費用がかかります。
また、駐車場経営であれば、アスファルト舗装や精算機の導入などが必要です。
一方の貸し農園は、基本的には建物建築やアスファルト舗装、大規模な設備投資は不要です。
所有する農地をそのまま貸し出しでき、初期費用を抑えて収益化を目指せます。
賃貸ニーズがない地域でも始めやすい
賃貸ニーズがない地域でも経営を始められることが貸し農園の魅力です。
エリアによっては、賃貸物件や商業施設などの活用にニーズがなく、収益化が難しいケースがあります。
交通の便が悪い立地や形状が複雑な土地であれば、賃貸物件の経営に向いていません。
一方、貸し農園であれば、田舎や郊外など賃貸ニーズのない地域でも土地活用がしやすいです。
最近は田舎で農業を始めたいと考える人が増えているため、貸し農園の需要は高いといえます。
土地荒れや税金の問題を解消できる
土地荒れや税金の問題を解消できることも貸し農園のメリットです。使われず放置されている農地はどんどん荒れてしまいます。
雑草や害虫によって荒れた土地は、周辺の人々に迷惑をかけたり、土地の資産価値が下がったりするリスクがあります。
また、遊休農地と見なされると、固定資産税が通常の農地よりも約1.8倍も高くなり、税負担が増えてしまうことがデメリットです。
貸し農園にしてほかの人に使ってもらうことで、土地荒れを防止し、固定資産税も従来のままとなります。
ほかの用途に転用しやすい
貸し農園であれば、ほかの用途に土地を転用しやすいメリットがあります。
賃貸物件をほかの用途に転用するとなると建物の解体工事が必要になり、高額な資金がかかります。
一方、貸し農園は土地にほとんど手を加えません。例えば、貸し農園をたたんで土地を売りたいと思った時も、スムーズに売却活動ができます。
ニーズがあれば、賃貸物件や駐車場経営などほかの土地活用に切り替えることも可能です。
様々な補助金・助成金が利用できる
貸し農園経営では、自治体の補助金・助成金を使えることがあります。多くの自治体が実施しているのが、市民農園の開設の一部費用を補助する制度です。
ほかにも、町おこしや農業復興を目的に、市民農園や体験型農業などの整備を補助する補助金制度を実施していることもあります。
ただし、自治体ごとに制度の名称や補助内容・要件などは異なるため、ホームページや窓口で確認してください。
貸し農園経営を始めるデメリット

貸し農園経営には多くのメリットがある一方でデメリットもあります。注意したい点は以下のとおりです。
農業委員会や自治体への届け出に手間がかかる
貸し農園経営を始めるためには、その地域の農業委員会や自治体から認定を受けなければなりません。そのため、届け出の提出に手間がかかります。
経営形態によっては届け出の内容が異なり、運営計画書の作成が必要になったり、承認・認定までに時間がかかったりすることがあります。
貸し農園経営を始めることを決めたら、速やかに計画を立てて準備や手続きを進めてください。
維持管理に手間がかかる
農園を他人に貸し出したからといって、土地の維持や管理の手間がなくなるわけではありません。
オーナー・管理者の立場として、定期的に巡回やメンテナンスを行うことになります。
農園の利用者が少なく土地が使われなければ雑草が生え、お手入れが必要です。また、農園の利用者の集客業務も行わなければなりません。
さらに、滞在型農園を経営する場合は、宿泊施設の維持管理もオーナーの責務です。
高収益を狙うのは難しい
貸し農園は、ほかの土地活用よりも高収益を狙いにくいこともデメリットです。
貸し農園の場合、賃料相場は月5,000円~1万円です。
土地が小規模であれば、回収した賃料から固定資産税や水道光熱費などの経費を支払いを考慮すると、年間で得られる収入はそう多くありません。
高収益を重視するのであれば、ほかの用途で土地を活用するほうがよい場合も考えられます。
なお、滞在型の農園であれば、宿泊施設の利用料を賃料に加えられるため、高収入を狙えます。
ただし、宿泊施設を建てるための初期費用が高額となるため、その分の回収や収入が安定化するまで時間がかかる可能性が高いです。
貸し農園経営の3つの開業方法

貸し農園経営の開業方法には、以下の3つがあります。経営形態によって選択できる開業方法が異なるため、対象の経営形態や届け出先などについて紹介します。
1.市民農地整備促進法
シェア型農園や体験型農園では、市民農園整備促進法に基づいて開業の手続きを行います。
届け出先は市町村(体験型農園は農業委員会)で、整備運営計画の提出が必要です。
また、貸し農園の経営は市民農園区域に指定される農地のみと限定されています。ほかにも、開業には休憩所・駐車場・トイレなどの付帯設備の設置が必要です。
比較的規模が大きな貸し農園を経営する場合に選ばれます。
2.特定農地貸付法
農地を小さな区画に分けて、区画ごとに貸し出す場合、特定農地貸付法に基づいて開業手続きを行います。
ただし、農業委員会から開業の承認を得なければなりません。開業地に制限はないものの、周辺の農家に影響が出る可能性があれば承認されない可能性があります。
また、特定農地貸付法に基づいた開業方法では、以下の貸付条件が定められています。
-
- 1区画の広さが1,000平米未満
- 貸付期間が5年以内
- 営利目的での栽培ではない
あらかじめ貸付協定や貸付規程を決めてから届け出してください。
3.農園利用方式
農家が開設する農園で体験型農業を提供する場合、農業利用方式で開業します。土地の貸付ではないため、貸付面積や期間、開業地などに制限はありません。
自治体や農業委員会への届け出は不要なため、比較的すぐに開業することが可能です。
なお、体験農業を提供するには、利用者との「農業利用契約」の締結が必要です。
貸し農園経営を成功に導くためのポイント

貸し農園は初期費用が少なく始めやすいものの、成功させるためにはポイントを押さえることが求められます。
ここでは、貸し農園経営を成功に導くためのポイントを紹介します。
立地ニーズを調べる
貸し農園を始める際には、立地のニーズを調査します。田舎や郊外で始めやすい貸し農園ですが、どの立地でも成功するわけではありません。
そもそも農地としてのニーズがなければ、収益化は困難です。
すでに農地を所有している場合、立地のニーズに合わせて農園の形態やサービス内容、ターゲット層を設定することになります。
貸し農園は高収益を見込めない傾向にありますが、立地ニーズ・サービス内容・ターゲット層がうまくかみ合わせることで、高い収益性に期待できます。
初期費用や固定費を抑えて始める
貸し農園経営で成功するためには、できるだけ初期費用や固定費を抑えることも大切です。最初は収益が少なく、赤字が続くケースも珍しくありません。
少しでも早く黒字化するためには、初期から支出を減らすことがポイントです。
専門知識が豊富なスタッフを雇用して技術指導サービスを提供したり、宿泊施設を運営したりして、良質なサービスを提供することが必要です。
ただし、スタッフの雇用や宿泊施設の建築、大規模な設備投資などは初期費用が高くつき、開業後も継続的にコストがかかります。
初期費用やランニングコストで収益が圧迫されないように注意して計画を立ててください。
区画面積ごとに料金を設定する
シェア型や営農者に向けて貸し農園を経営する場合、区画面積ごとに料金を設定することがおすすめです。
すべて同じ区画面積であれば管理がしやすいものの、大きな区画や小さな区画など複数の土地があると、利用者の幅広いニーズに応えられます。
また、面積ごとに適した料金を設定して管理すれば収益性が高まります。
定期的に管理を行う
貸し農園は、複数の区画を用意して貸し出すことが一般的です。すべての区画が使われているとは限らず、利用されない区画は放置すると荒れ果ててしまいます。
荒れ果てた農地の放置は、ほかの区画にも影響を与えてしまう可能性が高いことに注意が必要です。
また、利用者が区画の境界を越えて農地を使用してしまっているケースもあり、その場合はトラブルを回避するために適切な対応をとるのもオーナーの役目です。
農地の状態の維持や利用者から適切に農園を利用してもらうためには、オーナーの管理が欠かせません。
利用者とのトラブル対策ルールを決める
利用者とのトラブルを回避するために、貸し農園を利用するためのルールや対策を決めることも大切です。
農地の境界線や農園の使い方などで、利用者同士のトラブルが発生することがあります。
農園での禁止行為や規制を定めておけば、利用者同士のトラブルを抑えることが可能です。
万が一トラブルが発生した時のために、対応方法の策定や共有をし、適切に対処できるようにしておくことが求められます。
まとめ・貸し農園経営は始める前にリサーチが必須!
貸し農園経営は使っていない土地を貸し出すことで、収益を得られます。農地をそのまま活用でき、少ない初期費用で経営を始められることも魅力です。
ただし、すべての土地に貸し農園としての需要があるわけではないことに注意してください。
事前にリサーチしてニーズがあるかどうか、どのような経営形態・サービスがふさわしいかを見極めることが必要です。
田舎や郊外では比較的ニーズのある土地活用方法であり、土地の活用に悩んでいたり、農業関連のビジネスに興味があったりする場合には、おすすめのビジネスモデルです。
創業手帳では、脱サラしてブルーベリー観光農園の事業を展開し大成功を収めている「ブルーベリーファームおかざき」の畔柳氏と一緒に制作した「ブルーベリーガイド」を無料で配布しています。今では年間60日の稼働で年収2,000万円以上を得ているという畔柳氏のノウハウについて、ブルーベリー観光農園ではなくとも必見。ぜひお申し込みください。
(編集:創業手帳編集部)