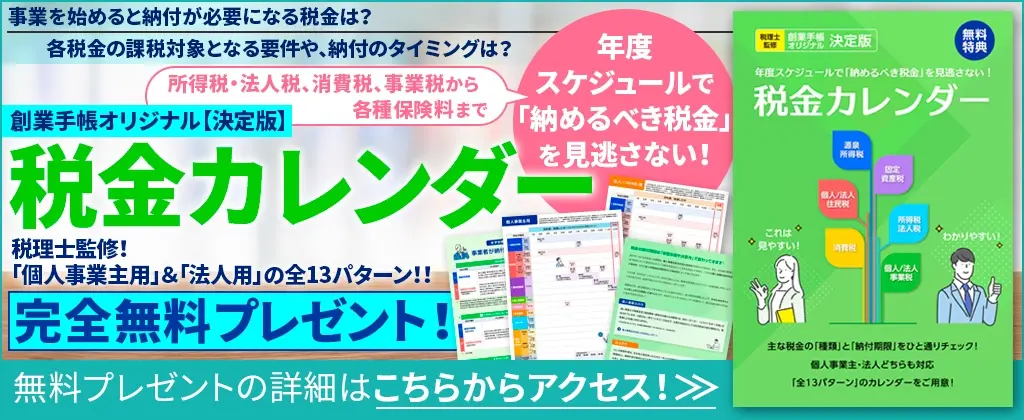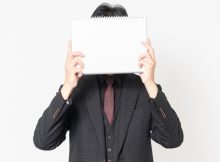税務調査を拒否したらどうなる?調査の種類から調査されやすい決算書の特徴まで解説
税務調査は原則拒否できない!

事業を営んでいると、「税務調査を実施したい」と突然連絡がくるケースもあります。
悪いことをしていなくても、「何か問題があったのでは?」と不安に思う人もいるかもしれません。
しかし、任意の税務調査は原則として拒否できません。罰則を受ける可能性もあるため、調査は受け入れる必要があります。
そこで今回は、任意の税務調査を拒否したらどうなるかを紹介するとともに、税務調査の種類や拒否できる正当な理由、税務調査が入る可能性が高い決算書の共通点などについて解説していきます。
税務調査を回避するためのポイントも紹介していくので、税務調査の実施に不安を抱えている人や税務調査を避けたい人はぜひ参考にしてみてください。
税務調査は突然やってきます。だからこそ、日ごろから正確な申告や期限管理が欠かせません。創業手帳では、重要な税金のスケジュールを一目で把握できる「税金カレンダー」を無料でご提供しています。調査リスクを減らすためにも、ぜひご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
任意の税務調査を拒否したらどうなる?

任意であれば税務調査を拒否できると考えるかもしれません。しかし、実際には拒否すると様々なリスクがあります。
拒否した場合、どうなってしまうのか解説していきます。
任意でも拒否すると罰則の対象になる
任意の調査なので「黙秘権を行使できる」と考える人もいます。しかし、犯罪捜査で認められているような黙秘権は税務調査では行使できません。
任意であったとしても、調査に対応をしなければ罰則の対象になることに注意が必要です。罰則内容としては、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
国税通則法によって罰則が適用されることが定められているため、正当な理由なく帳簿を見せなかったり、嘘をついたり拒否をしたりする行為は罰則の対象となってしまいます。
実際にはほぼ強制であることを覚えておいてください。
申告・納税漏れが発覚したら加算税も納めなくてはならない
税務調査によって申告漏れや納税漏れが発覚すれば、加算税を納めなくてはいけません。どういった加算税が課せられるのか解説していきます。
・過少申告加算税
期限内に申告や納税をしたとしても、本来納税すべきだった額よりも少ない場合に課せられる加算税が過少申告加算税です。
納める金額は、新たに納税すべき金額の10%です。
当初の申告納税額もしくは50万円のいずれか多い額を超えている場合には、超過分に対して15%の過少申告加算税が発生します。
ただし、調査を受ける前に修正申告を行えば過少申告加算税を払う必要はありません。調査の事前通知後に修正申告すれば減額されます。
・無申告加算税
期限内に申告や納税をしなかった際に課せられるのが無申告加算税です。
納税額に対して15%、50万円を越える部分は20%の加算税が発生します。調査を受ける前に申告すれば5%の減額が可能です。
・不納付加算税
法人や個人事業主が期限内に納付しなかった際に課されるのが不納付加算税です。
新たに納める必要がある税金の10%が課せられますが、税務調査を実施する前に自主的に納付をすれば5%に減額されます。
・重加算税
意図的に隠ぺいした場合などに課されるのが重加算税です。
過少申告加算税、不納付加算税に代えて課される際には35%、無申告加算税に代えて課される際には40%の重加算税が課される仕組みです。
重加算税が課されると納付額も増えることに注意してください。
税務調査の種類
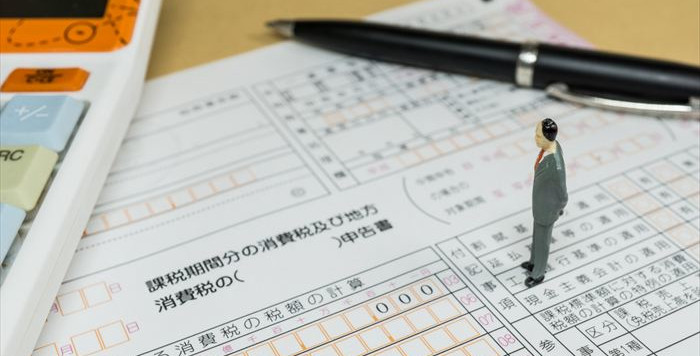
税務調査には、大きく分けると任意調査と強制調査があります。任意ですが調査は拒否できません。それぞれにどのような違いがあるのか認識していない人もいるでしょう。
ここでは、任意と強制それぞれの特徴を解説していきます。
任意調査
納税者が正しく税務申告をしているか税務署による調査が行われるケースがありますが、一般企業や個人事業主に対しては、多くの場合で任意調査が実施されています。
ただし、任意であっても税務調査を拒否すれば罰則を与えられる可能性があります。
強制調査
強制調査は、国税通則法にもとづいて国税庁査察部(通称:マルサ)が実施する調査です。
裁判所の令状によって実施され、捜査に強制力があるため拒否できません。
よほどのことがない限り強制調査は実施されませんが、悪質性の高い不正が発覚した場合や、刑事捜査に発展しそうな場合に強制調査が行われます。
税務調査を拒否できる「正当な理由」とは

税務調査は任意と強制いずれの場合でも協力しなければいけません。
しかし、正当な理由がある時は調査の延期が認められるケースもあります。どういった理由が当てはまるのか解説していきます。
拒否はできないが延期・再調整は可能
任意調査が行われる場合、基本的には調査を行う前に実施する旨の通知があります。事前通知の段階で、納税者と税務署との間で日程が調整される仕組みです。
しかし、事前に日程を決めた場合でも、事故での入院や急病など、当日までに何らかの事情によって日程変更を余儀なくされるケースもあります。
そのような時には、税務署が納税者の事情を考慮して日程の延期や再調整を行ってくれます。
緊急な事案が発生した際には、税務署に連絡して日時の変更が可能かどうかを相談してみてください。
自然災害や天災などやむを得ない場合も延期・中止になる
納税者本人の体調だけではなく、自然災害や天災といった事態に陥った時も延期や中止になる可能性があります。
地震や台風などの被害状況によっては、書類の紛失や破損など、提出するべきものが用意できないケースもあります。
そういったやむを得ない理由があれば、延期または中止になるかもしれません。
実際、コロナ禍では予期せぬ感染症の流行によって、税務調査が延期になった事例があります。
やむを得ない事情があれば、税務署に問い合わせてみてください。
税務調査が入る可能性が高い決算書の共通点

税務調査が入る可能性が高い決算書には、ある共通点があります。ここからその特徴を解説していくので、当てはまっている部分がないかチェックしてみてください。
売上げがギリギリ1,000万円を超えていない
売上げが1,000万円を越えると、翌年以降は課税事業者となるため消費税を納めなければなりません。
一方、売上げが900万円台を維持し続けていれば、消費税の支払いから逃れるために過少申告していると疑われるケースがあります。
特に、売上げの増加が見込まれているにも関わらず、売上高が一定であれば「課税対象額を意図的に減少しているのでは」と判断されやすくなってしまいます。
すべての取引きを正しく記録し、透明性を確保することが重要です。
同業種と比べて利益が少ない
税務署では、「この程度の売上であれば、おおよそ○%の利益が残る」といったデータを業種別に用意しているといわれています。
そのため、同業種と比較して明らかに利益が少なければ売上げや経費をごまかしていると判断されやすいです。
現金による取引きが多い
飲食店や小売店など、対価を現金で受け取っている業種の場合、税務調査の対象になりやすい傾向にあります。
特に、顧客との取引きで現金を使うケースが多い場合に当てはまる項目です。
銀行口座を活用して行う取引きであれば記録が残りますが、現金であれば記録が残らず、脱税しても証拠は残りません。そのため、調査の対象になりやすいです。
不安であれば、現金をやり取りした証拠を残しておいてください。
開業3年以上経過して売上げが伸びている
開業後3年以上経過してから売上げが伸びている事業者も税務調査が実施される可能性が高くなります。
開業後3年目以降は、経理処理に対する油断が出やすく、ミスも生じやすくなる時期です。
消費税が課税されるのは事業がスタートしてから3年目以降となるため、調査対象になりやすい特徴があります。
開業してから3年が経過し、売上げが伸びてきている場合には、徹底した会計処理を行うことを心掛けて、取引きの記録もしっかりと残しておくことが大切です。
経費に不審な部分が見られる
経費に不審な部分が見られる場合も調査が実施されやすくなる要因のひとつです。
事業に関連性のない経費が多く計上されている場合、経費とは異なるものを計上している可能性があると疑われます。
反対に、事業に必要な経費がなければ不審に思われるかもしれません。不審な経費がないか確認してみてください。
切りのいい数字が多い
決算書を確認した時、「交際費100,000円」「旅費交通費150,000円」のように、切りが良い数字が多く使われているのも怪しいと疑われる要因です。
これらはラウンド数字と呼ばれており、適当な数字を用いて集計していると疑念を抱かれやすいです。
相続税の申告をしている
相続税には、高額な資産が関与しています。そのため、相続税の申告をしている場合には税務署の調査対象になりやすいといわれています。
相続税の申告では、資産の評価が徹底されているか、贈与された財産がきちんと申告されているかなどを細かく確認されます。
財産の評価額が高かったり多くの財産が存在したりする相続には注意が必要です。
特定の相続人に対して優遇措置がとられている場合や、不動産評価と市場価値に大きな違いが見られる場合には、厳しいチェックを受けなければならないかもしれません。
税務調査を極力回避するためのポイント

意図的な不正がなくても、税務調査によって罰則を受ければ信用が大きく損なわれてしまいます。
大きな手間が生じるため、「税務調査は来てほしくない」と考える人も多いでしょう。
ここからは、税務調査を回避するためのポイントを解説していきます。
確定申告と納税を期日までに行う
調査が行われないためにも、確定申告や納税は期日までに行うようにしてください。特に、確定申告は正しい内容で作成して提出する必要があります。
ミスなく申告するためにも、収入や経費、税額といった部分には注意して、計算ミスや記入漏れがないか確認してください。
また、書類を用意して適切な申告をすることで、税務調査を避けられます。
さらに、利益が大きく変動している場合にはその要因を明確に記すことが必要です。
「本年中における特殊事情」の欄を使い、新製品の投入や事業拡大、経済状況の変化など、利益が変動した要因を具体的に記していきます。
証拠となる請求書や領収署などはすべて保管をし、必要に応じて提出できるよう準備しておいてください。
正確な会計仕訳を行う
会計仕訳も正確に記す必要があります。税務署では、KSKシステムによって不自然な数字を探し、税務調査の候補先を決めています。
不正確な会計の実施や脱税を疑われるような処理はKSKシステムに引っかかってしまうため、調査の対象となる可能性があります。会計仕訳は正確に入力するよう心掛けてください。
脱税の可能性がある取引先とは付き合わない
脱税といった不正行為を行っていなくても、取引先に脱税の疑いがあれば反面調査として調査対象になるケースがあります。
取引きを中止することで調査を防げる可能性があるため、不正行為の疑いがある会社とは付き合わないよう注意してください。
顧問税理士と契約を締結する
税理士と顧問契約することも税務調査対策となります。
税理士による指導のもとで申告が実施されているとわかれば、意図的な不正行為の可能性が低いと判断されるためです。
万が一、税務調査が実施されるとしても、顧問税理士がいれば書類の準備や税務署職員の対応をすべて行ってくれるため安心です。
不利にならないようサポートをしてくれるので、不安が大きければ顧問税理士による支援を受けることを検討してみてください。
税務調査が入りやすいタイミング
税務調査が実施される時期に決まりはありません。
ただし、確定申告が終わった後の4月~5月の間や税務署の人事異動が終了した7月~11月頃に実施されるケースが比較的多いといわれています。
特に、7月~11月の時期は2月~5月が決算月の法人が調査対象となりやすいです。国税の事務年度は7月スタートで、税務調査は7月1日から翌年の6月30日の期間で実施されます。
このうち、上期となる7月~11月は、2月~5月が決算月となる法人が主に調査対象となるため、重点的に確認が行われやすい時期です。
2月~5月が決算月の法人は7月~12月の税務調査に備えて念入りに準備をしておく必要があります。
まとめ・税務調査を拒否しなくてもいいように正確な会計処理・確定申告を心がけよう
税務調査には任意と強制の2種類があります。任意の場合は「拒否できる」と考える人も多いかもしれません。
しかし、原則として税務調査は拒否できず、場合によっては罰則を受ける可能性があります。日頃から正しい会計処理や確定申告を心がけてください。
税務調査を拒否することはできないからこそ、普段から抜け漏れなく対応しておくことが重要です。創業手帳で無料で配布している「税金カレンダー」なら、申告・納付の期限を一覧で確認でき、うっかり忘れを防げます。経営者の強い味方としてぜひご利用ください。
(編集:創業手帳編集部)