売掛金の仕訳方法とは?具体例や会計処理・管理での注意点もご紹介
売掛金の仕訳でお金の流れを把握しよう

個人事業主・企業が商品・サービスを提供する場合、売掛金という権利が発生します。
この売掛金に関するお金の流れを把握するためには、取引き一つひとつを仕訳に起こすことが大切です。
そこで今回は、売掛金の仕訳手順や仕訳例、会計処理や管理を行う上での注意点を紹介します。売掛金の仕訳方法について詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
売掛金とは

売掛金は、提供した商品・サービスの代金を将来受け取る権利を意味します。信用取引の帳簿では、勘定科目として使われています。
主に企業間で継続的に取引きを行う場合、一定期間分の代金をまとめて受け取るケースが多いです。
取引きごとに支払いが発生すると、毎回手間や手数料がかかってしまうので、後日まとめて支払う信用取引が定番です。
売掛金は流動資産に該当し、会計上では資産となります。
しかし、売掛金が高くなると、取引先から回収不可となった際に損失のリスクが高くなるので注意しなければなりません。
資金繰りに影響を与えるため、仕訳によって売掛金を管理する必要があるのです。
買掛金や未収金との違い
買掛金とは、商品・サービスを仕入れた際に発生する未払いのお金のことです。つまり売掛金と対照となる概念になります。
こちらは商品・サービスの提供を受けた企業や個人事業主が取引先に支払うべき債務です。賃借対照表では負債の部の流動負債に該当します。
未収金とは、事業活動以外で定期的に発生する取引きにおいて、金銭の回収がされてない債権のことです。
事業活動外の債権には、固定資産や有価証券の売却益、本業外の物件の賃貸収入など該当します。
代金を回収できていない点は売掛金と共通する要素です。しかし、売掛金は事業活動で発生する債権となるので、事業活動外であるかどうかが未収金との大きな違いとなります。
売掛金の仕訳の手順

売掛金が発生した場合、仕訳処理が必要となります。その手順は以下のとおりです。
1. 売掛金の計上
商品の納品やサービスの提供が完了した時点で、売掛金を計上してください。
タイミングは、商品・サービスを提供した時点をいつにするのかによって変わってくるため、実際に計上するタイミングは企業ごとに異なります。
例えば、取引先に商品を送った日にする企業もあれば、商品が届いた日や取引先が商品を検収した日とする企業もあります。
一般的には、納品書や請求書を送った時点とするケースが多いです。あらかじめ企業でタイミングを明確に定めた上で、売掛金の計上を行ってください。
2.請求書の発行と入金の確認
商品・サービスを提供した後は、取引相手に請求書の発行が必要です。取引先は請求書の内容に基づいて代金の支払いを行います。
そのため、請求書の発行業務は正確性が求められます。金額の間違いといった人的ミスを減らすために、自動化システムを活用するのもおすすめです。
請求書の発行後、指定された期日までに取引先から代金が支払われます。代金を受け取った際は、請求金額と実際の入金額に間違いがないかしっかり確認することが大切です。
万が一、入金金額が異なる場合は自社内で原因を調査し、社内で問題が見つからない時は取引先に確認を取るようにしてください。
3.売掛金の入金消込作業
入金消込とは、取引先からの入金額と請求金額を照らし合わせ、売掛金などの残高を消去する作業です。
この作業を行うことで、計上されていた売掛金(負債)をなくすことができます。入金消込を行うタイミングは、入金の確認ができた時点で行ってください。
4.取引先ごとに定期的な残高確認
継続して信用取引を行う取引先がいれば、取引先ごとに定期的に残高確認をしてください。
請求金額と入金額のズレだけではなく、期日にしっかり入金されているかどうかも把握しておかなければなりません。
売掛金の入金管理を行う際は、月末締めで翌月末の入金など取引先と入金期間を決めておくと管理しやすくなるのでおすすめです。
ほかにも取引先ごとに補助科目を設定し、勘定科目の中身を細かく分類させることで、売掛金の残高を把握しやすくなります。
【ケース別】売掛金の仕訳例
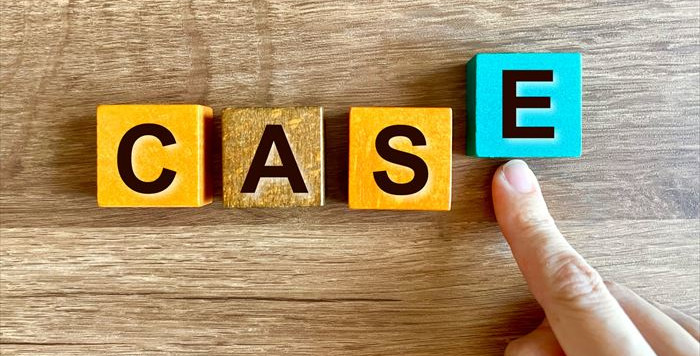
売掛金が発生するのであれば、経理業務のひとつである仕訳作業が必要です。信用取引のパターンは多岐にわたるので、ケース別に売掛金の仕訳例を紹介します。
売掛金が発生した場合
商品・サービスが1万円で売れて売掛金が発生する場合、仕訳方法は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 売掛金 | 10,000円 | 売上 | 10,000円 |
売掛金が発生した場合、資産が増加したことから借方の勘定科目は「売掛金」となります。売上は勘定科目において収益に該当するため、貸方に記載します。
消費税に関しては、課税事業者か免税事業者によって異なります。
課税事業者は税込経理方式と税抜経理方式のどちらかで処理し、免税事業者は税込経理方式で処理が必要です。
税込経理であれば借方と貸方の両方に消費税を反映させた金額を記載してください。
税抜経理では、借方は消費税を含む金額を書き、貸方は「売上」と税抜金額、その下に「仮受消費税等」という勘定科目で消費税分を処理します。
この時、売上と仮受消費税等の金額を合算し、貸方と同額になっていることを確認してください。
代金が現金で支払われた場合
取引先から1万円の代金が現金で支払われた場合の仕訳方法は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金 | 10,000円 | 売掛金 | 10,000円 |
売掛金が現金で支払われた場合、借方に現金と入金金額を記載します。反対に貸方に売掛金と記載して処理します。
代金が銀行振込で支払われた場合
取引先から1万円の代金が銀行振込で支払われた場合の仕訳方法は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 10,000円 | 売掛金 | 10,000円 |
銀行振込の場合、勘定科目は普通預金とすることがほとんどです。そのため、代金の支払いによって増えた普通預金は借方に記載します。
現金と同じく売掛金を記載するのは貸方です。
代金がクレジットカードで支払われた場合
取引先から代金をクレジットカードで支払われた場合、売上が発生した際と取引先から入金された際の両方で仕訳をします。
売掛金1万円、クレジットカード会社への支払手数料を500円とした場合の仕訳方法は以下のとおりです。
【売上が発生した時】
| 借方 | 貸方 | ||
| 売掛金 | 10,000円 | 売上高 | 10,000円 |
【代金の入金があった時】
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 9,500円 | 売掛金 | 10,000円 |
| 支払手数料 | 500円 | ||
売上が発生した時点では、売掛金として会計処理をします。その後、代金の入金があれば銀行振込と同じく、借方は普通預金で貸方には売掛金を記載してください。
代金からクレジットカード会社への支払手数料が差し引かれた際は、借方に支払手数料の勘定科目を追加し、手数料分を記載します。
その際、普通預金には支払手数料を差し引いた金額を記載してください。
売掛金の一部が支払われた場合
売掛金を一度に全額ではなく、数回に分けて支払われることがあります。例えば、3万円の売掛金に対して、現金1万円の支払いがあった際の仕訳方法は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金 | 10,000円 | 売掛金 | 10,000円 |
一部のみの支払いでも、全額で支払われたケースと仕訳方法は変わりません。実際に支払われた金額で仕訳します。
上記の例は現金となっていますが、支払われた方法に合わせて勘定科目を変更してください。
また、取引内容を明確にするために、摘要欄に取引先名や総入金回数のうち、何回目の支払いになるのか記録しておくのがポイントです。
売掛金回収前に返品された場合
取引先から代金が支払われる前に返品された場合、計上していた売掛金から差し引くための処理が必要です。
1万円の商品の返品を受けた際の仕訳方法は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 売上高 | 10,000円 | 売掛金 | 10,000円円 |
売掛金が発生した時は借方が売掛金、貸方が売上高となっていますが、返品を受けた際はその逆で処理してください。
売掛金を値引きした場合
もともと3万円の売掛金を1万円分値引きされ、2万円が現金で支払われた場合の仕訳方法は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金 | 20,000円 | 売掛金 | 30,000円 |
| 売上値引 | 10,000円 | ||
売掛金の値引きがあった場合、借方に売上値引きの勘定科目を追加して、値引きする金額を記載します。現金には値引きされた分の金額を記載してください。
そして、貸方の売掛金は現金と売上値引を足した金額を記載します。
売掛金を買掛金で相殺した場合
商品・サービスを販売する取引先から仕入れを行っていて買掛金が存在すれば、売掛金を相殺することが可能です。
取引先から許可を得た上で売掛金1万円と買掛金1万円を相殺した場合の仕訳方法は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 買掛金 | 10,000円 | 売掛金 | 10,000円 |
このケースでは借方に買掛金の勘定科目、貸方に売掛金の勘定科目を記載します。
なお、買掛金と相殺する際はトラブル防止のために、当事者同士で合意をとって会計処理を行ってください。
売掛金が回収不能になった場合
取引先の突然の倒産や自己破産などを理由に売掛金が回収できなくなる場合があります。
例えば、売掛金80万円の回収ができなくなった場合の仕訳方法は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 貸倒損失 | 800,000円 | 売掛金 | 800,000円 |
売掛金の回収が不可能となった際は、借方は貸倒損失、借方は売掛金の勘定科目で処理してください。
売掛金の仕訳・管理における注意点

売掛金は安定した企業を維持するために、適切に回収や管理をしなければなりません。ここでは、売掛金の仕訳や管理をする上での注意点を紹介します。
取引先ごとに帳簿を作成して管理する
売掛金は、取引先ごとに売掛金元帳を作成して管理するのがマストです。売掛金元帳は、日付順に売掛金の情報を記録する帳簿です。
取引先に商品・サービスを提供するために記録すれば、取引先ごとに残っている売掛金や入金消込を確認できます。
売掛金元帳への記録は手作業でもできますが、会計ソフトの活用がおすすめです。
会計ソフトであれば、データを入力するだけで売掛金元帳に自動的に転記してくれるので、経理業務の負担軽減やヒューマンエラーを防げます。
売掛債権の回転期間・回転率を把握する
売掛金を適切に管理するためにも、売掛債権の回転期間や回転率を把握することが大切です。
回転期間とは、売掛債権を回収するまでかかる期間を示します。
「365÷売掛債権の回転率」で回転期間を算出でき、この期間が短いほど短期間で売掛金の回収ができていると判断できます。
一方、回転率が指すのは、売掛債権を回収する速さです。回転率が高いほど効率良く売掛金を回収できています。
回転率は「売上高÷売掛債権額」で算出することが可能です。売上高は1年間で獲得した売上高の金額を使います。
売掛債権は、期首の売掛債権残高と期末の売掛債権残高の平均額を用いてください。
売掛金がマイナスの時はミスや過剰入金を疑う
売掛金は売上と同額で計上されるので、帳簿の記録で金額がマイナスになることはありません。
しかし、万が一にマイナスとなっていた時はミスや取引先からの入金ミスを疑ってください。
例えば、売掛金の金額計上をミスしていたり、そもそも請求書の金額が間違いだったりすることがあります。ほかにも金額を間違えて入金消込を行っているかもしれません。
売掛金がマイナスになるケースとしては、取引先のミスも考えられます。取引先からの過剰入金であれば、支払いに翌月の請求分を含んで支払ったのか事実確認が必要です。
そして、過剰入金があった際には余分に入金された分の対応も検討してください。
年度をまたいでの会計処理に注意する
締め日以降に発生した売掛金は、翌月分で処理されます。しかし、会計年度をまたぐ形で売掛金を処理する際は少し特殊なので注意してください。
例えば、請求書の締め日が毎月20日であれば、20日以降に発生する売掛金は翌月分として計上します。
しかし、会計年度を4月始まり3月末日締めとしている場合、3月21日~31日に発生した売掛金は今年度分の売掛金として計上しなければなりません。
また、今年度に発生した取引きに対する売掛金が会計年度をまたぐ場合、未収金として翌年度に繰り越す必要があります。
まとめ・売掛金は状況に合わせて適切に仕訳をしよう
売掛金は、商品・サービスを提供した際に将来的に金銭を受け取れる権利であり、事業の売上げに大きく影響する要素です。
回収できないと収入が入らず、倒産や自己破産といったリスクを高めます。
そのため、売掛金の発生や入金がある時点で適切に仕訳を行い、細かく管理していくことが大切です。
売掛金の仕訳は支払い方法や条件によって複数のパターンが存在するので、どのようなケースでどのような勘定科目を使うのか学ぶことをおすすめします。
創業手帳では、企業経営に欠かせない会計処理に関するノウハウを紹介しています。創業時期から役立つ情報を提供しているので、チェックしてみてください。
(編集:創業手帳編集部)



































