どうすれば会社を守れるか? 国際弁護士に聞く「採用トラブル予防」のコツ
弁護士法人堂島法律事務所の安田健一弁護士に、創業期の採用トラブル回避について聞きました

(2019/10/04更新)
人材の採用難で多くの企業が頭を抱えています。特にまだ社員数が少なく、一人の人材が占める役割が多いスタートアップの場合、気になるのは採用のミスマッチや方向性の違いによるトラブル回避です。仮に人材を採用できたとしても、その人材のスキルが戦力として乏しかったり、問題があったりすると大変です。また、急に社員が退職する場合も少なくないので、創業期の採用は慎重にならざるを得ません。
今回は、人材採用に悩める創業期の起業家のため、弁護士法人堂島法律事務所の安田健一弁護士に、採用のトラブル回避のコツや、試用期間の運用法を聞きました。

京都大学法学部・京都大学法科大学院・ニューヨーク大学ロースクール(LL.M.)各卒業北京及びバンコクでの勤務経験あり。国内・海外それぞれで日系大手企業の法務部に出向した経験を活かし、上場企業から中小企業・ベンチャーに至る多種多様な企業に法的サービスを提供している。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
「契約書は全てに優先する」わけではない
これから起業する、あるいは起業直後の皆様にまず何より知って頂きたいポイントは、「従業員保護のための法律は契約内容よりも優先する」ということです。専門用語では強行法規といいます。
簡単に言うと、会社側が有利な契約書を従業員と結んでも、労働法が優先するため、後で契約がひっくり返されることもある、ということです。契約の当事者が法律と違う合意をしても、法律の内容が優先します。
極端な例としては、入社希望者が自ら「残業代なんて1円も要りません」と言ってきて、それを条件に雇ったとしても、採用後にその人材から残業代を請求された時、裁判では負ける可能性が高いです。普通の商取引の感覚とは異なりますが、労働法という特別な分野ではこのようなことが起きてしまいます。経営者、起業家の方はご注意ください。
契約より優先される法律がある
社員を「クビ!」にできるか
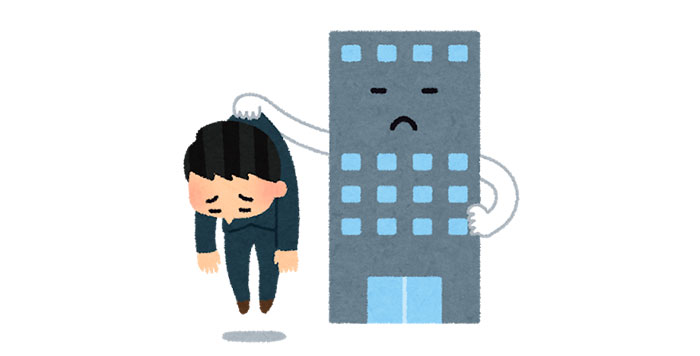
アメリカのドラマ・映画では、「お前はクビ!」というシーンが出てきます。(その決め台詞で有名になった人が今のアメリカのトランプ大統領ですね。)
アメリカではドラマのような突然の解雇は実際にあります。しかし、日本では難しいケースが多いです。労働者保護のレベルが全く違うためです。
日本には、従業員を保護するルールの代表的なものとして、「解雇の制限」があります。原則として解雇を自由に行えるアメリカとは異なり、日本では客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には解雇が無効になってしまいます。このハードルは相当に高く、特に成果をあげていない・能力がないといった理由で解雇をすることは大変困難です。そして、解雇が後から無効とされたとき会社には大きなダメージが生じます。
解雇無効のケースに注意
私は日本の弁護士資格の他に、ニューヨーク州の弁護士資格を取り、その後中国やタイなどでも仕事をしていました。例えばタイでは、日本と同様に正当な根拠のない解雇は許されないものの、必ず当該従業員が復職するわけではなく、裁判所が相当と認める場合には、雇用関係は復活させずに会社に損害賠償を命じることがあります。つまりお金で解決するケースがあるということです。
日本はそれと異なり、解雇が法律上の条件を満たしていない場合、解雇された人物が従業員としての地位を持っていることが確認されるとともに、それまで未払いだった賃料の支払いが命じられます。
例えば従業員を解雇したところ、その従業員は解雇が無効だと主張して訴えを起こしてきたとします。1年間争って最終的に解雇が無効だとされた場合、その従業員には裁判期間中も従業員の地位があったことになり、会社は原則として、裁判で争っていた1年間分の給料を支払わなければなりません。裁判期間中その従業員は会社のために働いていなかったにもかかわらず、です。
紛争になってから雇った弁護士の費用と1年間分の給与で数百万円以上が消えることになります。こういったトラブルが生じると、他の社員のモチベーションも下がりますし、立ち上げたばかりの基盤がまだしっかりしていない会社にとっては、数百万単位であっても経営がゆらぎかねない大きな損失です。
労働リスクは経営リスク
経営者はどう自衛するか?
昨今、会社員にとって転職はごく一般的な選択肢です。「絶対にこの職場で働き続けよう、だから多少のことは我慢しよう」という考えの人材はますます少なくなっています。また、今はインターネットを通じて、労働法の知識を身につけることも、気軽に相談できる弁護士や組合を探すこともできる時代です。従業員や元従業員とのトラブルは、以前より発生しやすくなっていると言えるでしょう。
採用にあたって起きやすいトラブルの原因と、自衛のために企業が取り組むべきポイントを解説します。
揉めやすいのは「期待と違う」とき。期待値すり合わせを
会社と従業員とのトラブルは千差万別ですが、入社してから早い時期にトラブルになりやすいのは、従業員が「説明された内容と違う」と感じるときです。経営者側が「期待を裏切られた。ミスマッチだった」と感じたとき、従業員の側もそう思っているかもしれません。そして、いわば騙されて入社したと自分で感じている従業員は、会社と揉めることにも抵抗を感じないというケースに経験上、多く出会います。
採用段階で、期待値の丁寧なすり合わせは必須です。
揉めそうなポイントは予め詰めておく
これまでに述べたとおり、いったん雇い始めると簡単に離れられないのは従業員の側ではなく、会社の側です。実際の職務内容やおおよその残業時間といった揉めやすいポイントについて、入社前に決めておきましょう。
例えば勤務地や業務内容について、雇用契約上広めに定めてあった場合、会社の業務命令として変更する権利が基本的にありますが、契約で定めた枠外のことをしてもらうには、従業員の同意を取らなければなりません。
揉めそうなポイントは、あらかじめ決めておく
契約期間の定め方を工夫することも有効
また、従業員を採用するときの最大のリスクともいえる解雇規制に対しても、契約の仕方を工夫しましょう。
例えば、相手の同意があればですが、常に定年までの終身雇用契約とするのではなく、契約期間を明記した有期雇用契約にすれば、リスクの軽減に役立ちます。
また、試用期間を定めることも有効です。ただし、試用期間後の本採用拒否も一種の解雇にあたり、無条件にできるわけではないことに注意です。通常の解雇と比較すると認められやすい、というレベルの認識にとどめてください。
試用期間を有効に活用するコツは、本採用の基準を明確に定めること、記録することの2つです。記録により、後から紛争になった場合に備えた対応をしておくことが重要です。
期間を設定した雇用では
1、本採用の基準を定める
2、記録を残す
まとめ
少子化と転職の一般化で、会社にとっては優秀な人材を確保し、中長期的に育成、活躍してもらうハードルが上がっています。
勘違いや誤解、あるいは理不尽な主張による係争(裁判で争うこと)は、仮に勝つことができたとしても、会社や、ほかの従業員だけでなく、貴重な時間を使う本人も含めて誰も得をしないことが多いでしょう。
スタートアップの場合、潤沢な時間と資金、人材がないなかで労務の対策は大変だと思いますが、採用トラブルによって会社に大きな損害が生じないように、「事前の同意を取る」、「記録に残す」、「試用期間を利用する」など、リスクヘッジ策を用いて会社と従業員双方を守るようにしましょう。
(監修:
弁護士法人堂島法律事務所/安田健一弁護士)
(編集: 創業手帳編集部)




































