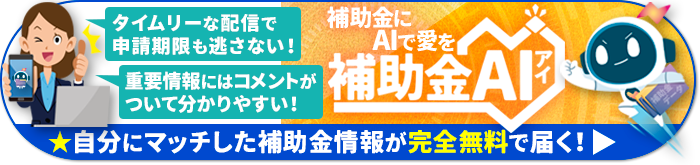地方で起業を目指す!メリットや成功事例、スタートアップ支援制度の種類・特徴を解説
地方起業に役立つスタートアップ支援制度について把握しよう!

地方には都市部とは異なる魅力が数多くあり、地域の特色を活かしたビジネスでチャンスを掴もうと、ローカルスタートアップを目指す起業家も少なくありません。
地方で起業する場合、スタートアップ支援を活用することでスムーズに起業できる可能性があります。
そこで今回は、地方での起業が注目される理由から起業に役立つ支援制度などについて解説します。地方起業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
創業手帳では、創業カレンダーを無料配布しています。創業に関してすべきことを確認できるカレンダーです。ぜひご活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
地方での起業が注目される要因

情報収集や人材の確保のしやすさ、利便性を踏まえると、ビジネスの拠点は東京や大阪といった大都市が選ばれがちです。
しかし、あえて地方を拠点に起業を目指す動きが増えています。
地方での起業が注目される理由には、都市部での起業と比べて低コストで始められる、競合が少なくビジネスを展開しやすいなどが挙げられます。
近年はインターネットを活用したビジネスが当たり前となっているので、場所を問わず事業を展開できることも地方を拠点にしやすくなった要因のひとつです。
また、地方では人口減少や少子高齢化が社会問題となっています。各地で人やビジネスの誘致を図りたいと考え、国や地方自治体では様々な支援制度を用意しています。
起業家向けの支援制度もあるため、それを活用して起業できることもメリットです。
地方で起業する際のおすすめの分野
地方での企業が向いている分野を6つ紹介します。興味のある分野を見つけて、起業の内容を検討しましょう。
-
- 支援制度が充実した「農業」
- 生産+加工+流通のメリットを掛け合わせた「6次産業化」
- 固定費が安い「飲食店」
- ライフスタイルに合わせて活動できる「ITベンチャー」
- 生活費を抑え都市部でリモートで働く「Webマーケター」
- 地方で新規顧客を期待できる「コンテンツ制作」
→生産は1次産業、加工は2次産業、流通や販売は3次産業のため
地方で起業するメリットとは
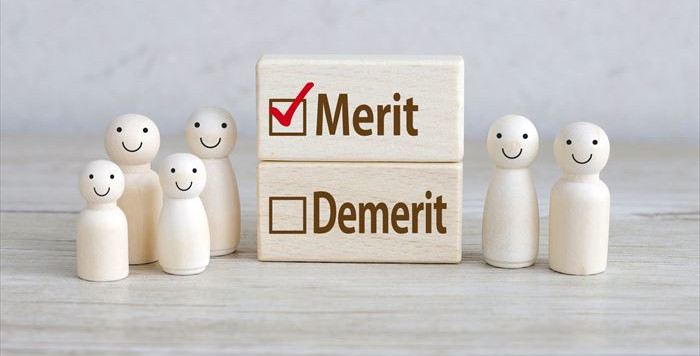
地方での起業には、起業家にとって様々な魅力があります。ここで、地方で起業するメリットについて詳しく解説します。
コスト削減がしやすい
地方では、ビジネスをする上で必要となる固定費を削減しやすいメリットがあります。
例えば、店舗や事務所を借りる場合は家賃が発生しますが、都市部よりも地方のほうが安い傾向にあります。また、従業員を雇った際に発生する人件費も低めです。
起業した直後は大きな売上げが出にくく、資金繰りが大変になってしまうケースは珍しくありません。
資金繰りが苦しい状況でも、家賃や人件費などの固定費は毎月支払いが発生するため、少しでも抑えたいところです。
そのため、コストを抑えて経営を始められることは、資金繰りに関する不安を和らげてくれるでしょう。
都市部より競合が少ない
都市部では企業数が多い分、競合も多くなるため、事業を有利に展開できない可能性があります。特に大手企業が競合の場合、スタートアップが太刀打ちするのは困難です。
逆に地方は競合が少なく、事業を展開しやすいことがメリットです。地方では大手企業が参入していない地域もあります。
強大なライバルが少ない分、地域にマッチした事業を展開できれば大成功を収められる可能性が高まります。
関連記事:田舎で起業できるおすすめのスモールビジネスアイデア12選。儲かるビジネスの成功例 | 起業・創業・資金調達の創業手帳
地方の特色を活かしたビジネスが実現できる
起業する地域の資源を活かして、新たなビジネスを展開できるのも地方起業の魅力です。
例えば、各地域では伝統的な工芸や文化がありますが、受け継がれなければ技術や文化はいずれ失われてしまいます。
地域の伝統を受け継ぎながら、今の時代や将来のニーズに合わせたアイデアを取り入れることができれば、ビジネスと地域の両方を盛り上げられるでしょう。
地域の人々からの関心や興味、信頼感も高まり、自社ブランドの価値の向上にもつながる可能性が高くなります。
その地域ならではの自然や特産物などが資源となるので、考え方次第で起業のアイデアは無限大です。
その地域の課題や悩みを解決できるビジネスのニーズも高いと言えます。
地方自治体や地元企業との連携が行いやすい
地方では自治体や企業間での人間関係が深くなる傾向にあります。そのため、自治体や地元企業と協力して、事業を展開しやすいこともメリットです。
自社だけではできないことでも、自治体や地元企業の連携を通じて実現できるかもしれません。
自治体や地元企業の経営者は地元愛や地域を盛り上げたい意識も強いので、そのニーズに合った事業であれば協力を得られる可能性もあります。
地域と良好な関係を築くことも、ビジネスを成功させる上での重要な要素です。
地方自治体の補助金や助成金を活用できる
地方自治体では、地方創生や地域経済の活性化を目的に様々な支援制度を用意しています。
そのひとつが、地域で起業する人や地元の経営者に向けて提供される補助金・助成金です。
補助金・助成金は返金が不要なため、資金調達の悩みを抱え込みがちの創業時期には嬉しい支援制度になります。
起業したい地域では、どのような補助金・助成金があるのか調べてみましょう。なお、補助金・助成金は一定の要件を満たさないと支給されない点に注意してください。
創業手帳では、たくさんある中の補助金・助成金について、ご自身で登録して頂いた都道府県情報などを基に今使える補助金・助成金を隔週でメールでお届けする「補助金AI」を運営しています。無料で利用いただけますので、是非ご活用ください。
地方で起業するデメリットとは
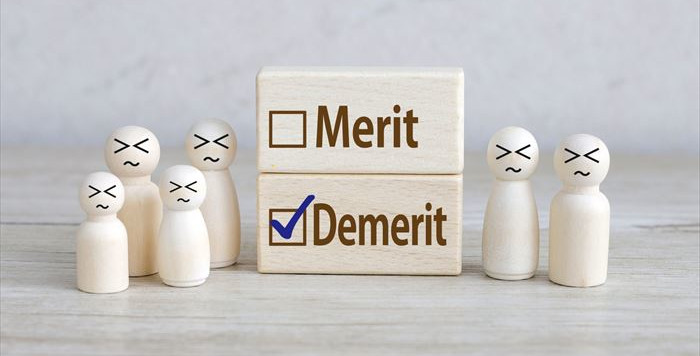
地方での起業には数々のメリットがありますが、反対にデメリットもあります。
メリットばかり重視して起業すると後悔する可能性があるため、起業前に知っておきたいデメリットをご紹介します。
都心部より市場規模が小さい
東京のような都心部と比べて、地方は人口が少なく、減少し続けている地域も珍しくありません。
人口が少ないゆえに市場規模も小さくなりやすく、想定していたほどの利益を得られない可能性があります。
特に地域の住民をターゲットにしている場合、市場規模が小さいことで事業が行き詰まる恐れがあります。
その地域での需要と事業内容の相性をよく加味しておくことが大切です。
また、インターネットを活用できる業種であれば、地域を限定せずに事業を展開でき、市場規模を拡大していくことができます。
都心部より人材の確保が難しい
事業を拡大していくとなると、新たに従業員を雇う必要があります。その際、人材の確保が難しい点が地方企業の悩みです。
特に若い人材は、仕事内容や待遇の良さなどを期待して都市部に流れる傾向があり、採用は難しくなっています。
また、スタートアップの時点では知名度も実績もありません。その点、知名度も実績も豊富な大手企業や中小企業に人材が流れ込んでしまいます。
人手は問題ないものの、ITや専門性が問われる技術や知識を持つ人材が必要になるケースも。
人口が減少している地域では、特定のスキルや経験を持つ優秀な人材を獲得できるチャンスも少なくなりがちです。
業種により新規参入が難しい場合がある
地方は競合が少ないことがメリットですが、業種によっては参入が困難なケースもあります。
例えば、起業する地域ですでに同業他社が高いシェア率を誇っている場合、新規で参入してシェア拡大を狙うのは困難です。
シェアが高いということは、歴史が長く地元からも信頼される企業である証拠です。
そのような企業を打ち破ることはスタートアップでは難しく、早期撤退となってしまう可能性があります。
地域で起業する際は、まず市場調査をして事業に参入できるか確認することが大切です。
同時に、移住者や新規での事業参入者が地元から好意的にに受け入れられる環境であるかどうかも調査することをおすすめします。
地方で起業するポイント
地方で起業をする際には、いくつか知っておきたいポイントがあります。これから地方起業をしたい方へ向けて、4つのポイントを解説します。
起業の目的をはっきりさせる
明確な起業の目的があると、事業の方向性がはっきりするため軸がブレず、周りからの共感を得やすくなります。
ターゲットが絞られコンセプトもまとまりやすいので、トラブルが起きたとしても軌道修正しやすいメリットがあります。
自分のやりたいこととニーズの一致する地域を探す
自分のやりたいことだけでなく、移住を検討する地域のニーズが一致しているかを確認しましょう。
移住先が求める事業であれば成功する可能性が高くなり、やりたいことを続けられます。
また地方は横のつながりが都市部より強い傾向にあり、事業が一部で受け入れられると、一気に広がる可能性があります。
補助金や助成金を活用する
地方自治体の中には、移住して起業する場合に補助金や助成金を支給するケースがあります。制度の利用には申請や受給のタイミングが重要なので、事前に情報収集して確実に手続きしましょう。
補助金や助成金は、例えば地方へ移住して起業をする人へ支給する「移住支援金」や、移住先地域が抱える課題の解決に取り組む人へ支給する「起業支援金」などがあります。
小規模から始める
事業が成功するとは限らないため、初期投資を抑えた小規模のビジネスから始めましょう。
早めに初期投資を回収し終えると、利益を手元に残しやすくなり、事業の安定が期待できます。
地方起業時に活用できるスタートアップ支援

国や地方自治体では、地方への移住や起業したい人のために支援を行っています。
地方起業ではどのような支援を利用できるのか、国や地方自治体の支援事業について解説します。
国の地方創生支援事業
代表的な国の取り組みとして、地方創生起業支援事業があります。
地方創生起業支援事業とは、地方企業や東京圏からUターンによる起業・就業する人を支援することを目的に、地方公共団体が中心となって実施されている事業です。
具体的な支援には、起業支援金と移住支援金の2つがあります。
起業資金は、地域の課題に対して、社会性・事業性・必要性の3つの観点(社会的事業)を持って起業する際に最大200万円の支援金が給付される制度です。
移住支援金は、東京圏に在住・通勤する人が他の地域に移住して、起業や就業するのを支援するための資金です。
移住者に最大100万円(単身者は最大60万円)が給付されます。18歳未満の世帯員と一緒に移住する場合は、18歳未満の子どもひとりにつき最大100万円が補助されます。
東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の1都3県です。これらの都市でも過疎化が進む一部市町村は条件不利地域と定められています。
起業支援金や移住支援金では、この条件不利地域への移住・起業も支給対象です。
地方に移住して、社会的事業で起業する場合は2つの支援金を組み合わせて、最大300万円(単身の場合は最大260万円)の支援が受けられます。
なお、実施期間や支給額など支援制度の詳しい詳細は地方公共団体によって異なるため注意してください。
関連記事:「起業支援金」とは?概要や地方で起業するメリットを解説 | 起業・創業・資金調達の創業手帳
地方自治体の支援事業
地方自治体も独自に起業家に向けて支援事業に取り組んでいます。今回は、4つの県の支援事業を参考にご紹介します。
長野県の支援事業
長野県は、“日本一創業しやすい県づくり”を目標に創業のための情報提供やセミナーの開催、支援機関を通じたサポートと幅広い支援を展開しています。
例えば松本市と長野市に「信州スタートアップステーション」を設け、コンサルタントや中小企業診断士などの専門家に創業・新規事業に関する悩みを相談することが可能です。
女性専用の相談窓口があるほか、月2回程度のスタートアップセミナーやワークショップといった支援も用意しています。
起業を支援する補助金も充実しています。
長野県内での起業を対象にして「ソーシャル・ビジネス創業支援金」をはじめ、市町村でも独自の起業支援補助金を利用することが可能です。
福島県の支援事業
福島県では、原子力災害の影響を大きく受けた12の市町村に移住して起業した人を対象にした支援制度を用意しています。
支援事業の対象となる12市町村とは、南相馬市・田村市・川俣町・浪江町・富岡町・楢葉町・広野町・飯舘村・葛尾村・川内村・双葉町・大熊町です。
主な支援制度のひとつが、「福島県12市町村起業支援金」です。
継続性が見込まれる事業で起業の際に発生した補助対象の経費のうち4分の3以内、最大400万円の補助が受けられます。
他にも、移住支援や各地域が独自で実施する補助金や起業プログラムを利用することが可能です。
徳島県の支援事業
徳島県でも、起業家に向けて幅広い支援が行われています。
例えば「スタートアップ創出促進補助金」では、地域課題を解決する事業で創業する人に向けて最大200万円の補助と伴走支援を行っています。
経営サポートを行う「はたらく女性応援ネット」、事業のスケールアップ支援を目的にした「女性起業塾」といった、女性起業家に向けた支援があるのも大きな特徴です。
徳島県での起業を目指すなら、とくしま・スタートアップ・プラットフォームの活用もおすすめです。
県内で起業を目指す人や、新規事業に立ち上げを目指す企業担当者・大学の研究者などが集まるプラットフォームで、特別講座の受講やその後の交流を通じて起業家仲間やビジネスパートナーを得ることができます。
経験豊富な創業コーディネーターによる起業の相談・支援を受けることも可能です。
石川県の支援事業
石川県では、成長が期待できるスタートアップの発掘と集中的な支援を積極的に行っています。
「創業サポートデスク」は創業に関する支援をワンストップで提供しており、起業の基本知識や事業計画書の作成、資金調達といった課題を解消して起業を目指せます。
完全オンラインの「創業塾」も実施しており、創業するために欠かせないノウハウを学ぶことも可能です。
女性起業家に向けて「いしかわ起業小町」という専用のプラットフォームを設け、個別相談や起業に関するイベント・セミナーなどを通じて伴走支援を行っています。
ローカルスタートアップ支援制度もおすすめ

国ではローカルスタートアップ支援制度と呼ばれるものが、総務省によって設置されています。
地域の資源を活かして地域の課題を解決するための小規模創業を支援し、良好な経済循環を生み出すことを目的にした制度です。
こちらも地方起業に役立つ支援制度であるため、詳細をご紹介します。
ローカルスタートアップ支援制度の概要
ローカルスタートアップ支援制度は、スタートアップ企業の創出・育成から起業施設支援の整備まで行っています。
支援内容は大きく4つに分かれており、事業の段階に合わせた支援を受けることが可能です。
| 事業の段階 | 支援内容 |
|---|---|
| 企画段階 | 以下の経費に対して特別交付税の措置が行われます。 ・会議や旅費など関係者との打ち合わせに必要な経費 ・創業支援等事業計画の作成に必要な経費 ・創業塾の実施や関係者の研修に必要な経費 ・広告費や企画運営費など案件応募に関する経費 |
| 準備段階 | 以下の経費に対して、特別交付税の処置が行われます。 ・地域資源の発掘や活用方法を分析に必要な経費 ・創業のためにビジネスモデル構築支援に関する経費 ・法人設立に必要な経費 ・オフィスの賃貸に関する経費 |
| 実施段階 | ・ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造交付金) 施設整備や備品費など民間事業者の初期投資費用に対して、自治体が地域金融機関の融資と組み合わせて公費により助成を行っています。 ・地域おこし協力隊員等の起業・事業継承 ・経費の特別交付税措置 |
| 立ち上げ後のフォローアップ段階 | 事業を立ち上げた後、事業の分析や再構築などフォローアップにかかる経費の特別交付税の措置を行っています。 |
ローカルスタートアップ支援制度の申請フロー
ローカルスタートアップ支援制度では、ローカル10,000プロジェクトを活用し、初期投資費用を支援してもらうことが可能です。
事業の発案や交付申請、事業開始までの流れは以下のとおりです。
1.事業計画書を作成する
まずは事業者が地域の活性化や課題解決に受けた事業を発案します。そして、民間事業者や地方自治体、地方金融機関と調整しながら事業計画書を作成します。
2.自治体から総務省に申請
地方自治体が総務省に交付申請を行います。毎月10日が申請の締め切り日となっています。申請すると、外部の有識者を通じて交付決定の可否が審査されます。
3.交付の決定後に事業開始
審査後、総務省と地方自治体が申請事業の交付を決定すれば、事業開始となります。申請から採択の決定まで1カ月半程度かかります。
ローカルスタートアップ支援制度の活用事例
ローカルスタートアップ支援制度は、様々な地方の事業で活用されています。その事例をご紹介します。
| 実施地域 | 支援内容 | 取組内容 |
|---|---|---|
| 岡山県高梁市 | ・公費による交付額 国費:16,666,000円 地方費:8,334,000円 ・融資 25,000,000円 |
・歴史的建造物の空き家を宿泊施設としてリノベーションし、町並みの保存・継承と観光復興・交流人口拡大を図った ・宿泊施設をお試し移住やワーケーション施設などに活用し、移住先候補地として市をPR ・宿泊施設の一部店舗では体験やオリジナル商品の販売を行い、観光拠点にする |
| 岐阜県各務原市 | ・公費による交付額 国費:25,000,000円 ・融資 25,000,000円 |
・地元大学生と共同開発した各務原ニンジンを使った和菓子スイーツを販売する拠点として、販売店舗を整備 ・岐阜大学と共同研究契約を締結し、スイーツ開発や店舗内装など大学生の意見を活用 ・県HACCP導入施設の認定を取得し、食品安全管理に関する規格・認証の仕組みを構築 |
※参考:総務省 令和5年度の地域力創造グループの施策等について①
地方で起業した成功事例を紹介
実際に地方で起業し成功した事例3つを、地方創生・地方再生・地方から海外展開まで進めた例に分けて紹介します。
成功事例1:地方創生の事例
青森県田舎館村で行っている「田んぼアート」は、水田をキャンバスに見立てて色の異なる稲を植え、巨大な絵画を作り観光振興を図るための取り組みです。
内閣府の地方創生加速化交付金と、文部科学省の地(知)の拠点大学による地方創生推進事業~地(知)の拠点COC+~を活用しています。
田舎館村は青森県内有数の稲作が盛んな地域で、田んぼアートは平成5年に村おこし事業として始まりました。「つがるロマン」をベースに7色12種の稲を使い、緻密なアートを完成させています。
高い芸術性が話題を集め、年間30万人以上が足を運んでいます。全国各地へ田んぼアートが広がり、田んぼアートサミットを開催するまでになりました。
また、冬季観光客増加を図るため、平成28年からスノーアートが核の「冬の田んぼアート」も始めています。
田んぼアートを観るだけではなく、稲刈り体験なども行って農業に触れるチャンスも提供しています。地元大学と連携し大学生が地元住民と協力して、田植えなどを実施していることも特徴です。
※参考:地方創生 事例集
成功事例2:地域再生の事例
山梨県早川町が取り組んだ「高品質ジビエを核とした活用による地域産業・交流プロジェクト」は、内閣府の地方創生推進交付金を活用しました。
質の高いジビエ肉を核に、自然環境と観光資源を生かして観光と農林業振興を図るもので、交流人口を増やし地域経済を活性化させることが目的です。
獣害駆除で出た肉を活用するジビエ事業を地域振興の軸にするため、既存のハム工場を処理加工施設にしつつ、鹿肉を特産品にするための施設「早川町ジビエ処理加工施設」を整備してスタートしました。
施設の管理・運営は、株式会社YAMATOへ委託しています。町だけでは事業の拡大が難しく、民間事業者の協力を得て事業が推進されました。
生産した加工肉は、ネット販売やふるさと納税で売上げをあげており、加工肉は食用だけでなくペット用商品の開発も進んでいます。
成功事例3:地方から海外展開まで進めた事例
台雲酒造株式会社は、創業者が日本酒のおいしさに感動したことをきっかけに、日・台の架け橋となるべく島根県出雲市で創業した企業です。
創業計画を立てる当初から海外輸入を視野に入れており、許認可をとれてかつ大型トラックの出入りができる広い土地探しに難航したものの、創業者自らが見つけ解決しています。
日本酒製造に必要な初期投資は、日本政策金融公庫と民間金融機関から融資を受けて資金調達し、あわせて創業先の商工会へ、県の支援や労務・税務の相談もできました。
製造する日本酒「台中六十五」は、島根県で栽培される蓬莱米「台中六十五号」を使っており、台湾のルーツを持っています。台湾をメインに香港へも販売中です。
今後は製造量を増やし販路拡大を目指すために、従業員を雇い、創業者自らが商談に出かける機会を増やそうとしています。
将来的には海外免税店での販売、飛行機内で提供されるアルコールのひとつにも選ばれることを目指して、品質と認知度アップに取り組んでいます。
まとめ・地方移住や起業支援を活用して地方で起業にチャレンジしてみよう!
人口減少や活性化が課題となっている地方では、人口流失の抑制と流入の促進を目指して様々な支援制度を用意しています。
地元や移住して起業する人に向けて手厚い支援を実施している地域もあるので、活用することで起業の不安や負担を軽減することが可能です。
地方で人々や社会に役立つビジネスをしたいと考えている方は、国や拠点にする地域のスタートアップ支援制度を調べてみてください。
創業手帳では、創業を起点としてするべきことが確認できる、創業カレンダーを配布しています。詳しくは以下のバナーから!

(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「補助金ガイド」は、数多くの起業家にコンサルティングを行ってきた創業アドバイザーが収集・蓄積した情報をもとに補助金・助成金のノウハウを1冊にまとめたものになっています。無料でお届けしますのでご活用ください。また創業手帳では、気づいた頃には期限切れになっている補助金・助成金情報について、ご自身にマッチした情報を隔週メールでお届けする「補助金AI」をリリースしました。登録無料ですので、あわせてご活用ください。