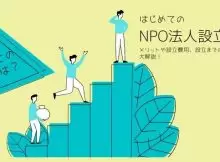創業メンバーは何人がベスト?人数ごとのメリット・デメリットと立ち上げメンバーの探し方・決め方まとめ
創業を支えるメンバー選び。誰を選ぶかで起業の成功が左右される共同創業メンバーの選び方・探し方

創業手帳には今まで170万部発行され、日々莫大な数の起業家の方の創業の相談に乗っています。中でも、「共同創業者を誰にするか」「共同創業者に株を配分するべきか」「役員報酬をどうするべきか」「そもそも共同創業者をどうやって探し決めたらいいのか」という相談を多く受けています。
起業の場合には特に人が大切になり、人・創業メンバーが大切になります。創業メンバーは、形がなくて難易度の高い創業初期において自分から課題に取り組み仕組みを作っていく人達であり、事業が成長していく原動力となる人たちです。
一方で、創業初期にはたくさん人を雇いたいものの、人件費を大企業のように沢山かけることができません。そのため、役員報酬や給与だけでなく、働き方ややりがい、場合によってはストックオプション、そして起業家や創業メンバーの熱意や魅力によってより優秀で合創業者のビジョンに合っている方に、限られた資金の中で働いていただかなくてはいけません。
そんな、難易度の高い創業メンバーの決め方・選び方、人数などについて、会社設立などの相談を多数受けている創業手帳が現場で使われているコツをまとめました。
何人で創業するのがベストなのか、人数ごとの考えられるメリット、デメリットについて解説します。自分の会社のケースをイメージしながらご覧ください。
「冊子版 創業手帳」では創業時や創業後に必要な知識や情報を掲載しています。また、創業時のメンバーや資金について整理するひな形もついていますので、活用してください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
創業メンバー数の違いによってどんなことが起こる?1人~3人の場合
創業に最適な人数はあるのでしょうか。人数の違いによってどんな影響が考えられるのかを見ていきます。
創業メンバーが1人の場合
創業メンバーが1人の場合の、会社運営におけるメリット・デメリットを見ていきます。
一人で創業の意思決定における注意点
何よりのメリットは、自分1人で会社に関わるすべての決定ができることです。持ち株比率100%にしておけばなおのこと、会社全体の舵取りがスムーズにできます。
サラリーマンとして大きな権限を持っていない方や、複数の強力な株主がいることによって意思決定できなかった経験を持つ経営者にとってとても魅力的に映るでしょう。
一方で、いわゆる「ワンマン経営」に陥りがちというリスクがあります。初期のころにはそこまで優秀なメンバーがいるわけではないので、社長が自らそこまで行わなければならないということが起こります。
また、組織は大きくなればなるほど複雑化していくため、組織の成熟度や組織マネジメントのスキルも必要になってきます。そのため、創業で立ち上げに集中しなければならないときに複雑な運営をしていくには困難が伴います。
ただ、対等に意見してくれる人が社内にいないので思考が固まりやすく、もし万が一誤った方向に進み始めた時に道を正すきっかけがなかなかつかめません。
解決策としては、指導や助言をしてくれる経験豊富な人物を外部から招き、定期的に打ち合わせをしておくなど、困った時に頼れる先を最初から見つけておくと安心です。
例えば、エンジェル投資家は成功した事業者であるケースが多いので、投資をしていただくとともにその方から人脈をいただくというケースもあります。うまくいくと非常に良い効果をもたらしますが、一方で経営の主導権を握られるというケースや創業初期のころは株式価値が高くないのでより多くの株式を握られてしまうケースがあります。そのため、エンジェル投資家の場合はお金だけでなく、どういう人物で何をしていただけるのかということを一番に判断していきます。
顧問税理士などの専門家を使うという方法もあります。税理士の中には税務会計しかやらない方と、事業計画や資金調達まで行うタイプの税理士の方もいます。
頼れる顧問税理士の場合には、経営の意思決定では大きな役割を果たします。月額数万円とはいえ、料金はかかりますが経営メンバーレベルの高い意思決定ができることや、資金調達や事業のレベルが上がっていくことを考えると社員を雇うことに比べると確実で安い投資といえるでしょう。
こうした専門家や経験豊富な人材をフルタイムでなく使うことによって意思決定の精度を高めたり、ノウハウを吸収することができます。一人起用の場合には、いかにこうしたフルタイムではない人材を使いこなすかということが重要になってきます。
一人で創業の場合のコストについて
また、コストも自分にのみしかかからないため、コストをコントロールしやすいのも大きなメリットです。会社運営では人件費が膨らみやすいという特徴があるので、その意味ではリスクが少ない運営方法といえるでしょう。
また、創業直後には社長が自ら見て判断しなければならない場面も多くあります。サラリーマンとして分業に慣れていると難しいかもしれませんが、初期のころは良い悪いは別として社長が直接業務を行う依存割合が高くなります。
一人で創業の場合のリスクについて
また、事故や病気も心配です。代表1人が倒れてしまった場合、会社のすべてが成り立たなくなり事業が中断してしまうこともあり得ます。パートタイム的に頼める人材やサポートいただけるプロの方を日頃から関係を作っておくことが有効です。
一人では軽視しがちですが、自分の作業手順をマニュアルや表などの資料にまとめておけば、アウトソーシングや何かあった場合の引き継ぎをする際や事業が成長して社員が増えた場合に対応しやすくなります。
創業手帳では170万人に使われている無料のガイドブックで創業の整理をすることができ、またそこで良い顧問税理士などの専門家やエンジェル投資家などの資金調達についても相談や紹介を無料で行っています。
「会社設立のおすすめ記事はこちらから」
【保存版】株式会社設立の「全手順」と流れを創業手帳の創業者・大久保が詳しく解説!
創業メンバーが2人の場合
異なる能力を持った人同士が協力し合う形で創業すると、お互いの足りない要素を補い効率のいい仕事が期待できます。例えば、Googleの場合は、セルゲイ・ブリンとラリー・ペイジの2人の創業者によって成り立っています。
2人であればブレーンストーミングミーティングもしやすく、また、自分たち以外に気を遣うことなくざっくばらんに意見交換ができるのも魅力です。
お金や権利、給料など多少言いづらいことでも相談しやすく、意思疎通がしやすいです。
一方、会社の立ち上げ時には課題が山積みで、判断を強いられる場面が続くため意見のすれ違いなどが生じます。その際、間に立つ人がいないのでずっと平行線のまま譲り合わないということも考えられます。1対1だからこそお互いに意見を曲げにくく、当然1人創業より意思決定に時間がかかることは見込んでおくべきでしょう。
また、互いに責任の押し付け合いにならないよう配慮するのも大切です。
最初の段階で「なあなあ」にせず、しっかり役割分担を決めておくことが鍵となりそうです。
営業と開発など役割を分けたほうが自分の仕事に集中できるという面もあります。ただ、創業初期のころは業務が流動的だったりしますのでお互いにサポートしあうという姿勢が必要です。心強い右腕となれるようなパートナー関係を築けるよう配慮しましょう。
会社立ち上げ時に求められる創業メンバーとは
自分自身も創業初期のころは業務内容を創業共同者と役割分担することによって自分自身の仕事に集中できたこともありますが、一方で、創業初期のころはその時々で会社にとって必要な事柄に対して役割を問わず柔軟に対応せざるを得なかったケースもあります。そういったケースに柔軟に対応できるような姿勢が創業メンバーには求められるでしょう。
会社の成長とともに表面化するリスクと回避方法
創業初期にある程度の役割分担を決めますが、多くの場合、共同創業者間の役割は変化していきます。社長が役割を背負うことによって社長の成長度合いがほかのメンバーよりも進みすぎることもありますし、途中から優秀なメンバーが入ってきて幹部としての役割を担うということも、起業の創業メンバーとしてはよくあることです。
こうした場合に、株式のシェアでもめるケースが多々あります。株式のシェアというのは会社の所有割合であり発言権のシェアなのですが、後で変更しにくいという特徴があります。
よくある間違えとして、創業メンバー2.3人で均等に分けるということがありますが、意思決定権が分散したり、外部資本を入れる場合に主要株主が分散していると嫌煙される傾向があり、資金調達がしにくいということにもなりかねません。
創業メンバーに対して株式のシェアをするのもひとつですが、代表者のシェアをより高く持ち、役員報酬や役員報酬が高く払えない場合にはストックオプションによって魅力を提示するという方法もあります。
ストックオプションとは会社が将来大きくなってエグジット、つまりIPO上場やM&Aなどによって創業者が莫大な利益を得たときに利益をシェアする仕組みです。通常の株式をシェアする場合、生株(なまかぶ)に比べると議決権が制限されるという特徴がありますので、意思決定の分散が起こりにくいというメリットがあります。
「起業の流れのおすすめ記事はこちらから」
普通の人が起業するには。起業の成功に大切な5ステップを創業手帳の大久保が解説!
創業メンバーが3人の場合
メンバーが2人の場合同様に、多様な経験や能力を吸収でき、主要な幹部陣を作れるということがメリットになります。特に投資家は創業者代表を最も重視しますが、次に重視するのは経営者が集めたメンバー、つまり複数のチームを重視します。
特に事務手続き等が多く、やらなければいけないことが山積する創業期においては、人手を増やして馬力を上げるのは重要です。
「三人寄れば文殊の知恵」の言葉があるように、会社が停滞した時にも新しい意見が出やすく、成長のきっかけが作りやすい人数バランスともいえるでしょう。
ただし、最初は対等であったはずの3人でも、そのうち1人でもモヤモヤと不満を抱えるようなことになると歯車が狂いだします。悪い流れになると1人だけ解任してメンバーから抜けるという事態になる可能性があります。そうなると、会社全体に与えるモチベーションダウンの影響は計り知れず、力関係のバランスを取るのに苦労するというデメリットがあります。
2人創業の時以上にお互いの専門分野を細かく決定し、「みんなで相談しながら決める」というよりは「各自の専門分野についての責任を持つ。その上で意見を出し合う」というスタンスで行くと経営はスムーズに進むでしょう。
1人起業でも解説しましたが、経験豊富な外部のプロを入れることによって3人の意思決定の統一をしやすくするという方法もあります。特に多人数で運営して運営が複雑化するような場合には専門家のしっかりとした見解は非常に有効です。
4人以上でスタートするとどうなる?
人数が多くなるとどんな影響があるのでしょうか。人数が増える分、メリットもデメリットも振れ幅が大きいかもしれません。
創業メンバーが4人以上の場合
4人以上にしたらどうなるでしょうか?学生時代の友人たちやサークル主導で会社をおこす場合や、親戚一同で起案した場合などに考えられるケースです。
注意したいのは、「船頭多くして船山に上る」状態になってしまわないか、ということです。誰が代表なのか、誰がどこまでの権限を持つのかが不明瞭になり、重要な意思決定を行う際のスピード感に欠けてしまう可能性があります。
また、持ち株比率の決定についても悩みの種になります。貢献度に合わせて報酬の基準を決めるのは難しく、人間関係のバランスが崩れることが心配です。できることなら創業メンバー間のいざこざは避けたいものです。
それぞれの間で不満が出ないよう力関係を調整することに必死になってしまい、本来必要なはずの本業の方に時間と労力が割けなくなることが考えられます。株式を1人に偏らせるなど、絶対的な代表者が誰なのかは明確にしておく必要がありそうです。
しかし、違った得意分野を持つ人同士が集まれば、お互いの不足部分を補い合えるのはメリットです。また、出資金額などの面で負担が減ることもあり、複数人での創業は利点も多いのが特徴です。
共同創業者間の株式割合は慎重に!変化に柔軟に対応するための注意点
創業手帳でも多くの創業メンバーとともに起業したという経験がありますが、株式が分散しないように配慮したり、ストックオプションや責任の度合いを変えたりして、その後のメンバー変更に柔軟に対応してきました。
実感としては創業メンバーは会社のステージや規模内容によって良いか悪いかは別として変わっていく傾向が強いです。その際に、ベストな意思決定は変わっていき、メンバーも柔軟に変えていきますが、一方で株主構成だけは変えにくいので株式会社を選択する場合には、株式だけは安易に分散させないという選択肢が良いです。また、創業者からの相談もこのパターンが多いです。
まとめ
会社の経営は、いつも好調に進むとは限りません。万が一のことがあった時に力を発揮するのが創業メンバーです。
メリットだけでなくデメリットも頭に入れた上で、創業メンバーを誰にするか決めるのが理想的です。
絶対の正解はありませんが、自分の会社をどう成長させたいかというビジョンを胸に、慎重に検討する必要があります。
自分の会社をどう成長させたいかというビジョンをもとに、将来の成長を見越した優秀なメンバーをうまく集めていきましょう。その際に重要になるのが経営者の熱意やビジョンで、創業メンバーへの役員報酬やストックオプションも大事ですが、それ以上に経営者や事業・チームの魅力というのが大切になります。
起業したあとに考えられるリスクやトラブルの解決策などが載っている「冊子版 創業手帳」も併せてご覧ください。
(編集:創業手帳編集部)