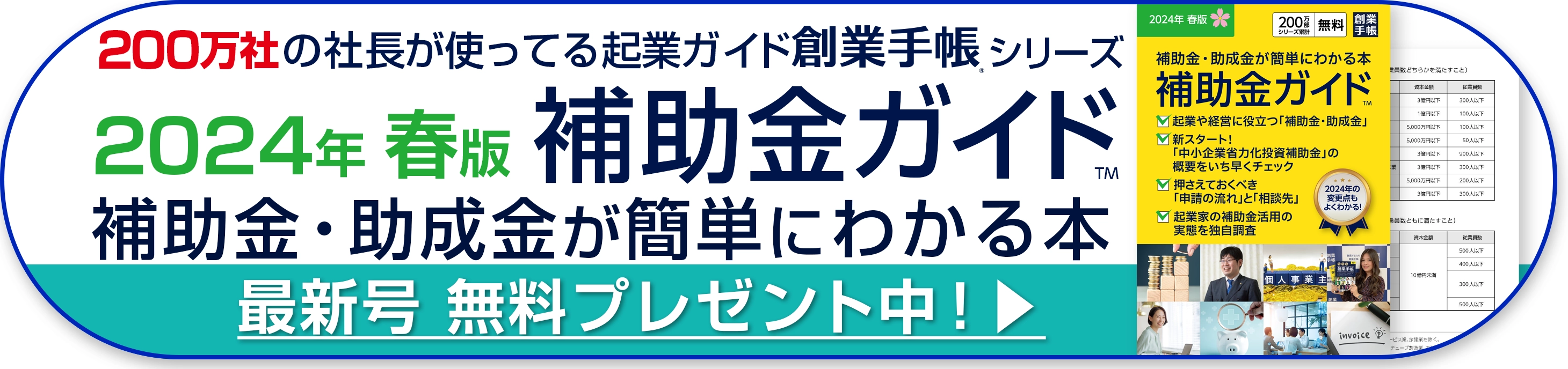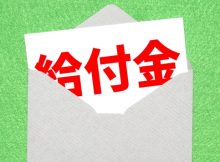シニア起業時に役立つ補助金や助成金を紹介!活用のポイントも解説します
負担軽減のためにも補助金や助成金を活用しよう

定年退職を機に起業を検討している人もいるでしょう。これまでの経験やスキル、人脈などを活かして起業すれば、多くのメリットがあります。
しかし、起業するためには資金を確保しなければいけません。
今回は、シニア起業時に活用できる給付金や助成金、融資制度について解説するとともに、給付金制度を活用するポイントを紹介していきます。
シニア起業を目指している人は、ぜひ参考にしてみてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
シニア起業時に活用できる補助金・助成金

ここからは、シニアが起業する際に活用できる補助金と助成金を解説していきます。
小規模事業者持続化補助金(創業型)
小規模事業者持続化補助金(創業型)は、小規模事業者向けの支援策です。
持続化補助金とも呼ばれ、小規模事業者が経営を見直して持続的な経営に向けた経営計画を立てた上で実施する販路開拓や生産性アップのための取組みを支援する制度です。
創業枠のほかに、通常枠や賃金引上げ枠、卒業枠や後継者支援枠があります。
原則として電子申請システムを利用して申請します。操作手引きに沿って入力してください。
なお、申請時にはGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウントを取得する必要があります。
アカウントの取得には数週間程度かかるので、未取得であれば早めに登録を実施してください。
対象者・対象経費
| 製造業その他 | 常時使用する従業員数20人以下 |
| 商業・サービス業(宿泊業と娯楽業を除く) | 常時使用する従業員数5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員数20人以下 |
上記に該当する法人や個人事業、特定非営利活動法人が対象となります。
また、以下の要件をすべて満たす必要もあります。
-
- 法人の場合は、資本金や出資金が5億円以上の法人に直接または間接的に100%株式保有されていない
- 直近3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていない
- 商工会議所の管轄地域内で事業を実施している
- 持続化補助金で採択を受けて補助事業を実施した場合、各事業の交付規定で定めている「小規模事業者持続化補助金にかかる事業効果および賃金引上げ等条項報告書」が本補助金の申請までに受領されたものであること
- 卒業枠で採択された事業を実施した事業者ではない
なお、創業枠での申請となるため、産業競争力強化法に基づく認定市区町村もしくは認定市区町村と連携した認定連携創業支援等事業者が実施した「特定創業支援等事業による支援」を受けた日及び開業日が、公募の締切り時から起算し過去3年の間であることが要件です。
対象経費は以下の通りです。
-
- 機械装置等費
- 広報費
- Webサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 委託、外注費
補助率・補助上限額
補助率は2/3で、補助上限額は200万円です。免税事業者のうち、インボイス発行事業者の登録を受けた場合は、補助上限額を一律で50万円上乗せされます。
起業支援金
内閣府は、地方活性化に向けて「地方創生移住支援事業」を手掛けており、その中で地方での起業を目指している人に対しての支援として起業支援金を支給しています。
地域の課題解決のために新たに社会的事業を起業する人を対象に助成を行い、効果的な起業を促進して課題解決を通して地方創生の実現を目指すことが目的です。
公募が開始されたら執行団体に対して申請を提出し、審査が行われた後に問題がなければ交付が決定します。
しかし、交付が決定してもすぐに支援金が支払われるわけではありません。
開業届や法人を設立し、伴走支援によるサポートを受けながら実績を定期的に報告する必要があります。その後、支援金が支払われる仕組みです。
対象者・対象経費
新しく起業する場合の要件は以下の通りです。
-
- 東京圏以外の都道府県や市区町村もしくは東京圏内の条件不利地域で社会的事業の起業を行う
- 国の交付決定日以降から補助事業期間完了日までに個人開業届や法人設立を実施していること
- 起業地の都道府県内に居住している、または居住の予定があること
事業承継や第二創業する場合に満たすべき条件は以下の通りです。
-
- 東京圏以外の都道府県や市区町村または東京圏の条件不利地域でSociety5.0関連業種などの付加価値の高い分野において事業承継もしくは第二創業を実施する
- 国の交付決定以降から補助事業期間の完了日までに事業承継や第二創業を行っている
- 事業を行う都道府県内に居住している、または居住する予定である
新たに起業する場合や事業を承継する場合をはじめ、第二創業をする場合には、どちらも上記の項目を満たすことで支援金が交付される仕組みです。
補助率・補助上限額
起業支援金は、起業時に必要となる経費の1/2に相当する額を交付し、最大で200万円を受け取ることが可能です。
移住支援金と組み合わせた利用もでき、単身世帯であれば最大で60万円、世帯であれば最大で100万円が支給されます。
なお、18歳未満の世帯員と一緒に移住する場合は、18歳未満1人につき最大で30万円が加算されます。
移住をともなう起業を目指しているなら、活用を検討してみてください。
創業助成金(東京都)
東京都内で操業を予定している中小企業者、もしくは創業してから5年未満の中小企業者向けに、創業初期に必要となる経費の一部を助成する支援策が創業助成金です。
東京都内の開業率向上を目標に、東京都と公益財団法人東京都中小企業復興公社が支援策を提供しています。
申請は郵送か電子申請で行われています。郵送の場合は、申請書の申請に加えてWeb登録の手続きも必要です。
なお、一般書留か簡易書留、レターパックプラス(赤色)のいずれかで期間中での必着分のみが有効となるので、余裕を持った申請が大切です。
対象者・対象経費
助成金の対象となるのは、東京都内での創業を具体的に計画している個人もしくは創業後5年未満の中小企業者のうち、一定の要件を満たしている人です。
具体的な要件は、創業助成金の募集要項を確認してください。
対象となる経費は以下の通りです。
-
- 賃借料
- 広告費
- 器具備品購入費
- 産業財産権出願・導入費
- 専門家指導費
- 従業員人件費
- 市場調査や分析などの委託費
補助率・補助上限額
助成率は、対象経費の2/3以内です。
上限額は400万円となっており、事業費および人件費の助成限度額は上限300万円、委託費の助成限度額の上限は100万円となっています。
交付が決定した日から6カ月以上2年以下が助成対象期間です。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者の生産性アップや持続的な賃上げに向けた新製品の開発、新サービスの開発に必要となる設備投資を支援する補助金制度です。
製品・サービス高付加価値化枠とグローバル枠の2つがあります。
申し込みは電子申請で行う必要がありますが、事前にGビズIDのアカウント取得が必要です。
また、通常の場合は申請書類として以下を提出しなければなりません。
-
- 直近2期分の貸借対照表
- 損益計算書、販売費および一般管理費明細書
- 製造原価報告書(未作成の場合、省略可)
- 個別注記表を(PDF 形式)
- 創業1年未満の場合は事業計画書および収支予算書
対象者・対象経費
ものづくり補助金の対象者は以下の通りです。
・製品・サービス高付加価値化枠
日本国内に本社があり、国内市場向けに事業展開を行っている中小企業もしくは小規模事業者
・グローバル枠
日本国内に本社があり、海外展開を目指している中小企業もしくは小規模事業者
補助対象経費をみていきます。
・共通
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
・グローバル枠【海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ】
海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
補助率・補助上限額
補助率は、製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠ともに中小企業1/2、小規模事業者2/3となっています。
補助上限額は以下の通りです。
-
- 製品・サービス高付加価値化枠:750万円~2,500万円(従業員数に応じて異なる)
- グローバル枠:最大3,000万円
シニア起業時に活用できる融資制度

ここからは、シニアが起業する際に活用できる融資制度について解説していきます。
新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)
新規開業・スタートアップ支援資金(旧:新規開業資金)(女性、若者/シニア起業家支援関連)は、日本政策金融公庫による融資制度です。
新しく事業を始める人もしくは事業をスタートしてからおおむね7年以内の女性、35歳未満または55歳以上の男性を対象にした制度です。概要は以下の表の通りです。
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内(措置期間5年以内) 運転資金:10年以内(措置期間5年以内) |
| 担保・保証人 | 要相談 |
| 併用可能な特例制度 | 創業支援貸付利率特例制度、設備資金貸付利率特例制度(東日本版) など |
女性・若者・シニア創業サポート2.0(東京都)
東京都で実施されている融資制度で、原則として東京都内の女性や若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)の創業者が対象です。
低金利・低担保の融資に経営サポートをプラスした制度で、地域創業アドバイザーの意見を参考に審査が実施されて融資が実行されます。
融資が実行された後には事業を軌道にのせるための支援を行ってくれるので、持続的な経営に役立ちます。
| 融資限度額 | 1,500万円以内(運転資金のみは750万円以内) |
| 返済期間 | 10年 |
| 担保 | 無担保 |
| 保証人 | 法人:必要となる場合あり 個人事業主:不要 |
| 利率 | 固定金利1%以内 |
地方自治体の支援
東京都以外の地方で起業する場合には、地方自治体による融資制度を活用することも可能です。
開業融資制度として、無担保や無保証人といった特徴を持つ支援策が用意されています。
例えば、名古屋市では創業や分社化の資金に利用できる制度として「新事業創出資金」が用意されており、最大で3,500万円の融資を受けられます。
自治体の制度を確認してみてください。
給付金制度を活用する際のポイント

最後に、給付金制度を活用する場合のポイントを解説していきます。
正しい申請の手順を確認する
制度をスムーズに活用するためにも、申請の手順をあらかじめ確認し、計画的に手続きを進めることが大切です。以下を参考に申請を行ってください。
①募集要項の確認
対象者や提出期限、必要な書類や審査基準などをしっかりと確認してください。
②条件の確認
細かい条件が設定されているケースもあるため、該当しているか確認が必要です。わからない部分があれば担当窓口や専門機関に相談してみてください。
③提出書類の準備
提出書類に不備があれば審査が進まないので、正確な情報を記載してください。
④書類の提出
すべての書類を揃えたら、再度確認して提出します。
⑤進捗の確認
書類を提出した後は、正常に受理されたかどうかの確認が必要です。審査が進む段階で追加の書類提出や修正を求められるケースもあるため、事前に備えておいてください。
必要書類の準備と理想のタイミング
給付金制度の活用時には書類の準備が欠かせません。一般的に求められる書類は以下の通りです。
-
- 事業計画書
- 収支計画書
- 法人登記証
- 税務関連書類
上記以外の書類が必要になるケースもあるので、要項を必ず確認し、必要に応じて担当窓口への確認も行ってください。
申請できる期間が決まっているケースも多くあり、不備が多ければ受給のチャンスを逃してしまう恐れもあります。
活用したい場合には、すぐに募集要項の確認を行い、必要な書類の準備に取り掛かってください。
まとめ・シニア起業向けの給付金制度を理解することが大切
起業するためには資金が必要ですが、補助金や助成金を活用すれば資金繰りを安定化させられます。
各制度の要項を確認し、条件に当てはまるものを選んで申請を行ってください。
ただし、提出する書類が複数あるので、あらかじめ確認してから不備のないように申請してください。
創業手帳では、経営者の方々がよく利用する補助金・助成金をランキング形式で解説した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。また、登録された都道府県の補助金・助成金情報を月2回メールで配信する「補助金AI」サービスも無料でご利用いただけます。ぜひ情報を掴むうえで、ご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「補助金ガイド」は、数多くの起業家にコンサルティングを行ってきた創業アドバイザーが収集・蓄積した情報をもとに補助金・助成金のノウハウを1冊にまとめたものになっています。無料でお届けしますのでご活用ください。また創業手帳では、気づいた頃には期限切れになっている補助金・助成金情報について、ご自身にマッチした情報を隔週メールでお届けする「補助金AI」をリリースしました。登録無料ですので、あわせてご活用ください。