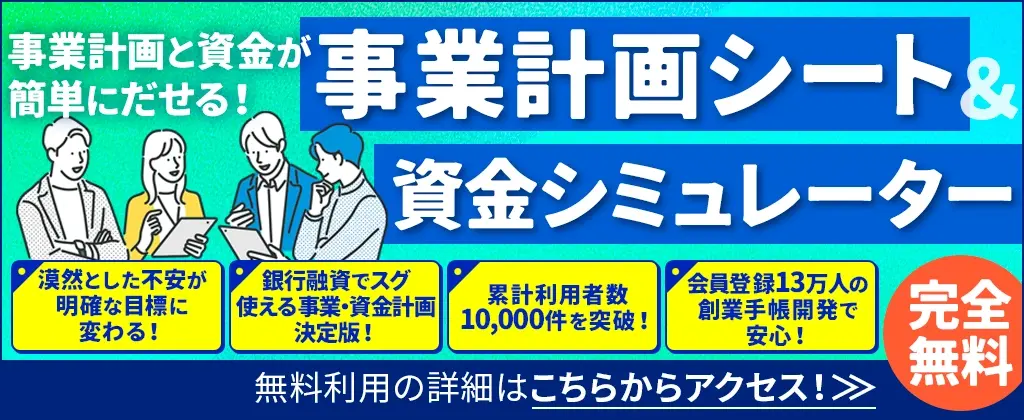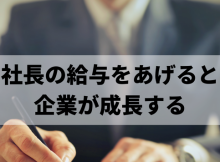役員報酬ゼロは法的に可能?メリット・デメリット、社長の給料なしの影響とは
社長の給料ゼロは良いこと?リスクを知って役員報酬を決めよう

社長の給料(役員報酬)をゼロにすることは、起業時のコスト削減や赤字の対策になります。役員報酬を当面支払わないことで会社にお金が残せるため、資金繰り面で効果的です。
役員報酬をゼロにすることは法律上可能ですが、社会保険の加入や税金負担、さらには社長個人の信用にまで影響を及ぼします。
本記事では、役員報酬をゼロにした場合のメリット・デメリットから、具体的な決め方までをまとめました。起業初期はもちろん、経営途中で行き詰った時の対応策として活用できます。
創業手帳では、資金や事業計画でお悩みの方へ「事業計画シート&資金シミュレーター」をご用意しました。役員報酬とも関わってくる、資金計画についてぜひこちらをご活用ください。銀行融資にもご活用いただけます。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
役員報酬はゼロにできる!給料と違って自由設定が可能

社長の給料、正しくは「役員報酬」をゼロに設定することは、法律上まったく問題ありません。
会社法や税法に「役員報酬を必ず支払わなければならない」という規定はなく、株主総会や社員の同意を経て決定するなど、ルールの範囲内であればゼロにできます。
ただし、法的な問題がないことと、会社や社長個人に影響がないこととは別問題です。役員報酬をゼロにしたことでどんな影響が出るかまでを理解した上で判断しなくてはなりません。
役員報酬と給料の違い
社長や役員に支払う「役員報酬」と、従業員に支払う「給料」とでは、以下のように性質が異なります。
- 役員報酬:会社法に基づき、株主総会や社員の同意によって決められる報酬
- 給料:労働契約に基づく給与所得
給料とは、会社と労働契約を結んでいる従業員に労働の対価として支払う報酬です。労働契約は労働基準法や最低賃金法などの法律に従う必要があり、会社判断だけで自由に変えていいものではありません。
社長(取締役)は労働契約を結ばず、報酬はすべて役員報酬として支払われます。会社法で定められたルールの下であれば、基本は自由に変更可能です。
なお原則、役員報酬と給与は両方同時にもらうことはできません。
役員報酬をゼロにするメリット

社長の給料となる役員報酬をゼロにした場合、経営面や個人の税金に対してメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのかを解説します。
資金繰りや赤字の対策になる
役員報酬をゼロにした分、会社の収益が増えるため資金繰りを優先できます。これは赤字対策にも有効です。
創業当時は、想像していたとおりに利益が出るとは限りません。
役員報酬を払い続けて経営をますます圧迫するよりも、役員報酬をゼロにすることで一時的に黒字経営を保ちやすくなります。
個人の所得税や住民税の負担を抑えられる
社長個人に対するメリットは、所得税や住民税の負担を軽減できることです。
所得税や住民税は、収入によって納める金額が変わるので、役員報酬をゼロにすればその分支払う税金も減ります。
特に所得税は役員報酬がゼロになった月から減る即効性があるため、会社の負担と個人の負担の両方にとってプラスです。
株主や関係者に対して誠意を見せられる
業績が悪化した際に役員報酬をゼロにすることで、株主や関係者に誠意を見せる効果が期待できます。
大きな赤字を出した場合、株主に対して適切な対応が必要です。一般的には役員報酬の減額を選ぶケースが多いですが、減額ではなくゼロにすることで、経営の立て直しに力を入れる覚悟をアピールできます。
従業員や出資してくれた知人など、ほかの関係各社にも同様の誠意を見せることができるしょう。
役員報酬をゼロにするデメリット

役員報酬をゼロにすることは法律上では問題なくても、会社や社長個人にデメリットとしてふりかかる可能性があります。ゼロにするかどうかは、以下のデメリットも理解した上で慎重に判断してください。
社会保険の恩恵を得られない
役員報酬をゼロにすると、厚生年金や健康保険といった社会保険の加入資格を失うので、国民健康保険と国民年金への切り替えが必要です。
実は、厚生年金と健康保険にはさまざまな恩恵があるため、一時的な保険料の減少だけで報酬をゼロにすると、万が一の時に困る可能性があります。
| 項目 | 厚生年金+健康保険 | 国民健康保険+国民年金 |
|---|---|---|
| 保険料 | 会社と折半 | 全額自己負担 |
| 老後の年金 | 基礎老齢年金+厚生年金 | 基礎老齢年金のみ |
| 補償の有無 | 傷病手当、出産手当金など | 基本的になし |
| 扶養制度 | あり(配偶者や子供の保険料は無料) | なし |
特に家族がいる社長の場合、扶養制度がなくなることで、かえって保険料の総額が大きくなる恐れもあります。
自身の保険料の負担だけではなく、総合的なメリット・デメリットまで想定しておかなくてはなりません。
節税どころか負担が増える可能性がある
役員報酬をゼロにしても、必ずしも節税になるとは限りません。
役員報酬がなくなった分、会社の利益が増えますが、同時に法人税の課税所得も増加します。そのため、トータルで見ればむしろマイナスになるケースもあるのです。
さらに一部の税金や保険料は、前年の所得を基準にして支払う額が決まります。以下のように、報酬をゼロにしたからといってすぐに負担が軽くなるわけではありません。
| 年次 | 収入 | 年間国民健康保険料の目安 | 年間住民税の目安 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 500万円 | 約39万円 | 約25.5万円 |
| 2年目 | 0円 | 約39万円 | 約25.5万円 |
| 3年目 | 0円 | 約2万円 | 約5,000円 |
報酬をゼロにした翌年は、個人の生活資金が非常に苦しくなる可能性があります。
必ず節税になる、すぐに楽になると思って報酬をゼロにするのは早計であるといえるでしょう。
金融機関や取引先の信用を得られにくい
役員報酬をゼロにすると、法人としても個人としても信用面で不利になることがあります。
・法人の信用
会社が融資を受ける際には決算書を見せるので、役員報酬がゼロであることも融資先にわかります。「経営に余裕がないのでは」「生活資金はどうしているのか」と不信感を持たれやすく、融資が減額されたり、取引条件が厳しくなったりするかもしれません。
不動産収益や配偶者の収入など、ほかの収入手段を証明できなければ、信用に足らないと判断されてしまうでしょう。仮に赤字から黒字にするために役員報酬をゼロにする場合でも同じです。
・個人の信用
社長個人の信用情報に関しては、住宅ローンやクレジットカードの申し込み時に不利になる可能性があります。報酬がゼロでは返済能力を証明できず、審査落ちや利用限度額の縮小につながりかねません。
このように、法人・個人のどちらの信用にもマイナスになる場合があることを理解しておく必要があります。
役員退職金に影響する可能性がある
役員退職金は「平均役員報酬 × 在任年数 × 功績倍率」で決めるのが一般的です。
役員報酬をゼロにしている期間があると、在任年数・功績倍率が同じでも平均役員報酬が下がるため、退職金の支給額も大きく減ってしまいます。
| 報酬ありを10年間継続した場合 | 報酬を2年間ゼロにした場合 |
|---|---|
| 平均報酬30万円・在任10年・功績倍率2.0
30万円 × 10年 × 2.0 = 600万円 |
平均報酬24万円・在任10年・功績倍率2.0
24万円 × 10年 × 2.0 = 480万円 |
役員報酬を2年間ゼロにしただけで、役員退職金の差が120万円出てしまいました。
退職金は損金算入できるため法人にとっては節税効果が高く、社長にとっても老後の資金源として重要な役割を持ちます。
報酬をゼロにすると、将来の退職金が目減りするという長期的なデメリットにつながることを把握しておきましょう。
役員報酬を設定・変更する時期や方法

社長の給料をゼロにするデメリットを大きく感じたのであれば、会社設立時にしっかり役員報酬を決めることが大切です。
ここで、社長の給料を決定する時期や方法をご紹介します。
役員報酬を設定・変更できる基本の時期
役員報酬を決められる時期・変更できる時期は、基本的に「事業年度が始まってから3カ月以内」です。起業時であれば、会社設立日から3カ月以内が期限になります。
3カ月を過ぎると当年度の役員報酬は変更できません。変える場合には次の事業年度を待つ必要があります。
特に起業して1年目の場合、設立日から3カ月以内に役員報酬の金額を決めておかないと、役員報酬を経費計上できなくなるので注意しましょう。
役員報酬に金額に応じて、毎月支払う税金や社会保険料は変わってきます。1年後に変更できるからと安易に考えず、創業時から慎重に検討することが大切です。
基本の時期以外に変更できるタイミング
原則として、役員報酬は年度開始から3カ月を過ぎたら変えることは認められませんが、合理的な理由がある場合は例外的に変更できます。代表的な理由は次の2つです。
- 役員の地位や職務が大きく変わった場合
- 資金繰りや経営状況が著しく悪化した場合
社長から会長に就任した、退任役員の職務を兼務することになったなど、社長の立場が大きく変わった時は認められることがあります。ただし肩書きが変わっただけで、実態に変化がなければ変更できません。
業績の急激な悪化などで経営責任を果たすために役員報酬を減額するのは、合理的と判断される傾向です。個人的な都合による変更と見られないよう根拠を残しておく必要があります。
これらの例外はあくまで客観的に妥当と認められる場合に限られ、税務署から厳しくチェックされる点にも注意が必要です。
役員報酬を変える手順
会社法により、役員報酬は株式総会の決議で決めなければなりません。定款で定めることもできますが、その場合でも「株式総会で決める」と定めることが多く、金額は株式総会を開いて決めるパターンが一般的です。
株式総会で役員各自の金額が決定する場合もありますが、役員報酬の総額だけが決まり、個々の内訳は取締役会や取締役の判断で決まるケースが多くあります。
株式総会や取締役会で決める際は、税務調査などに対応できるように、日付や理由などを書いた議事録を作成・保存してください。
ゼロにした役員報酬を有償に戻す時も、同様の手順で行いましょう。
役員賞与を変える場合の注意点
役員「賞与」については、事前確定届出給与として届け出ている場合は、役員報酬と同様に株式総会での決議をもって変更します。
届け出ていない場合には決議は不要です。ゼロにしても税務上などで問題はありません。
一方、届け出ていたのに支給日までに賞与を支給しないと、支給しなかった分は支給免除扱いになります。これは債務免除益として計上する必要があり、課税対象になるのです。
余計な課税を避けるためにも、支給日が到来する前に株主総会や取締役会で不支給の決議を行い、役員本人も受領辞退をしておきましょう。
役員報酬を決めるポイント

役員報酬を決める際、自分と会社のどちらにも負担がない金額を考えなければなりません。ここで、役員報酬を決める時に意識したいポイントをご紹介します。
毎月の粗利や固定費を予想してから決める
役員報酬は原則1年間変更できず、無理な金額を設定すると会社の資金繰りが悪化する原因となります。
それを回避するためには、毎月の粗利や固定費を考慮して決めることがポイントです。
まず、1年間の売上金額や売上げから仕入額を差し引いた粗利を予想してください。同時にオフィスの家賃や社員に支払う給与など固定費がどれくらいかかるのか予想します。
おおまかに粗利や固定費が予想できると、会社の経営に負担を与えない役員報酬の金額をイメージしやすくなります。
個人と会社が支払う税金を考慮する
社長の給料を考える時は、個人と会社が支払う税金のバランスも重要です。どちらにどんな影響がどれだけ起こる可能性があるのか、以下にまとめました。
| 役員報酬の判断 | 法人側の影響 | 個人側の影響 |
|---|---|---|
| 報酬を維持する | ・利益減で税金が下がる
・資金が残りにくい ・信用が保てる |
・税金が上がる
・収入が確保できる ・信用が保てる |
| 報酬をゼロにする | ・利益増で税金が上がる
・資金が残りやすい ・信用が落ちやすい |
・税金が下がる
・収入がなくなる ・信用が落ちやすい |
どちらか片方の税金の支払いがきつくならないように、個人と会社の納税額などをシミュレーションしながら検討することが大切です。
また、役員報酬をゼロにするのではなく、今よりも低い金額で支給する方法もあります。社会保険などのメリットを維持しつつ会社負担を軽減できるので、同様に個人と会社への影響を含めて検討しましょう。
同業他社と比べて不相当な金額は避ける
同業他社と比較して決めるのもおすすめです。役員報酬が同業や同じ規模の会社よりも高い場合、不相当と判断されて損金計上が認められないことがあります。
逆に高額ではなく報酬ゼロの場合は、社長個人の生活基盤やローン審査への影響が出やすく、金融機関や取引先からも不安視されがちです。
会社としても「なぜゼロにしているのか」という合理的な理由が説明できなければ認められにくいでしょう。
同業他社と比較して検討した上で不当に高い金額は避けるほか、負担を軽くするためのゼロ報酬や減額についても慎重に判断してください。
まとめ:役員報酬=社長の給料をゼロは一時的な対策として考えよう
社長の給料となる役員報酬はゼロにすることが可能ですが、社会保険に加入できなかったり、法人税などの税金の負担が増えたりするなどのデメリットがあります。
そもそも役員報酬を削らないと経営が成り立たない状態は健全とはいえません。取引先や金融機関に与える恐れもあるので、適切な役員報酬を受け取りつつ黒字経営を目指すことが理想的です。
資金計画を立てながら、個人の生活や会社経営に支障のない範囲の役員報酬を考えてみてください。
役員報酬の設定に悩むのは、経営判断のほんの一部にすぎません。資金繰りや税金、採用や販路拡大など、社長は次々と意思決定を求められます。
そんなときに役立つのが「創業手帳(無料)」です。資金調達の方法や税金イベントなど、経営に直結する情報を1冊に凝縮。シリーズ累計250万部発行、数多くの起業家に支持されている経営バイブルです。
創業期の資金計画から黒字化へのヒントまで、社長の不安を解消する気づきが得られます。
公的融資の仕組みやメリットもわかる!「資金準備チェックシート」は以下のバナーから!
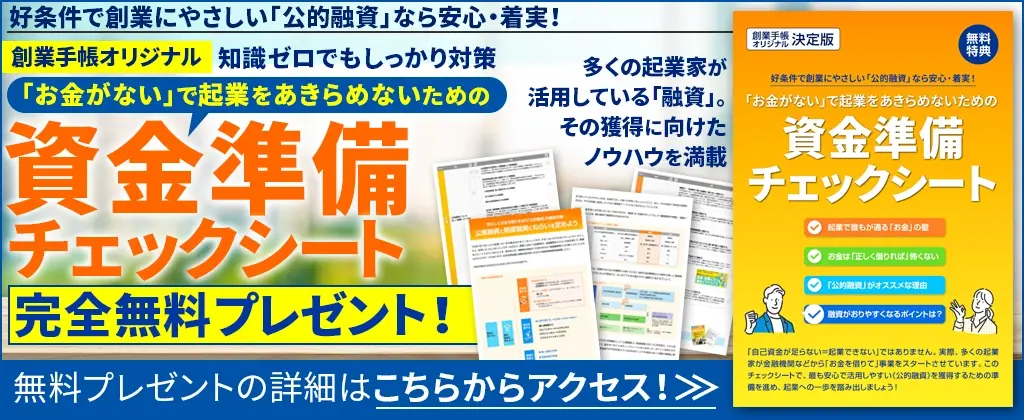
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。