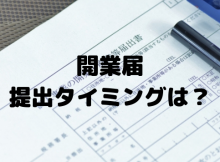ピボット(事業転換)の正しいタイミングは?判断基準や失敗しないためのポイント解説
事業戦略のひとつとしてピボットの見極めが重要

新規事業に取り組んでいると、思うように計画を進められないこともあります。
このような状況に陥った場合でも、ピボット(事業転換)を行うことで事業の成長可能性を引き出すことが可能です。
事業戦略として用いられるピボットですが、実際にどのタイミングで行うと有効なのか疑問に思う人も多いかもしれません。
この記事では、ピボットについて紹介しつつ、正しいタイミングや判断基準、失敗しないためのポイントを解説します。
新規事業をスタートさせた人や、これから始めようと検討されている人は、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
ピボット(事業転換)とは?

ピボットとは、事業の中で軌道修正や戦略を転換することを意味する言葉です。
綿密に計画を立てて新規事業をスタートさせたとしても、初期は失敗してしまうことも少なくありません。
しかし、ピボットを繰り返し行うことで、その都度仮説を立てて実行に移し、効果を検証する中で市場のニーズに合ったものを提供できるようになっていきます。
ピボットが重視される理由
ピボットは事業戦略の中でも重要度が高まっています。その理由として挙げられるのが、顧客ニーズの多様化や変化のスピードが速い点です。
インターネットやスマートフォン、SNSの普及に伴い顧客ニーズの多様化が進んでおり、消費者の価値観は常に変化しています。
例えば昨日までは支持していたサービスに対して、今日になった途端陳腐にみえてしまい、支持できなくなることもあるでしょう。
こうした変化にも柔軟に対応できるように、ピボットを事業戦略として取り入れる企業が増えています。
また、現在の市場は「VUCAの時代」と呼ばれています。
変動性(Volatility)・不確実性(Uncertainty)・複雑性(Complexity)・曖昧性(Ambiguity)といった、将来の予測が困難な状況にあるといわれているのです。
このような状況下だと、最初に立てた事業計画がそのまま成功するとは限りません。
最初の事業計画に固執しすぎると失敗するリスクもあることから、柔軟な方向転換ができるピボットの重要性が高まっています。
事業撤退との違い
ピボットと似たような戦略として挙げられるのが、事業撤退です。しかし、ピボットと事業撤退は、似ているようで大きな違いがあります。
それは、事業を継続しているのか、それとも事業を終了しているか、という点です。
ピボットは事業戦略を転換させるだけで、事業を終了させるわけではありません。
失敗した場合でもそこで得たリソース(知識・ノウハウ・顧客基盤など)を活かし、事業の軌道修正を図っていきます。
一方、事業撤退はリソースや時間、費用などをこれ以上費やさないように、事業を戦略的に終了させることです。
ピボットは事業を継続しながら修正し、成功可能性を探る前向きな戦略なのに対して、事業撤退は損失がこれ以上拡大しないようにするための戦略になります。
ピボット(事業転換)を実施するベストタイミングはいつ?

事業を進めていく中で、ピボットを行うタイミングについても把握しておく必要があります。ここで、ピボットを実施するベストなタイミングを紹介します。
事業の方向性を見直したいとき
ピボットを実施するタイミングとして、事業の方向性を見直したいときが挙げられます。
事業の方向性を見直すきっかけとしては、例えば事業の収益が伸び悩んでいるときなどです。
-
- 売上目標に到達しない
- 事業をスタートさせた当初は新規顧客数が多かったものの、徐々に減り始めている
- 市場の競合数が増え、自社の優位性が失われてしまった など
このような状況下にある場合は、現在の事業戦略を続けても成功する可能性は低いため、新たに方向性を見直すためにピボットを行います。
また、事業を手がける中で法規制に該当する部分が見つかってしまい、事業継続が困難になった場合も事業の方向性を見直す必要があります。
顧客からの反応が想定していたものと違っていたとき
新規事業をスタートさせ、いざ商品・サービスを市場に投入したにも関わらず、想定していたほどの反応を得られない場合もあります。
例えばターゲットに設定した顧客層とは別のターゲット層が利用したり、メインの機能ではなくサブ機能ばかり注目されたりするなどです。
顧客からの反応が想定していたものと違っている場合、企業側はターゲット層のニーズをきちんと理解できておらず、ズレが生じている可能性があります。
企業側と顧客側にズレが生じたまま事業を継続しても、自然と修正されることはありません。
そのため、ピボットによって事業を転換し、本当のニーズを探っていくことが重要となります。
より大きな市場・事業機会が見つかったとき
事業がうまくいき、売上目標をクリアしている場合でも、ピボットを実施するタイミングはあります。
例えば、現在の市場よりも大規模な市場があったり、新たな事業機会が見つかったりしたときです。
これまではひとつの業界で特定の使い方しかできないと考えていた商品やサービスが、別の業界でも全く別の課題を解決できることに気づけた場合は、新たな事業機会を手にするためにもピボットの実施を検討する必要があります。
また、ターゲット層の中でも一部の顧客セグメントで爆発的に売上が伸びていた場合、よりセグメントに特化させることも考えられます。
当初の事業計画とは異なるものの、このままでは大きな機会損失につながってしまう場合は、ピボットの検討が重要です。
新規事業の立ち上げ後
ピボットは新規事業の企画段階において、顧客ニーズを調査した際に表面化した企業側とのズレや、テストマーケティングなどでユーザーから想定した反応・評価がもらえなかった場合に行われる傾向です。
すでに事業が動き始めている場合、ターゲット層や市場自体を変更するとなると、一から事業戦略を立て直す必要があり、時間と手間がかかってしまいます。
この場合、ターゲットや市場を変えるのではなく、提供する商品・サービスで転換を図る方法が適しています。
例えばSNSの「Instagram」は、元々チェックイン機能をメインとするSNSアプリでした。
しかし、利用パターンの分析によって画像をアップロードするユーザーが多いことが判明し、サービスを一度停止してからInstagramという名前に変え、再リリースをして成功に至っています。
ピボット(事業転換)の判断基準

ピボットのタイミングについて解説してきましたが、本当にピボットを実施するかどうか判断する必要があります。ここで、ピボットの判断基準について解説していきます。
ニーズや市場規模の大きさ
顧客ニーズの調査や市場調査を行った際に、当初の想定より小さい場合もあります。ニーズや市場規模が小さいと、いくら素晴らしい商品・サービスを提供できたとしても、売上が伸びず頭打ちになる可能性が高いです。
ターゲットとなる顧客層のニーズや市場規模を正確に把握し、「顧客数は確保できそうか」「市場が継続して成長する見込みがあるのか」などを元に、ピボットをするか判断することが大切です。
なお、顧客ニーズや市場規模が小さかったとしても、別の既存事業とシナジーがあり貢献することに割り切っている場合は、無理にピボットをする必要はありません。
KPIの達成状況と改善見込みの有無
KPI(重要業績評価指標)とは、組織・ビジネスの目標を達成する上で、プロセスや事業成果を定量的に把握するための指標です。
ピボットの実施を判断する際に、経営者の勘や経験に頼ってしまうと失敗するリスクが高まります。そこで、客観的なデータとしてKPIの達成状況を確認することが大切です。
例えば、売上成長率や利益率から判断する場合、成長率の鈍化・停滞がみられるか、利益率の低下が継続しているか、などをチェックします。
KPIの達成状況を把握した上で、複数の指標が鈍化や停滞などがみられる、もしくは改善する見込みがない場合は、ピボットを検討すべきといえます。
継続するための資金・体制の確保
ピボットは事業撤退とは異なり、事業を継続したまま戦略の軌道修正を図ることになります。
そのため、ピボットの判断基準として、このまま事業を継続するための資金や体制は確保できるかどうかも重要です。
また、ピボットによる軌道修正を図る場合にも、新たな商品開発や施策の実行、組織の再編などが必要となり、かなりのコストがかかってくる場合もあります。
さらに、ピボットに伴い必要なスキルを持つ人材の確保や、外部からの支援・委託の有無など、体制面において持続できるかも検討しなくてはなりません。
事業環境の維持
新規事業の企画段階でピボットの実施を判断したい場合、事業環境が維持されているかどうかも重要な判断基準となります。
例えば新型コロナウイルスの感染が拡大し、世界的にパンデミックが発生した際も、市場動向やユーザーのニーズは大きく変化してしまいました。
事業計画を立てたときと状況が変わっていることから、このまま新規事業を立ち上げたとしても失敗する可能性が高いです。
ピボット(事業転換)で失敗しないためのポイント

実際にピボットを行ったとしても、必ず成功するとは限りません。しかし、以下のポイントを押さえることで失敗するリスクを最小限に抑えることも可能です。
ここで、ピボットで失敗しないためのポイントを紹介します。
長期的な視点を持つ
ピボットは、事業を進めていく中で生じた短期的な問題を解決するための手段ではありません。
問題が生じてしまった際にはその本質を見極め、失敗した要因を分析する必要があります。
例えば市場環境が悪化していると、早く成果を出したいという焦りからピボットをしてしまうケースもあるかもしれません。
しかし、この市場環境の悪化が一時的なものだった場合、ピボットをしたことで持続可能性のチャンスを失ってしまうことになります。
こうしたリスクを防ぐためにも、ピボットを検討する際には長期的な視点を持ち、冷静に判断することが重要です。
意思決定は迅速に行う
市場や顧客ニーズは常に変化をし続けており、意思決定が少し遅れてしまうだけで機会損失が増えてしまうリスクがあります。
特に新規事業を立ち上げたばかりの頃やスタートアップ企業は、リソースが限られていることもあり、最大限の効果を出すためにも迅速な判断が必要です。
ピボットを実行するかどうか迅速に判断するためにも、事前にピボットまたは撤退する判断基準を明確に定めておくことが大切です。
また、希望的観測によって意思決定が遅れてしまわないように、客観的なデータや事実に基づいて判断することもポイントになります。
メンバー全員が納得できる形にする
ピボットの判断は経営者が行うことになりますが、経営者だけで完結してしまうと、プロジェクトチームの中で混乱を招いたり、モチベーションが下がったりする可能性が高いです。
経営者はピボットをする理由と今後の方向性について具体的にチームへ共有し、ベクトルを向き直させるプロセスが重要となります。
チームや社員全体へ共有する際には、一方的に知らせるのではなく、きちんと双方でコミュニケーションが取れるように時間を作ることも大切です。
企業理念や価値観を損なわないようにする
ピボットは事業戦略を変えるための手段であり、理念やビジョンを変えることではありません。
もしもピボットを実行する目的が短期的な利益を求めることだった場合、企業としての理念や価値観が失われてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
例えば長期的に環境保護に取り組む企業が目先に利益に捉われ、ピボットで転換した事業が環境負荷をかけていた場合、企業やブランドに対するイメージが悪くなり、また顧客や社員からの信用も損なわれてしまいます。
短期的な利益を求めるとピボットを失敗するリスクもあるため、注意が必要です。
既存顧客には丁寧なフォローを行う
ピボットによって事業の方向性を変えようとした際に、社員や関連企業、取引先だけでなく、既存顧客にも丁寧なフォローが必要です。
既存顧客は元々これまで手がけてきた事業を通して応援してくれていた人々になります。
ピボットの実施後もそのまま顧客として利用してくれる可能性が高いです。
しかし、突然事業内容を変更・終了してしまうと、顧客は「裏切られた」と感じてしまうかもしれません。
既存顧客へのフォローとして、まずは事前に事業転換を実施する告知とその説明を行い、これまで事業を利用してもらったことに対する感謝の言葉を伝えます。
さらに、事業転換後の移行プランを提示して顧客が不利益にならないよう努め、顧客からの質問・意見に対応する窓口を用意します。
こうしたフォローによって、既存顧客と関係を維持したまま事業転換を行えるようになるでしょう。
まとめ・事業を成功に導くためにピボットの正しいタイミングを見極めよう
ピボットは事業の失敗を糧に、知識やノウハウを得て戦略の方向性を変える手段です。
正しいタイミングを見極め、判断基準に基づいて慎重に検討することで、事業を成功に導けるでしょう。
失敗しないためのポイントも押さえつつ、ピボットを活用してみてください。
創業手帳(冊子版)は、起業家や創業したばかりの人、事業運営でお悩みの人などに、経営に役立つ様々な情報をお届けしています。ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)