【個人事業主必見】国民健康保険組合に加入するメリット・デメリットとは?
個人事業主は国民健康保険組合に加入できる!
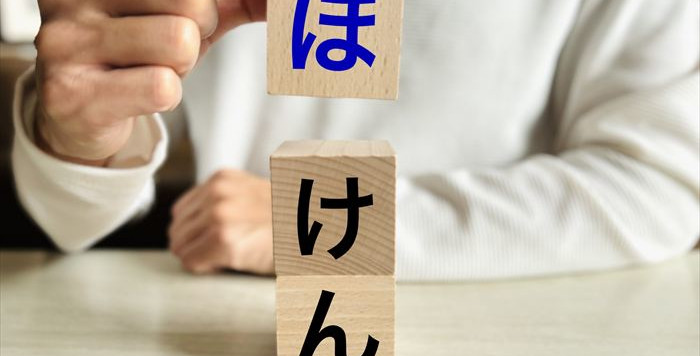
日本では、国民皆保険制度によって国民全員が健康保険に加入できるようになっています。
企業に勤めていればその会社の健康保険、退職して個人事業主になった場合は国民健康保険(国保)または国民健康保険組合(国保組合)への加入が必要です。
一方、個人事業主の場合には、国民健康保険か国民健康保険組合のどちらかを選ぶことになります。
しかし、国民健康保険組合とはどういったものか詳しくわからない人もいるかもしれません。
そこで今回は、国民健康保険組合と国民健康保険の違いについて紹介しつつ、国保組合に加入するメリット・デメリットを解説します。
個人事業主になったばかりの人や、これから個人事業主として独立を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
国民健康保険組合(国保組合)とは?

国民健康保険組合とは、医師や弁護士、美容師、建設業界など、特定の職種に従事する人が組合員として加入できる組合です。
日本の医療保険には職域保険と地域保険の2種類があり、国保組合は地域保険に該当します。
国保組合は国民健康保険法第13条で、同種の事業または業務に従事しており、当該組合の地区内に住所を有する人を組合員として組織することと定められています。
国民健康保険法によって規定された法定給付に加え、各組合が独自に提供する保険給付・保健事業を行っていることも特徴のひとつです。
なお、法人の事業主や従業員であれば健康保険が強制適用されるため、国保組合に加入することはできません。
国民健康保険との違い
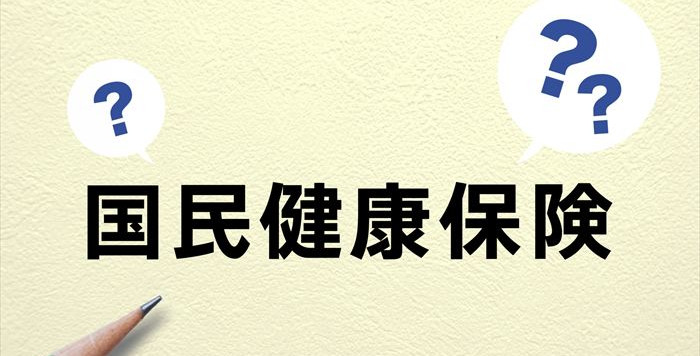
ここからは、国保組合と国保の違いについて解説します。
加入対象者の違い
国保と国保組合では、加入できる対象者に大きな違いがあります。
国保は、法人の健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度の対象者以外であれば、個人事業主はもちろん、主婦やフリーター、定年退職者、新生児に至るまで加入できます。
一方の国保組合は、業種や住んでいる地域などが限定されており、誰でも加入できるわけではありません。
なお、どちらも原則世帯単位で加入することになります。例えば、世帯主の個人事業主が国保から国保組合に加入し直した場合、家族も一緒に国保組合に加入します。
家族に対しては業種に関する要件がなく、加入する組合の仕事をしていなかったとしても問題ありません。
加入要件の違い
日本国内に居住しており、他の医療保険に加入していない場合は、国保に強制的に加入することになります。
一方、国保組合の場合は対象の業種を営んでおり、その組合が対象とする地域に事業所または住所がある場合に加入できます。
そのため、国保組合に加入するかどうか迷っている場合は、一旦国保に加入しておき、国保組合への加入について検討してみてください。
ただし、国保組合の加入要件は各組織によって異なる部分があるかもしれません。加入を検討する際は、該当組織の加入要件を確認しておくことが大切です。
保険料の違い
国保と国保組合では、保険料にも違いがあります。
国保の保険料は、加入者一律で計算される「均等割額」と前年の所得に基づいて計算される「所得割額」の合計から決定されます。
また、収入・年齢によって変動するだけではありません。各自治体によって保険料率にも差があります。
一方、国保組合の保険料は、国保と同じように所得額の基準を保険料の算定に含めている場合もありますが、年齢や資格などによって決まる組合もあります。
この場合、所得額の増減は保険料に影響しないことになります。
ただし、算出方法の違いは組合によって異なるもので、事業主が選べるものではありません。
また、保険料を計算する際に対象となる所得は、国保の場合だと世帯内の加入者全員分の所得になります。
しかし、国保組合の場合は世帯の加入者全員か、もしくは加入する事業主のみの所得のどちらかです。事業主が自由に選択できるわけではなく、各組合によって異なります。
国民健康保険との共通点はある?
国保と国保組合は加入対象者や加入要件、保険料などに違いがありますが、共通する部分もあります。
| 個人事業主の加入可否 | 加入できる |
| 加入者の保険料負担割合 | 基本全額自己負担 |
| 医療費の自己負担 | 現役世代は3割負担 |
| 医療費が高すぎる場合の給付制度 | 高額療養費・高額介護合算療養費 |
| 入院時の給付制度 | 入院時食事療養費、移送費など |
| 出産時の給付制度 | 出産育児一時金のみ |
| 葬祭の給付制度 | 葬祭費または葬祭の給付 (名称は地域で異なるが、内容は同じ) |
| 家族の保険料 | 一律に設定 (具体的な金額は地域・組合で異なる) |
保険料の自己負担割合や法定給付に関しては、国保と国保組合に大きな差はありません。
国民健康保険組合に加入するメリット

ここからは、国保組合に加入するメリットを3つ紹介します。
保険料が一定になる
保険料が一定になることがは、国保組合に加入するメリットのひとつです。国保は、前年の所得額によって今年支払う保険料が決定します。
収入が少ない人にとってはメリットになりますが、収入が多いほど支払う保険料も増えてしまうことはデメリットです。
一方の国保組合は、前年の所得額を問わず、一定の保険料が設定されている場合もあります。
人数や年齢によって変動はありますが、収入は保険料に影響せず多く稼いでいる人はメリットも大きくなります。
付加給付制度を設けている場合がある
付加給付制度とは、各組合で1カ月間に支払われる医療費の自己負担限度額を決め、限度額を超えてしまった場合の費用を払い戻す制度を指します。
自己負担限度額は組合によって異なるものの、厚生労働省が指導する金額は1人あたり月額25,000円です。
例えば、1カ月間の総医療費が数十万円を超えた場合、健康保険による給付と高額療養費による払い戻しを受けられます。
しかし、25,000円を超えた場合は超過分が付加給付として支払われます。
国保組合の各組織によって名称は異なるものの、付加給付制度を設けている場合もあるため、万が一高額な医療費を負担することになっても安心です。
独自の保健事業を利用できるケースもある
国保組合の各組織によって、独自の保健事業が提供されている場合もあります。例えば、東京都弁護士国民健康保険組合では以下の保健事業を提供しています。
-
- 健康診断事業
- 春季・秋季健康診断
- 特定健診・特定保健指導
- その他健診(子宮がん・乳がん検診、歯科検診)、人間ドックの斡旋
- メンタルヘルス・カウンセリング
- 保養施設・レジャー施設の利用
- スポーツクラブの斡旋
- その他健康づくり事業(出産祝品の贈呈、無受診世帯の表彰など)
組織によって内容は異なるものの、個人事業主でも福利厚生のように活用できるのは魅力的です。
国民健康保険組合に加入する際のデメリット・注意点

国保険組合に加入すると様々なメリットがありますが、その一方でデメリットに感じてしまう部分もあります。ここで、デメリットや注意点を把握しておいてください。
世帯単位で加入しなくてはならない
国保組合に加入する場合、同一世帯で国保に加入している人も国保組合に入り直すことになります。
会社の健康保険や協会けんぽ、共済などの社会保険に加入している人を除き、世帯全員が国保組合に加入しなくてはならないと決まっているためです。
世帯の人数によっては、国保組合に加入するよりも国保のほうが保険料を抑えられる場合もあることに注意してください。
減免措置が用意されていない
国保に加入している場合、保険料の支払いが難しくなった場合は世帯の保険料を減額または免除する措置が用意されています。
-
- 災害減免(自然災害や火災などで自宅または事務所が著しい損害を受けた場合)
- 生活困窮減免(病気やケガなどを理由に生活が困窮した場合)
- 収入減少減免(退職や事業の休廃止などから収入が著しく減少し、資産が一定の金額以下だった場合)
- 給付制限減免(刑事施設や少年院などで拘禁または収容された場合)
これらの減免措置は国保組合に加入していると受けられません。そのため、万が一の事態も想定して金額を準備しておく必要があります。
加入条件が厳しい組合もある
国保組合は各組織で加入条件が異なりますが、中には厳しい条件を設けている組織もあります。
加入条件には、地域と業種以外にも、組合加盟の団体の会員であることを条件としている場合があります。
個人で国保組合に加入することはできず、まずは組合加盟の団体の会員にならなくてはいけません。
また、75歳以上の後期高齢者や、65歳以上75歳未満で広域連合から認定を受けている障害者の場合も加入できないことに注意してください。
国保と国保組合、個人事業主はどちらに加入すべき?

国保と国保組合の特徴は一長一短で、人によって国保のほうが良い場合と国保組合のほうが良い場合に分かれます。
例えば、独身などで世帯人数が少ない場合や、収入がそれほど多くない場合には、前年の所得によって保険料が決まる国保に加入するのがおすすめです。
一方、収入が多い場合は一定の保険料が設定されている国保組合に加入すると、保険料を安く抑えられる場合もあります。
いくら保険料を支払うことになるかシミュレーションしてみてください。
主な国民健康保険組合の例

国保組合には、地域や業種ごとに多くの組織が存在します。ここで、一部の国保組合の組織の特徴や加入条件、保険料、給付の一例などを紹介します。
東京美容国民健康保険組合
東京美容国民健康保険組合は、美容師が加入できる国保組合です。
東京都内の事業所で美容師として働いている人で、東京都(島しょを除く)・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に居住している人が加入できます。
一般被保険者(40~64歳以外)の保険料は、事業主組合員だと1人あたり月額21,500円(均等制)、同一世帯家族は1人あたり月額9,500円(人頭割)です。
病気・ケガをした時や交通事故に遭った時などに保険給付を受けられるだけでなく、出産手当金や入院手当金、葬祭費などが現金で給付されます。
文芸美術国民健康保険組合
文芸美術国民健康保険組合は、1953年に旧厚生省の認可を受けて設立された国保組合です。主に小説家や画家などのクリエイターが加入できます。
日本国内に住所を有していることと、組合加盟団体の会員であることが条件です。
加盟団体は非常に多く、例えば日本映画ペンクラブや日本アニメーション協会、日本グラフィックデザイン協会、日本ネットクリエイター協会などがあります。
保険料は組合員が1人あたり月額25,700円、家族は1人あたり月額15,400円で一律です。
また、産前産後の被保険者には保険料を4カ月分軽減する「保険料軽減措置」も用意されています。
東京土建国民健康保険組合
東京建設業国民健康保険組合は、東京土建一般労働組合に加入している人が利用できる国保組合です。
東京土建一般労働組合では、建設産業で働く事業主や一人親方、職人(従業員)は誰でも入れる労働組合になります。
国保組合に加入するためには、労働組合の組合員となること以外に、以下の条件があります。
-
- 建設産業を主たる事業としている
- 東京都内に住所がある
- 茨城県・千葉県・神奈川県・山梨県・栃木県の一部、群馬県の一部、静岡県の一部に住所があって都内の事業所に勤務している
保険料は区分によって異なりますが、個人事業所の事業主(第1種)だと都内居住者で33,450円、都外居住者だと35,750円になります。
また、一人親方や個人事業所の事業主、法人事業所の代表者以外の役員で、すべての所得合計額が200万円以下(第2種)の場合、都内居住者で27,250円、都外居住者で29,550円になります。
まとめ・国民健康保険組合への加入前にメリット・デメリットを比較しよう
個人事業主が加入する健康保険には種類がありますが、それぞれ特徴が異なるため、自分や家族に合った健康保険に加入することが大切です。
保険料のシミュレーションも行いつつ、最適な健康保険に加入できるよう比較・検討してください。
個人事業主としての健康保険や税金、資金計画までトータルで押さえたい方は、創業期のノウハウをまとめた『創業手帳』をぜひお役立てください。無料でお届けいたします。
(編集:創業手帳編集部)





































