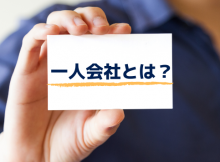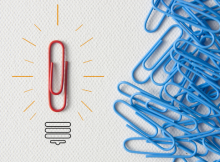法人から個人事業主に戻る「個人成り」とは?必要な手続きと流れをわかりやすく解説
個人成りとは?要点をおさえよう

個人事業主が法人化することを法人成りと呼び事業が成長した節目と考えられています。逆に法人化してから法人を辞めて個人事業主に戻ることは、個人成りとよびます。
個人事業主から法人化するケースは多い一方、法人から個人に戻るのは珍しいパターンです。
法人成りするメリットがある一方で、法人から個人成りして個人事業主に戻ることにもメリットがあります。
本記事では、その手続きの流れや注意点、法人化を考える際に押さえておくべきポイントを解説します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
法人から個人に戻す時に考えられるパターン

いわゆる法人成り、法人化するのは決して簡単ではありません。法人化するためには費用も手間もかかります。
そこまでして法人化したとしても、法人を辞めて個人に戻るケースがあります。法人から個人に戻す時に考えられるパターンとは、どのようなものがあるのでしょうか。
事業規模を縮小するケース
法人から個人に戻す理由として、事業の縮小や撤退を計画しているパターンがあります。
売上や従業員数が減少し、法人維持コストが経営を圧迫する時には、個人事業主に戻す選択が現実的です。
法人には固定的な税負担があるため、税負担が利益に対して重すぎる場合、個人事業に戻すことで経費削減できます。
法人を維持するためには会計や登記業務の事務負担もあります。個人になれば経営体制がシンプルになるので事務負担も削減可能です。
副業や小規模事業に切り替えるケース
法人にすると形態では社会保険料や会計処理の負担が発生します。法人は社長だけでも社会保険の加入が義務になり会計処理も煩雑です。
個人事業主は社会保険の加入義務がなく、確定申告で対応可能です。法人に比べて手続きやコストが格段に少なく済みます。
法人として事業規模を広げるよりも、副業や小規模事業を継続するほうが事業以外の負担を減らせます。
本業以外の副業や趣味的活動では、法人より個人事業主のほうが柔軟に継続しやすくなるのです。
赤字が続いているケース
法人で売上が減少して赤字が続いている場合、個人成りを考える人が増えます。
法人は赤字でも均等割の法人住民税が毎年発生するため、資金繰りが悪化する要因となってしまいます。
社会保険料の負担も法人維持の大きな固定費です。赤字の時には税負担や社会保険の負担を減らして個人事業に戻す利点が大きくなります。
赤字が慢性化している場合は、法人格を維持するよりも個人成りが合理的と考える経営者は多いでしょう。
経営者のライフスタイル変更
個人成りには経営者のプライベートやライフスタイルも関係しています。
定年後のセカンドライフとして事業を小規模に続けたい場合には、法人を解散して個人化する選択が有効です。
体力面やプライベートを充実させたいといった理由から、ビジネスを縮小しようと考えているケースは珍しくありません。
ライフスタイルの変化に合わせて事業規模を柔軟に変更できる点が、個人事業主の強みです。
事業を趣味的として続けたり、時間を限定して活動したりする場合には、法人よりも個人のほうが負担が軽く継続が容易です。
業種や取引先の影響によるケース
業界や取引先によっては個人との取引きをしていないなど法人格を求められることがあります。
取引きに影響するから法人になっているような場合には、要件が緩和されると個人事業に戻ることが可能です。
近年は、働き方の自由化が進みフリーランス需要が拡大、法人でなくても取引きが成立しやすくなるケースが増えました。
法人格による信用が不要となった場合、柔軟性やコスト削減の観点から個人化が合理的と判断するケースがあります。
法人から個人事業主に戻る流れ

個人から法人化する法人成りの方法は知っていても、個人成りの方法はあまり知られていません。
法人から個人事業開業までには複数の登記や税務申告が必要であり、順序を誤らず対応することが重要です。
ここでは、法人から個人事業主に戻る流れを説明します。
法人を解散・清算する場合の流れ
法人を終わらせる手続きのことを、法人の解散・清算と呼びます。
自分ひとりの会社であれば自分で決めて解散できますが、正確にいえば株主総会での解散決議をして事業活動を停止させます。
法人を解散させるには、法務局で解散登記と清算人の選任登記が必要です。清算は、債権、債務を整理する業務です。
財産目録と貸借対照表を作成して債権者保護手続きを実施、解散してから2カ月以内に税務署に解散確定申告書を提出してください。
債務を処理して資産の売却などが完了してから清算決了の登記を申請して法人格が消滅します。この清算決了から1カ月以内に税務署に清算決了確定申告書を提出しましょう。
これらの手続きには費用も発生します。解散関連の登記にかかる登録免許税が合計3万9,000円、官報公告費用4万円程度です。
手続きを司法書士や税理士などの専門家に依頼する場合にはその費用も必要です。
法人を休眠する場合の流れ
法人は、解散・清算しなくても休眠させる方法もあります。
休眠は法人格はそのまま維持して事業を休止状態にする手続きです。休眠は、将来的にまた事業をしたくなった時に復活させられます。
休眠するためには、所轄の税務署と都道府県税事務所、市区町村役場に事業を休止する旨の「異動届出書」を提出してください。
従業員が在籍しているのであれば、給与支払事務所等の廃止届出書も税務署に提出し、給与の支払い(源泉徴収義務)の停止を届け出します。
休眠から事業を再開したい場合には、休眠した時と同じように税務署等に異動届を提出してください。
休眠は、解散と違って登録免許税や公告費用は発生しません。しかし、会社自体は存続しているので、確定申告は必要です。
税金面では法人住民税の均等割は毎年課税されます。市区町村によって課税のルールが違うこともありますが、約7万円が課される可能性があるので事前に確認してください。
個人事業主としての開業手続き
法人の処理が終わってから、個人事業主として事業をはじめる手続きを行ってください。これは一般的な開業手続きと同じです。
開業届での提出期限は事業開始から1カ月内とされています。税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出して事業の開始を届け出てください。
さらに個人事業主として青色申告を選ぶ場合には、青色申告承認申請書を提出します。どちらの手続きも手数料などはかかりません。
法人から個人に戻る際の注意点

法人から個人事業主に戻ることには、経済面、実務面での合理性があります。しかし、個人に戻ってからこのようなはずではと後悔するケースもあります。
法人から個人に戻る時に注意してほしいポイントをまとめました。
法人解散の手間とコスト
法人の解散と清算については前述しましたが、解散の手続きは決して簡単ではありません。
日常の業務と並行して解散の手続きをするのは想定以上に負担になる可能性があります。
また、従業員や株主がいる場合には、事前に話し合って理解を得ることも必要です。
困難を乗り越えて法人を解散しても、個人事業主として開業する手間もあります。事業によっては個人成りしてから、新しく許認可の取り直しが必要です。
個人事業主になったことで許認可が下りない場合もあるので、事前に個人成りしても事業の継続に問題はないか確認しておいてください。
従業員と社会保険の切替
解散する法人に従業員がいる場合はさらに手間がかかります。
従業員は、雇用契約終了や再雇用契約が必要です。さらに社会保険の資格喪失届の提出も行ってください。
法人代表者自身も、厚生年金から国民年金、健康保険から国民健康保険へ切替を行います。
従業員への説明や手続きが遅れるとトラブルになるため、計画的に対応するようにしてください。。
赤字の引き継ぎはできない
事業で赤字が出た場合には、繰越欠損金として翌期以降に繰り越しをして黒字と相殺することが認められています。
しかし、法人の時に発生した繰越欠損金は個人事業主に引き継ぎができません。
そのため、法人のままであれば繰越欠損金を使って税額を抑えられたのに個人事業主になって繰越欠損金が引き継げない可能性もあります。
税務上不利になってしまうので、個人成りのタイミングは慎重に決定してください。
個人の事業責任
法人から個人事業主になった時には、有限責任から無限責任になります。株式会社では、負債があったとしても会社の資産の範囲以上には責任を負いません。
しかし、個人事業主で無限責任になった時には、個人に関わる責任はすべて個人で負います。
自宅や個人の資産まで債務返済に使わなければならないことがあるので慎重に判断してください。
融資や保証の扱い
法人から個人事業主になることで、第三者からの信用は低くなる可能性があります。
法人は登記されている上、決算の透明性が高いことで一般的には信用されていることが多いでしょう。
個人事業主になって社会的信用が下がれば、融資や保証を受けにくくなるかもしれません。ルールとして法人として取引きをしていない会社もあります。
個人成りの時には、個人事業主になっても同じ仕事が続けられるかどうかも確認しておいてください。
法人化する前に考えておくべきこと
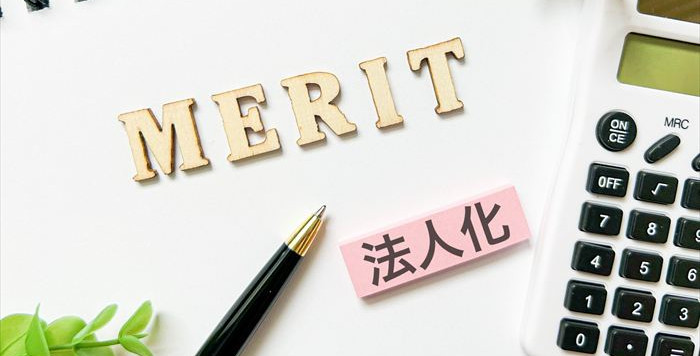
法人から個人へ戻すのは簡単ではありません。この事実を踏まえ、最初に法人化を検討する段階では下記のことをを考慮してください。
維持コストの負担
法人を維持するだけで毎年法人住民税が最低7万円発生します。これは赤字でも必ず支払わなければいけません。
また、社会保険料も法人代表者分を含め固定的に発生する費用であり毎年大きな負担となります。
法人化する時には、これらの維持コストが事業規模に見合うかを事前にシミュレーションするようにしてください。
事業規模と安定性
法人化は固定で発生する費用や事務負担が大きいので売上や利益が安定している事業に適しています。
そのため、利益変動が大きい、不安定な状況ではリスクは高くなってしまいます。
順序としては、いきなり法人成りを目指すよりも個人事業で安定的に利益を出せるかを見極めた上で、法人化を検討することをおすすめします。
売上変動が大きい業種であれば、赤字の時に税金を負担しない個人事業主のほうが法人よりも有利に働く場合があるからです。
信用や資金調達の必要性
法人は社会的信用が高く、取引先や金融機関からの信頼を得やすいため資金調達に有利といわれています。
法人化する時には、法人化によって融資や大手企業との取引拡大があるかどうかを確認しておいてください。
もしも信用力向上が不要な事業形態であれば、費用や手間をかけて法人化しなくても、そのまま個人事業を維持するほうが合理的かもしれません。
手続き・事務作業量の違い
法人は決算公告や法人税申告など手続きが複雑であり、個人事業に比べて事務負担が大きくなります。
扱う書類も多いため、法人化によって監査対応や資料整理の労力も増えることは覚悟しなければいけません。
税務処理も、個人事業では確定申告で完結できます。
法人化する時には、アウトソーシングや従業員を増やすなども検討して業務規模に応じて適切な形態を選ぶようにしてください。
将来の事業承継や廃業のしやすさ
法人は開業する時も手続きが多くありますが、解散登記や清算結了が必要であり廃業する時にも煩雑です。
個人事業主であれば、廃業届を提出するだけなので費用もかからず比較的簡単に完了可能です。
その一方で、事業承継する場合には、法人のほうが株式譲渡でスムーズに移転できるメリットがあります。
事業の規模や今後の展望によって、どちらが有利か不利かが分かれます。
長期的に廃業や承継を想定するなら、法人と個人の違いを事前に把握して自分のビジョンに適しているほうを選択してください。
まとめ|法人から個人への逆戻りは慎重に
法人から個人に戻すには解散登記や法人税の確定申告など、複数の手続きを経る必要があります。
法人をやめるために資産や負債、社会保険の整理がともなうため、想定以上に時間と費用がかかる点は注意してください。
個人事業主から法人化を検討する際は、将来の維持コストや事業計画を踏まえ、個人成りのリスクも考慮して判断しなければいけません。
創業手帳(冊子版)は、中小企業経営者や個人事業主にとって役立つ記事を多数掲載しています。無料でお配りしていますので、起業に興味がある方や既に会社を経営されている方などお気軽にお取り寄せください。
(編集:創業手帳編集部)