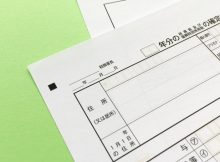会計ソフト購入の経費はどの勘定科目?仕訳例やIT導入で使える導入補助金の活用方法もご紹介
会計ソフトを購入した際の費用は経費計上できる!

会計ソフトは経理業務を手助けしてくれる便利なツールの一つです。
しかし、購入した場合、経費として計上できるのか、経費になるならどのように仕訳をすれば良いのかと悩む方も多いのが実情です。
そこで今回は、会計ソフト購入した際の勘定科目のルールや仕訳例を詳しく解説します。
あわせて、申請できる補助金制度もご紹介しているので、会計ソフトの購入を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
創業手帳では、税理士監修の「税金カレンダー」をリリースしました!カレンダー形式で、税金の納付期限が確認できるだけでなく、主な税金の対象者や概要なども解説しています。13種類の異なるパターンをご用意。無料で提供していますので、ぜひお気軽にご利用ください。
この記事の目次
会計ソフト購入時の勘定科目のルール
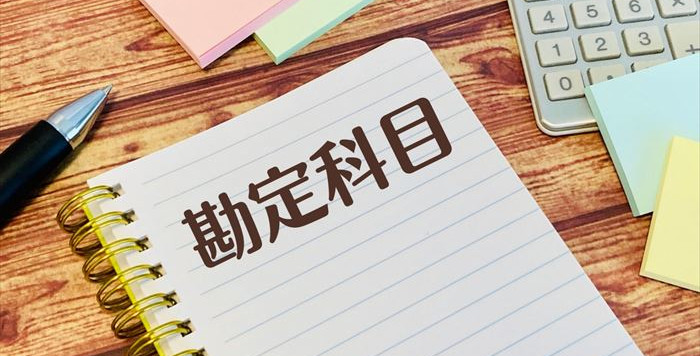
会計ソフトの購入や使用料を仕訳する場合、勘定科目に悩む方も多いでしょう。
しかし、会計ソフトに限らず、全ての勘定科目は、必ずしもこの勘定科目でなければならないといった明確なルールはありません。
したがって、どの勘定科目で仕訳するかは、企業や事業主が自由に設定することが可能です。
ただし、向こう見ずに仕訳をしてしまっては、財政状況を正確に把握でず、さらに銀行や税務署から不信感を持たれる可能性があるなどのデメリットがあります。
また、企業会計の一般原則の1つである「継続性の原則」によって、同じ内容の取引きでは同じ勘定科目を使うよう定められているため、各企業で振り分けルールを統一するのが基本です。
一般的なのは「通信費」または「消耗品費」
会計ソフトにかかる費用は、「消耗品費」あるいは「通信費」のどちらかが使われるのが一般的です。
帳簿は自社の関係者のみならず、社外の人間に提示することもあるため、誰が見てもわかりやすいよう、一般的な勘定科目を使用するのが望ましいです。
・通信費
業務上使用する手紙などの郵送代、電話代やインターネット代などの通信関連に掛かる経費を計上する勘定科目
・消耗品費
主に短期間で消耗するもの、あるいは使用可能期間1年未満、もしくは取得価格10万円未満の備品の購入費用を計上する勘定科目
ちなみに、会計ソフトには「クラウド型」と「インストール型」の2種類あり、どちらを選択するかによって勘定科目が異なるケースが多いです。
以下では、クラウド型とインストール型の勘定科目について解説します。
クラウド型を購入した場合の勘定科目
アカウント登録後、ブラウザや専用アプリを使って会計ソフトのサービスを利用する方法をクラウド型といいます。
インターネットを介し、クラウド上にあるデータへアクセスするため、ログインすれば、いつでもどこでも帳簿を確認することが可能です。
クラウド型の会計ソフトは、月額利用料を支払って使用するシステムを採用していることが多く、「通信費」の勘定科目を使用するのが一般的です。
また、全額経費として計上できます。
ただし、明確なルールはないため、企業によっては、消耗品費や外注費などの勘定科目をを使っていることもあります。
インストール型を購入した場合の勘定科目
インストール型は、パソコンなどの端末に、会計ソフトをインストールし利用する方法です。
帳簿を見るには、ソフトをインストールした端末を使用する必要がありますが、インターネットに接続しなくても利用できます。
インストール型のソフトは、一度購入すれば追加費用がかからない買い切り型であることがほとんどです。
そのため、ソフト購入にかかった費用は、「消耗品費」の勘定科目を使い、経費計上するのが一般的です。
ただし、購入費用が10万円以上かかった場合は、無形固定資産として資産計上し、減価償却する必要があります。
勘定科目は一度決めたら継続して運用する
企業会計の継続性の原則において、同じ内容の取引は、同じ勘定科目を使うよう定められています。
正当な理由がない限り、一度決めた勘定科目は変更することなく、継続して利用する必要があります。そのため、仕訳を行う際は企業内でルールを統一しましょう。
継続性の原則を守らない場合、自社の財政状況を正しく把握できないほか、銀行や税務署から不信感を持たれる可能性があります。
自社はもちろん、第三者からの信用を失わないためにも、一度決めた勘定科目は継続して運用することが大切です。
会計ソフト購入時の仕訳例
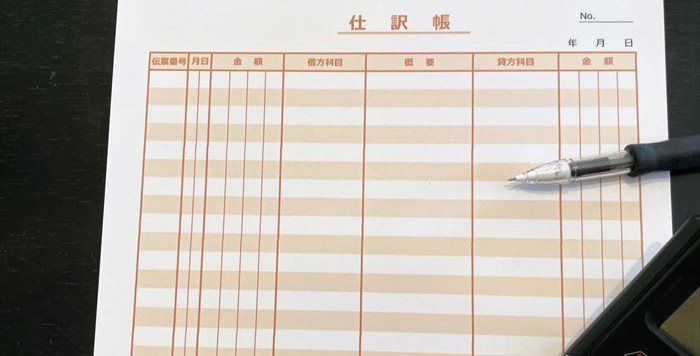
会計ソフトを購入した際、どのように仕訳すべきなのかという点について、クラウド型や月額・サブスクなど、それぞれの事例に合わせて仕訳例をご紹介します。
仕訳時に気になるポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
クラウド型の仕訳例
クラウド型の会計ソフトの場合、「月額・サブスク型」と「年間使用料」と2つの方法があります。以下では、それぞれの仕訳例をご紹介します。
月額・サブスクの場合
月額・サブスク型の場合、勘定科目は通信費を使うのが一般的です。
| 借方 | 貸方 | ||
| 通信費 | 10,000 | 普通預金 | 10,000 |
月額1万円の利用料を普通預金口座から支払う場合の仕訳は上記のように行います。支払いが現金であれば、貸方科目は「現金」となります。
計上日は実際に口座から引き落とされた日、現金で支払った日を入力します。
月額・サブスク型の場合、毎月支払いがあるため、決算時には12ヶ月分が正確に計上されているかどうかを確認することが大切です。
年額払いの場合
クラウド型の中には、使用料を1年分まとめて支払う方式を採用しているものもありますが、年額払いだからといって、利用料を12カ月分に分けて毎月計上する必要はありません。
| 借方 | 貸方 | ||
| 通信費 | 120,000 | 普通預金 | 120,000 |
引き落としのあった日付に1年分まとめて計上しましょう。
いつからいつまでの期間分の使用料なのかについて摘要欄に入力しておくと、後から見返した時に判別しやすくなるためおすすめです。
別途サポートの利用料金がかかった場合
会計ソフトの利用時にサポートサービスを利用した場合、別途費用が発生することがあります。
サポートにかかる費用に関しても、どの勘定科目を使うのか明確な決まりはありませんが、「諸経費」や「支払手数料」を用いるのが一般的です。
| 借方 | 貸方 | ||
| 支払手数料 | 1,000 | 普通預金 | 1,000 |
会計ソフトの中には、サポート費用が月額料金に含まれていることがあります。
また、環境構築までの一定期間はセットになっていることもあるため、そのような場合は、通信費や消耗品費として計上すると良いでしょう。
インストール型の仕訳例
インストール型の場合、購入にかかった金額を消耗品費として一括で計上するのが一般的です。
パッケージを購入する方法のほか、インターネットから料金の支払い後インストールする方法もありますが、どちらの方法であっても消耗品費で問題ありません。
ただし、金額が10万円未満か10万円以上かによって、必要な仕訳が異なるため注意が必要です。
10万円未満の会計ソフトを購入した場合
10万円未満であれば、消耗品費として一括計上して問題ありません。購入した日付で、経費として計上しましょう。
| 借方 | 貸方 | ||
| 消耗品費 | 95,000 | 現金 | 95,000 |
10万円以上で無形固定資産として計上する場合
消耗品費が使えるのは10万円未満のものまでです。10万円を超える場合は、固定資産として計上しましょう。
なお、固定資産には車両や機械のように形がある「有形固定資産」、特許権やソフトウェアのように形のない「無形固定資産」があります。
ソフトウェアは無形固定資産となるため、通通常通り仕訳する場合、以下のようになります。
・購入時
| 借方 | 貸方 | ||
| ソフトウェア | 200,000 | 現金 | 200,000 |
次に、年度末に原価償却を行います。事業用会計ソフトの耐用年数は5年のため、減価償却費は200,000円÷5年=40,000円とします。
・年度末
| 借方 | 貸方 | ||
| 減価償却費 | 40,000 | ソフトウェア | 40,000 |
10万円以上で少額減価償却資産の特例を受ける場合
10万円以上の場合、通常通り仕訳をするほかに、特例を使用する方法があります。なお、特例には下記の2つの方法があります。
-
- 少額減価償却資産の特例(中小企業の特例)
- 一括償却資産の損金算入
少額減価償却資産の特例は、中小企業が使える特例であり、利用するには以下の条件を満たす必要があります。
-
- 従業員数500人以下
- 資本金あるいは出資金が1億円以下
- 確定申告時に「少額減価償却資産の取得価格に関する明細書」を提出
詳しい条件は、国税庁のホームページなどをご確認ください。
| 借方 | 貸方 | ||
| 消耗品費 | 200,000 | 現金 | 200,000 |
少額減価償却資産の特例を利用した場合、30万円未満のものであれば、原価償却の必要がなく、一括で費用計上できます。
10万円以上で一括償却資産の損金算入を利用する場合
もう1つの特例は、「一括償却資産の損金算入の特例」です。この特例では、取得価格10万円以上20万円未満の減価償却資産は、3年間に渡り損金として算入できます。
17万円のソフトを購入したと仮定した場合、購入時と原価償却時の仕訳例は以下の通りです。
・購入時
| 借方 | 貸方 | ||
| 一括償却資産 | 180,000 | 普通預金 | 180,000 |
・原価償却時
| 借方 | 貸方 | ||
| 減価償却費 | 60,000 | ソフトウェア | 60,000 |
購入時は、かかった金額を「一括償却資産」として全額計上します。その後、年度末に原価償却の仕訳を行います。ただし、原価償却は通常の5年ではなく、3年で計算します。
したがって、原価償却費は180,000円÷3年=6万円となります。
会計ソフト購入時の消費税額は取得価額に含まれる?

会計ソフトを購入する際にかかる消費税をどのように処理するかについては、経理の方法によって異なります。
経理の方法には、「税込経理」と「税抜経理」があり、税込経理はその名の通り消費税込みの金額を記帳する方法です。
一方、税抜経理は仮払い消費税などの勘定科目を使って、消費税と商品価格を分けて記帳する方法です。
消費税の申告・納税義務がある事業者の場合、税込経理と税抜経理のどちらかを任意で選べます。
しかし、消費税の納税義務が免除されている事業の場合は、税込経理のみとなります。
税込経理での仕訳例
税込経理の場合、無形固定資産として計上するかどうかの基準となる10万円は、消費税込みの金額で考えます。
したがって、本体価格が98,000円の場合、消費税額9,800円を加算すると総額が10万円を超えるため、無形固定資産として勘定科目「ソフトウェア」を用いて仕訳します。
| 借方 | 貸方 | ||
| ソフトウェア | 107,800 | 現金 | 107,800 |
税抜経理での仕訳例
税抜経理の場合、消費税抜きの本体価格が10万円を超えるかどうかで判断します。
本体価格98,000円、消費税9,800円の場合、10万円未満となるため、勘定科目「消耗品費」によって処理します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 消耗品費 | 98,000 | 現金 | 107,800 |
| 仮払い消費税 | 9,800 | ||
会計ソフト購入時に経費削減するなら「IT導入補助金」を活用しよう
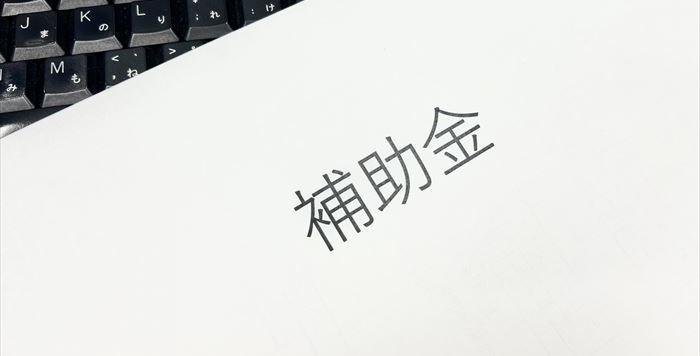
補助金制度を活用すれば、会計ソフト購入にかかる経費を削減できる可能性があります。ここでは、会計ソフト購入時に使える「IT導入補助金」について解説します。
IT導入補助金とは?
IT導入補助金は、業務効率化やDX等をサポートするソフトウェアやサービスといったITツールの導入を支援するための補助金制度です。
中小企業や小規模事業者等の労働生産性の向上を目的としたもので、安価なITツールにもできるため、会計ソフトを購入するのであれば、ぜひ活用したい補助金の1つです。
ただし、IT補助金を利用するには審査があり、申請すれば誰でも使えるものではありません。
また、補助対象となるITツールは、事前に事務局による審査を通過したものだけであることを理解しておく必要があります。
IT導入補助金の補助対象者
IT導入補助金を利用するには、資本金と常勤の従業員数が規定以下である必要があり、業種によってそれらの上限は異なります。
また、あくまでも中小企業や小規模事業者を対象としているため、大規模の企業グループ企業や課税所得額の大きい企業などは利用できません。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
| ゴム製品製造業((自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
| ・製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報サービス業 | 3億円 | 300人 |
| ・卸売業 | 1億円 | 100人 |
| ・旅館業 | 5千万円 | 200人 |
| ・サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5千万円 | 100人 |
| 小売業 | 5千万円 | 50人 |
| その他業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
採択率アップにつながるポイント
先に述べたとおり、IT導入補助金は申請したからといって、必ず支給されるわけではなく、事務局による審査に通らない可能性も十分あり得ます。
そこで、以下では採択率を上げるポイントをご紹介します。
審査項目に合わせて申請内容を作る
IT導入補助金の審査では、申請内容がIT導入補助金の目的に合致しているか、チェックされています。
申請内容は審査項目にしっかりと目を通した上で、作成することが大切です。
なお、審査項目は公募要領などで公表されており、申請枠によって審査項目は異なります。チェックする申請枠を間違えないよう注意してください。
加点項目を活用する
加点項目とは、条件を満たしたり、取得したりすることで審査を有利に進められる項目のことです。
取得したからといって必ずしも採択されるわけではなく、取得していなくても採択されたケースもあります。
しかし、加点項目の中には取得するのが当たり前となっている項目もあるため、できる限り取得しておくことをおすすめします。
なお、加点項目はIT導入補助金の公式ホームページから確認できます。申請枠によって加点項目が異なるため、ぜひチェックしてみてください。
自由記述の項目もできるだけ埋める
IT導入補助金では、自社の事業や強みについてなど、一部の項目で自由記述が可能です。
全て埋めたからといって必ずしも採択されるわけではないものの、できるだけわかりやすいよう、制限ぎりぎりまで書くことをおすすめします。
なお、基本的に各種項目は選択肢から選ぶものが多いです。しかし、自社の強みや弱みは、「その他」を選択することで自由記述できるようになっています。
会計ソフトを購入する際は経費計上と補助金を上手に活用しよう
会計ソフト購入時の仕訳は、価格や種類によって異なります。
絶対にこの科目を使用しなければならないといった決まりはありませんが、一度決定したら継続して利用することが重要です。
また、会計ソフトの購入では、IT導入補助金を使える可能性があります。
うまく活用すれば購入にかかる負担を軽くできます。今回紹介した内容を参考に、申請する際は採択率をアップできるよう工夫してみてください。
創業手帳の『税金カレンダー』を活用すれば、税金の支払いタイミングが一目瞭然です。無料でご利用いただけますので是非ご活用ください。
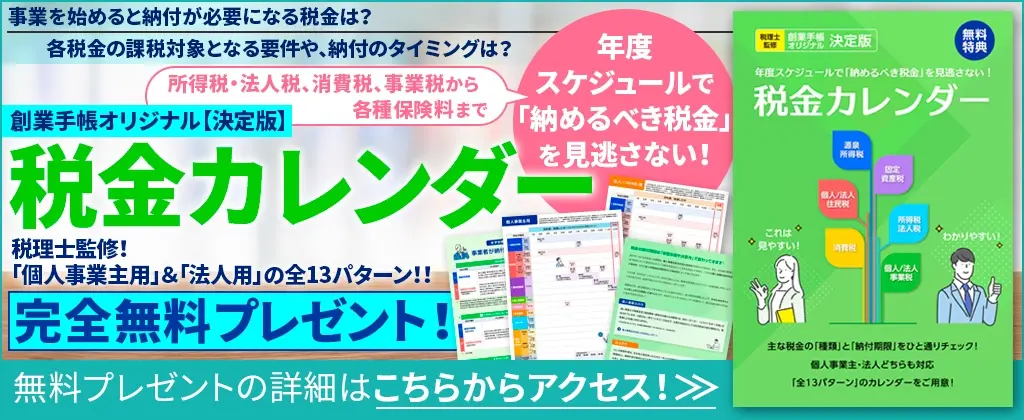
(編集:創業手帳編集部)