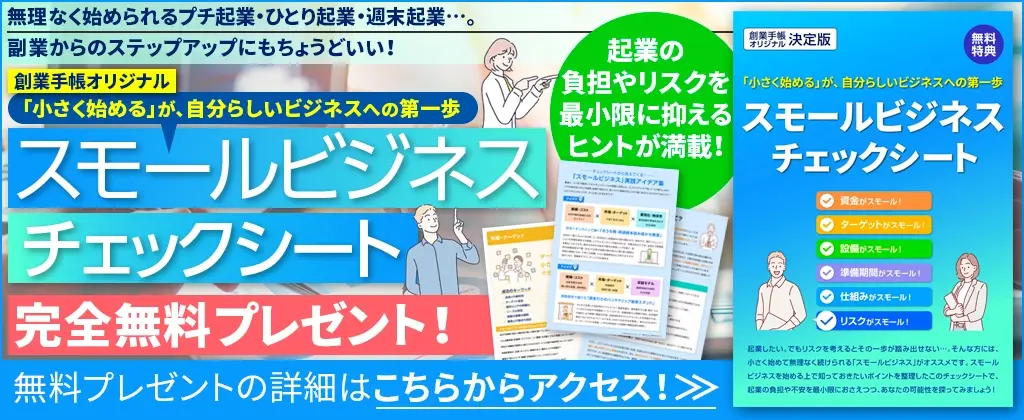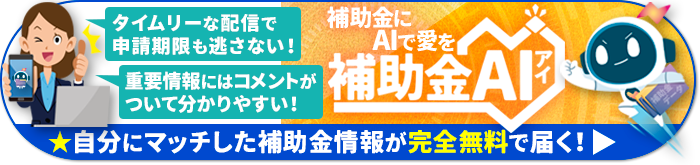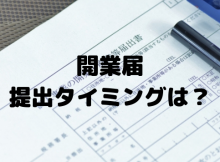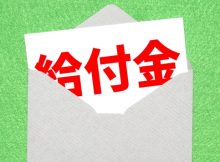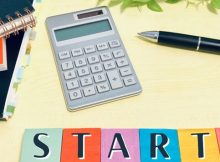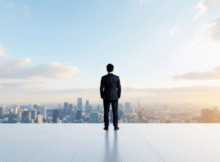副業でも給付金や補助金はもらえる?活用できる制度や注意点を徹底解説!
副業でも「個人事業主」になれば支援制度の対象に。受け取るための準備と注意点

副業している人が対象の補助金や助成金は存在します。しかし、誰でも利用できるわけではありません。
給付金や助成金、補助金といった制度を活用する場合、事業者としての登録があることが前提となっています。そのため、税務署への開業届の提出が必要です。
開業届を提出すれば個人事業主になるため、副業でも制度を活用できます。
今回は、副業向けの制度について解説するとともに、副業している人が使える補助金や助成金、給付金などの支援制度の種類をはじめ、活用のポイントなどについて解説していきます。
制度を活用して資金繰りをしたいと考えている人はぜひ参考にしてください。
創業手帳では、登録した都道府県の補助金・助成金情報を月2回メールで配信する「補助金AI」サービスを無料で提供しています。ぜひご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
副業者向けの制度の種類
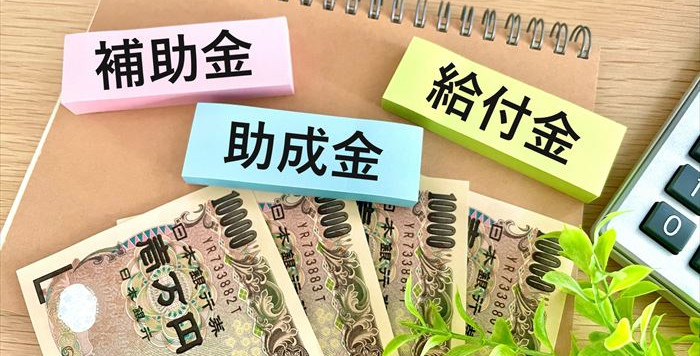
副業者向けの制度には、給付金・補助金・助成金といった種類があります。給付金は無償でお金をもらえる制度で、申請をクリアすれば現金を受け取れます。
給付金の使い道を限定しない制度も多いので、様々な用途で使える点が特徴です。しかし、制度の数は少なく、減収が給付の条件になっているケースもあります。
なお、補助金と助成金は、現金が貰える点では給付金と同様です。
しかし、用途が定められていることや、投じた費用の○割分を補助するという形で自由に使えるお金ではないことが大きな違いです。
補助金は主に経済産業省や地方自治体が管轄する施策となり、開発投資や設備投資を促進することを目的とした事業を支援するための制度です。
一方の助成金は、主に厚生労働省が管轄する制度です。従業員の雇用や労働環境など、人に対する制度といえます。
副業をしている人が使える補助金・助成金・給付金・支援制度

ここからは、副業の確定申告をしている人が利用できる制度を紹介します。ぜひ参考にしてください。
中小企業省力化投資補助金
中小企業の売上拡大や生産性アップを後押しするために、人手不足に悩んでいる中小企業に対して省力化投資を支援する制度が中小企業省力化投資補助金です。
企業の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることが目的です。一般型とカタログ注文型があります。
【一般型】
企業ごとに最適な省力化設備の導入を支援することが目的で、事業内容や現場に合わせた設備導入やシステム構築が補助対象です。
補助上限額は従業員数によって異なります。
| 従業員数 | 補助上限額 |
| 5人以下 | 750万円(1,000万円) |
| 6~20人 | 1,500万円(2,000万円) |
| 21~50人 | 3,000万円(4,000万円) |
| 51~100人 | 5,000万円(6,500万円) |
| 101人以上 | 8,000万円(1億円) |
※大幅な賃上げを行う場合は、()内に上限額を引き上げ
副業者となる小規模事業者であれば、補助金額が1,500万円までの補助率は2/3、1,500万円を超える部分の補助率は⅓です。
【カタログ型】
汎用製品をカタログの中から選んで導入し、企業の付加価値や生産性向上、賃上げにつなげることを目的とした補助金で、カタログに登録されている製品が補助対象となります。
| 従業員数 | 補助上限額 |
| 5人以下 | 200万円(300万円) |
| 6~20人 | 500万円(750万円) |
| 21人以上 | 1,000万円(1,500万円) |
※賃上げ要件を達成すると()内に上限を引き上げ
補助率は1/2以下となっており、補助対象経費の総額に補助率を乗じた額が上限額を上回る場合、上限額の範囲内での補助金が交付される仕組みです。
小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)
小規模事業者が制度変更に対応するために経営計画を作成し、販路開拓や生産性アップの取組みを支援する制度が小規模事業者持続化補助金です。
補助率と補助上限額は以下の通りです。
| 類型 | 一般型・通常枠 |
| 補助率 | 2/3(賃上げ特例に申請する赤字事業者の場合は3/4) |
| 補助上限 | 50万円 |
| インボイス特例 | 補助上限額に50万円を上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 補助上限額に150万円を上乗せ |
| 上記特例条件を共に満たしている事業者 | 補助上限額に200万円を上乗せ |
インボイス特例、賃金引上げ特例に関しては、それぞれの要件を満たしている場合のみ上限額に上乗せされます。
IT導入補助金
IT導入補助は、生産性アップや業務効率化を図るためのITツール導入を支援する補助金です。
ソフトの導入を考えている副業者の中には、費用がかかるからと諦める人もいるかもしれません。
しかし、IT導入補助金を活用すれば、国が費用を補助してくれます。
-
- 通常枠
- 複数社連携IT導入枠
- インボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)
- セキュリティ対策推進枠
以上の種類から、対象経費に合わせて選ぶことが可能です。
ただし、補助上限や補助率は、それぞれ異なるのであらかじめ確認しておいてください。
なお、IT導入補助金のホームページの補助金シミュレーターを利用すれば、申請可能額を把握するために役立ちます。
自治体による制度の活用
都道府県や市町村では、創業する人向けの制度を設けているケースもあります。制度を活用すれば、事業に必要な備品や機械の導入、販路開拓費の費用を補助してくれます。
例えば、創業支援等事業計画は、地域の創業者を支援するために、市区町村が金融機関や商工会議所、専門家らと連携して実施している支援制度です。
計画に認定された自治体では、以下のような支援策を行っています。
-
- 創業支援セミナーの開催
- 専門家による経営のアドバイスや個別相談の実施
- 補助金や支援制度の案内
- 創業融資支援
ただし、支援内容は自治体によって違いがあるので事前に確認しておいてください。
また、多くの自治体で実施されている制度ではありますが、認定を受けていない地域もあります。
自分が住んでいる自治体が当てはまっているか確認することも大切です。
業務改善助成金
副業であっても、従業員を雇用している人もいます。その場合に利用できる制度が業務改善助成金です。
設備投資を実施して、最低賃金を一定額引き上げた場合に費用の一部を助成してくれます。
引き上げる最低賃金額や労働者の人数によって、助成上限額が異なり、最大で600万円が補助されます。
申請に必要な書類は、賃金引上げ計画書や事業実施計画書などです。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金も、従業員を雇用している副業者が使える制度です。
従業員に対して職務に関連する専門的な知識や技術を習得させるための訓練を受講する事業主を支援するための制度で、研修における経費や研修期間中の賃金を一部助成してくれます。
-
- 人材育成支援コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスクリング支援コース
受給できる上限額はそれぞれ異なります。
| 人材育成支援コース | 1,000万円 |
| 教育訓練休暇等付与コース | 定額30万円(要件を満たせば36万円) |
| 建設労働者認定訓練コース | 1,000万円 |
| 建設労働者技能実習コース | 500万円 |
| 人への投資促進コース | 最大2,500万円 |
| 事業展開等リスクリング支援コース | 1億円 |
副業を始めると、収益の仕組みや給付金などの制度だけでなく、コスト管理や税金面での準備も欠かせません。創業手帳では、そうした副業の始め方を整理できる「スモールビジネスチェックシート」を無料プレゼントしています。小さくても利益を出す工夫から、リスクを抑える視点、制度を活かすための準備までまとめていますので、ぜひご活用ください。
副業者が給付金制度を活用する際のポイント

制度の活用は副業者にとって大きな力となります。しかし、活用する際には注意点もあります。
以下のポイントに注意してください。
最新の情報をチェックする
補助金や助成金といった制度は頻繁に変更されています。公募期間や申請の締切りをはじめ、対象者や経費の要件、補助率や上限、申請方法や必要書類などです。
毎年同様ではないため、知人の話や古い情報を信じると、申請できない可能性もあります。
申請をする際には必ず年度の最新の公募要項を確認し、実施する自治体や省庁などの公式サイトをチェックするようにしてください。
制度の趣旨と合っているか確認する
事業の種類や目標、計画と制度の趣旨が一致しているか確認することも大切です。
制度によって支援する分野や経費の対象は異なり、場合によっては申請できない可能性もあります。公募内容をよく確認して理解するようにしてください。
応募期限に余裕があるか確認する
制度によっては予算や採択件数に決まりがあるケースもあります。
また、応募申請期間が短い場合も多く、書類の作成や用意、情報収集に時間がかかってしまうと応募期間に間に合わない可能性があります。
補助金や助成金を受け取るために、事前に申請スケジュールを立てて計画通りに申請作業を進めていくことが大切です。
投資資金の必要性
補助金や助成金は原則後払いです。
実績を報告してから支払い請求を行うため、補助金や助成金を受け取る場合でも、事前に資金調達が必要です。
必要な資金を確実に準備し、事業を開始できるよう準備を進めてください。資金が足りない場合には、金融機関に相談して資金繰りをする必要もあります。
専門家への相談を検討する
制度の申請には時間がかかります。自分だけで対応することが難しい場合には、専門家への相談も検討してみてください。
補助金の場合は、経営コンサルタントや中小企業診断士、税理士などに相談すると、事業計画策定のアドバイスをもらえるほか、申請書類の作成支援を受けられます。
助成金の場合は、社会保険労務士に相談してください。雇用関連の助成金であれば、申請代行が可能なケースもあるので、期限に間に合わせるためにも早めに相談するほうが良いかもしれません。
他の給付金を貰いながら副業してもいいのか?

他の給付金を受給しながら副業できるかどうか不安に感じる人もいるでしょう。副業での収入に対する疑問を解決していきます。
失業手当を貰いながら副業する場合
失業手当は、労働者が失業した際にハローワークで手続きをすると受け取れるお金です。
働く意欲があり、求職活動をしているにも関わらず就職できない人に対して支給されるものです。
離職前から事業規模で副業をしている場合は、収入を得ている状態となり失業とはみなされないため、失業手当は受け取れません。
なお、事業規模の副業でなければ失業保険の給付が認められるケースもあります。
注意すべき点は以下の3つです。
-
- 待機期間中に副業をしない
- 副業する時間を1日4時間未満にする
- 副業の時間を週20時間未満にする
介護の給付金を貰いながら副業する場合
介護休業中であれば、月に10日(または80時間)を超えて就労すると、介護休業給付金を受給できません。
あらかじめ休日を指定して、月10日以下(80時間以内)になるように副業をする必要があります。
育児休業給付金を貰いながら副業する場合
育児休業給付金は、介護給付金と同様に月に10日を超えて働くと、給付金を受給できません。
また、休業開始前の給与の8割を超える金額を受け取る場合も、給付金を受け取れないこととなっています。
副業で稼ぎたいと考えている人は、月10日以下に抑えて働くようにしてください。
傷病手当金を貰いながら副業する場合
業務外の病気や怪我による療養で仕事に就けず、給与を受け取れない際に支給されるのが傷病手当です。
体を休めて治療に専念することが目的のため、基本的に副業は認められていません。
ただし、リハビリを兼ねた簡単な内職であれば、職場復帰を目指す場合に限り例外として認められるケースもあります。
手作業による組み立て作業やデータ入力など、体に負担をかけないような業種を選ぶことが大切です。
まとめ・副業で使える給付金制度の内容を理解して選ぼう
副業者でも使える制度は複数あるため、制度の趣旨や最新情報をチェックして、自分の副業に適したものを選んで活用してみてください。
申請する余裕がない人は専門家への相談を検討してみてください。
気付かた時にはもう申請が終わっていた…そんな事にならないために、創業手帳では登録した都道府県の補助金・助成金情報を月2回メールで配信する「補助金AI」サービスを無料で提供しています。ぜひご活用ください。
給付金や補助制度を活用するには、事業の方向性や収益の見通しを整理しておくことが重要です。
創業手帳作成の「スモールビジネスチェックシート」(無料) では、副業や小さな事業を軌道に乗せるための準備ポイントをまとめました。収益化の工夫、コストやリスクの抑え方、税務面での注意点まで網羅しています。副業を安心して続け、制度を効果的に活かしたい方は、ぜひご覧ください。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。