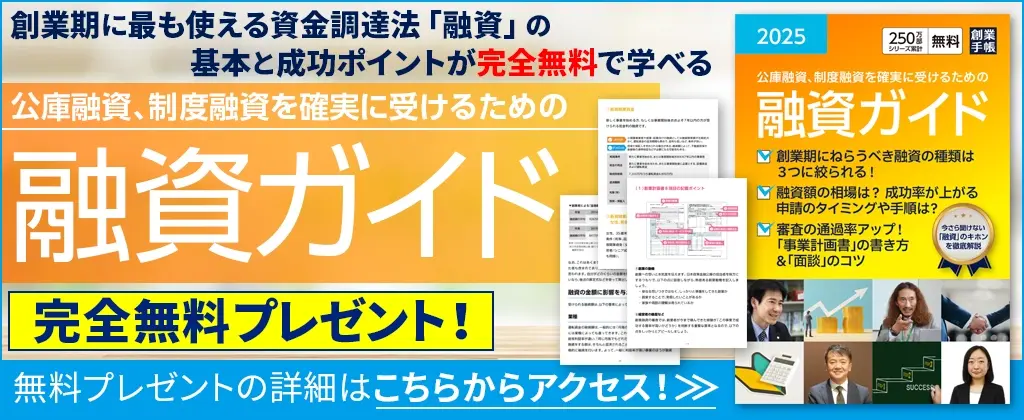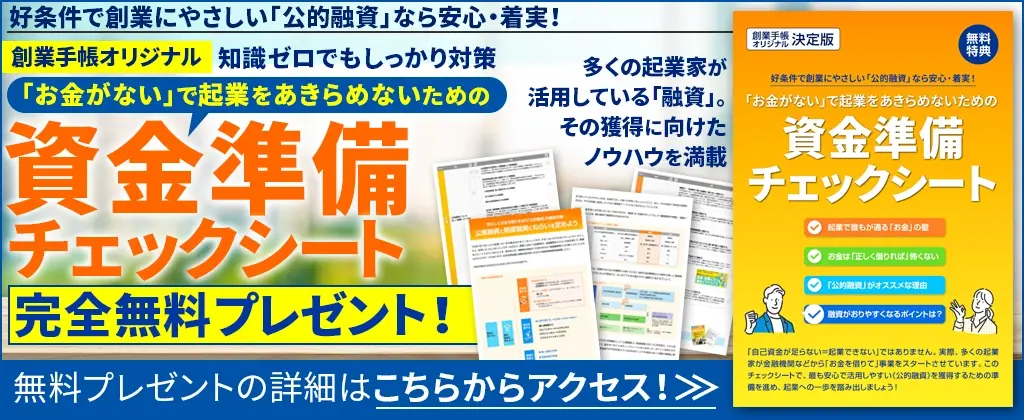法人の創業で使える融資とは?公庫融資や制度融資を徹底解説!
法人の創業には「公庫融資」と「制度融資」がおすすめ
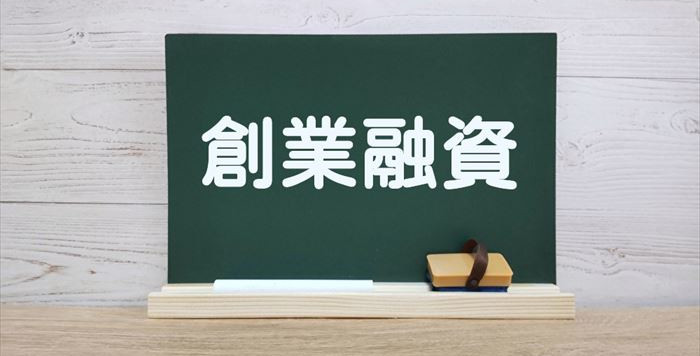
法人を創業する場合、資金調達に融資を利用する機会が多くなります。
融資には公的融資と制度融資というものがあり、それぞれ適用要件などが異なるので確認することが重要です。
創業時の融資として「新創業融資制度」を思い浮かべる方も多いと考えられますが、この制度は2024年3月31日で終了となっているので、他の融資制度を利用することになります。
今回の記事では、法人の創業に役立つ融資制度や制度融資の概要、融資を受ける際の注意点などについて解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
創業初期の起業家への強い味方!無料で提供している融資ガイドが、資金調達のタイミングや審査のポイントを詳しく解説します。融資を早期に申し込むことで得られるメリットを知り、効果的な資金計画を立てましょう。さらなるビジネスの成功に向けて、この機会にぜひ融資ガイドをご利用ください。
また、資金準備チェックシートでは、初心者におすすめの公的融資について基本から解説しています。起業のタイミングでも無理なく活用できる公的融資の準備や面談のポイントなどがわかります。ぜひこの機会にご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
1.新たに拡充された幅広い方向けの公庫融資「新規開業資金」

新創業融資は2024年3月31日をもって終了となっていますが、創業時に利用できる「新規開業資金」という融資制度があります。
これは、新たに拡充された制度であり、幅広い方を対象にした公庫融資です。まずは、新規創業資金の概要や種類について解説していきます。
新規開業資金の概要
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 対象者 | 新たに事業を始める方もしくは事業開始後おおむね7年以内の方 |
| 自己資金の要件 | なし |
| 担保・保証人 | 希望を考慮しながら相談の上決定する |
| 利率 | 基準利率 ※基準を満たした場合は特別利率が適用となる |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |
新規開業支援金は、日本生活金融公庫が行っている融資制度です。
これから新たに事業をスタートしようと考えている方や事業を開始してからおおむね7年以内の方であれば、利用可能となっています。
事業を円滑に進めるためには資金が必要不可欠です。
スタートしたばかりだと資金調達が難しいケースも珍しくないため、このような融資制度は前向きに検討すべきだと言えます。
新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)の概要
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 対象者 | 新たに事業を始める方もしくは事業開始後おおむね7年以内の方の中で、女性もしくは35歳未満か55歳以上の方 |
| 自己資金の要件 | なし |
| 担保・保証人 | 希望を考慮しながら相談の上決定する |
| 利率 | 条件によって特別利率A・B・Cが適用となる
特別利率A:年利1.75%~2.85%(2024年4月1日時点) |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |
特別利率は、年齢の条件を満たす方、認定されている創業塾や創業セミナーなどを受けた方、技術・ノウハウに新規性がみられる方などの条件によって決定されます。
利率を抑えながら融資を受けられるので、女性や35差未満の若者、55歳以上のシニアに該当する場合は、前向きに活用を検討してみてください。
新規開業資金(再挑戦支援関連)の概要
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 対象者 | 新たに事業を始める方もしくは事業開始後おおむね7年以内の方の中で、以下の条件全てに該当する方 ・廃業経験を持つ個人もそくは廃業経験を持つ経営者が営む法人であること ・廃業した時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込みなどであること ・廃業の理由や事情がやむを得ないものなどであること |
| 自己資金の要件 | なし |
| 担保・保証人 | 希望を考慮しながら相談の上決定する |
| 利率 | 基準利率 ※基準を満たした場合は特別利率が適用となる |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内) |
過去に廃業歴がある場合は、この制度を活用するのがおすすめです。基本的には新規開業支援金と同じですが、特別利率の利用ができます。
また、返済期間も通常より長いといった点もメリットです。
新規開業資金(中小企業経営力強化関連)の概要
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 対象者 | 新たに事業を始める方もしくは事業開始後おおむね7年以内の方で以下のいずれかに該当する場合 ・「中小企業の会計に関する基本要領」か「中小企業の会計に関する指針」を適用している ・適用する予定の方で、自分自身が事業計画書の策定を行って中小企業等経営強化法で定められている認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方 |
| 自己資金の要件 | なし |
| 担保・保証人 | 希望を考慮しながら相談の上決定する |
| 利率 | 特別利率A:年利1.75%~2.85%(2024年4月1日時点) |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |
この制度は、新たに営もうとする事業について適正な事業計画が策定されていて、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる場合に利用できます。
厳しいように思われますが、基準を満たせば特別利率が適用になるので、メリットは大きいです。
新規開業資金のメリット
新規開業資金のメリットは、以下のような点が挙げられます。
-
- 融資の限度額が大きめに設定されているので、1つの融資で創業資金を集められる
- 利率が低いため、経済的に資金調達できる
- 返済期間を長めに設定できるので、返済の負担を軽減できる
- 据え置き期間を設定できることから、創業直後の資金繰りが有利になる
創業時には大きなお金が必要になる場合もあります。そのような時、融資限度額は7,200万円という点は非常に魅力的です。
メリットはこのようにいくつもあるので、利用を検討する価値は大いにあります。
新規開業資金のデメリット
新規開業資金を利用するなら、デメリットも把握しておく必要があります。デメリットには、以下のような点が挙げられます。
-
- 新規開業資金は設備資金や開業後数年間の運転資金を含む開業資金にしか使えない
- 民間の金融機関と比べると着金までの時間がかかる
- 担保や保証人は基本的に必要となる
資金調達の方法としておすすめではありますが、新規開業資金は開業時の資金にしか利用することができません。
また、実際に資金が得られるまでにお金がかかると必要な時にお金が手元にないといった可能性も考えられます。
担保や保証人が用意できない場合は、他の融資を建都しなければいけない可能性も出てきます。
2.スタートアップが対象の公庫融資「スタートアップ支援資金」

日本の経済成長や社会課題の解決を先導する存在として、スタートアップ企業の成長が期待されています。また、日本政策金融公庫ではそのような企業の支援を行っています。
概要やメリット・デメリットは以下のとおりです。
スタートアップ支援資金の概要
| 融資限度額 | 直接貸付 20億円 |
| 対象者 | 以下の条件全てに該当する方 ・事業計画書を策定し、事業の成長を図ること ・次のいずれかに該当すること ①一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員以外)などまたは独立行政法人中小企業基盤整備機構もしくは株式会社産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合などから出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権及び新株予約権付社債など)を受けている ②JーStartupプログラムもしくはJーStartup地域版プログラムに選定された |
| 自己資金の要件 | なし |
| 担保・保証人 | ・担保設定の有無、担保の種類などは、相談の上決定する ・保証人はなし |
| 利率 | ①に該当する方:特別利率②(上限2.5%) ②に該当する方:特別利率②(上限2.5%)、基準利率(上限2.5%) |
| 返済期間 | 設備資金・運転資金:20年以内(うち据置期間10年以内) |
日本公庫各支店の中小企業事業の窓口で詳しく説明を聞くことができます。
スタートアップ支援資金のメリット
スタートアップ支援資金のメリットには、以下のような点が挙げられます。
-
- 融資限度額が直接貸付で20億円までとなっている
- 保証人が必要ない
- 新株予約権が新株予約権を取得すれば担保なしで利用できる
スタートアップ支援資金の融資限度額は20億円と多額の融資にも対応しています。
新規開業資金の対象にならない方でも条件を満たせば利用できる可能性があるので、前向きに検討してみてください。
スタートアップ支援資金のデメリット
スタートアップ支援資金のデメリットも把握しておく必要があります。具体的に挙げられるのは、以下のような点です。
-
- 事業計画書の策定と事業の成長が見込まれることが前提となっている
- 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会の会員になっていたり、独立行政法人中小企業基盤整備機構や株式会社産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合などから出資を受けたりしていなければいけない
- JーStartupプログラムもしくはJーStartup地域版プログラムに選ばれていなければいけない
新規開業資金よりも利用できる方の条件はクリアしやすいように感じますが、誰もが受けられるわけではありません。
それを加味したうえで利用しないと、そもそも利用できずに終わってしまう可能性もあります。
地方自治体・金融機関・信用保証協会による「制度融資」とは?

制度融資を賢く利用すれば、経済的に資金調達ができます。続いては、制度融資のメリット・デメリット、種類についてご紹介します。
制度融資のメリット
制度融資のメリットには、事業者の目的に合わせた制度を利用できるといった点が挙げられます。
東京都では、創業や事業承継、工場・事務所の増設、海外展開などの新たな事業を展開するための資金として利用できる制度融資があります。
その他にも「働き方改革支援」など、東京都の制作に対応した制度融資もあるので、多岐にわたる用途で活用できる制度です。
制度融資のデメリット
制度融資にはメリットもありますが、他の制度と同じくデメリットだと感じてしまう部分もあります。
デメリットとして挙げられるのは、銀行融資よりも申し込みから着金までに時間がかかってしまう傾向があるという点です。
制度融資は地方自治体に申し込みをしてから金融機関経由で信用保証協会に保証を申し込むなどのステップが増えるため、着金までに時間がかかってしまいます。
創業時に使える制度融資について

創業時に使える制度融資にはいくつもの種類があります。ここでは3つピックアップしてご紹介します。
「女性・若者・シニア創業サポート事業」(東京都)
東京都の「女性・若者・シニア創業サポート事業」は、融資限度が1,500万円です。
対象となるのは、東京都内で創業の計画がある方、または創業後5年未満の方、地域の需要や雇用を支える事業を行う方になります。
また、女性や若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)のいずれかに該当することも条件に含まれています。
「中小企業制度融資『創業』」(東京都)
東京都の「中小企業制度融資『創業』」は、融資限度額が3,500万円となっています。
対象となるのは、東京信用保証協会の保証耐衣装となる業種を営んでいる中小企業の経営者で、以下のいずれかに該当する方です。
-
- 現在は事業を営んでいない個人で、創業に関する具体的な計画を立てている
- 創業した日から5年未満の中小企業者など
- 分社化しようとする会社または分社化により設立された日から5年未満の会社
「創業支援融資」(神奈川県)
神奈川県の「創業支援融資」は、融資限度額が3,500万円です。
1カ月以内に新たに個人事業を創業予定の方、2カ月以内に新たに法人事業(NPO法人、医療法人以外)を創業予定の方、事業を行っていない個人が事業をスタートして創業後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)などの条件を満たすと利用できます。
法人設立で創業融資を受ける際の注意点

法人設立で創業融資を受けるのであれば、いくつか把握しておくべき注意点もあります。最後に、どのような注意点があるのかご紹介します。
無理のない返済計画を立てる
融資を受けるのであれば、無理のない返済計画を立てることが必要不可欠です。融資は借入なので、当たり前ですが返済の義務があります。
融資を受けたら、毎月融資額に利息を加えた金額を返済していかなければなりません。
返済計画を立てる際は、毎月の売上げだけで考えるのは避けるようにしてください。
なぜなら、売上げから人件費や家賃、仕入れ代、その他の経費などを差し引いたものが利益になるからです。
さらに、法人税などの税金もかかるので、それらを考慮した上で考えるようにすると、無理のない返済計画が立てやすくなります。
返済義務が生じない資金調達方法も検討する
創業資金を調達する時に、返済義務が生じない資金調達方法も検討するのもおすすめです。
その方法のひとつに助成金があります。助成金は基本的に返済義務がなく、収入として扱うことができます。
しかし、事実と異なる報告を行うと助成金の返済義務が発生する場合もあるので注意が必要です。不正受給をした場合は、ペナルティも課せられます。
事業計画書や創業計画書の内容を充実させる
法人を設立したばかりだと実績や信用がないため、融資が下りない場合もあります。
そのような事態を回避するためには、事業計画書や創業計画書の内容を充実させることがポイントです。
例えば日本政策金融公庫の場合、創業融資を受けるときに創業計画書や月別収支計画書を提出し、それを踏まえた審査が行われます。
経営者の経験や能力、返済の可否などを重点的にチェックされます。そのため、それらがしっかりと伝わる創業計画書を作成することが重要です。
まとめ・法人を設立するなら状況に合った創業融資を計画的に活用しよう
法人を設立する時は、それぞれの状況に合わせた創業融資を計画的に活用することがポイントになります。
創業融資や制度融資を上手く活用することで、円滑に事業をスタートできるからです。そのためには、どのような融資制度があるのか把握しておくことも大切です。
無料でお読みいただける「融資ガイド」では融資にまつわる重要なポイントをわかりやすく解説しています。公的融資に特化した「資金準備チェックシート」とあわせて是非ご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「資金調達手帳」は資金調達の方法をはじめとし、キャッシュフロー改善のマル秘テクニックや創業計画書の書き方も充実。無料でお届けいたしますのでご活用ください。