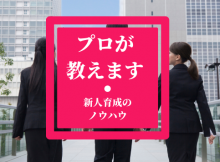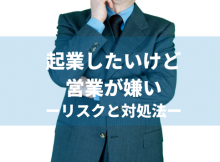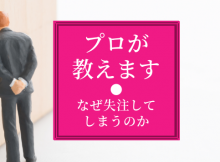深刻化する営業人材不足。今すぐ始められる6つの解決策とは
社内育成から営業代行まで全解決策を徹底解説

昨今、多くの企業が「営業人材不足」という深刻な課題に直面しています。
新規顧客の獲得や既存顧客への対応がままならず、売上確保が難しくなってきているのが現状です。
では、なぜこれほどまでに営業の人材が不足しているのでしょうか? そして、限りあるリソースの中でどのように成長戦略を描いていけばいいのでしょうか?
本記事では、営業人材不足が起こる背景や、社内・社外のリソースを活用して不足を補う具体的な方法を営業支援・コンサルティング事業を展開する株式会社エッジコネクションの代表大村氏に解説していただきます。

延岡高校、慶應義塾大学経済学部経済学科卒業後、米系金融機関であるシティバンク銀行(現SMBC信託銀行)入行。2007年、株式会社エッジコネクション創業。営業支援業を軸に、現在は人事・財務課題も対応する「営業・人事・財務課題伴走型支援企業」として展開。経営危機を乗り越えた経験を生かし、コンサルティング業や、ラジオ・YouTube・コラム・Instagramなど、各種メディアで発信中。
これまでに1600社以上を支援し、継続顧客割合は平均75%台。地元宮崎でも地域振興に尽力し、延岡市立地促進コーディネーターや延岡デジタルクロス協議会人材支援委員長を務める。
2024年7月、「24歳での創業から19期 8期連続増収 13期連続黒字を達成した黒字持続化経営の仕組み」を出版。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
なぜ営業の人材不足が起きているのか

そもそも、なぜ営業人材不足が起きているのでしょうか?
企業の新規事業拡大や顧客獲得競争が激化する一方で、若年層の労働人口は減少傾向にあり、営業職としてのキャリア形成に不安を抱える人も増えていることが原因です。
以下、それぞれを具体的に解説していきます。
若年層の人口減少
総務省の人口推計によれば、2001年には157万人いた新成人が、2023年には117万人まで落ち込んでいます。これは約20%もの大幅な減少であり、社会に新たに参入する労働力全体が確実に目減りしていることを示唆しています。
その結果、営業という重要な役割を担う人材の数も自然と減少せざるを得ない現実が浮き彫りになっています。
働き方改革による人材の流動化
働き方改革の推進に伴い、長時間労働の是正が一層進められました。その結果、以前は「転職したくても時間がない」と嘆いていた営業職の方でも、新しいキャリアを模索しやすい環境が整いつつあります。
さらに、スマートフォンを通じて多様なメディアや職種の情報が容易に収集できるようになったことも、他の仕事への興味をかき立てる要因の一つです。
こうした背景が、営業職への人材参入を鈍化させる大きな要因となっています。
対面コミュニケーションに不慣れな若者文化
スマートフォンの急速な普及によって、LINEなどのチャットアプリを使った気軽なやり取りが当たり前になりました。
その結果、以前のように相手の自宅へ電話し、家族や年長者とやり取りをする機会が激減し、子供の頃から別世代との対面コミュニケーションを培う場面が著しく減っています。
さらに、若者の間でお酒を飲む習慣が減少傾向にあり、飲み会を通じて初対面の人たちと親睦を深める機会も少なくなりがちです。
このような状況が、営業活動で求められる対人スキルの形成を難しくしている要因の一つと言えるでしょう。
営業の人材不足を解決できる6つの方法

このような時代背景の中、どのように営業人材の不足を解消できるのか、いくつかポイントをご紹介します。
【内部】での3つの対応
教育体制を整える
先述したように、友人宅に電話をかけて親御さんと会話する機会や、お酒の席であまり親しくない人と関係を深めるといった経験が激減しており、日常生活だけでは営業職に必要なコミュニケーションスキルを習得するチャンスが圧倒的に不足しているのが現状です。
このような状況では、「営業なんてそのうち慣れる」「営業はセンス次第」といった旧来の考え方だけで人材を育てるのは難しくなってきています。
むしろ、段階的なカリキュラムや具体的なマイルストーンを設け、一人ひとりが着実にスキルを身に付けられるような体系的な育成体制を構築することが欠かせません。
離職率を下げる
せっかく育てた営業職が退職してしまっては、それまでかけた手間暇が無駄になってしまいます。
よって、営業職が離職しないかどうかには細心の注意が必要です。
具体的には、以下のようなポイントを常に意識しましょう。
-
- 売上目標が過大になってないか
- 相談できる環境か
- 成長を実感しているか
- 実績と給料が連動しているか
まずはこの4点を日頃から確認するようにしましょう。
採用率を上げる
どれだけ離職が出ないように気を使っても、家族の都合など避けられない離職もあります。
また、離職が出ず、育成もしっかり機能していれば企業として成長しているでしょうから増員の必要があります。
つまり、採用率の向上は避けては通れません。
そのとき、営業職の人気はなくなってきているのが実状ですので、それを踏まえた採用戦略を立てる必要があります。
具体的には、社風、オフィスの綺麗さ、福利厚生など、業務内容以外で求職者が頑張りたいと思える自社のポイントを見つけ出し、しっかりとアピールしましょう。
【外部】での3つの対応
マッチングサービスの活用
現在では、ビジネスマッチングを支援する各種サービスが数多く展開されています。
こうしたサービスを活用することで、自社に興味やニーズを持つ企業から直接アプローチを受ける可能性が高まります。
ただし、これらのサービスはあくまで「マッチングが成立する」ことを前提としているため、マッチング不成立の場合には全く連絡が得られないという課題があります。
結果的に待ちの姿勢に陥りやすくなる点が大きなデメリットといえるでしょう。
人材派遣の活用
次に、人材派遣会社から営業職経験者を派遣してもらうという方法があります。
営業職を経験した人ですから、一から営業を教える必要がありませんし、その人が元々持っている人脈などを活用できる可能性があります。
人材派遣会社を活用する上での難点としては、企業側が自社社員同様にマネジメントを行わなければならないことが挙げられます。
派遣社員であっても、勤怠や作業進捗などの管理を定期的に把握する必要があります。さらに、派遣契約の特性上、重要な人材に成長したとしても契約満了や急な事情で退職されてしまうリスクは否めません。
営業代行の活用
最後に、営業代行業者の活用が考えられます。営業代行業者は、文字通り営業を代行してくれますので、マッチングサービスのように待ちの一手になったり、自社で営業スタッフをマネジメントしたりというデメリットを払拭できます。
営業代行の活用について
ここまで、営業の人材不足を解決できる6つの方法を紹介してきました。
その中でも特に注目を集めているのが営業代行の導入です。
営業代行を活用することで、どのように効果を最大化できるか、ポイント詳しく見ていきましょう。
営業代行を活用するメリット
営業代行を活用するメリットとして、以下のような点が挙げられます。
1.営業スタッフのマネジメントをしなくて良い
営業スタッフをマネジメントすることは、企業側にとって負担です。具体的には、育成コスト、管理監視コスト、モチベーション管理コストなど、様々な面で時間や手間のコストが発生します。営業代行を活用することで、これらコストから一気に解放されます。
2.営業スキルの担保
営業スタッフを新規で採用した場合、どの程度のスキルがあるか未知数です。しかし、営業代行を活用すると、中の社員はそれなりに営業経験があることは間違いありませんので、最低限の営業スキルを保有している前提でその後のシミュレーションをすることができます。
3.コストの最適化
営業スタッフを自社社員として雇用すると、給与の支払いが必要になります。また、その営業スタッフに実力不足など問題が生じても、一方的に解雇することはできません。 一方、営業代行業者に支払う費用は業務委託費です。契約期間が満了すれば支払いを止めることができ、必要最低限の費用負担で済みます。
4.他社の成功事例からの提案
営業代行業者と共同でプロジェクトを進めると、「もっとこうしてはどうか?」などの提案を受ける場面が少なくありません。これらの提案は、同業界や類似プロジェクトで成果を上げた事例から導き出されている可能性が高く、自社だけでは入手しづらい他社の成功ノウハウを間接的に取り込むことにつながります。
営業代行を活用するにあたっての注意点
営業代行も、どんな業者に発注しても問題ないというわけではありません。活用にあたっての注意点があります。
1.委託する業務範囲のすり合わせ
営業代行業者には、アポイントを取得するまで、初回商談のヒアリングまで、成約が取れるまで、など、どこまでの業務を請け負うかという点について様々な種類があります。また、営業活動には、リスト作成、営業資料作成など、周辺業務もたくさんあります。どこまでを営業代行業者がやってくれるのかという認識を正確にすり合わせていないと、「やってほしいと思っていた業務をやってくれない」といったトラブルが発生します。
2.実績の確認
営業代行業者を活用するメリットのところで、営業スキルが担保されていることや他社成功事例を入手できることを紹介しました。これらのメリットが成立する背景は、その営業代行業者がしっかりと実績を積んでいることです。つまり、創業間もなかったり、ある特定の業界に特化していたりすると、その限りではありません。よって、発注前にその営業代行会社の実績をしっかり確認するようにしましょう。
3.機密情報の管理
営業代行業者に業務を依頼する際は、顧客情報や自社の営業戦略などの機密情報を取り扱う機会が必ず発生します。万が一、情報漏洩が起これば会社の信用が大きく損なわれ、深刻な打撃を受けるおそれがあります。こうしたリスクを避けるためにも、契約前に代行業者のセキュリティ対策や情報管理体制を徹底的にチェックすることが不可欠です。
具体的には、NDA(秘密保持契約)の締結やアクセス権限の制限、データの送受信方法の安全性などを評価し、自社の基準を満たしているかを確認しましょう。
4.クレーム対応フローの明確化
顧客からのクレームや問い合わせが発生した場合、どこまでを代行業者が対応し、どの時点で自社がフォローに入るのかを事前に取り決めておくことが不可欠です。クレームが大きくなる前に迅速かつ適切に対処するためにも、連絡手段や報告のフローをあらかじめ共有し、スムーズに問題解決ができる環境を整えておきましょう。
営業代行の具体的な活用方法

最後に、営業代行を活用するときに失敗しないプロセスについてご紹介します。
1. 代行してほしい業務範囲を決める
BtoBの営業活動は主に以下のような流れで進みます。
ターゲット選定→ターゲットリスト作成→アポ取り→初回商談→提案→成約
これらのプロセスのうち、どこを委託するのかを決めましょう。やってほしい業務と実際にやってくれた業務にズレがあると、プロジェクトが成功しないのは当然です。
2.実績や情報管理の状況を把握しながら業者を選定する
依頼する業務を確実に実行できるかどうかを見極めるうえで、自社と同じ業界での営業実績やターゲット分野への知見はもちろん、業者がどのように情報を管理・保護しているかもしっかりチェックする必要があります。機密情報や顧客データの取り扱い体制に不備があれば、委託後に大きなリスクが発生するおそれがあります。これらの点を総合的に確認して、安心して任せられる業者を選定しましょう。
3.下請け扱いではなく、パートナーとして密に連絡を取り合う
営業活動は、実際に進めてみるまで相手の反応を予測しきれない部分が多々あります。もし思わしくない手応えがあった場合、営業戦略全体の練り直しが必要になる可能性も否定できません。こうした局面で、営業代行業者を単なる“下請け”扱いし、「後は任せたよ。結果出してね。」という姿勢だけでは、相談や議論がスムーズに進まず、有用なアイディアが生まれないままプロジェクトが失敗に終わるリスクが高まります。逆に、業者とワンチームとして密にコミュニケーションを取り合いながら進めることで、小さな変化や市場の反応をいち早く共有でき、改善策の検討や実装を素早く行えるようになります。その結果、成果を最大化できるだけでなく、業者との信頼関係もより強固になるでしょう。
いかがでしたでしょうか?営業人材の確保が難しい状況だからこそ、営業代行業者をうまく活用して自社の営業活動を強化していただければと思います。
(執筆:
株式会社エッジコネクション 代表取締役 大村 康雄(おおむら やすお))
(編集: 創業手帳編集部)