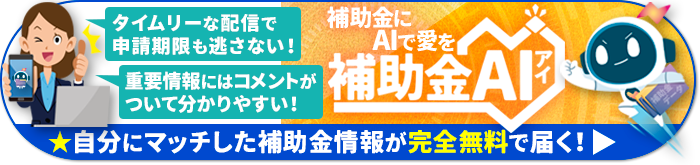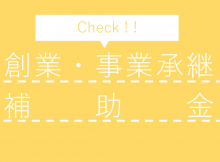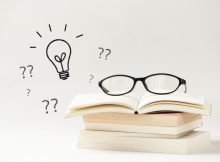【2025年最新】電気料金補助終了後はどうなる?企業が知っておくべき対策
電気料金の補助が2025年3月で終了!高騰する光熱費に対してどう対応すべきなのか

2025年1月から3月にかけて、政府による「電気・ガス料金負担軽減支援事業」が行われていました。4月以降は政府による補助がなくなるため、一般家庭や企業では、電気代負担が重くなったと感じるかもしれません。
電気代は企業にとってコストの一つであるため、補助金の終了によりコスト負担が重くなります。特に昨今はエネルギー価格の高騰に伴って電気代の値上げが行われているため、節電の意識を持つ重要性が高まっています。
今回は、政府による補助金事業が終了したことによる影響や、今後予想される企業への影響などを解説します。あわせて、企業が取り組める節電対策も解説するため、参考にしてみてください。
政府の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」とは

「電気・ガス料金負担軽減支援事業」とは、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の一環で行われていた補助金事業です。物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、家庭の電力使用量が多い1月から3月にかけて、電気・ガス代を支援していました。
「生活者」「家庭」という文言が含まれていますが、企業も補助金の対象です。「電気・ガス料金負担軽減支援事業」では、以下のように電気代・ガス代の値引きが行われていました(ガス代は家庭及び年間契約量1,000万㎥未満の企業等が対象)。
| 電気代の値引き単価 | 都市ガス代の値引き単価 | |
| 2025年1月・2月使用分 | ・低圧の電気代:2.5円/kWh ・高圧の電気代:1.3円/kWh |
10.0円/㎥ |
| 2025年3月使用分 | ・低圧の電気代:1.3円/kWh ・高圧の電気代:0.7円/kWh |
5.0円/㎥ |
2025年3月使用分の請求は4月に行われるため、4月使用分(5月請求分)以降は補助金終了後の金額が反映されます。
なお、内閣府の資料によると、補助金による家計の節約効果は以下のように試算されています。
| 電気料金 | ガス料金 | 合計 | |
| 2025年1月・2月使用分 | 2.5円/kWh×400kw=1,000円 | 10.0円/㎥×30㎥=300円 | 1,300円 |
| 2025年3月使用分 | 1.3円/kWh×400kw=520円 | 5.0円/㎥×30㎥=150円 | 670円 |
上表は一般家庭における節約効果であるため、消費電力量が多い企業であれば、節約効果はさらに大きかったはずです。
暖かくなるにつれて暖房を使用する頻度は減るとはいえ、企業では空調や照明を常時つけていたり、そもそもの契約アンペア数が高かったりします。
電気代の負担を軽減し、最終的に残せる利益を少しでも多くするためにも、自助努力による節電に取り組むことが大切です。
電気代やガス代が高騰している背景や理由

電気代やガス代が高騰している理由は、国際情勢の緊迫化やエネルギー資源の高騰、円安などさまざまです。
どのような背景・理由で電気代が高騰しているのかを見ていきましょう。
世界的なエネルギー資源価格の上昇
ロシアによるウクライナ侵攻やパンデミック後の経済回復によるエネルギー需要の増加などが重なり、エネルギー資源が高騰しています。
電力やガスの使用に欠かせない石油や天然ガスの価格が大きく上昇しており、調達コストが高騰している分、家庭や企業へ最終的に転嫁されているのです。
日本は天然資源が乏しいため、石油や天然ガスを輸入に頼っています。経済産業省の資料によると、日本は石油火力や天然ガス火力をはじめとした火力発電の構成が70%を超えており、エネルギー資源価格の影響を強く受けるのです。
円安
円安によるエネルギー調達のコスト増加も、国内の電気代やガス代の値上げにつながっています。エネルギー資源の取引は米ドルで行われており、円安になると、日本からすると調達コストが増えます。
つまり、同じ数量のエネルギーを購入する際に必要な円の金額が増えるため、発電コストやガス供給コストが上昇するのです。
コスト増は、最終的に家庭や企業へ転嫁されます。このように、エネルギーを輸入に頼っている日本にとって、円安は電気代やガス代の高騰につながる大きな要因なのです。
再生可能エネルギー発電促進賦課金の値上げ
「FIT制度」により、電力会社には再生可能エネルギーの買い取りが義務付けられています。
電力会社にとっては、エネルギーの買い取りによってコストが増加します。買い取りにより増加したコストについて、家庭や企業が負担するのが「再生可能エネルギー発電促進賦課金」です。
ここ数年、再生可能エネルギー発電促進賦課金は以下のように値上がりしています。
- 2023年度:1.40円/kWh
- 2024年度:3.49円/kWh
- 2025年度:3.98円 /kWh
昨今は再生可能エネルギーの発電量が増えている背景もあり、電力会社の買い取りコストが増えています。今後ますます再生可能エネルギーが普及すれば、家庭や企業における電気代の負担は重くなっていくでしょう。
しかし一方で、地球温暖化対策を進めていくうえでは、発電するときにCO2を出さない「再エネによる発電」を増やしていく必要があるのです。
補助金の終了による企業への影響

電気代やガス代の値上がりが続いている中で、さらに政府による補助金が終了すると、企業にとってはコスト増加を感じやすいでしょう。
以下で、具体的に考えられる企業への影響を解説します。
経営コストの増大
消費電力量によるものの、補助金終了後は毎月の電気料金が数%〜十数%上昇する可能性があります。
2025年3月使用分では、低圧の電気代で1.3円/kWhの補助が行われていました。月間の消費電力量が2,000kWhとした場合、2,600円のコスト増です。
特に、電気を大量に使用する製造業やオフィスを構える企業などでは、より影響が大きくなると予想されます。夏場になると、冷房の運転時間が長くなることにより消費電力が増えるため、さらにコスト増を感じるでしょう。
利益率の圧迫
コスト増は、企業の利益を圧迫します。昨今は電気代やガス代だけでなく、さまざまな原材料費や運送コストも上昇しています。
増加したコストについて、自社の商品やサービスの値上げでカバーできるかもしれません。しかし、コスト増加をカバーしきれない場合、自社の負担が増えて最終的に売上高に占める利益率が低下してしまいます。
利益率の低下により、従業員への賃上げが難しくなったり、金融機関から融資を受けづらくなる可能性があります。つまり、長期的に見ると人材定着や資金調達の面で、不利になってしまうかもしれません。
電気代の値上げに今すぐ取り組める企業向けの対策

電気代の値上げに対応するためには、自社で消費電力を抑えるための取り組みが効果的です。
今すぐ取り組める企業の対策を紹介するので、参考にしてみてください。
エネルギー使用量の削減
現在使用している設備を、省エネ性能が高い設備へ入れ替える方法があります。具体的には、LED照明や高効率モーターの導入を通じて、消費電力削減と電気代の節約効果が期待できます。
経済産業省によると、68Wの蛍光灯器具から34WのLED照明器具に交換すると、年間での節約効果は約2,108円です(年間2,000時間使用した場合)。交換する箇所を増やすほど、より節約効果が高まります。
他にも、テレワークやフレックスタイムを導入して、オフィスの稼働時間を短縮する方法も効果的です。業務を効率化して残業時間を抑制すれば、消費電力を抑えられるでしょう。
再生可能エネルギーの活用
太陽光発電を活用し、使用電力を抑える方法があります。自社の屋根や敷地内に太陽光パネルを設置し、発電した電力を自家消費すれば電気代を抑えられます。
初期投資が必要になるものの、長期的に見れば電気代削減が期待できるでしょう。
また、蓄電池を導入すれば、昼間に発電した電力を夜間利用できます。昼間は照明の使用を抑えて、暗くなった時間帯は蓄電池を利用すれば、電気代を削減できるでしょう。
新たな電力契約・サービスの検討
電力の自由化に伴って、契約する電力会社を選択できるため、電力契約・サービスの見直しも検討しましょう。複数の電力会社が多様な料金プランを提供しているため、自社の使用形態に合ったプランを選べば、コスト削減につながります。
空調の最適化
一般的に、新しい電化製品ほど消費電力が小さく、電気代を節約できます。長年にわたって同じ空調を使用している場合は、エネルギー効率の高い空調設備に更新するとよいでしょう。
冷房時は26〜28℃・暖房時は18〜20℃を徹底し、設定温度を最適化することも効果的です。フィルターが汚れていると電力消費が増えてしまうため、フィルターの定期清掃も行いましょう。
さらに、断熱材や遮熱フィルムの活用すれば室内の温度変化を抑えられ、冷暖房の効率を向上できます。
補助・助成制度の活用
政府や自治体では、省エネ投資をした企業に対して、補助金や助成金を支給しています。
例えば、「省エネ・非化石転換補助金」を活用すれば、省エネ設備・機器と非化石エネルギーを使用する設備・機器の導入・更新費用の一部について補助を受けられます。
中小企業の場合は補助率が最大で2/3、補助上限額は40億円です。工場や事業場において、既存の設備からエネルギー消費効率の高い設備へ更新する際に、有効活用しましょう。なお、2025年度の公募スケジュールは以下のように公開されています。
| 一次公募 | 2025年3月31日(月)~4月28日(月) |
| 二次公募 | 2025年6月上旬~7月上旬 |
| 三次公募 | 2025年8月上旬~9月上旬 |
また、東京都では「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業」を行っています。高効率空調設備やLED照明設備、高効率ボイラーなどの省エネ設備を導入した中小企業に対して、最大で5,000万円を補助しています。
補助金・助成金制度を活用すれば、自己負担を抑えつつ将来の電気代を節約できるでしょう。長期的に見れば投資額以上の節約効果が期待できるため、利用できる補助金や助成金がないか調べてみてください。
他社事例:省エネ・再エネ導入の成功ポイント

実際に、省エネに取り組んだり、省エネへの投資を通じてコスト削減に成功した企業の事例を紹介します。
山梨積水株式会社
山梨積水株式会社では、2019年4月に大型自家消費型太陽光発電設備を導入し、年間700MWh以上の発電を実現しました。発電量は工場の年間使用電力量の約6%に相当しており、電気代のコスト削減につながっています。
また、エネルギーマネジメントシステムを導入して不要電力の早期発見とコントロールを行うことにより、年間使用電力量の約27%を削減しています。合計で30%以上の消費電力の節約につながっているため、効果的な取り組みといえるでしょう。
株式会社ローソン
コンビニでおなじみのローソンは、2008年2月から検証として、42店舗にLED店内照明を導入しました。検証結果を踏まえて、2009年6月以降の新店舗の看板や店内照明に改良型のLED照明を導入しました。
光のムラを解消したり、環境に応じた照度調整したり工夫を重ねた結果、店舗全体の照明に関して約35%(店舗全体の電気消費量の約5.4%)の消費電力削減に成功しています。
このように、LED照明に変更するだけでも、年間の電気代を5%程度節約できます。従来の電球や蛍光灯を使用している場合、LEDへの変更を検討するとよいでしょう。
まとめ:消費電力を抑える方法を実践して利益率を向上させよう
政府による補助が終了することで、企業にとって電気代はますます負担の大きい支出となる事態が考えられます。特に昨今はさまざまなコストが上昇しているため、自社の利益を守るためにも、コスト意識を持つことは大切です。
企業が電気代の値上げに対抗する手段として考えられるのが、「エネルギー使用量の削減」「再生可能エネルギーの活用」「新たな電力契約・サービスの検討」「空調の最適化」「補助・助成制度の活用」です。
自社の中でも、「消費電力を抑えるための工夫はないか」を、意識的に考えてみてください。あわせて、省エネの設備投資を通じて、長期的な視点で電気代の節約をすることも効果的です。
創業手帳が発行する「補助金ガイド」では、中小企業の経営や事業継続に関するお役立ち情報、最新の補助金・助成金制度に関する情報をお届けしています。また、都道府県別の最新の補助金・助成金情報を知れる「補助金AI」も無料でご利用いただけるので、ぜひご活用ください。
また、経費の取り扱い方についてわかりやすくまとめた「経費で損しないためのチェックリスト」もご用意しています。コスト削減の重要性が高まっている今こそ、経費削減のポイントや適切な節税手段を知っておきましょう。

(編集:創業手帳編集部)