会社売却の注意点とは?失敗しないポイントやおすすめの相談先なども解説
会社売却はメリットもあるが注意すべきポイントが多い!

会社売却は、まとまった資金が手に入ったり事業の整理や継続ができたりするなど、魅力的なメリットが多々ある一方で、注意点も数多く存在します。
そこで今回は、会社売却の注意点や失敗しないためのポイント、会社売却の際におすすめできる相談先を紹介します。
また、会社の売却件数が増えた理由についても解説するため、会社売却やM&Aを検討中の人はぜひ最後まで読んでみてください。
創業手帳ではM&Aに関して初歩的なところから解説した「中小企業のためのM&Aガイド」を無料でお配りしています。あわせてご活用ください。
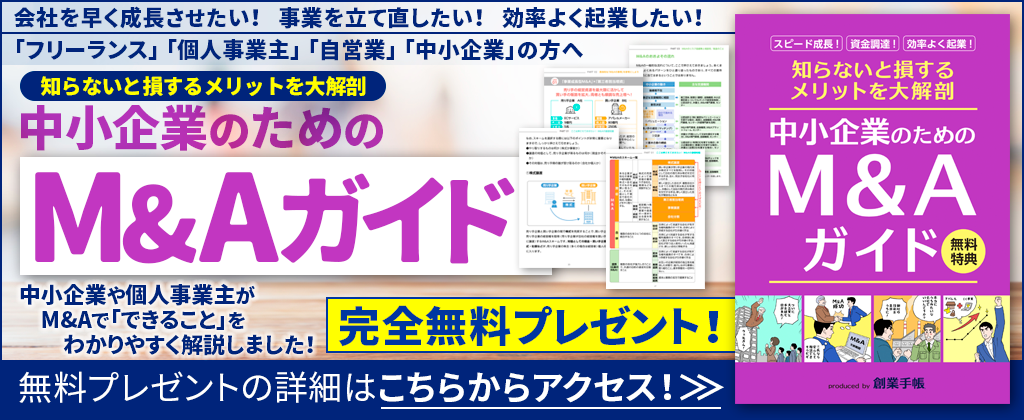
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
中小企業の会社売却が増えた背景

日本ではM&Aが最盛期です。コロナ禍の1年を除き、M&Aの実施件数は右肩上がりで増加しています。
M&Aが増えている理由として挙げられるのが、大企業だけではなく、多くの中小企業経営者も会社を売りたいと考えているということです。
以下では、会社を売りたいと考える中小企業の経営者が増えた理由を詳しく見ていきます。
後継者問題
後継者がいない場合、経営者が引退となれば会社は廃業するほかありません。
そうなれば、従業員は解雇され職を失います。また取引先や仕入れ先も、経営に支障をきたす可能性があります。
しかし、会社を売却して新たな経営者に引き継ぎできれば、廃業せず会社を存続させることが可能です。
日本の中小企業のうち、後継者がいない会社は半数以上といわれています。
以前に比べれば、後継者不在の割合は減少傾向にあるとのことですが、まだまだ安心できるレベルではありません。
新型コロナウイルスの影響
2020年に流行した新型コロナウイルス感染症は、リーマンショックを乗り越えた世界経済に甚大なダメージを与えました。
日本も例外ではなく、新型コロナウイルスの流行により経営難に陥った中小企業も多く、廃業を避けるためにM&Aを選択した中小企業が増加したといわれています。
大型M&Aよりも小規模・中規模のM&Aのほうが増加傾向にあることから、中小企業もM&Aに積極的だったことがわかります。
経営の安定化
経営者の中には、経営の安定化を目的に、会社を売却したいと考えるケースも多くあります。
資本力のある企業に会社を売却すれば、親会社からの資金面でのバックアップに期待できることが理由です。
中小企業は、資金面に余裕がなければ経営が不安定になることも珍しくありません。
しかし、M&Aによって資金面に余裕ができれば、資金繰りの心配から解放され、経営に集中できます。
イグジット戦略の採用
イグジット戦略の採用もM&Aが増加している理由のひとつといわれています。
イグジットとは、創業者や投資が企業の株式などを売却し、起業時にかかった資金を回収することです。
イグジットする方法やタイミングを決めることを、イグジット戦略といいます。
M&Aによるイグジットを実施した起業家は、経営者としての手腕を評価される傾向にあり、その後の起業時にはベンチャーキャピタルなどから資金調達しやすくなります。
そのため、近年は積極的にM&Aを行い、イグジット達成後にまた新たな事業を手掛ける起業家が増えているのです。
会社売却における注意点

増加傾向にあるM&Aは、必ずしも希望どおりに事が進むとは限りません。
会社を売却する際は、不要なトラブルを避けるためにも注意点を把握しておいてください。ここからは、会社を売却する際の注意点を紹介します。
希望の条件で売れない場合がある
会社を売却する場合、希望額や条件を設定した上で買い手を探す必要がありますが、必ずしも買い手が見つかるとは限りません。
また、買い手が見つかったとしても、希望より低い価格を打診されることもあります。
譲歩せず希望どおりの条件で進めようとした場合、売却するのが難しくなる可能性があります。
会社を売却するためには、ある程度条件を譲歩するなど譲り合うことが大切です。交渉を円滑に進めたいなら、妥協点をあらかじめ決めておいてください。
タイミングがずれると失敗しやすい
会社を売却するのに最適なタイミングとして、業界再編が行われている時期が挙げられます。
この時期は買収に積極的な企業が多く、売却する側に有利に進めやすいことが理由です。
反対に、業界再編が落ち着きタイミングを逃してしまえば、買い手を見つけるのが難しく、希望どおりの条件で売却できないかもしれません。
会社を売却する際は、タイミングを逃さないよう準備をすることが大切です。
ロックアップが設けられる可能性がある
ロックアップとは、買収した会社の役員や従業員に引継ぎのために一定期間在籍してもらうことで、キーマン条項とも呼ばれています。
業績の悪化や買収による混乱を避け、事業をうまく進めるため設定されるものですが、会社を売却しても一定期間は業務を継続しなければいけません。
そのため、すぐに引退したい人や、新たな事業を始めたいと考える人にとっては、ロックアップの存在がネックになる可能性があります。
売却先を探すのに時間がかかってしまう
会社の売却はすぐにできるものではありません。
希望する条件に合う相手を探さなければならず、もし買い手が見つかったとしても条件が折り合わなければ交渉が難航するケースもあることが理由です。
また、会社を売却するためには様々な工程をこなす必要があり、すべての手続きを終えるまでに1年以上かかることも珍しくありません。
会社の売却には時間がかかる可能性があることを考慮しておいてください。
従業員の雇用条件が悪化する恐れがある
会社を売却する場合、従業員の処遇や雇用条件を確認しておくことも大切です。売却には、会社そのものを売却する株式譲渡と、会社の一部を売却する事業譲渡があります。
株式譲渡では、従業員の雇用契約も含めたすべてが買い手に引き継がれます。
しかし、事業譲渡の場合、会社と従業員の契約は解消され、従業員は新たに買い手企業と雇用契約を結ぶことになるでしょう。
そのため、従業員の雇用条件が悪化したり、場合によっては失業したりすることがあることに注意が必要です。
取引先・顧客との関係が変わるリスクがある
会社を売却することにより、取引先や顧客との関係が変わるリスクがあることも、注意しなければならないポイントのひとつです。
売却によって事業内容や契約内容に変更が生じた場合、取引先や顧客との関係が悪化する可能性があります。
また、担当者が変わることで、これまで築いていた信頼関係が崩壊し、事業に影響を及ぼすこともあるかもしれません。
会社を売却する際は、売却後も取引先や顧客と良好な関係を維持できるよう配慮が求められます。
株式の譲渡所得に対して税金が発生する
会社売却では、株式の譲渡所得に対し税金が課せられます。課税対象は、総収入金額から取得費や各種手数料などの必要経費を差し引いた金額で、税率は20.315%です。
なお、20.315%の内訳は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%で、復興特別所得税は2037年までの時限措置です。
経営者が受け取れる売却益は、これらの税金が差し引かれた後の金額となります。
税金額によっては売却後の計画に支障をきたす可能性もあるため、十分に考慮しておくことが大切です。
売却後に競業避止義務が発生する
競業避止義務とは、使用者と競合する業務を行わない義務のことで、競業する事業を起こしたり、競業他社に就職したりすることを禁止するものです。
会社を売却した後に、経営者が同じ事業を展開した場合、買い手が不利益を被る可能性があります。
会社法では、譲渡日から20年間、特約があれば30年間、売り手が同一事業を行うことを禁止しています。
会社を売却する際は、売却後に競業避止義務に該当する行為を行うことがないよう、注意してください。
会社売却で失敗しないためのポイント

ここからは、会社売却で失敗しないためのポイントを詳しく見ていきます。
目的を明確にして現状を分析する
会社を売却する目的は企業によって異なります。売却する上で優先したい条件も様々です。
会社売却で失敗しないためには、目的を明確にして自社の現状を分析することが大切です。
売却する目的や譲れない条件などを明確にしたり、自社の強みや弱みを正しく把握して現状分析したりすることで、理想の買い手のイメージが固まり、候補先の選定や交渉がスムーズに進むかもしれません。
企業価値を正しく把握する
売却先との交渉をスムーズに進めるためには、自社の企業価値を正しく把握することが大切です。
交渉の場で売り手と買い手が互いの希望条件をぶつけるだけでは、話はまとまりません。また、相手の希望条件に対する譲歩ができないこともあります。
そのため、適切に企業評価を行うことが望ましいです。
企業評価を行い、企業価値を把握できれば、売却を進める上でのリスクを洗い出すことにもつながります。
従業員に丁寧な説明・サポートを行う
友好的にM&Aが行われた場合、従業員の雇用は継続され、売却後も同じように業務が行われることが一般的です。
しかし、M&Aが行われることを知った従業員には不安や動揺が広がる可能性があります。
そのため、M&Aを実施する場合は従業員の不安を解消できるよう、事実を正確かつ丁寧に伝えることや、対応策を講じてサポートすることが重要です。
会社売却時におすすめの相談先

最後に、会社を売却する場合におすすめできる相談先を紹介します。会社売却で失敗しないためにも、自分に合った相談先を選んでください。
事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎ支援センターは、国が設置する公的な相談窓口です。
親族内への承継や第三者への引継ぎなども含め、中小企業の事業承継に関するあらゆる相談に対応しています。
また、創業を目指す起業家と、後継者のいない企業と個人事業主を引き合わせる後継者人材バンクサービスなどの支援事業も行っています。
47都道府県すべてに設置されており、基本的には無料で利用することが可能です。
M&A仲介会社
M&A仲介会社は、売り手と買い手企業の間に立ち、双方の中立的かつ客観的な立場からM&Aが成約するようサポートする企業です。
仲介会社は様々あり、各企業によって特徴や強みが異なります。
利用する際は、費用をはじめ、アドバイスやサポート対応、得意分野などを確認した上で、自社に合うサービスを選んでください。
士業事務所
会計士や税理士、弁護士などの士業事務所も、M&Aに関する相談を受け付けています。
各士業事務所の得意分野にもよりますが、M&Aに関わる財務や法務などの専門的な知識を活かしたアドバイスやサポートが期待できます。
M&Aの中でも最も複雑で難しいといわれるデューデリジェンスも、士業事務所なら委託することが可能です。
経営コンサルタント・ファイナンシャルプランナー
経営コンサルタントやファイナンシャルプランナーもM&A仲介業務を行っています。
M&Aを検討する企業は、助言業務やサポートを受けることが可能です。ただし、中小企業よりも大企業を担当することが多い傾向にあります。
金融機関
銀行や証券会社などの金融機関もM&A仲介業務を行っており、M&Aに関する相談をすることが可能です。
金融機関であれば各支店間のネットワークを活かし、仲介会社とはまた違う情報によるサポートを受けられる可能性があります。
ただし、メガバンクや証券会社は、大企業を担当することがほとんどです。中小企業の場合は、地方銀行や信用金庫に相談すると良いかもしれません。
まとめ・注意点を押さえて適切な方法で会社売却を行おう
会社売却することで、資金を得られたり事業を継続できたりするなどのメリットがあるため、M&Aの実施件数は増加傾向にあります。
しかし、必ずしも希望の条件で売却できるとは限らず、タイミングがずれると失敗しやすいなど、注意しなければならない点も数多く存在します。
会社の売却を検討中の人は、今回紹介した内容を参考に、必要に応じて各専門機関に相談してみてください。
M&Aと聞くとまだネガティブなイメージをお持ちの方が多いかと思います。M&Aについての知識を正しく持っておくことは事業の成長にも関わる重要なことです。創業手帳ではM&Aに関して初歩的なところから解説した「中小企業のためのM&Aガイド」を無料でお配りしています。あわせてご活用ください。
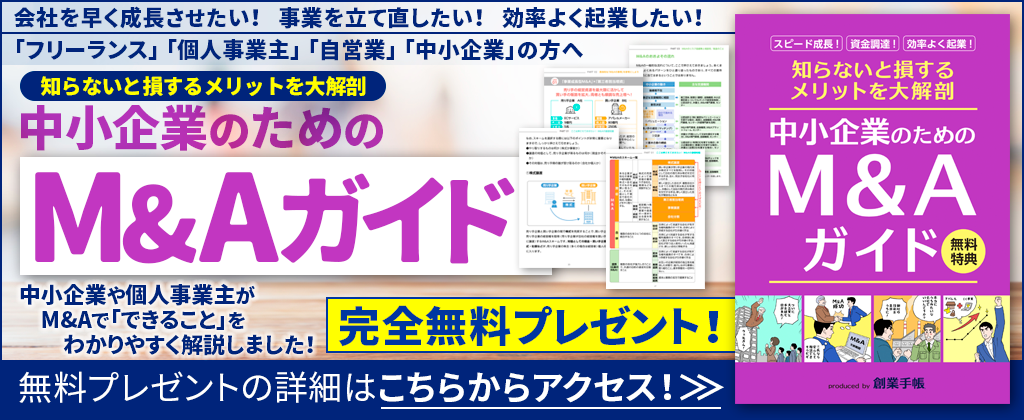
(編集:創業手帳編集部)




































