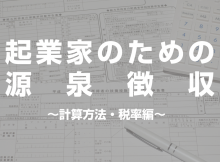【2025年改正】ふるさと納税はどう変わる?ポイント付与禁止・制度の今後を解説
ふるさと納税のポイント付与が10月から全面禁止に!改正後も続けるべき理由を解説

2025年10月1日から、ふるさと納税における仲介サイトのポイント付与が全面禁止となります。楽天ポイントやPayPayポイントなど、これまで寄付の大きなインセンティブとなっていた各種ポイント還元が一切受けられなくなるのです。
すでに2025年8月の寄付額は前年同期比で1.8倍以上に増加、8月最終週には3.1倍超という驚異的な伸びを見せており、9月には年末並みの「駆け込み寄付」が予想されています。この改正により、ふるさと納税の市場構造は大きく変わることになるでしょう。
今回は、2025年10月からのふるさと納税制度改正について、その内容と背景、事業者への影響、そして改正後も制度を活用すべき理由を、起業家・経営者の視点から解説します。
税金は避けられませんが、正しい知識で“余計な負担”を減らすことは可能です。
『税金チェックシート』には、納税額が数十万円単位で変わることもある重要な注意点を整理しました。
ふるさと納税を含め、税金で損をしないために、今すぐチェックしてみてください。無料でダウンロードできます。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
2025年10月からふるさと納税制度が改正される
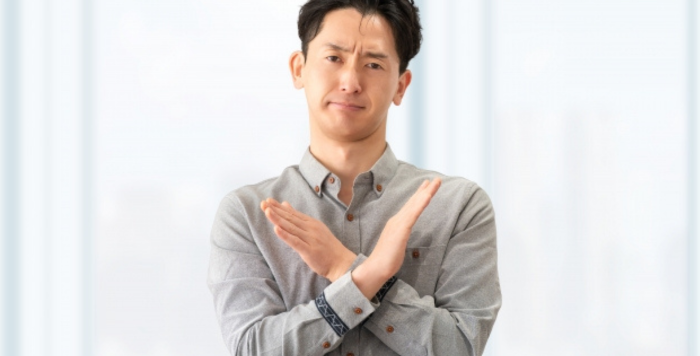 2025年10月1日より施行される今回の改正は、総務省が2024年6月25日に発表した「ふるさと納税の指定基準の見直し」に基づくものです。最大のポイントは、「寄附者に対しポイント等を付与するポータルサイト等を通じた寄附募集を禁止」することです。
2025年10月1日より施行される今回の改正は、総務省が2024年6月25日に発表した「ふるさと納税の指定基準の見直し」に基づくものです。最大のポイントは、「寄附者に対しポイント等を付与するポータルサイト等を通じた寄附募集を禁止」することです。
具体的には、総務省告示第203号において「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益を提供する者(第三者を通じて提供する者を含む)」を通じた募集が禁止されます。ただし、「通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当するもの」は除外されるため、クレジットカードの通常ポイント(1%程度)などは引き続き付与されます。
この改正により、楽天ふるさと納税の最大30%還元キャンペーンや、au PAYふるさと納税の10%ポイントバックといった大型還元施策は完全に姿を消すことになります。2023年度には約9,739億円と過去最高を記録したふるさと納税市場にとって、大きな転換点となることは間違いありません。
ふるさと納税の仕組みと改正ポイント
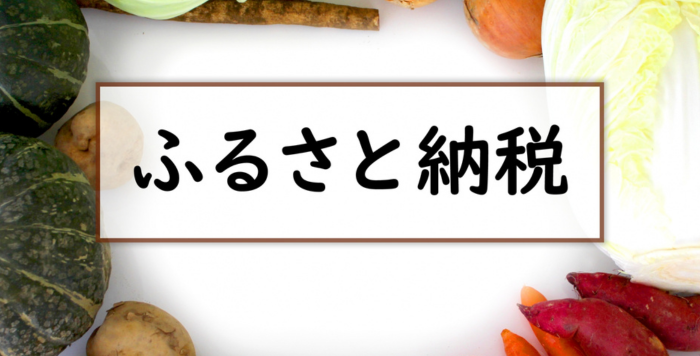 ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付することで、寄付額から2,000円を引いた金額が所得税・住民税から控除される制度です。本来の目的は、都市部に集中する税収を地方に分散させ、地域経済の活性化を図ることにあります。
ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付することで、寄付額から2,000円を引いた金額が所得税・住民税から控除される制度です。本来の目的は、都市部に集中する税収を地方に分散させ、地域経済の活性化を図ることにあります。
寄付者にとっては、実質2,000円の負担で全国各地の特産品を受け取れるメリットがあります。また自治体にとっては住民以外からも財源を確保できる手段となっています。
ふるさと納税は返礼品を通じて地域の魅力を全国に発信し、地場産業の振興や関係人口の創出にもつながる制度です。2008年の開始以来、市場規模は拡大を続けてきました。2023年度には約9,739億円と過去最高を記録し、地方創生の重要な柱として定着しています。
以下では、今回の改正の焦点となる「ふるさと納税のポイント付与」の実態と、2025年10月からの改正内容について詳しく解説します。
ふるさと納税のポイント付与とは
ふるさと納税のポイント付与とは、仲介サイトが独自に提供していた寄付金額に応じたポイント還元サービスのことです。代表的なものとして、楽天ふるさと納税の楽天ポイント、au PAYふるさと納税のPontaポイント、ふるなびのAmazonギフト券コードなどがありました。
これらのポイントは、通常の買い物と同じように付与され、多くの場合寄付額の3〜5%、キャンペーン時には10〜30%という高還元率を実現していました。例えば、10万円の寄付で最大3万円分のポイントが戻ってくるケースもあり、実質的な負担を大幅に軽減する仕組みとして機能していたのです。
仲介サイトにとっても、ポイント還元は他社との差別化や新規顧客獲得の最大の武器でした。実際、楽天ふるさと納税は楽天市場の会員基盤を活かし、全寄付額の30〜40%程度のシェアを占めるまでに成長しています。
2025年10月からポイント付与全面禁止に
改正後は、仲介サイトを通じた寄付に伴うすべてのポイント付与が禁止されます。これには楽天ポイント、PayPayポイント、Amazonギフト券など、あらゆる形態の経済的利益が含まれます。
ただし、重要な例外があります。クレジットカード決済やQRコード決済の通常ポイントは、「通常の商取引に係る決済に伴って提供されるもの」として除外対象となります。つまり、楽天カードで決済した際の通常の1%ポイントや、PayPay決済の基本還元分は引き続き獲得可能です。
この線引きのポイントは、「ふるさと納税だから特別に付与されるポイント」か「通常の決済で付与されるポイント」かという点にあります。前者は禁止、後者は継続という明確な区分けがなされたわけです。
ふるさと納税改正の背景
 総務省が今回の改正に踏み切った背景には、本来の制度趣旨からの逸脱があります。ふるさと納税は本来、都市部に集中する税収を地方に分散させ、地域活性化を図ることが目的でした。寄付者が応援したい自治体を選び、その地域の特産品を通じて交流を深める仕組みとして設計されていたのです。
総務省が今回の改正に踏み切った背景には、本来の制度趣旨からの逸脱があります。ふるさと納税は本来、都市部に集中する税収を地方に分散させ、地域活性化を図ることが目的でした。寄付者が応援したい自治体を選び、その地域の特産品を通じて交流を深める仕組みとして設計されていたのです。
しかし実態は、「どのサイトで寄付すれば最もポイントが多くもらえるか」が寄付先選定の最大の基準となっていました。自治体や返礼品の魅力ではなく、仲介サイトのポイント還元率で寄付先が決まる状況は、明らかに制度趣旨に反するものでした。
さらに、ポイント競争の激化により、仲介サイト間の消耗戦も深刻化していました。楽天やPayPayといった大手プラットフォームは資金力を背景に高還元率を実現できる一方、中小の仲介サイトは競争から脱落する構図が生まれていたのです。
総務省の原文では、この状況を「寄附金の使途や地域の魅力に着目した寄附」へと転換する必要性を強調しています。今回の改正は、ふるさと納税を本来あるべき姿に戻すための、いわば「リセット」と位置づけられるでしょう。
ふるさと納税は2025年9月までの寄付がお得!
 2025年9月は、ポイント還元を受けられる最後のチャンスとなります。すでに市場では「駆け込み寄付」の動きが顕著に表れており、さとふるの2025年8月最終週の寄付額は前年同期比3.1倍超を記録しました。
2025年9月は、ポイント還元を受けられる最後のチャンスとなります。すでに市場では「駆け込み寄付」の動きが顕著に表れており、さとふるの2025年8月最終週の寄付額は前年同期比3.1倍超を記録しました。
過去の事例を見ると、2023年10月の制度改正(募集経費の見直し)の際には、9月の寄付額が前年の4.5倍に急増し、年末並みの水準に達しています。今回も同様のパターンが予想され、2025年9月は「第二の年末商戦となる可能性が高いでしょう。
駆け込み寄付を検討している方は、以下の点に注意が必要です。まず、返礼品の在庫切れや配送遅延のリスクが高まります。人気の返礼品は早めに品切れとなる可能性があるため、注意してください。
また年間の寄付上限額を超えないよう注意が必要です。ポイント目当てで過剰に寄付してしまうと、控除限度額を超えた分は純粋な持ち出しとなってしまいます。事前にシミュレーションサイトなどで自身の控除上限額を確認しておきましょう。
ふるさと納税は改正後もお得な制度
 ポイント付与が禁止されても、ふるさと納税の基本的なメリットは何も変わりません。むしろ、制度本来の魅力が際立つことになるでしょう。
ポイント付与が禁止されても、ふるさと納税の基本的なメリットは何も変わりません。むしろ、制度本来の魅力が際立つことになるでしょう。
第一に、実質負担2,000円で返礼品が受け取れる仕組みは継続します。寄付額から2,000円を除いた分が所得税・住民税から控除される基本構造に変更はありません。また、返礼品の価値を寄付額の3割以下とする「3割ルール」も維持されるため、返礼品の質が急激に低下することもないでしょう。
第二に、ワンストップ特例制度も引き続き利用可能です。確定申告が不要な給与所得者で、寄付先が5自治体以内であれば、簡単な手続きで税額控除を受けられます。この利便性は改正後も変わりません。
そして最も重要なのは、返礼品の本来の価値で勝負する時代になることです。これまでポイント還元に隠れていた「地域の魅力」「商品のストーリー」「生産者の想い」といった要素が前面に出てきます。地方の優れた産品や体験型サービスを、純粋に評価して選ぶことができるようになるのです。
実際、地域ブランドの構築に成功している自治体は、ポイント競争に頼らずとも安定した寄付を集めています。北海道の海産物、宮崎県の和牛、山梨県のワインなど、確固たるブランド力を持つ返礼品は、改正後も変わらぬ人気を維持するでしょう。
ふるさと納税改正の影響―地方企業と仲介サイトは再編必至
 今回の改正は、ふるさと納税に関わる事業者に大きな影響を与えます。とりわけ地方企業と仲介プラットフォームにとっては、ビジネスモデルの転換を迫られる重大な局面となるでしょう。
今回の改正は、ふるさと納税に関わる事業者に大きな影響を与えます。とりわけ地方企業と仲介プラットフォームにとっては、ビジネスモデルの転換を迫られる重大な局面となるでしょう。
地方企業への影響は業種によって大きく異なります。食品加工業(精肉・海産物・果物)や酒造・飲料メーカーなど、ふるさと納税経由の売上が年間収益の30〜50%を占める企業も少なくありません。これらの企業は、ポイント目当ての寄付者が減少することで、一時的な売上減少に直面する可能性があります。
しかし、これは「商品力で勝負する時代」への転換点とも捉えられます。差別化の軸が「ポイント還元率」から「商品の品質・ストーリー・希少性」へと移行することで、本当に優れた商品を持つ企業にはむしろチャンスが広がります。伝統工芸品や地域限定の体験型サービスなど、独自性の高い返礼品を提供する企業は、改正後も堅調な需要が期待できるでしょう。
仲介プラットフォームへの影響は甚大
仲介プラットフォームへの影響はさらに深刻です。楽天やPayPayなど、ポイント還元を最大の武器としていたサイトは、根本的な戦略転換を余儀なくされます。すでに各社はUI/UXの改善、検索機能の充実、地域ストーリーの訴求など、ポイント以外での差別化を急ピッチで進めています。
またサブスク型サービスや寄付金の使途可視化機能など、新たな付加価値サービスの開発も活発化しています。「寄付金がどのように使われたか」を追跡できる機能や、寄付者と自治体をつなぐコミュニティ機能など、「体験価値」で勝負する動きも活発化するかもしれません。
マーケティング・広告業界にとっては、新たなビジネスチャンスが生まれています。自治体や地元企業から「返礼品のブランディング」「SNS広告運用」「ストーリーテリング」などの依頼が急増すると予想されます。地方創生×デジタルマーケティングという新市場が立ち上がりつつあるのです。
まとめ
2025年10月からのふるさと納税制度改正により、仲介サイトのポイント付与は全面禁止となります。これは単なる規制強化ではなく、制度を本来あるべき姿に戻すための必要な措置といえるでしょう。
ユーザー目線では、ポイント還元を受けられる最後のチャンス、9月中の「駆け込み寄付」がおすすめです。10月以降は「返礼品の価値」と「地域の魅力」で勝負する新たな競争が始まるでしょう。ポイント依存から脱却し、商品力やブランド力を磨いてきた地方企業にとっては、むしろ好機となる可能性があります。
また改正後もふるさと納税は、地方創生と節税を両立できる利用者にとってはメリットのある制度として存続します。むしろ、本来の価値で評価される健全な市場へと生まれ変わることで、持続可能な地域経済の発展に貢献する制度として、新たな段階に入るのではないでしょうか。経営・マーケティングの視点では、仲介サイトの今後の動向に注目です。
ふるさと納税のルールが変わるように、税制は毎年のように改正されます。
知らないうちに損をしてしまうことのないよう、節税の基本を整理しておくことが大切です。
創業手帳オリジナルの『税金チェックシート』では、事業に役立つ節税のポイントをわかりやすくまとめています。ぜひ合わせてご確認ください。無料でダウンロードできます。

(編集:創業手帳編集部)