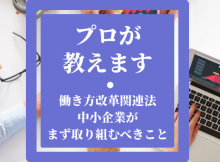役員退職金はどのように準備する?7つの方法と向いている企業の特徴を解説
中小企業の事業主・役員も計画的に老後へ備えよう

役員退職金とは、代表取締役や取締役など、役員に対して支給する退職金です。通常の労働者に対して支給する退職金とは異なり、役員退職金規程で計算方法や支給方法などを定める必要があります。
役員退職金を導入すれば、企業としては法人税を節税できたり、事業承継をスムーズに行えたりするメリットがあります。また、役員が自分の業務に注力するためにも、役員退職金の導入は有意義です。
今回は、役員退職金を準備するメリットや具体的な7つの方法を解説します。損金算入するための適切な役員退職金を設定する方法も解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
役員退職金とは?

役員退職金は、会社への貢献に対して支給される報酬です。どのような役員が支給対象者となるのか、また支給するための条件は何かを確認しましょう。
支給対象者と条件
役員退職金は、会社の取締役・監査役などの役員が支給対象者となります。会社法361条により、「定款の定め」または「株主総会の決議」によって支払いが決まる旨が定められています。
役員退職金を適切に支給するためには、あらかじめ定款で役員退職金に関する事項を定める必要があります。しかし、多くの企業は定款で退職金に関する内容を定めていないため、株主総会または取締役会で具体的な金額や支給時期などを決定するのが一般的です。
なお、役員退職金は法律で支給が義務付けられたものではありません。制度の有無だけでなく、会社ごとに支給額の算定方法や支給時期は異なります。
役員退職金の種類

役員退職金は、退職・勇退したときに支給される「退職慰労金」と、死亡したときに支給される「死亡退職金」にわかれます。
役員退職慰労金
退職慰労金は、役員が任期満了・勇退・辞任・解任などの理由により、退任するタイミングで支給される退職金です。労働者に対する退職金と同じように、これまでの貢献や功績に対する感謝として、支給されます。
中小企業では、形式的に退任したあと、実質的に役員としての職務を継続するケースがあるかもしれません。この場合、「退職の事実がない」として税務署から退職金の支給が否認され、退職金を損金算入できない可能性があります。
役員死亡退職金
死亡退職金は、役員が在任中に死亡したとき、遺族へ支給される退職金です。遺族の生活保障や相続税を支払うための現金を用意する目的で、活用されています。
死亡時に支給されるため、受取人は役員の法定相続人(配偶者や子など)となるのが一般的です。税法上は「死亡退職金」として相続税の課税対象となり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられます。
退職慰労金と同様に、支給金額は役員退職金規程や定款で定めておくか、株主総会の決議を経て決定します。
役員退職金を準備するメリット

企業が役員退職金制度を導入し、準備を進めることで、節税を行えたりスムーズな事業承継を実現できたりするメリットがあります。
経営者をはじめとした役員のモチベーション向上にも寄与するため、企業全体で生産性の向上が見込めるでしょう。
1.法人税の節税につながる
役員退職金は、金額が確定した事業年度において損金算入ができます。損金算入できれば法人税の課税対象となる所得を圧縮できるため、法人税の節税につながります。
たとえば、法人税率が23.2%の会社が1,000万円の役員退職金を支払う場合で考えてみましょう。この場合、「1,000万円×23.2%=232万円」の節税効果を得られます。
ただし、支給する役員退職金は「適正な金額」である必要があります。税務署から、役員退職金額が「適正ではない(過大である)」と判断されると、適正額を超えた部分は損金算入できません。
適切な役員退職金の目安は記事の後半で詳しく解説するため、あわせて参考にしてみてくください。
その他にも、税金については知識があるかないかで支払い額が数十万円と変わるケースもあります。創業手帳では無駄な税金を支払わないためにも税金対策についてチェックできる「税金チェックシート」を無料でお配りしています。こちらもあわせてご活用ください。

2.事業承継をスムーズに行える
役員退職金制度があれば、役員は安心して退任後の生活を送れます。生活のために何年も役員を続ける必要がなく、後の世代へスムーズに事業承継ができるでしょう。
実務上では、役員退職金を支払う現金を用意するために、会社が役員が保有している株式を購入するケースがあります。会社が株式を買い取る(金庫株)ことで外部の人に株式を保有される事態を防ぎ、後継者が経営権を握りやすい環境を整備する効果も期待できます。
また、あらかじめ役員退職金規程を整備し、金額や支給条件を明確にすることで「いつ、どのような条件で事業承継をするか」という具体的な計画を立てられます。先代と後継者の双方が計画的に事業承継を進めるうえで、役員退職金の整備は効果的です。
3. 経営者のモチベーション向上につながる
役員は企業経営の意思決定に関与するため、一般的な労働者よりも重い責任を負います。退任時に業績や貢献度に応じた適切な報酬が支払われることを明示しておくことで、役員が在任中に企業価値の向上に注力しやすくなるでしょう。
功績や成果に応じた役員退職金を受け取れれば、目先の利益だけでなく、会社の長期的な成長や価値向上に注力するモチベーションが生まれます。
また、役員の中でも役職が上がるほど、受け取れる退職金額が増えるのが一般的です。これにより、「より大きな責任を引き受け、より高い成果を挙げる」というモチベーションの創出につながるでしょう。
4. 長期的な資金計画・経営管理の一環となる
役員退職金は、一度に大きな金額を支払うのが一般的です。
役員退職金規程を整備し、役員の退任時期や支払う退職金を決めておけば、退職金の支給を見越した資金計画を立てられます。たとえば、業績のよい年は退職金の積立てを増やし、業績の悪い年は抑えるといった調整が可能です。
これにより、将来のキャッシュアウトに備えた経営が可能になり、想定外の支出で資金繰りが苦しくなる事態を防げるでしょう。
また、役員退職金を支払うタイミングは役員の交代時期でもあります。経営者の退任時期や事業承継のタイミングなど「経営の節目」でもあるため、中長期的な経営計画を練り直すきっかけにもなるでしょう。
役員退職金を準備する7つの方法
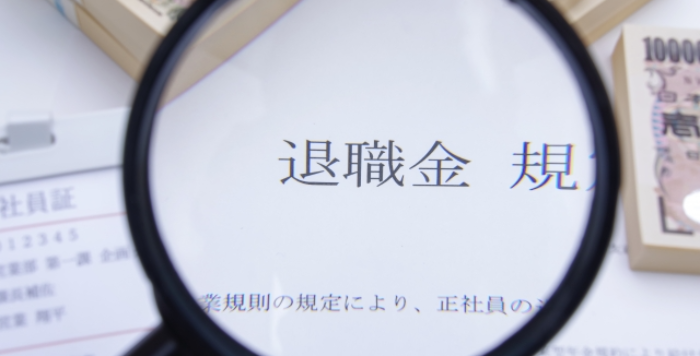
役員退職金を準備する方法は、主に7つあります。それぞれの特徴やメリット、向いている企業の特徴などを解説するため、自社の実情にあわせて導入を検討してみてください。
1.小規模企業共済制度に加入する
小規模企業共済制度とは、中小企業の経営者や役員が退職金を準備するための制度です。中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営しています。
毎月一定額を積み立て、廃業や退職時に共済金を受け取れる仕組みです。
| 主な特徴 | ・国が運営する制度で安全性が高い ・掛金は月額1,000円〜70,000円(500円単) ・掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象 ・受取時は退職所得または一時所得として課税される ・事業資金の貸付制度あり |
| メリット | ・掛金の全額所得控除による節税効果がある ・強制力のある積立で確実に準備できる ・決まった利回りで運用されるため、安全性が高い ・解約手当金を事業資金として活用できる |
| デメリット | ・加入対象者が限定されている ・掛金の上限(月額70,000円)がある ・積極的な運用ができない ・途中解約時にペナルティがある ・法人税の損金算入ができない |
| 向いている企業 | ・個人事業主や小規模法人 ・堅実に資産運用したい ・退職金の原資を確実に積み立てたい |
小規模企業共済の掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲で、500円単位で自由に設定が可能です。個人事業主の場合、掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として事業主の所得から控除できます(法人が納めた掛金に関しては、損金または必要経費には算入できません)。
小規模企業共済では、加入者が掛金を運用するのではなく、中小機構が運用します。基本的に1.0%の予定利率で運用されますが、実際の利回りは運用状況によって変動します。実際に、令和5年度の運用利回りは3.44%でした。
緊急時に事業資金を用意する手段として、貸付制度を利用できる点は小規模企業共済の特徴です。リスクを抑えて、安全かつ確実に役員退職金を用意したい方にとって、向いている制度といえるでしょう。
2.法人保険に加入する
生命保険会社は、経営者の万が一の事態に備えられる法人保険を取り扱っています。この法人保険には貯蓄性がある商品もあり、役員退職金を準備する手段として活用できます。
| 主な特徴 | ・法人が契約者・保険料負担者、役員が被保険者となる ・退職時の解約返戻金や死亡時の死亡保険金を退職金原資として活用できる ・複数の保険商品を組み合わせることが可能 |
| メリット | ・保険料は全額損金または一部損金算入が可能 ・保険料の損金算入による法人税の繰り延べ効果がある ・役員の急死時にも退職金の支払いが可能 ・契約者貸付による資金調達が可能 |
| デメリット | ・保険商品の選択や仕組みが複雑 ・短期解約時の解約返戻金は低額になる ・保険料の全額損金算入には条件がある ・定期的に保険料を支払う必要がある |
| 向いている企業 | ・役員の死亡リスクに備えたい ・計画的に退職金を準備したい |
役員退職金として活用できる法人保険は、「定期付養老保険」「逓増定期保険」「長期平準定期保険」などさまざまです。支払った保険料は原則として全額損金算入でき、保険金を受け取ったときに収入として計上するため、税金の繰り延べ効果があります。
役員が在任中に死亡するという予期せぬ事態が発生した場合でも、保険金により遺族や退職金を渡せる点は、法人保険を活用するメリットです。
ただし、保険契約から短期間で解約すると、受け取れる解約返戻金が支払った保険料を下回ります。契約期間が短いほど受け取れる解約返戻金は少額になり、損失が大きくなってしまう点に留意しましょう。
3.預金を積み立てる
預金積立は、会社が計画的に退職金用の貯金をする方法です。普通預金・定期預金・決済性預金など、積立用で使用する口座はさまざまです。
| 主な特徴 | ・特別な手続きなく簡単に開始できる ・普通預金、定期預金、決済性預金などを活用する |
| メリット | ・手続きが簡単 ・引き出しの自由度が高く資金繰りに柔軟に対応できる ・積立額の増減を自由に調整できる ・運用リスクがない ・手数料や管理コストが低い ・会計処理がシンプル |
| デメリット | ・税制優遇がなく節税効果がない ・低金利環境では運用益がほとんど期待できない ・業績が悪いと予定通りの積立が難しい場合がある ・事業資金と混同するリスクがある ・インフレに弱い |
| 向いている企業 | ・キャッシュフローに余裕がある ・資金使途の柔軟性を重視している ・自社のペースで退職金を用意したい |
預金を積み立てて役員退職金を用意する場合、預金口座を開設するだけで、すぐに始められます。自社のペースで積み立てられるため、お金の自由度・流動性を重視している企業に向いています。
預金は元本保証であるため、元本割れのリスクがありません。安全確実に資金を積み立て、手数料や管理コストを抑えられるメリットがあります。
ただし、リスクがほとんどない分、リターンも期待できません。運用により効率よく資産を増やせず、インフレによる目減りが生じる可能性がある点に注意が必要です。
4.個人型確定拠出年金制度(iDeCo)に加入する
個人型確定拠出年金制度(iDeCo)とは、会社ではなく役員が個人で加入して、自分専用の退職金を準備する制度です。自分で掛金を拠出し、自分の責任で運用します。
| 主な特徴 | ・役員個人が掛金を拠出し自己責任で運用する制度 ・掛金は月額5,000円から68,000円まで(働き方により上限額が異なる) ・掛金は全額所得控除の対象 ・60歳以降に年金または一時金として受け取る |
| メリット | ・掛金の全額所得控除による所得税・住民税の節税効果がある ・運用益に対する課税がなく複利効果が高い ・受取時に退職所得控除または公的年金等控除が適用される ・元本変動型商品(投資信託)と元本確保型商品(定期預金・保険など)で、自分で運用商品を選べる ・法人の資金繰りに影響せず、役員個人で準備できる |
| デメリット | ・60歳まで原則として引き出せない(途中解約不可) ・運用責任は役員個人が負う ・運用結果次第では資産が減少するリスクがある ・手数料がかかる(口座管理料、運用商品の信託報酬など) ・法人税の節税効果がない(法人の損金にならない) |
| 向いている企業 | ・退職金の準備を役員個人の判断に委ねたい ・企業規模や資金力に関わらず役員の自助努力を重視する ・複数の退職金準備方法を併用したい |
個人型確定拠出年金制度で拠出した掛金は全額所得控除となり、運用益は非課税、受取時も税制優遇が適用されます。「個人型」という名称のとおり、企業で制度を整備するのではなく、加入を希望する役員が個人で加入する仕組みです。
個人型確定拠出年金制度で受け取れる金額は、運用成績次第です。リスクを取って運用した結果、運用結果がよければ想定以上の退職金を用意できる可能性があります。
一方で、運用成績が悪いと拠出した掛金よりも受け取れる金額が下回る「元本割れ」が発生します。自分のリスク許容度に合わせた商品選択を行い、定期的な運用状況の確認と必要に応じて見直すことが大切です。
5.中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)に加入する
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは、取引先の倒産による連鎖倒産を防止するための共済制度です。解約時、最大で拠出した掛金の100%を返戻金として受け取れるため、役員退職金を準備する手段としても活用できます。
| 主な特徴 | ・中小企業の取引先倒産に備える共済制度 ・月額5,000円〜20万円(5,000円単位)で掛金を設定できる ・掛金の累計上限額は800万円 ・40ヶ月以上納付した場合、解約時に掛金の一部が戻る(最大で100%) |
| メリット | ・掛金は全額損金算入できる ・取引先倒産リスクへ備えられる ・取引先倒産時には掛金総額の10倍まで無担保・無保証人で借入可能 |
| デメリット | ・本来の目的は取引先倒産対策で、退職金準備が主目的ではない ・短期間での解約は解約手当金が大幅に減額される ・共済金の借入れを行うと解約手当金が減少する ・運用により増やせない |
| 向いている企業 | ・取引先の倒産リスクがある ・複数の退職金準備方法を併用したい |
経営セーフティ共済で拠出した掛金は、全額を損金(経費)として計上できます。解約時に手当金として掛金が戻ってきたときは課税対象になるため、税金の繰り延べ効果があります。
そもそも、経営セーフティ共済は中小企業の連鎖的な倒産を防ぐ趣旨の制度です。そのため、解約時に受け取れる金額は掛金の最大100%に留まり、運用により増やすことはできません。
つまり、経営セーフティ共済は取引先が倒産した場合のような、事業経営におけるリスクへの備えとして活用すべきです。あくまでも、退職金の用意は副次的である点に留意しましょう。
6.企業型確定拠出年金制度(企業型DC)を導入する
企業型確定拠出年金制度(企業型DC)は、企業が従業員や役員のために掛金を拠出し、加入者自身が運用する年金制度です。役員が自分自身の退職金を準備する手段としても活用できます。
| 主な特徴 | ・企業が掛金を拠出し、加入者が自己責任で運用する制度 ・掛金は企業規約で定めた範囲内で設定できる(上限55,000円) ・役員・従業員ともに加入可能 ・60歳以降に年金または一時金として受け取る |
| メリット | ・掛金の全額損金算入による法人税の節税効果がある ・加入者が得る運用益に対する課税がなく、複利効果が高い ・従業員も含めた退職給付制度として一元管理できる ・元本変動型商品(投資信託)と元本確保型商品(定期預金・保険など)で、自分で運用商品を選べる ・企業が倒産しても資産は保全される ・役職に応じて掛金設定額に差をつけることが可能 |
| デメリット | ・厚生局への届出や運営管理機関の選定など、制度導入・維持に一定のコストと手間がかかる ・途中で運用資産を引き出せない ・運用責任は加入者が負う ・事前に制度設計が必要 ・他の退職金制度との調整が必要な場合がある |
| 向いている企業 | ・役員と従業員の両方に退職給付を提供したい ・法人税の節税効果を重視したい ・企業として運用責任を負いたくない ・退職金の将来債務を確定させたい ・福利厚生を充実化させて長期的な人材確保・定着を図りたい |
確定拠出年金法では、企業型DCの設立に人数要件は設けられていません。企業型確定拠出年金制度は、厚生年金の適用事業所であれば、企業規模に関係なく導入できます。企業として確定拠出年金制度を導入して掛金を拠出し、加入する従業員や役員が、個人の責任で運用します。
企業が拠出する掛金は全額損金算入が可能で、将来債務が発生しません。企業としては財務的なリスクを負わないため、中小企業にとって導入しやすい制度といえるでしょう。
制度の導入・維持にあたって、手間とコストが発生する点に注意が必要です。運営管理機関ごとに手数料体系やサポート体制が異なるため、複数の機関を比較検討したうえで、制度の導入を検討してみてください。
7.有価証券で運用しながら用意する
有価証券(株式・債券・投資信託など)で運用しながら、退職金を用意する方法もあります。預金よりも高いリターンが期待できるため、リスクを取って運用できる財務的な余力がある場合、検討の余地があるでしょう。
| 主な特徴 | ・会社名義での投資となり、会社の資産として計上する ・退職金支給時に有価証券を換金または現物支給する |
| メリット | ・預金以上の運用益(配当、利息、値上がり益)を期待できる ・特別な契約や制度加入は不要 ・換金性・流動性が高く現金化しやすい ・投資対象や運用スタイルを柔軟に選択できる ・インフレヘッジ効果が期待できる ・配当や利息による定期的な収入を得られる ・投資の分散化により、リスク調整ができる |
| デメリット | ・価格変動リスクがあり、元本割れの可能性がある ・運用益は法人税の課税対象となる ・特別な税制優遇措置がない ・専門的な投資知識や運用判断が求められる ・退職金準備資金と事業資金の区分が曖昧になりやすい |
| 向いている企業 | ・余剰資金が豊富 ・運用する財務的な余力がある ・金融・投資の知識や経験がある ・長期的な視点で運用できる |
有価証券で役員退職金を用意する場合、運用益や値上がり益を含めた資産が、支給する退職金の原資となります。預金以上のリターンが期待できるため、リスクを取って運用したい方に向いている方法です。
有価証券を売却して得た資金から退職金を支給(現金支給)するか、有価証券のまま役員に退職金として支給する(現物支給)ことも可能です。運用方法だけでなく、支給方法も柔軟に決定できる点は、有価証券を活用するメリットです。
ただし、企業名義で運用するため、運用益は法人税の課税対象です。また、有価証券には運用リスクがあるため、財務的な余裕や金融・投資の知識が求められる点に注意しましょう。
制度を併用することも可能
これまでに紹介してきた役員退職金制度を、複数併用することも可能です。代表的な併用方法として、以下が挙げられます。
- 企業型確定拠出年金と小規模企業共済
- 企業型確定拠出年金と中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
- 企業型確定拠出年金とiDeCo
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金は、リスクを取って運用できる特徴があります。一方で、小規模企業共済や中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、保守的な制度といえるでしょう。
それぞれを組み合わせることで運用のリスクを軽減し、安全かつ確実に役員退職金を用意できます。もちろん、上記の組み合わせに加えて預金や有価証券を活用し、さらに方法を分散させても問題ありません。
自社の財務状況にあわせて、適切な方法で役員退職金の準備を進めましょう。
適切な役員退職金の金額とは

支給する役員退職金は、適正な金額でなければ、全額を損金算入できません。「適切な金額」の考え方について解説します。
功績倍率法による算定が一般的
役員退職金は、「功績倍率法」という方法に基づいて計算するケースが一般的です。「最終役員報酬×在任年数(役員としての勤続年数)×功績倍率」という計算式で算出します。
功績倍率の一般的な目安は、以下のとおりです。
| 役職 | 一般的な功績倍率 |
| 会長・社長 | 3.0 |
| 専務取締役 | 2.5 |
| 常務取締役 | 2.0 |
| 取締役 | 1.5 |
| 監査役 | 1.0〜1.5 |
たとえば、「最終報酬月額50万円・在任期間15年・功績倍率3.0」の社長が受け取る役員退職金は、「50万円×15年×3.0=2,250万円」です。
最終的に、役員退職金が適切かどうかは同業他社との比較や従業員との均衡など、さまざまな観点から評価されます。
税務上の注意点と損金算入の上限
税務署から「役員退職金が過大」と指摘される事態を防ぐためにも、事前に役員退職金規程や定款で計算方法を定めておくとよいでしょう。また、株主総会や取締役会での議事録を保管し、役員退職金を決定した経緯を説明できるように備えることも大切です。
なお、役員退職金が過大でなければ、全額を損金算入できます。後になって指摘を受けないためにも、事前に同業類似法人の支給水準と照らし合わせ、自社で設定している水準が適切かどうかを確認しましょう。
また、退任直前に役員報酬を引き上げると、不当な操作と見なされる可能性があります。さらに、形式的な退任ではなく、実質的な退職の事実が求められる点にも注意が必要です。
まとめ:適した方法で役員退職金を準備しよう
役員退職金を準備する方法次第では、法人税を節税できます。また、スムーズな事業承継を実現したり、経営者のモチベーション向上につながったり、企業経営の面でもよい影響が期待できるでしょう。
役員退職金を用意する方法は主に7つあり、それぞれ特徴やメリットが異なります。自社の財務状況や用意したい金額などに応じて、適した制度を導入しましょう。
創業手帳(冊子版)では、退職金を準備する方法をはじめ、中小企業の経営者に役立つ情報を掲載しています。資金繰りや人材採用に関する情報など、企業経営で欠かせない情報もお伝えしていますので、ぜひ有効活用してください。
(編集:創業手帳編集部)