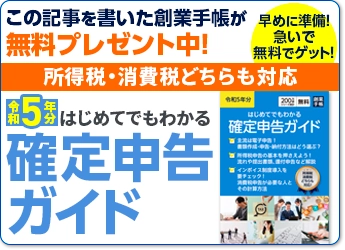退職金を受け取ったら確定申告は行う?退職金にかかる税金や申告が必要なケースを解説
退職金を受け取っても確定申告は原則不要!

法人によって高額な退職金を受け取るケースがあるため、受け取った後に確定申告が必要なのか気になるところです。
結論からいうと、退職金の確定申告は原則不要です。しかし、確定申告が必要となる特殊なケースがあるので注意してください。
そこで今回は、退職金による確定申告が必要なケースや確定申告をやっておいたほうがよいケース、受け取り方別の課税方式の違いなどについて解説します。
将来退職金を受け取る予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
創業手帳では「難しい」と思われがちな確定申告について、基本からわかりやすく解説した「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。はじめての方はもちろん、毎年行っている人でも、毎年いくつかの変更点が発生する確定申告ですので、こちらで内容をおさえられます。ぜひあわせてご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
退職金の受け取り後に確定申告が必要なケース

退職金の受け取り後に確定申告が必要なケースには、以下4つのパターンがあります。
公的年金などが合計400万円を超えている場合
国民年金や厚生年金などの公的年金などを複数受給しており、その合計が400万円以上の場合、確定申告が必要になります。
公的年金には、確定申告不要制度があります。公的年金が源泉徴収の対象・収入の合計額が400万円以下など条件を満たしていれば、原則確定申告は不要です。
しかし、公的年金などの収入の合計が400万円を超えている場合は条件から外れてしまうため、退職金も含めて確定申告をしなければなりません。
年金所得があり、他の所得金額が20万円を超えている場合
公的年金を受け取っており、年金かかる雑所得以外の所得金額は20万円以上となるケースも確定申告の対象です。該当する所得は、以下のとおりです。
-
- 雑所得(個人年金や原稿料など)
- 給与所得
- 配当所得(株式の配当金など)
- 一時所得(生命保険の満期返戻金など) など
上記で述べたとおり、公的年金などの合計が400万円以下であれば、確定申告は不要です。
しかし、合計400万円以下でも所得合計が20万円以上あれば退職金も含めて確定申告が必要になります。
転職先で年末調整を行ったが、前職の源泉徴収票を提出していない場合
転職した場合、その会社で年末調整が行われるため確定申告は基本的に不要です。
しかし、その際に年度中に在籍していた前職の源泉徴収票を提出していない場合、その分の所得に対する所得税は自ら確定申告をする必要があります。
前職の源泉徴収票を提出していない場合、所得税が正しく計算できません。
とくに退職から再就職するまで期間が空いている場合、所得税の過払いが発生していることがあります。
そのため、源泉徴収票を提出できなかった場合は、確定申告をして払い過ぎた税金を還付してもらう必要があります。
各種控除を利用したい場合
15種類ある所得控除の中には、年末調整では受けられないものもあります。例えば、医療費控除や寄附金控除が該当します。
これらの各種控除を適用したい場合、退職金の金額も記載した上で確定申告を行ってください。
退職後、年度内に再就職をしなかったために年末調整が受けられないときも各種控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
退職金の受け取り後に確定申告をしたほうがよいケース

上記の条件を満たさない場合、退職金の確定申告は不要ですが、状況によってはしたほうがよいケースもあります。そのケースは、以下のとおりです。
年度の途中に退職した場合
年度の途中で退職した場合は確定申告をしたほうがよいです。年末調整では、基礎控除をはじめ、社会保険料控除や扶養控除などの各種控除が適用されます。
しかし、退職した場合、以前在籍していた勤務先で年末調整をしてもらうことができません。
年末調整が行われないと所得税の計算が正しく行われず、控除が適用されないことで税金を払い過ぎている可能性があります。
退職金も含めて確定申告をすれば、正しい所得税を申告できるため、払い過ぎた分を取り戻すことができます。
状況によっては追加で納付しなければならないケースもあるため、脱税を避ける意味でも確定申告をしたほうがよいです。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
退職前に前職の勤務先で「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合も確定申告をしたほうがよいです。
事前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職所得控除を適用した上で税金が源泉徴収されます。
提出していないと退職所得控除が適用されず、一律20.42%の税金が差し引かれるため、払い過ぎている分は確定申告を行って還付してもらわなければなりません。
確定申告をする際は、前職の勤務先で発行される「退職所得の源泉徴収票」が必要になるので、時期が来るまでなくさずに保管してください。
不動産所得・事業所得が赤字だった場合
不動産所得や事業所得があり、退職したその年度の所得が赤字のときも確定申告をしたほうがよいケースに該当します。
確定申告をしていれば、退職所得から赤字を差し引くことで税金を減らすことが可能です。
ただし退職所得からの損益通算は、あらかじめ給与所得・配当所得・雑所得から損益通算を行い、それでも赤字が残った場合にできるという点に注意してください。
退職金にかかる税金の種類

退職金も課税対象となります。退職所得控除によって源泉徴収される税金を抑えられますが、その範囲を超えた分は納税しなければなりません。
退職金にかかる税金は、所得税・復興特別所得税と住民税の2種類に分けられます。
所得税・復興特別所得税
個人が所得を獲得した場合、それに対して課せられる国税です。
復興特別所得税は、東日本大震災の復興のための財源として、2013年から2037年まで支払う義務がある税金になります。基準所得額の2.1%が所得税に上乗せされる形です。
所得税の税率は、5~45%の間で所得額によって変動します。日本では累進税率を採用しているため、所得が多いほど所得税が高くなるのが特徴です。
住民税
個人が住む都道府県・市区町村に納税する地方税になります。住民税は所得に基づいて計算されるため、所得税が確定した後に計算されるのが特徴です。
また、退職金の場合、分類課税となるため給与所得とは別に税金の計算することになります。
退職金にかかる住民税は、所得税と同じく受け取る際に源泉徴収されます。そのため、納税に関する手続きを個人で行う必要はありません。
確定申告にも影響する退職金の受け取り方

退職金の受け取り方には、一時金を受け取る方法と年金形式の2種類に分けられます。
どちらの方法で受け取るかによって課税方式が変わり、納める税金が変わってくるので注意が必要です。受け取り方別の課税方法が以下のとおりです。
一時金で受け取る場合
一時金の場合、一度にまとめて退職金を受け取ることになります。この場合、退職所得にかかる所得税と住民税の源泉徴収は、支払う勤務先が手続きを行います。
そのため、退職者は基本的に確定申告などの手続きをする必要がありません。
一時金で受け取ると高額な税金が発生するため、軽減措置として課税方式は他の所得と別で計算する分離課税となっています。
また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職所得控除が適用され、税金の負担を軽減できます。
一度に退職金にかかる税金を納税できるため、年金形式で受け取る場合よりも税金の総額は安くなる傾向があるのも特徴です。
年金形式で受け取る場合
年金形式で受け取る場合、数年にわたって退職金が支払われます。所得の種類は雑所得になり、公的年金等控除を適用できるのが特徴です。
このケースも退職金を受け取るタイミングで、一律7.657%の税率で自動的に源泉徴収されます。
課税方式は雑所得と他の所得と合算する総合課税になるため、他の所得を得ていたり、各種所得控除を適用したりする場合は確定申告が必要です。
ただし、すでに公的年金を受け取っている人は条件を満たしていれば、確定申告は不要になります。
年金1年で受け取る退職金の金額が一時金と比べて少なく、1年間に納める所得税や住民税は少ないです。
しかし、退職金の運用状況や公的年金の受給額など退職後の生活や各種控除の適用によって、毎年納める税額は変わってきます。
そのため、総合的に見ると税金は年金形式のほうが高くなる傾向にある点に注意してください。
退職金にかかる税金の計算方法

税金の計算方法がわかれば、退職金(一時金)にかかる税金の目安をシミュレーションすることが可能です。
退職金にかかる税金をシミュレーションしてみたいときは、以下の手順で計算してみてください。
1.退職所得控除額を算出する
一時金で受け取る場合は退職所得控除が適用されるため、まずは控除額を求めなければなりません。
退職所得控除額の計算方法は、勤続年数20年を起点に異なります。
-
- 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(※控除額が80万円以下の場合は80万円)
- 勤続年数20年以上:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数が15年であれば、控除額は「40万円×15年=600万円」となります。
勤続年数が30年であれば、控除額は「800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円」と計算することが可能です。
なお、年度の途中の退職によって勤続年数が「○年○カ月」となる場合、1年未満の端数は1年切り上げて計算してください。
例えば、勤続年数10年5カ月であれば、計算上では11年となります。
また、障害を理由に退職した際は、100万円分の控除額が上乗せされるので計算する際は注意してください。
2.退職所得を算出する
次に課税退職所得がいくらになるのか、以下の計算式で求めます。
課税退職所得=(源泉徴収される前の退職金額-退職所得控除額)×1/2
退職金が2,500万円で退職所得控除が1,500万円だった場合、課税所得税は「(2,500万円-1,500万円)×1/2=500万円」と算出されます。
なお、勤続年数5年以下の役員などが特定役員退職手当として退職金を受け取る場合、計算において「1/2」は不要です。
3.退職所得の税額を求める
課税退職所得がわかったら、それに対する税額を計算します。以下のとおりです。
退職所得の税額=(課税退職所得×所得税率-控除額)×102.1%
課税所得税が500万円の場合、所得税の税率は20%、所得額は42万7,500円です。
所得税の金額は、「(500万円×10%-42万7,500円)×102.1%=58万4,522円(端数切捨て)」となります。
4.住民税を計算する
最後に退職所得にかかる住民税を以下の計算式で計算します。
住民税=課税退職所得×10%
住民税の税率は一律10%(都道府県民税4%+市区町村税6%)です。課税所得税が500万円の場合、住民税は「500万円×10%=50万円」です。
上記で求めた所得税と合算すれば、退職金にかかる税金の合計は「58万4,522円+50万円=108万4,522円」とシミュレーションできます。
こんなときはどうなる?特殊なケースでの退職金受け取りでの確定申告

相続人が本人に代わって退職金を受け取るなど、特殊なケースで退職金を受給するケースがあります。その場合の対応は以下のとおりです。
本人の死亡で相続人が退職金を受け取った場合
退職金を受給する本人が死亡した場合、その退職金は相続財産として被相続人が受け取ることになります。
このケースは退職手当金等として支払われ、法定相続人は相続税を納めなければならず、確定申告が必要です。
相続税には非課税限度額があるため、退職手当金等を含めて相続財産の金額によって相続税がかかりません。限度額の範囲内であれば、基本的に確定申告は不要です。
非課税限度額は、「500万円×法定相続人の人数(相続放棄した人も含む)」で計算できます。
計算する際は、法定相続人の数を明らかにしておく必要があります。
失業手当を受け取った場合
退職後に再就職活動を行うにあたって、雇用保険の失業手当を受け取ることが可能です。
失業手当は失業中も生活できるように保障してくれる制度であり、同じ収入でも非課税となっています。そのため、失業手当に対して確定申告をする必要はありません。
1年に複数回退職金を受け取る場合
複数の企業で働いていたが一度に退職することになったなど、1年に複数回の退職金を受け取る特殊ケースがあります。
このケースでは、基本的にそれぞれの企業に「退職所得の受給に関する申請書」を提出することになります。
同時に複数の企業に申告書を出す際は、申告書に提出の順位を記載してください。
退職金をすでに受け取っている場合、勤務先に支払者(企業)の名称や退職金の金額、源泉徴収税額などを記載した申告書を提出します。
その際、受け取り済みの源泉徴収票も添付してください。
まとめ・確定申告は原則不要だが、必要なケースや行ったほうが良い場合もある!
退職金は、長年勤めたことに対する功労を意味するがあり、退職後の生活を支えるお金です。
基本的に確定申告は必要がありませんが、状況によっては手続きが必要、または行ったほうがよいケースもあります。
自分はどのケースに当てはまるのか確認して、退職金にかかる税金も適切に納税しましょう。
退職金の税金は人によって異なるため、ご紹介した計算方法を参考に、どれだけ納めるのかシミュレーションしてみるのもおすすめです。
創業手帳では、わかりやすく簡単に解説した「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。あわせてご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)