“やばい赤字”の見極め方|利益が出なくても潰れない会社の共通点とは?
「やばい赤字」さえ見極めれば赤字が出ても会社はつぶれない
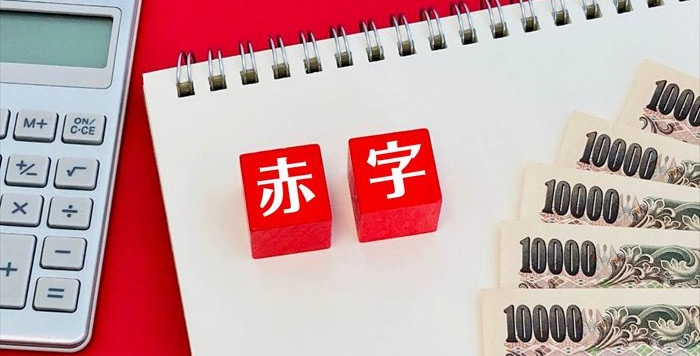
赤字が続いている、黒字だったのに売上が低迷して赤字に転換したと聞くと、会社が倒産するのではないのかと不安に感じるのは当然です。
しかし、一言で赤字といっても「やばい赤字」とそうでない赤字があります。逆に、現在黒字であったとしても倒産するリスクがないとは言い切れません。
ここからは「やばい赤字」の見極め方を紹介します。
赤字だからとむやみに心配するのではなく、その本質を理解して必要な対応につなげてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
そもそも「赤字=やばい」なのか?

赤字とは、支出が収入を超えている、もしくは利益が出ていないため収支が損失となっている状態です。
一般的にいわれる利益には、売上総利益や経常利益、税引前利益、当期純利益といった種類があり、赤字も内容によって営業赤字や経営赤字と呼ばれることがあります。
さらに、赤字には「投資型赤字」と「消耗型赤字」があり、意味合いが異なります。
赤字が出たからといってすぐに危険とは限りません。どのような赤字なのか、それぞれの赤字を理解して正しく状況を把握することが大切です。
投資型赤字は事業拡大や設備投資、人材採用などにともなう赤字です。一方で消耗型赤字は売上低迷や経費過多によって日々の経営が圧迫される赤字となります。
もしも、それらが採算が取れる投資による赤字であれば、先行投資での赤字を乗り超えて投資資金を回収でき、将来的に収益をもたらします。
赤字だから即「やばい」と決めつけるのではなく、その赤字が何に起因しているのか、将来どう回収するのかを見極めるようにしてください。
「やばい赤字」の3つの兆候
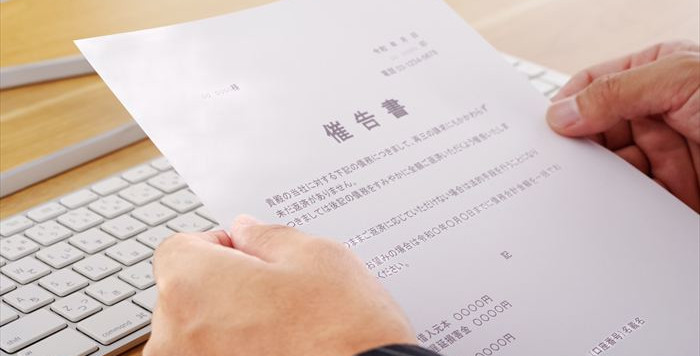
どのような赤字が出れば会社が危ない状態なのか、「やばい赤字」であるかを見極めるにはその兆候を見逃さないようにしてください。
ここからは、「やばい赤字」の兆候をまとめています。
資金繰りが回らなくなりつつある
会社が置かれた状況を、明確にあらわすのがキャッシュフローです。
毎月の支払いに追われ、手元の現金が常にギリギリ、あるいは足りなくなってきている場合は注意してください。
たとえ黒字であっても、借入金や取引先への支払いが多いと資金繰りが悪化して黒字倒産してしまう可能性があります。
「利益は出ているのにお金がない」という状態は、キャッシュフローが崩れているサインです。
キャッシュの流れを把握するには資金繰り表をつけて出ていったお金と入ってきたお金がどのくらいなのかを注視してください。
短期借入れが増え続けている
見た目では資金が足りていても短期借入れが増え続けている場合には注意してください。
これは、運転資金を補うために短期の借入れを繰り返している状態で、返済に追われている状態になってくると非常に危険です。
特に、返済のためにさらに借り入れる「自転車操業」のような状態になっている場合、長期的に経営が維持できません。
短期借入れが増えている時には、自転車操業を脱出するために、借入れの使い道や返済計画を見直してください。債務整理して無理がない返済計画を立てるのも有効な手段です。
税金や支払いの延滞が発生している
会社の経営が悪くなっている兆候としてわかりやすいのが各種支払いの延滞です。法人税、消費税、社会保険料などの支払いが遅れはじめたら、経営の黄色信号と考えます。
納税や社会保険の支払いは義務です。そのため、滞納は信用低下や行政処分につながるリスクもあります。
延滞税や加算税が発生するだけでなく、金融機関から融資を受けられなくなったり、信用低下で取引先が離れたりするかもしれません。
滞納が起こりそうな時には、早い段階で税務署に相談してください。
相談することで納税の猶予が受けられる可能性があります。また、税理士や専門家に相談する方法も検討してください。
どこまでの赤字なら“許容範囲”?

赤字になったからすぐに倒産ではないといっても、赤字が膨らめば不安に感じる人もいるでしょう。どこまでの赤字であれば許容できるのか考えてみてください。
ここでは、許容範囲となる目安の数字を紹介していきます。
自己資本の範囲内かどうか
1つの目安が、赤字が「自己資本(純資産)」の範囲内で収まっているかどうかです。
自己資本とは、資本金や資本剰余金、利益剰余金などで構成され、返済義務がないお金です。
会社が利益を出せば利益剰余金として自己資本に足されます。しかし、赤字では利益がマイナスになっているため、マイナスが算入され自己資本が減少してしまうのです。
最終的に自己資本がマイナス(債務超過)になれば、信用低下や融資制限など深刻な影響が出てしまいます。
金融機関や仕入れ先は、債権を回収できない可能性がある会社とは取引を避けます。
取引が少なくなり、資金調達もできなくなれば経営がさらに苦しくなる可能性もあるので早い段階で対処しなければいけません。
営業キャッシュフローがプラスか
営業キャッシュフローは、キャッシュフロー計算書の項目の1つです。会社のキャッシュフローの中で営業取引から生じた現金収支が営業キャッシュフローです。
営業キャッシュフローがプラスであれば、本業の儲けによる現金の流入がある状態であり、一時的な赤字がでても支払いに困りません。
赤字があったとしても減価償却などの非現金支出によって赤字になっているだけで、実際はキャッシュに余裕があるケースもあります。
逆に、営業キャッシュフローがマイナスの時は、営業活動の現金収入で支出をカバーできていないため、資金繰りの悪化や黒字倒産のリスクが高まります。
債権の回収を早めたり、自社の支払いを遅らせたりといったキャッシュフローの改善が必要です。
赤字が何期続いているか
赤字は、一時的か何期も続いているかによっても評価が変わります。
一時的な赤字は許容されますが、3期以上連続赤字になると信用不安が強まり、金融機関の評価にも影響が出始めます。
「継続赤字かどうか」は、倒産リスクの有力な判断材料とされているので、赤字に転換した時点で赤字が続かないようにするための改善が必要です。
財務改善とともに、売り上げの低迷や利益率の低下が原因の場合には、状況悪化に対応するための経営計画が求められます。
金融機関からの評価に影響があるか
赤字によって対外的な評価がどうなるかも判断基準です。赤字であるかどうかは、金融機関の評価にも直結しています。
特に赤字が2期連続になると、融資審査が厳しくなったり、信用格付けが下がったりする可能性もあり経営への影響は免れません。
金融機関からの評価を高めるには、今後の見通しを示すよう求められます。
具体的には、経営改善計画書を作成して赤字の原因分析、具体的な改善策を策定してください。
数値目標とともに示して黒字までの道筋を示すことによって評価につながる可能性があります。
赤字が続くとどうなる?倒産のリスクと前兆
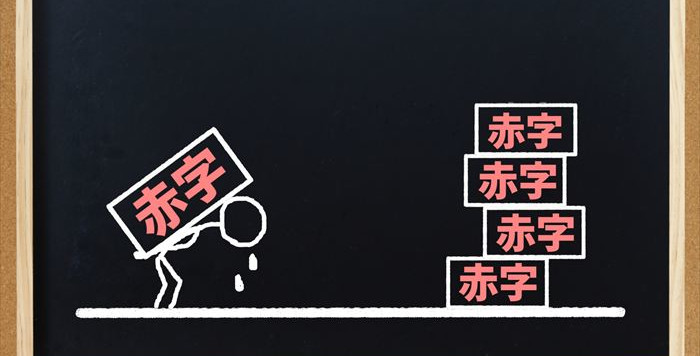
赤字がすでに続いている場合、倒産リスクについても考えなければいけません。
赤字によって自己資本(純資産)が減り続け、最終的にマイナスになる債務超過が続けば、企業の財務基盤は極端に脆くなってしまいます。
これにより、返済不能になる可能性が高いと金融機関からの融資が受けにくくなったり、融資の条件が悪化したりと支障が出るようになるでしょう。
赤字が続くと取引先や従業員からの信用も低下する上に、「あの会社は危ないのでは?」という噂が広がって、仕入れ条件の悪化や人材流出を招きます。
取引先や人材が離れだした時には倒産リスクが高まったといえます。
赤字になってからは、「赤字の深刻度」を定期的に見直し、可能な限り早めに経営改善の手を打つことが重要です。
赤字でも評価される会社の共通点

赤字でも金融機関や取引先からの評価が下がってしまうとは限りません。どのような会社が赤字でも評価されるのか共通点をまとめました。
事業に将来性がある
評価される赤字企業の多くは、新しい市場や需要を捉えており、今後の成長が見込まれる分野に取り組んでいます。
例えば、脱炭素やヘルスケア、DXなど、成長産業に挑戦している企業は、初期投資によって赤字があったとしても「先行投資型の健全な赤字」と見なされるケースがあります。
赤字になった時には、その赤字が次の事業を見据えたものであることを利害関係者に説明できるように準備しておいてください。
収益改善の計画が明確
赤字になっても「いつまでに、どのように黒字化するのか」という収益計画が明確な企業は信頼されやすくなります。
収益計画は売上高の見通し、コスト削減策、新サービスの展開など、具体的なアクションプランを数字で語るようにしてください。
逆に、今後の収益改善計画のない赤字は「改善見込みなし」と判断されてしまいます。具体性や数字の根拠がない計画も信頼を得られないので注意してください。
資金調達や人材投資が積極的に行われている
自己資金だけでなく、外部からの資金調達に成功している企業も評価されやすい傾向があります。
資金調達に成功していることで、返済に不安がない、これから利益が出ると評価されていると推察できるからです。
さらに将来を見据えて優秀な人材を採用・育成していることも、長期的な成長の証とみなされます。
「今は赤字でも、攻めの姿勢で未来に投資している」会社は、金融機関やパートナー企業から信頼されやすい傾向があります。
経営管理が徹底されている
赤字であっても、月次で試算表を出し、キャッシュフローや経費の動きをしっかり管理している会社は、改善余地があるとみなされます。
経営管理の基本として資金繰り表は必ず作成してください。
資金繰り表は、いつまでにいくらの入金があり、いつまでにいくらの支払いがあるのかを記載した表です。
資金繰り表で資金の流れが把握できれば、キャッシュフローが悪化する前に、資金調達の策を探すことができます。
資金繰り表を作成した次の段階として月次決算も作成します。
利益を月次管理できるようになれば、経営判断がスピーディーになり金融機関から資料の提出を求められた時にも役に立つでしょう。
赤字になった時にも資金繰り表と月次決算があれば、改善策も立てやすくなります。
補助金・助成金・制度融資を積極活用している
赤字でも、国の支援策(制度融資・補助金・セーフティネット貸付など)を活用して資金繰りを安定させる企業は、経営努力が評価されます。
以下は、赤字でも利用できる制度です。
・地方自治体の制度融資
都道府県や市町村では融資制度が用意されていて、状況に応じて有利な条件で資金調達できる制度があります。
一時的に経営が悪化した会社を支援する制度が用意されていることもあるので、まずは窓口に相談してみてください。
・日本政策金融公庫の融資制度
日本政策金融公庫は新しく事業を始める人や一時的に業況が悪化している人といった状況に応じた融資を提供しています。
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)は一時的に売り上げ減少等の悪化をきたしている人に向けて経営基盤の強化を図るための資金を提供しています。
“やばくなる前”にできる対策
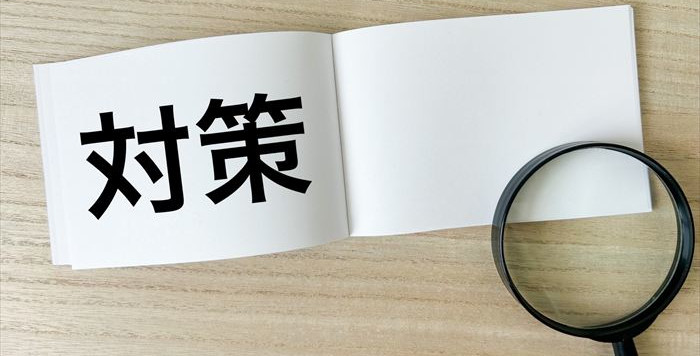
赤字になったとしても対応する方法はいろいろあります。しかし、「赤字で経営がやばい」と感じる前に対策を講じることも考えてください。
やばくなる前にできる対策をまとめました。
キャッシュフローの見直し
経営の悪化を防ぐには、まずは現金の「入り」と「出」の動きを把握します。
定期的に資金繰り表を作成し、数カ月先までの資金残高を見える化することで、支払不能のリスクを回避できます。
キャッシュフローが苦しい場合には、売上の回収サイト(入金タイミング)と支払いサイト(出金タイミング)を調整できる余地がないか見直してください。
不要な固定費の削減
売上が伸びない時は、固定費を見直すのが最も手堅い経営改善策です。
具体的には、事務所家賃やサブスク、保険、通信費といった固定費です。これらの小さな固定費でも積み上がると、長期的に大きな差が生まれます。
不要な固定費を削減するために、使っていないサービスや「惰性で契約している経費」がないか洗い出してみてください。
利益率の高い商品・サービスへの集中
経営改善には利益率が高い事業に集中することも検討します。すべての事業や商品に手を広げるのではなく、少ないコストで利益を確保できる稼ぎ頭に注力するやり方です。
売上は少なくても利益率が高い商品は、経営の安定を支える柱になりえます。
混同されることもありますが「売れている商品」と「儲かっている商品」は違うので、自社の利益構造を分析して、今はどの商品に力を注ぐべきかを考えてください。
外部専門家への相談
自社だけで対策が見つからない時には、税理士・中小企業診断士・金融機関の担当者など、第三者の視点を借りることで、自分では気づけなかった改善点が見つかるケースがあります。
「少しでも不安を感じた時点」での相談が、倒産リスクを未然に防ぐ第一歩です。
商工会議所では、各地域の中小企業を支援していて、中立の経営指導員が相談に応じてくれます。
資金調達や販路開拓など必要に応じて専門家やほかの支援機関と連携して課題解決を目指すことも可能です。
まとめ|「赤字=終了」ではないが、放置はNG
赤字になったからといって会社が倒産したり、事業が終わったりするわけではありません。しかし、赤字になってからの財務状況をそのままにしていいわけでもありません。
赤字から脱却するためには自社の数字と向き合い、早期の対策で悪化を回避します。まずは現状を正しく把握することが第一歩です。
赤字を克服するためには、資金繰りの改善とあわせて「資金調達の正しい知識」を持つことが欠かせません。
『はじめての資金調達手帳』では、公的融資や制度融資の基本、申請の流れや審査のポイントまでをわかりやすくまとめています。資金の不安を解消し、経営を立て直す第一歩として、ぜひご活用ください。無料でダウンロードできます。
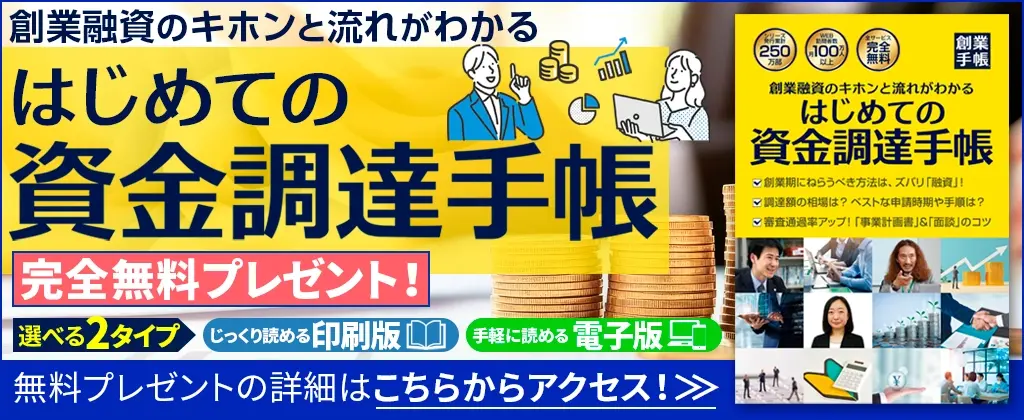
(編集:創業手帳編集部)




































