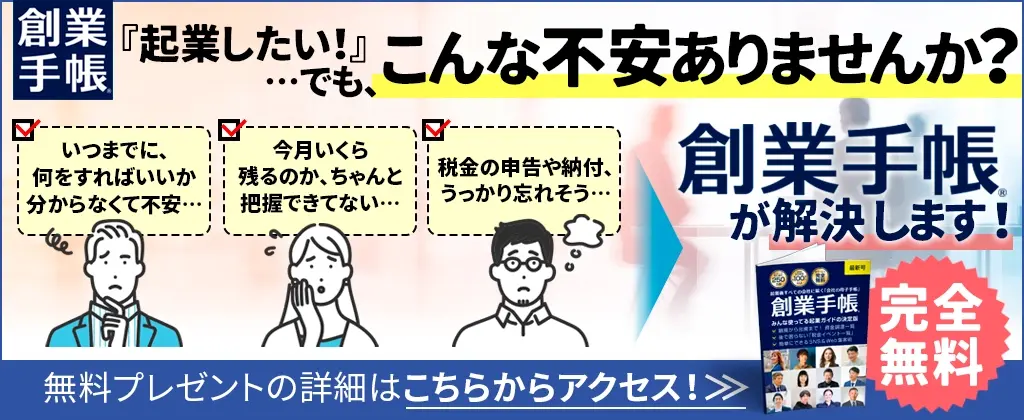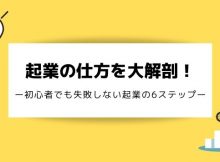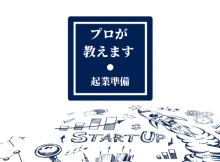シニア起業でよくある失敗パターンとその回避法|定年後に後悔しないために
成功のカギは「失敗パターンの回避」にあり

定年退職後は、これまでの経験や知識を活用して新しいことをはじめたいと考える人もいるでしょう。
一方で「退職金を使って起業したけれど、思ったようにいかない…」そんな声も少なくありません。
本記事では、50〜60代で起業を考えている方に向けて、シニア起業でありがちな失敗例とその回避策を具体的に紹介します。
後悔しない起業に向けた第一歩として、ぜひご覧ください。
起業で失敗しないためにも、事前準備は重要です。創業手帳では、起業前後のやることリストがカレンダー形式でわかりやすく管理できる『創業カレンダー』を無料でお配りしています。起業予定日を決めれば、前後1年間のTODOリストが完成。ぜひこちらもあわせてご活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
なぜシニア起業は失敗しやすいのか?

シニア起業をしたものの、うまくいかずに撤退するケースも少なくありません。どうしてシニア起業で失敗してしまうのか理由をまとめました。
「退職金一括投資」が多い
シニア世代の大きな特徴として、若い世代と違って失敗時のやり直しが困難な点が挙げられます。シニアは体力にも不安があり、本来はリスクを抑えるべき年代です。
しかし、シニア起業には退職金や今までの貯金を一括で事業につぎ込んでいるケースがあります。
退職金や貯蓄をまとめて事業に投入すると、資金ショートで早期撤退しなければならない可能性もあります。
老後資金と事業資金を分けずに計画すると、失敗時に生活基盤まで失うリスクが高いので注意してください。
スタート時点で相談相手がいない
起業時に誰にも相談せずにひとりで事業を進めることはおすすめできません。
知り合いが多いシニアであっても、定年退職により職場の同僚や上司との関係が希薄になり客観的意見を求める相手がいない場合、自分で事業に関わるすべてをこなそうとしてしまいます。
特に、家族や友人に心配をかけたくない思いが強い人は、ひとりで判断して進めてしまう傾向があるので注意してください。
経営経験のない中で重要な決断を独断で行うと、致命的なミスを犯してしまうかもしれません。
商工会議所や中小企業支援センターでも相談を受け付けているので利用してみましょう。
市場分析や競合調査を怠りがち
経験があることがマイナスに働くケースもあります。シニアは、働いてきた年数が長いからこそ長年の経験から「なんとかなる」という楽観的な判断をしてしまいがちです。
特に市場分析やマーケティングは比較的新しい分野であり、苦手とするシニアもいます。
インターネットでの情報収集や現代的な市場調査手法に不慣れだと、情報収集が不十分になってしまいます。
マーケティングをおろそかにして同世代の価値観で需要を判断してしまうと、実際のターゲット層のニーズとギャップが生じて失敗してしまう可能性が高いです。
シニア起業でよくある失敗パターン

シニア起業で失敗する人はある程度パターンに区分されます。どういった失敗パターンがあるのかまとめました。
原因と回避法をまとめて紹介するので、起業する時の参考にしてください。
1. 準備不足で勢いだけの起業
シニア起業で意外と多いのが勢いで押し切ろうとして準備が整っていないケースです。勢いだけで家族の反対を振り切って家族不和を招くケースもあります。
【原因】
このパターンの原因は、定年退職という人生の転機で「何かやりたい」という気持ちが先行し、冷静な計画を立てずに進めたことです。
「なんとかなる」という楽観的な思考で、具体的な事業計画や市場調査を怠ってしまうケースはシニア起業でも多く見られます。
シニアには、退職金という資金があるため、準備不足でも「お金があるから大丈夫」と錯覚してしまうことが多いのです。
【回避法】
準備不足で勢いだけの起業を避けるには、事業計画の策定と市場調査に時間をかけ、感情的な判断を避けるようにします。
市場調査についてあまり知らない場合には新しく勉強してみてください。
商工会議所などの創業セミナーに参加し、客観的な視点から事業の実現可能性を検証するのも有効な手段です。
小規模なテストマーケティングを実施し、実際の需要を確認してから本格始動するようにしてください。
2. 過去の経験にこだわりすぎて柔軟性がない
シニアの経験は武器であり、経験を活かして起業する人は多くいます。しかし、経験にこだわりすぎれば逆に足かせになってしまうかもしれません。
【原因】
経験にこだわりすぎるのは長年の成功体験が自信となっているからです。自信があるからこそ現在の市場環境や消費者ニーズの変化を受け入れられず失敗してしまいます。
外部がアドバイスしても「自分のやり方が正しい」という固定観念が強く、新しい手法やアドバイスを拒絶してしまうケースもあります。
こだわりが強すぎれば時代の変化についていけず、デジタル化やSNS活用などの現代的な手法を軽視して失敗してしまうかもしれません。
【回避法】
定期的に同業界の最新動向を調査し、自分の知識をアップデートする習慣を身につけてくると良いでしょう。
若い世代の意見を積極的に聞き、世代間のギャップを理解して柔軟に対応するようにしてください。
過去の成功体験は参考程度に留めて、現在の市場に合わせたビジネスモデルを構築します。
3. 健康や体力の問題を軽視する
ジムやランニングなど健康に気を遣うシニアは多いでしょう。一方で、鍛えているからと健康や体力の問題を軽視するシニアもいます。
せっかくビジネスがうまくいっているのに健康面、体力の問題で続けられないケースもあるので過信は禁物です。
【原因】
現役時代と同じペースで働けると過信し、年齢による体力低下を軽視してしまうと無理がたたって事業に影響を及ぼしてしまいます。
事業計画で病気やケガのリスクを想定せず、自分ひとりですべてを担う前提で事業計画を立てていると、事業の継続自体が危ぶまれる可能性もあります。
また、起業によって会社員時代から生活が変化しているかもしれません。生活が変化しているのに健康管理を疎かにして、ストレスや過労で体調を崩してしまうことがあります。
起業すると人件費を削減したいからと無理して働いてしまう人も珍しくありません。
【回避法】
健康や体力の問題に気が付けるように起業してからも定期的な健康診断を受けてください。
自分の体力と健康状態を客観視して無理のない事業規模に設定するようにします。
また、どれだけ気を付けていても病気やケガで働けないケースはあります。もしもの場合に備えて代替案を事前に準備し、事業継続計画を立てておくようにしてください。
4. 家族の理解を得ずにスタート
起業する時には、必ず家族の理解を得るようにします。しかし、生活への不安から反対されるかもしれません。
そういった場合に家族の理解を得ないままでは事業成功も難しいです。
【原因】
家族に心配をかけたくない思いから、起業の計画や不安をひとりで抱え込んでしまうケースはよくあります。
「自分のことは自分で決める」という独立心が強すぎると、家族との相談を軽視してしまいがちです。
しかし、退職金の使用や生活費への影響について、家族との合意形成を怠ってしまうと禍根が残り家族との関係も悪化します。
【回避法】
起業を検討している段階から早めに家族と率直に話し合って、理解と協力を求めるようにしてください。家族が反対する場合は、多くは生活や経済面での不安があるからです。
事業計画書をもとにして家族にも説明し、どういったリスクがありどう対策するかを話します。隠し事はせずに透明性を保つことが大切です。
必ず家族の不安や懸念はしんしに受け止めてください。受け流すのではなく、一緒に解決策を考える姿勢を示すことで、協力関係を築き上げられます。
5. デジタル・インターネット集客の軽視
シニアの中には、デジタル・インターネット集客に疎い人も多いかもしれません。デジタル・インターネット集客を軽視すると事業でも失敗してしまうことがあります。
【原因】
「人とのつながりや口コミだけで十分」とデジタルマーケティングの重要性がわからないままビジネスをはじめると集客で後れを取ってしまいます。
シニアはインターネットやSNSに対する苦手意識があり、学習することを避けてしまう人もいるでしょう。
従来の営業手法だけにに固執してオンライン集客の可能性を見落としてしまうとビジネスの幅も広がりません。
【回避法】
インターネットやインターネット集客をはじめるためには、基本的なホームページ作成やSNS運用について学習し、最低限のデジタル対応を身につけてください。
若い世代の顧客層にもリーチできるよう、従来手法とデジタル手法を組み合わせるのが理想的です。
どうしても苦手に感じる場合には、デジタルマーケティングの専門家に相談し、自社に適したオンライン戦略を策定してください。
6. 資金繰りや利益計画が甘い
シニアの多くは、現役時代の貯金や退職金を原資にして事業をはじめます。しかし、資金面に余裕があるからこそ失敗してしまうケースがあります。
【原因】
シニア起業は退職金があることで資金的な危機感が薄く、詳細な資金計画を立てずにはじめてしまうことがあります。
売上予測が楽観的すぎて、実際の市場での収益獲得の困難さを過小評価してしまいます。
その結果として固定費や運転資金の計算が甘くてキャッシュフローの管理ができず、気が付けば資金が尽きてしまっているといった失敗も発生してしまうのです。
【回避法】
資金繰りに失敗しないためには、老後資金と事業資金を明確に分離し、事業失敗時でも生活に支障がない範囲で投資してください。
過度な楽観を避けて保守的な売上予測を立て、最悪のシナリオでも事業継続できる資金計画を策定します。
また、資金繰りについては税理士や会計士に相談し、適切な資金管理と利益計画の立て方を学ぶようおすすめします。
7. 経験不足の業種への挑戦
シニアになってから今まで未経験の業種に挑戦するのは勇気が必要です。また、イメージしていた仕事と違って、「このようなはずじゃなかった」と感じるかもしれません。
【原因】
「昔からの夢だった」という感情的な理由で、業界知識が不足している分野に参入してしまうのは典型的な失敗しやすい起業のひとつです。
独学で勉強していたり、趣味で続けていたりする分野かもしれませんが、趣味レベルの知識で事業化できると過信すると、プロとしての技術や経営ノウハウが不足していてビジネスとして成立しないことがあります。
想定外のトラブルを避けるためにも業界特有のリスクや規制、競合状況を把握するようにしなければいけません。
【回避法】
未経験分野への参入する前には、業界研究と技術習得に専念する期間を必ず設けてください。可能であれば実際にその業界で働いてから起業します。
その後、小規模なテスト事業からはじめて、段階的にスキルと知識を積み上げてから本格参入するようにしたほうが良いでしょう。
また、その業界の経験者に実務的なアドバイスを継続的に受けたり、ビジネスパートナーを探したりすることも検討してください。
シニア起業で失敗を防ぐための事前チェックリスト

「自分は失敗しないから大丈夫」と過信するのは危険です。以下では、シニア起業で失敗を防ぐための事前チェックリストと紹介しています。
自分に当てはまる項目がないかチェックしてみてください。
上記のチェックリストは、チェックが少ないから起業をやめたほうが良いといった性質のものではありません。チェックを増やしていけるように積極的に取組むものです。
事業計画の段階を進めていくと、徐々にチェックが付けられるようになります。チェックがすべてつくように努力してください。
シニア起業前に活用できる支援制度・相談先

シニアが起業で失敗しないためには、利用できる制度やサポートはすべて使ってください。
多くのサポートは年齢不問で提供されています。どういった支援制度や相談先があるのか、以下でまとめました。
商工会議所・中小企業支援センター
起業の相談や情報収集の手段として、公的支援機関の窓口があります。具体的には、各地の商工会、商工会議所や中小企業支援センター、よろず支援拠点などです。
全国各地にある商工会議所では、起業前の事業計画作成から開業後の経営まで無料で相談可能です。
中小企業支援センターも全国に設置され、専門家による個別相談や業界特有の課題にも対応してもらえます。
定期的に創業セミナーが開催されていて起業に必要な基礎知識を体系的に学習できるので、利用してみてください。
シニア向け創業スクール
起業を志す人は多く、シニアに絞った創業スクールも開催されています。
シニア向けの創業スクールでは、同世代の仲間と一緒に起業ノウハウを学べる上、年齢特有の課題や不安について経験豊富な講師から具体的なアドバイスを受けられます。
また、交流や人脈を広げる場所としても有効です。
卒業後も同期生とのネットワークを活用して、情報交換や相互支援ができるため、起業へのモチベーションアップにもなるでしょう。
小規模事業者持続化補助金などの支援制度
起業時に受けられるサポートには、各種の補助金もあります。
例えば、小規模事業者持続化補助金は、条件を満たした小規模事業者の販路開拓の取組みなどの経費の一部を補助するものです。
利用するためには、経営計画を策定して商工会・商工会議所の支援を受けながら取組む必要があります。
また、地方自治体が独自の起業支援制度を提供しているケースもあります。どういった制度が利用できるのか調べてみてください。
創業手帳など無料の情報ツール
情報は多くあっても困らないものの、多すぎると今度は情報を持て余してしまいます。
創業手帳は起業に必要な手続きや制度を網羅した無料の冊子です。起業直後の全法人に届く起業・資金調達メディアです。
オンライン版では最新の支援制度情報や成功事例を随時更新しており、常に最新情報を入手できます。
業種別の起業ガイドや資金調達の方法など、実践的なノウハウが豊富に掲載されているので定期的にチェックしてください。
まとめ:リスクを知れば、シニア起業は怖くない
シニア起業は長年の「経験」と人生設計の「時間的余裕」を活かせる貴重なチャンスです。
失敗の落とし穴を事前に知っておくことで、一つひとつ丁寧に対策を立てられます。
着実に成功するためには無理をせず小さくはじめて、周囲の協力や信頼を獲得してください。公的支援や専門家のアドバイスを積極的に活用すると良いでしょう。
創業手帳(冊子版)は、起業に必要なノウハウを一つの冊子にまとめた「起業のためのガイドブック」です。資金調達方法から資金繰りの基礎や、税金の知識などがこの一冊でおさえられます。
また、起業のために必要な準備としてわかりやすいのが「創業カレンダー」です。起業予定日を記入すると、その予定日を起点に前後1年間のやることがカレンダー形式で把握することができます。どちらもあわせてご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)