オムニチャネルは今後の販売戦略を担うシステム!メリットや活用ポイントを解説
オムニチャネルは小売業で広がっている販売戦略。どう利用すべきか徹底解説します。

オムニチャネルは、近年小売り業で徐々に導入が進んでいる販売戦略です。
PCやスマホなどのデバイス普及により、インターネットを活用し、様々な方法で顧客と接点を持てるようになりました。
その中でも、オムニチャネルが持つ多様性は、これからの販売戦略に大きな変化をもたらすはずです。
今回は、オムニチャネルがどのようなものか、メリット・デメリットだけでなく、活用ポイントも解説します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
オムニチャネルとはどのようなものか
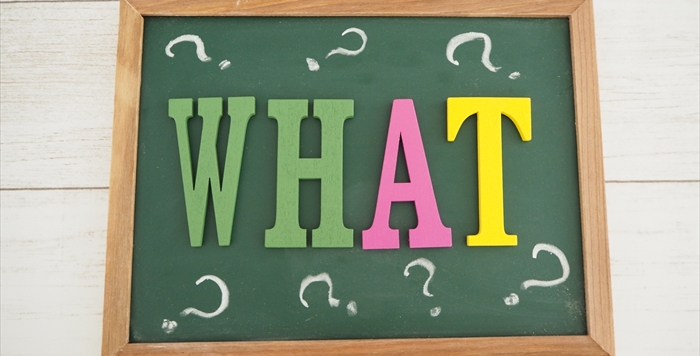
まずは、オムニチャネルの概要について説明します。
オムニチャネルの概要について
オムニチャネルとは、インターネットを介したECサイトやアプリなどにとどまらず、実店舗やTVや雑誌も含め、様々な分野から顧客と接点を作り販促を行う戦略です。
従来は、実店舗の宣伝をするためにチラシやカタログなどアナログな手法が採られていましたが、インターネットの活用により、顧客が情報を得る方法が多様化してきました。
そのため、アナログな手法に加えてIT技術も駆使した情報発信、かつ、それらの各媒体を連携させて販路を広げることが、オムニチャネルの目的です。
ちなみに、「オムニ」の意味は「あらゆる」で、「チャネル」は「顧客との接点・媒体」のような意味です。
オムニチャネルの形態イメージ
オムニチャネルの形態として、イメージをひとつピックアップしてみます。
顧客が最初に利用する媒体が実店舗で、そこで探している商品がない場合でも、インターネットに接続してオンラインショップで探せば、まだ販売しているかもしれません。
また、オンラインショップでは、別の実店舗と連携して在庫確認ができるケースも存在します。
そして、店舗のECサイトやアプリにアクセスして、在庫があればそこから購入することができるため、顧客は希望の商品を手にすることができるでしょう。
こうしたパターンにおいて、顧客が商品を求めて接する媒体は実店舗・ECサイト・アプリと多様であり、さらに、媒体間での連携も取れています。
オムニチャネルでは、顧客の購買体験が広がり、それを実現するのは媒体同士のつながりです。オムニチャネルが目指すところは、垣根のない購買体験といえます。
オムニチャネルの種類について
オムニチャネルの種類は、下記のように多種多様です。
-
- ECサイト
- ホームページ
- アプリ
- SNS
- メルマガ
- チャットボット
- 実店舗
- コールセンター
- TV
- 雑誌
- 新聞
- カタログ
- 屋外(ビルや駅、電車など)の広告、看板
など
さらに、上記の媒体をそれぞれに連携させることで、より幅広い販路拡大を狙うことができます。
オムニチャネルの市場規模は拡大の一途
あるデータでは、商品を購入したケースのうち、オムニチャネルを利用した場合の売上は年々増加の一途をたどっているという結果が出ていました。
2017年におけるオムニチャネル市場での売上は、およそ50兆円を記録しており、2021年にはおよそ65兆円にまで伸びています。
さらに、2022年以降の予測ではおよそ4兆円ずつ成長することが見込まれており、さらに市場に浸透していくとされています。
また、近年の在宅時間の増加によりオムニチャネルの利用率は高まっており、経済効果としても有益であると見られているようです。
オムニチャネルを導入するメリット・デメリット

オムニチャネルを導入するにあたり、メリットとデメリットがそれぞれに存在します。
オムニチャネルのメリット5つ
1.顧客満足度アップを狙える
前述のとおり、オムニチャネルの仕組みを利用すれば、実店舗で購入できなかったものをネットショッピングなどで手に入れることが可能です。
オフラインでの体験とオンラインでの体験を組み合わせることにより、顧客は望んだ商品をピンポイントで購入でき、結果的に顧客満足度のアップが狙えます。
2.顧客それぞれに適したアプローチが可能
オムニチャネルでは、PCやスマホで商品を閲覧した際、ほかのサイトに表示される広告に同ブランドや類似商品を提示することができます。
また、登録したECサイトやアプリのメルマガでは、閲覧履歴をもとにしたおすすめ商品が案内されます。
つまり、媒体こそ異なっていても顧客は同様の商品の情報を得ることができ、顧客の好みそれぞれに適したアプローチができる仕組みです。
3.顧客ニーズをピンポイントに絞れる
前述の2.に関連する内容ですが、様々な媒体を通して顧客のニーズをピンポイントに絞ることで、顧客はその商品の購入に踏み切りやすくなります。
そのため、顧客は同様の商品を自ら検索して探す手間が省け、スムーズな購入体験が実現します。
販売経路が違っても同様の商品が手に入ることは、オムニチャネルのメリットのひとつです。
4.販売のチャンスを逃しにくい
例えば、実店舗での在庫がない、もしくは、実店舗まで行くことができない顧客がいるケースでは、それだけで販売のチャンスを逃がしてしまいます。
しかし、オムニチャネルでオンライン上もしくはほかの実店舗との連携を取り、トータルの在庫管理ができれば、商品の販売を何らかの媒体で購入することが可能です。
そのため、顧客が他店に流れる恐れを食い止めることにもつながります。
5.顧客分析にも役立つ
オムニチャネルで複数の媒体を持つことにより、それぞれから年齢層やニーズ、購買行動のデータをより多く収集できます。
その結果、実店舗でのみ得た情報よりも精度が上がって的確な顧客分析が実現し、より効率的なマーケティングの施策を講じてさらなる売上アップを期待できます。
オムニチャネルのデメリット5つ
1.チャネルの連携が難しい
オムニチャネルでは、オンラインとオフラインを問わず連携を取って売上アップを狙うものであるため、連携するためのシステムが欠かせません。
オンラインのチャネル同士であれば比較的容易に連携できますが、オフラインとのバランスを取るためには、在庫管理や顧客データベースの整備などが難しい場合もあります。
2.複数チャネル構築費用がかかる
これからオムニチャネルを導入する場合、チャネルを増やす分、構築費用が発生します。
ECサイトやアプリなどの作成のほか、チャネルを連携させるシステムの整備や顧客データ収集システムの生成にも費用がかかり、売上を圧迫する恐れもあるかもしれません。
3.すぐに結果が反映されるわけではない
オムニチャネルを導入したとしても、その日から売上が伸びるわけではなく、結果が出るまでには複数のチャネルを顧客に周知し、購買体験に満足してもらう必要があります。
その上で、売上が伸びない時にはその原因を究明し、改善した後にまた結果を分析する必要があるため、結果を出すには長期的な視点が求められます。
4.チャネル間での顧客の取り合いが起きやすい
複数のチャネルを構築したとしても、双方の連携がうまくいかなければ、相乗効果は得られません。
特に、オンラインとオフラインのチャネルの関係性には注意が必要です。
ECサイトやアプリの普及により、その利便性から顧客がオンラインに流れ、実店舗と顧客の取り合いになってしまうだけになる危険性もはらんでいます。
5.顧客へ周知するための施策が必要
前述のように、結果を出すためには顧客にチャネルを周知することから始めなければなりません。そこで重要なのは、チャネルをどのように顧客に周知するかです。
オンラインチャネルの存在をアピールするためには、何らかの施策を練る必要があります。
例えば、検索エンジンの上位にヒットさせるSEO対策や、顧客の傾向に応じたDSP広告(特定層のユーザーに向けてメディアに広告を表示させる)などがあげられます。
オムニチャネルとほかのチャネル・用語との違い

オムニチャネルは、ほかのチャネル形態から徐々に進化を遂げてきたものです。では、それらとの具体的な違いは何でしょうか。
チャネルの種類と変遷
シングルチャネル
シングルチャネルは、顧客との接点がひとつしかないことを示します。例えば、実店舗のみ、コールセンターのみのような形態です。
インターネットや通販の普及が一般的になる前は、シングルチャネルの形態が一般的でした。
マルチチャネル
マルチチャネルは、チャネルが複数あることでより顧客との接点が増えるものです。
実店舗を持ちながら通販も行っている、メールやコールセンターなどにアクセスできる状態がこれにあたります。
しかし、それぞれのチャネルに連携が取れていないため、顧客情報の共有や在庫管理が難しい形態です。
クロスチャネル
複数のチャネルがあり、特定のチャネル間でのみ連携が取れている状態がクロスチャネルです。
例としては、実店舗とオンラインショップのみ、メールとコールセンターのみが連携しているような形です。
それぞれに、情報共有は可能ですが、すべてのデータを一元化するには今一歩及ばないといえます。
オムニチャネル
上記のチャネル形態から、チャネルの分類をなくしてどのチャネルからでも情報共有できるのが、オムニチャネルです。
顧客は、実店舗・オンラインショップ・メール・コールセンターをはじめ、チャットボットなども活用して購買体験ができ、顧客情報や在庫管理も、どのチャネルからでも行えます。
さらに、全チャネル同士で情報共有できることから、取り次ぎの必要もなくなり顧客も企業もスムーズな対応が可能です。
オムニチャネルはほかの類似形態とどう違うか
O2O
O2O(オーツーオー)は、英語でOnline to Offlineを指します。つまり、オンラインからオフラインへ顧客を誘導することを目的とした施策です。
O2Oの例としては、サイトやアプリ、メルマガでキャンペーンの告知・クーポン発行を行い、実店舗に顧客を呼び込むなどがあります。
O2Oは、一方通行の顧客へのアプローチですが、オムニチャネルでは双方の行き来が可能であり、O2Oからさらに進化した形といえます。
OMO
OMO(オーエムオー)とは、英語でOnline Merges with Offlineと表記します。「Merges」は「併合・統合」のような意味があり、オンラインとオフラインを統合する施策がOMOです。
例えば、実店舗で見つけた商品について、QRコードの読み取りなどで商品情報を得られたり、閲覧情報がデータベース化され、顧客情報と結びつけられたりするものです。
オムニチャネルが企業発信のものだとすれば、OMOは顧客発信で情報を得ることが可能で、顧客はさらに新しい購買体験を得られます。
オムニチャネルが小売りの成長のカギとなる
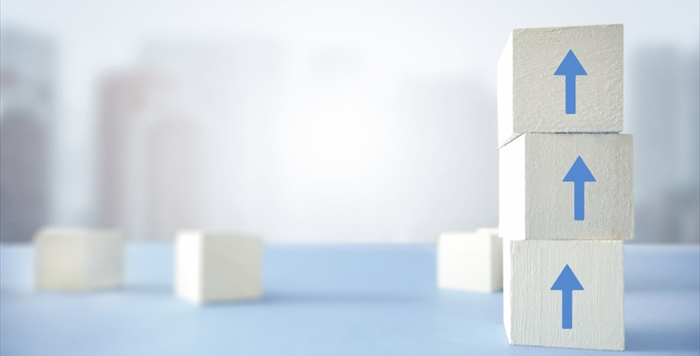
オムニチャネルが注目されているのは、小売りにおける顧客体験が変化したことによるものといえます。
オムニチャネルが注目を集めた経緯
スマホおよびSNSなどの普及
スマホの普及により、顧客はECサイトやアプリ、サイトに表示される広告の複数媒体から情報を得ることが可能になりました。
これにより、閲覧する媒体はひとつではなくなり、顧客は複数の媒体を介して商品にたどり着く動きをします。
さらに、SNSの普及で企業やインフルエンサーなどからの情報を気軽に受け取り、多角的に商品を検討できます。
以上の点から、顧客が昼夜を問わず好きなタイミングで購買意欲を持ち、豊富な情報から取捨選択できることが注目されるポイントのひとつです。
口コミを参考にした選別
商品の使い心地や性能は、実際に手に取らなければわかりづらいですが、このような場合に役に立つのが口コミです。
SNSで個人が自由に発言できることで、多くの人々の口コミを参照できるようになりました。これは、良い評価だけではなく悪い評価も同時に受け取れるということです。
それらの口コミを鑑みて、顧客が総合的に商品を判断できるようになったことも、顧客体験の変化といえます。
顧客ニーズの細分化
SNSの普及は、顧客が多様な情報を得られることにも関連しています。
特定の商品だけではなく、そこに別の価値が付随した商品や好みに合った商品情報を幅広く得ることで、顧客のニーズの多様化が進んできました。
このような動きは、顧客が本当に欲しいものを買いたいという欲求を促すものであり、その購買体験を実現できるのがオムニチャネルの仕組みです。
オムニチャネルを成功させるためのポイントとは

オムニチャネルを成功させるためには、以下のようなポイントを押さえると良いです。
ターゲット層に合ったチャネルを構築する
企業が打ち出す商品には、年齢や性別、職業などの属性によりターゲットが絞られています。
そのため、展開するチャネルも、ターゲットとする層に見合ったものでなければなりません。
例えば、10代の若者を狙うならSNSでの情報発信に力を入れると良いでしょう。
30代くらいの会社員男性をターゲットにするなら、夜の遅い時間でも閲覧や問い合わせができるECサイトが良いです。
さらに、そのECサイトに設置されたチャットボットなどがあれば、いつでも顧客とつながれます。
また、新たなターゲットを設定するとしたら、これまでにはない新たなチャネルの構築も必要でしょう。
チャネルで得たデータを有効活用する
オムニチャネルの展開により、複数のチャネルから得た情報は、単にデータベース化するだけではなく有効に活用すべきです。
顧客の購買行動やニーズの分析はもちろん、特に問い合わせの多い内容は、あらかじめヘルプページにまとめたりチャットボットで回答できたりと施策を講じるのもひとつの方法です。
顧客の声や行動を分析して施策の先回りをすることも、オムニチャネルだからこそできることです。
外部のチャネル提供サービスをうまく利用する
企業が、複数のチャネルを自社のみで運営することは、ある程度負荷のかかる作業であることは否めません。
オムニチャネルの運営により、本来のコア業務がおろそかになってしまっては本末転倒です。その問題を解消するには、外部のチャネル提供サービスの力を借りる手もあります。
外部にサービス運用を委託すれば、本来の業務を圧迫することなく良い商品を提供し続けることができ、商品情報の発信を外部に任せれば効率的にコア業務を行うことが可能です。
例えば、チャットボットでの問い合わせシステムやコールセンターとの連携のような仕組みは、サービスとして提供している会社が多く存在します。
各チャネルでブランドイメージを統一する
複数あるチャネルのイメージが異なっていると、顧客が戸惑ってしまうことは想像に難くありません。そのため、各チャネルではブランドイメージの統一が重要です。
統一したイメージにより、顧客は様々な媒体を通じてブランドに対する一貫した印象を持ち、安心してどのチャネルからでも利用したいと思えるようになるでしょう。
また、ブランドイメージの統一は、チャネル間での情報共有にも反映されます。
情報の一元化により、顧客の購買行動を把握しデータ化すれば、複数のチャネルを利用しても同様の購買体験が可能です。
これにより、顧客はブランドに対して安心感や信頼感を持ち、リピーターになる確率も上がります。
まとめ
オムニチャネルとは、小売り業において、より効率的な販売活動が行えるだけではなく、顧客の立場に立った時にも満足感を得られる戦略です。
顧客のニーズや、情報収集方法の変化や多様化に合わせ、企業とターゲット層に適したオムニチャネルを構築することが大切といえます。
オムニチャネル導入の計画を立てる時は、長期的なスパンでトライアンドエラーを繰り返し、チャネルを成長させることを考えてみましょう。
(編集:創業手帳編集部)




































