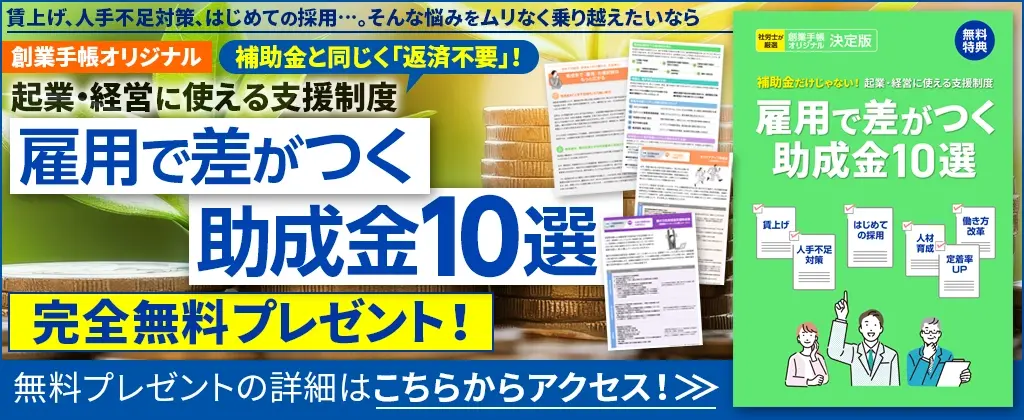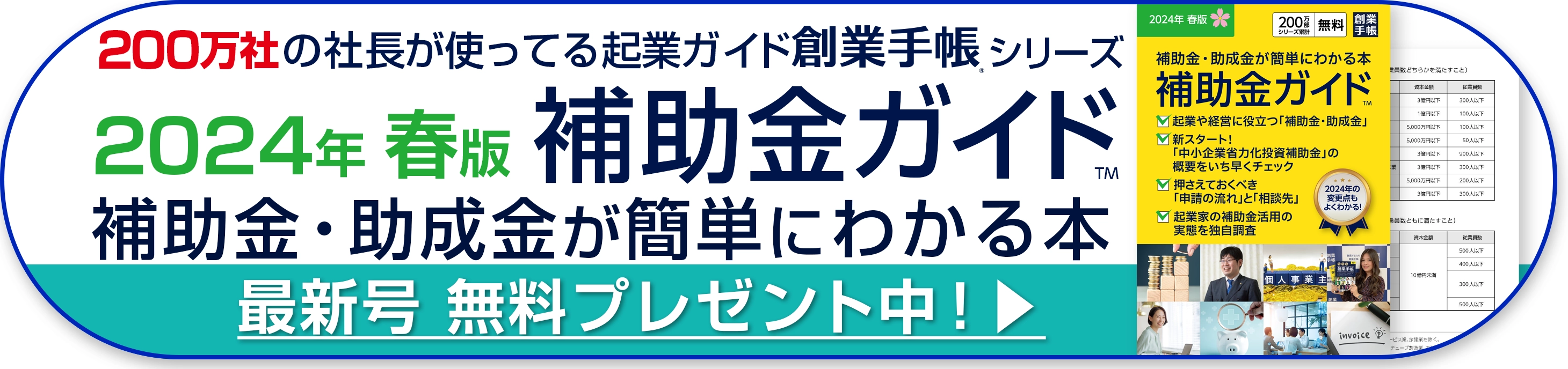【2025年改正】高年齢雇用継続給付が縮小!事業主が知っておくべき対策とは
高年齢労働者処遇改善促進助成金の活用も要検討

2025(令和7)年4月1日より、高年齢雇用継続給付金が縮小されます。場合によっては、60~64歳の従業員に支給される給付金が減額となるため、従業員の生活に影響が出る可能性が考えられるでしょう。
65歳以降も優れた人材を確保したい場合に有効活用できる制度が、高年齢労働者処遇改善促進助成金です。いずれも高年齢者の雇用を促進するための制度ですが、併用はできないため、自社の状況に合わせて使い分けましょう。
今回は、高年齢雇用継続給付金が縮小される内容や、高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給条件などを解説します。高年齢者の雇用促進、雇用の確保を検討している事業主の方は、ぜひ参考にしてみてください。
創業手帳では、経営者の方々がよく使われている補助金・助成金を厳選して紹介した「補助金ガイド」を無料でお配りしております。あわせてご活用ください。
また、創業手帳では、高齢者雇用・正社員化・育児支援などに使える助成金を厳選した、「雇用で差がつく助成金10選」を無料配布中です。高齢者雇用の継続には、制度対応やコスト面の課題もつきものです。そんな時には、ぜひ返済不要の助成金を活用しましょう!
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
高年齢雇用継続給付が15%から10%へ縮小される影響
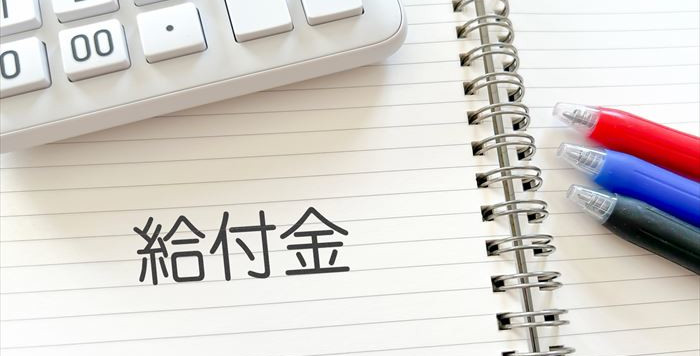
2025(令和7)年4月1日より、高年齢雇用継続給付の支給率が、最大で15%から10%に縮小されます。高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とした給付金制度です。
「60歳時点の給与」と「60歳以降の給与」を比較し、給与が減少しているとき、60歳から64歳の期間中に給付金を受け取れます。
昨今は60歳以上になっても働く方が増えている背景もあり、以下のように縮小されることになりました。
- 2025年3月31日以前の方:各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
- 2025年4月1日以降:各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給

なお、給付率は「60歳時点の賃金と比較した60歳以降の賃金の差」で、以下のように決まります。
| 60歳時点の賃金と比較した60歳以降の賃金の差 | 支給率 |
| 75%以上 | 0%(支給なし) |
| 64%超75%未満 | 0%~10%未満(逓減) |
| 64%以下 | 10% |
例えば、60歳到達時の賃金月額が30万円で、60歳以降における支給対象月の賃金が18万円の場合で考えてみましょう。60%に給与が下がっているため、2025年3月31日以前と2025年4月1日以降では、以下のように差が発生します。
| 時期 | 支給額/月 |
| 2025年3月31日以前 | 18万円×15%=2万7,000円 |
| 2025年4月1日以降 | 18万円×10%=1万8,000円 |
給付の縮小に伴って、毎月の手取り額に1万円以上の影響が出る可能性も考えられます。60歳~64歳以下の従業員を雇用している事業主の方は、給付が縮小される点について、あらかじめ対象者に伝えておくとよいでしょう。
高年齢雇用継続給付が支給されない人
高年齢雇用継続給付金は、すべての高年齢労働者に支給されるわけではありません。以下に該当する場合、支給されないため注意しましょう。
- 60歳以降の賃金が60歳時点の賃金の75%以上である場合
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者でない場合
- 雇用保険の被保険者期間が5年未満の場合
- 役員であった者(雇用保険に加入していないため)
- 60歳以降の雇用継続後の勤務が週20時間未満の場合(雇用保険に加入しないため)
- 雇用継続後の賃金が376,750円以上の場合(2024年8月1日以降。毎年8月に改定)
なお、60歳に達した日の時点で雇用保険の被保険者期間が5年未満でも、その後5年以上の要件を満たすと支給対象となります。
事業主から見た高年齢雇用継続給付のメリット

高年齢雇用継続給付は、その名の通り高年齢者の雇用を継続することを主眼に置いた給付金制度です。
60歳以降は60歳時点よりも給料が低くなってしまう可能性がありますが、給付金があることで、従業員は「継続して就労したい」という意欲が増します。
企業にとっては、技能・スキル・知識を持った高齢者を雇用できるため、労働力の確保につながるでしょう。
高い技能やスキルを持つ従業員を継続雇用しやすくなる
多くの企業は定年を60歳に設定しています。60歳で定年した後、嘱託社員や契約社員として再雇用するケースはよくあることです。
高年齢雇用継続給付金により、高い技能やスキルを持つ従業員を継続雇用しやすくなります。60歳の方でも心身ともに健康であり、しかも高い技能やスキルを持っているのであれば、企業にとって貴重な戦力となるはずです。
一般的に、定年後再雇用になると給料が低くなります。例えば、60歳時点で月給40万円だった従業員が、継続雇用後は月給25万円になると、スキルの高い従業員にとって転職や退職を考える要因となりかねません。
しかし、高年齢雇用継続給付金があることで、給料減の一部をカバーできます。給付金により実質的な収入減少を抑えられれば、従業員は継続して働くモチベーションを保ちやすくなるでしょう。
その結果、高い技能やスキルを持つ従業員を継続雇用しやすくなります。賃金負担を抑えつつも、熟練した人材を確保できる点は事業主にとってメリットといえるでしょう。
労働意欲がある高齢者を活用できる
給付金という経済的なインセンティブがあることにより、高齢者の労働意欲が高まると期待できます。自社の業務に熟練しており、またモチベーションが高い高齢者を継続雇用することにより、人材確保と生産性の向上を図れるでしょう。
60歳以上の方の多くは、退職後も「経験を活かして働きたい」「社会とのつながりを持ちたい」「健康のために働きたい」「年金だけでは不安だから、働いて収入を得たい」など、さまざまな理由で就労意欲を持っています。
もともと労働意欲がある高齢者に対して、高年齢雇用継続給付による経済的なインセンティブを与えられれば、長期的な継続雇用につながるでしょう。
高年齢雇用継続給付金は、雇用保険に加入すれば、正社員でなくても短時間勤務やパートタイムでも対象です。高齢者の体力や生活スタイルに合わせた働き方を提案できれば、快適に働いてもらえるでしょう。
事業主から見た高年齢雇用継続給付のデメリット
事業主からすると能力・意欲のある高齢者を雇用しやすくなる高年齢雇用継続給付金ですが、いくつかデメリットもあります。
老齢厚生年金の支給停止に配慮する必要がある
高年齢雇用継続給付金と65歳になるまでの老齢年金(特別支給の老齢厚生年金や繰上げ受給している老齢年金など)を併給する場合、年金の一部が支給停止されます。
最高で標準報酬月額の6%にあたる年金額が支給停止となるため、生活に影響が出るかもしれません。例えば、標準報酬月額が20万円の場合、20万円×6%=1万2,000円の年金が減額されます。
60歳~64歳以下で、年金を受給している従業員がいる場合は、減額が発生する点について配慮する必要があります。事前に説明をして、理解を得ておきましょう。
2カ月に一回申請が必要
高年齢雇用継続給付金の申請は、原則として2カ月に1回ハローワークに対して行います。従業員が自身で申請することも可能ですが、実務上は企業が行うのが一般的です。
2カ月に一回申請が必要であるため、事務的な負担が発生する点はデメリットといえるでしょう。
高年齢労働者処遇改善促進助成金とは

高年齢の労働者の就業を促進する制度に、「高年齢労働者処遇改善促進助成金」があります。
60歳~64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、賃金のベースアップをした事業主に対して支給されます。具体的な支給要件や支給額を見ていきましょう。
支給要件
高年齢労働者処遇改善促進助成金を受給するためには、以下の支給要件をクリアしなければなりません。
- すべての対象労働者の1時間あたりの賃金を60歳時点の75%以上に増額する
- 改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額が改定前より減少している
- 支給申請日において改定後の賃金規定等を継続して運用している
例えば、60歳時の時給が2,000円だった従業員の場合、改定後の時給を1,500円(2,000円の75%)以上に増額する必要があります。
賃金規定を改定し、高年齢雇用継続基本給付金の総額が改定前より減少していること、支給申請日において改定後の賃金規定を継続して運用していることも求められます。
支給額
高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給額を計算方法は、以下のとおりです。
| (改定前の高年齢継続基本給付金の総額-改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額)× 2/3 ※1 |
※1 中小企業以外は1/2
つまり、高年齢雇用継続基本給付金の受給額の変化に応じて、受給できる高年齢労働者処遇改善促進助成金は決まります。
改定前に受給していた高年齢雇用継続基本給付金の総額が30万円、改定後が0円の場合、助成額は「30万円×2/3=20万円」です。
なお、支給対象期は第1期から第4期まで(6ヶ月ごと)の最大4回、最長で2年間受給できます。
申請手続き
高年齢労働者処遇改善促進助成金の申請手続きは、以下のとおりです。
- 賃金規定等改定計画書を作成する
- 賃金規定等改定予定日の前日までに労働局長(提出先は管轄の労働局またはハローワーク)に提出し、認定を受ける
- 賃金規定等の改定を実施する
- 改定後の賃金規定等を6ヶ月以上継続して運用する
- ハローワークが指定した給付金支給申請月の翌月初日から2ヶ月以内に申請する(電子申請も可能)
手続きで不明点があれば、労働局かハローワークで聞くとよいでしょう。
高年齢雇用継続給付と高年齢労働者処遇改善促進助成金は併用できない

高年齢雇用継続給付と高年齢労働者処遇改善促進助成金は、併用できません。それぞれの制度は相互に排他的であるためです。
| 高年齢雇用継続給付 | 高年齢労働者処遇改善促進助成金 | |
| 目的 | 高年齢者の安定した雇用継続のための経済的支援 | 労働を希望する高年齢労働者の処遇改善 |
| 支給対象 | 従業員に直接支給 | 事業主に支給 |
| 支給要件 | 「60歳時点の給与」と「60歳以降の給与」を比較し、給与が減少している | 賃金規定等の改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額が、賃金規定等の改定前よりも減少している |
高年齢雇用継続給付は、「60歳以降の給与」が「60歳時点の給与」よりも減少していることが要件です。一方で、高年齢労働者処遇改善促進助成金は60歳から64歳の従業員の給与を引き上げることが要件となっています。
それぞれの給付金と助成金は両立できないため、状況に応じてどちらの制度を活用するか考える必要があります。
高年齢労働者処遇改善促進助成金の活用がおすすめの事業主

60歳以上の従業員の給与を引き上げれば、高年齢労働者処遇改善促進助成金を受給できます。
高年齢労働者処遇改善促進助成金の活用がおすすめできる事業主の特徴を見ていきましょう。
根本から賃金を見直したい事業主
60歳~64歳の高年齢労働者の処遇を根本から改善し、賃金ベースを増額することで、高齢者雇用を促進できます。現在の給与規定を根本から見直し、高齢者の雇用や定着を促進したいと考えている事業主に向いているでしょう。
60歳以降の賃金が低いと、従業員の就労意欲を損ねてしまいます。「やっている仕事は60歳前後で変わらないのに、給料だけ下がってしまった」「安い賃金だから、相応の仕事をしていればよい」というモチベーションだと、生産性が停滞してしまうでしょう。
高年齢労働者処遇改善促進助成金を活用して根本から賃金を見直せば、高年齢労働者のモチベーションを高められます。その結果、業務生産性が向上する期待が持てるのです。
技能やスキルがある高齢者を雇いたい事業主
賃金のベースを向上させれば、技能やスキルがある高齢者を雇いやすくなるでしょう。定年後再雇用の従業員を継続的に雇用するだけでなく、新たに雇い入れる際にも、他社よりよい条件を提示できれば採用で有利になります。
人材採用だけでなく、人材定着にも賃金ベースの増額は効果的です。年齢に関係なく人材確保を進めたいとき、高年齢労働者処遇改善促進助成金を有効活用するとよいでしょう。
今後はますます、60歳以上の労働者が増えていくと考えられます。助成金を得られるのは65歳に到達するまでですが、その後も継続的に優れた人材を雇用したいときに高年齢労働者処遇改善促進が役立つでしょう。
人手不足解消に取り組む事業主
昨今は、就労意欲の高い高年齢労働者が増えています。実際に、内閣府の資料によると令和5年度における60~69歳の就業率は以下のとおりでした。
| 男性 | 女性 | |
| 60~64歳 | 84.4% | 63.8% |
| 65~69歳 | 61.6% | 43.1% |
| 70~74歳 | 42.6% | 26.4% |
人材不足に悩む企業としては、即戦力になる人材は貴重です。賃金のベースを高めて競合となる企業と差別化できれば、高年齢労働者を雇い入れやすくなり、人手不足の解消につながる可能性が考えられるでしょう。
まとめ:高年齢雇用継続給付と高年齢労働者処遇改善促進助成金を活用して高齢者雇用を促進しよう
高齢者人口が増加する中で、高齢者の方を積極的に雇用する動きは進んでいくと考えられます。年齢に関係なく、知識・技能・スキルを有している人材は、貴重な労働力となってくれるためです。
2025年4月より高年齢雇用継続給付が縮小となります。従業員が受給できる給付金額が少なくなるため、注意が必要です。
高年齢者の雇用を促進する制度として、高年齢労働者処遇改善促進助成金もあります。60歳~64歳の従業員の賃金をベースアップした事業主が受給できるため、活用を検討してみてください。
創業手帳では、事業主の方に役立つ補助金・助成金に関する情報を解説した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。3ヶ月1度内容を更新し、最新情報をお届けしているため、ぜひご活用ください。
さらに、創業手帳では、新たな人材を求めている方、人材育成のために何をすべきか悩んでいる方などにおすすめの「雇用で差がつく助成金10選」を無料配布しています。国や自治体から支給される、返済不要の助成金を使ってぜひ雇用を成功させましょう。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「補助金ガイド」は、数多くの起業家にコンサルティングを行ってきた創業アドバイザーが収集・蓄積した情報をもとに補助金・助成金のノウハウを1冊にまとめたものになっています。無料でお届けしますのでご活用ください。また創業手帳では、気づいた頃には期限切れになっている補助金・助成金情報について、ご自身にマッチした情報を隔週メールでお届けする「補助金AI」をリリースしました。登録無料ですので、あわせてご活用ください。