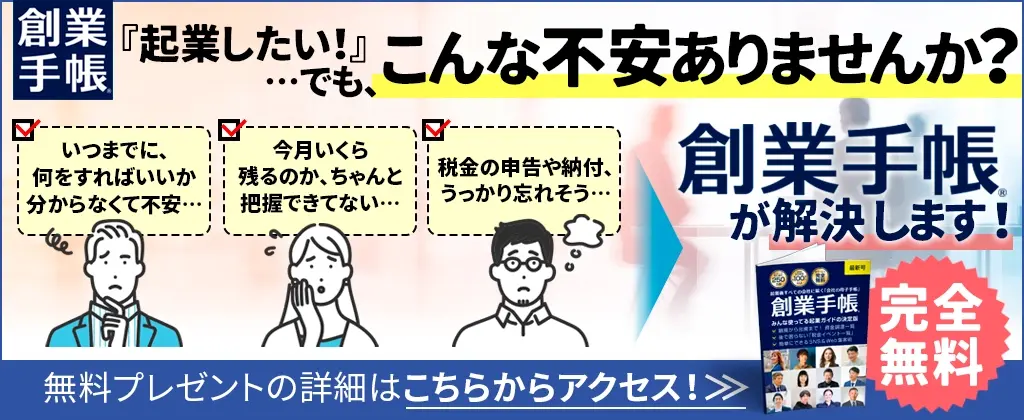会社設立に役員は必要?ひとりでもできる?基本からわかりやすく解説
会社形態ごとに役員のルールは異なる

会社設立を検討する際、「役員は何人必要?自分ひとりでも設立できる?」といったことで悩む人も多いかもしれません。
株式会社や合同会社では設置要件や任期、報酬の決め方が異なり、実務上の注意点もあります。
本記事では、会社形態ごとの役員の必要条件やひとり会社の運営ポイント、登記や税務の注意点までをわかりやすく解説します。
これから会社を設立する際の参考にしてください。
『創業手帳』は、会社設立後に必要な手続き・資金調達・税務・人事など、経営の基礎が一冊でわかる起業ガイドです。無料でお届けしていますので、ぜひご参考ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
そもそも「役員」とは?会社における役割

取締役や会社役員といった言葉は日常的に耳にする機会があります。しかし、役員とはどのような立場なのか、定義が何であるかは知っているでしょうか。
ここでは、そもそも「役員」が何なのか、会社における役割は何かをおさらいします。
役員は会社の業務執行や意思決定を担う立場
役員とは、会社における経営方針、事業の意思決定や業務執行、監査を担う立場を指す言葉です。
会社法上の取締役・会計参与・監査役が含まれるほか、税務上では理事や監事、清算人なども含まれます。
実質的に経営に関与する相談役や会長、顧問も役員に含まれることがあります。
会社によっては専務や常務執行役員が設置されている場合もありますが、企業独自に設定するものであり職務内容や経営への関与度合いによって判断しなければいけません。
役員の主な種類は以下の通りです。
| 役員の種類 | 主な役割 | 設置義務 |
|---|---|---|
| 取締役 | 会社の業務執行を決定・監督する。取締役会がない場合は個別に業務執行。 | 1名以上必須 |
| 代表取締役 | 会社を代表し、業務執行の最終責任を持つ。 | 取締役会を設置する場合は必ず選任が必要。取締役会がない場合は、取締役1名が代表取締役を兼ねてもよい。 |
| 監査役 | 取締役の職務執行を監査する。 | 原則任意。ただし、大会社など一定の場合は必須。 |
| 会計参与 | 取締役と共同して計算書類を作成する。 | 取締役会を設置する非公開会社で監査役がいない場合に設置。 |
| 会計監査人(公認会計士等) | 会計監査を行う。 | 上場会社や大会社では必須。 |
上記のような役員は経営を担う立場であり、株主や従業員とは異なる法的地位と義務を負う立場で登記が必要です。
株主や従業員との違い
役員と従業員、株主との違いは会社との関係性です。まず、社員は会社と雇用契約を結んで労働力を提供する立場です。
一方で役員は、労働基準法上の労働者には当たらず、委任契約である任用契約を結んで仕事を行います。
役員は雇用関係にはないので、労災保険や雇用保険の対象外です。ただし、社員と同じように勤務している実態がある場合には例外とされています。
さらに株主は、会社の株式を所有している会社の所有者であり、役員は株主から任命されて経営業務を提供しています。
つまり、株主が所有している会社で実務的な経営業務を役員が実施するという関係です。中小企業の場合には、株主が取締役として経営を担っているケースも多くあります。
会社形態別|必要な役員の数と種類

会社の規模や事業によって置かれている役員の数や種類は違います。ここでは、会社形態別に最低限必要な役員の数と種類をまとめています。
株式会社の場合
株式会社の役員の人数は、会社法で規定があり、会社の形態によって最低人数が変わります。株式譲渡制限会社と取締役設置会社を以下では紹介しています。
どのような会社の形態にするかによって必要な役員も変わるので、それぞれの内容を把握してから会社形態を決定してください。
株式譲渡制限会社
株式譲渡制限会社とは、すべての株式において譲渡制限に関する規定がある会社をいいます。
つまり、株主が株式を譲渡するためには、取締役会か株主総会の許可が求められる会社を指します。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
出典『e-Gov法令検索「会社法(平成十七年法律第八十六号)」』
株式譲渡制限会社は、取締役1名以上で設立でき、取締役会の設置は義務ではありません。
設立する会社を株式譲渡制限会社にするには、定款に株式の譲渡に関する制限があると記載します。
記載していない場合には、公開会社となって取締役会設置会社として役員の設置が必要です。
取締役会設置会社
取締役会設置会社では3人以上の取締役設置が義務づけられています。
5 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。
出典『e-Gov法令検索「会社法(平成十七年法律第八十六号)」』
取締役会を設置するかどうかは原則任意ではありますが、株式譲渡に制限を設けない公開会社や監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は取締役会の設置が必須とされています。
合同会社(LLC)の場合
株式会社は、出資者である株主と経営を担う取締役員は別である、所有と経営の分離が原則です。
一方で合同会社は、会社の経営者が出資者であり、社員といえば出資者であり、出資していない社員を社員とは呼びません。
合同会社では、出資した社員全員が経営権を持ち、出資と設立、業務執行と代表のすべてを社員がおこないます。
そのため、株式会社のような取締役や監査役といった「役員」という概念はありません。
合同会社を設立するため必要な人数は決まっていないため、社員ひとりだけでも合同会社を設立することが可能です。
「ひとり会社」の役員はどうなる?

会社の形態を選べば「ひとり会社」の設立は可能です。
合同会社はひとりで設立可能であり、さらに代表取締役が自社の株を持っていて株主と代表取締役を兼任してひとり会社を設立することも可能です。
ただし、1人で設立したとしても会社設立時に求められる手続きや書類は同じになります。
設立登記や税務上の手続きもすべて自分だけでこなすため、手続きや作業の負担が大きくなる点には注意してください。
ひとり会社に特有のリスクと注意点
自由に意思決定したいとひとり会社を選択するケースもあります。しかし、ひとり会社特有のリスクについても知っておいてください。
ひとり会社の場合、1人で持ち分を独占して単独の意思決定で事業をおこないます。
事業の意思決定を自分だけの判断でできることはメリットではありますが、意思決定の客観性が欠ける点に注意してください。
同じ立場で相談できる相手がいない点もデメリットであり、事業の成否も個人の能力に左右されます。
1人でプレッシャーや責任を負い続ける苦しさから続けられないケースもあるかもしれません。
ひとり会社のほうが、資金調達や取引先との契約の際に信用されにくい点もデメリットです。
1人で経営していると、万が一自分が働けなくなれば事業が完全に停止してしまいます。
そのため、取引先や金融機関から事業の継続性が低いとみなされてしまうリスクがあります。
ひとり会社ならではのメリット
会社を設立する時には、商号や事業内容、定款など決めなければいけないことが山のようにあります。
複数人で設立すると、皆が納得しないからと決定できずに手続きが進まないケースがあります。
1人で会社を立ち上げるのであればすべての意思決定を自分で下すので、意思決定がスピーディーなため、ビジネスチャンスを逃さない点も経営上有利です。
ひとり会社は、自分の裁量で事業の意思決定するだけでなく、自分の働き方の決定権も自分にあります。
働く場所や時間も自分の裁量となるので、自分のペースで自由に経営したい人に適したスタイルです。
役員の任期・報酬・登記の注意点

会社役員は、社員とは立場が違い、任期や報酬についても規定があります。どのような点に注意しなければならないのか以下にまとめました。
任期の設定
役員には任期があり、株式会社の取締役任期は原則2年と定められています。
ただし、非公開会社では定款で最長10年まで延長可能です。10年以内であれば、1年でも9年でも問題ありません。
役員の任期はひとり会社であっても同じです。ただし、役員の再選が禁止されているわけではないので、再度選任して会社経営を続けることになります。
以下が会社法上の規定です。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
出典『e-Gov法令検索「会社法(平成十七年法律第八十六号)」』
任期が終わった役員は原則退任しますが、継続する時には一度退任してから重任手続きを行います。
これには株主総会の決議が必要で、議事録をもとにして法務局で役員変更の登記をしなければいけません。
役員が任期満了で退任した場合には決議は不要です。ひとり会社の場合には、代わりがいないので役員の重任になると予想されます。
重任するごとに法務局での手続きが必要になるので、手間を減らすのであれば任期を10年にしておくことをおすすめします。
役員報酬の決め方と税務上の注意点
役員報酬は、役員が働いて受け取る報酬です。
しかし、社員の給与とは扱いが違います。社員の給与と異なり役員報酬は原則としてその年度を通じて一定です。
増額や減額をしたい場合には、株主総会で決める必要があります。
役員報酬は、事業年度開始(期首)から3カ月以内の期間を除いては、原則変更は認められません。
税法上の損金として認められる役員報酬は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3種類です。
それぞれ支払方法の要件が定められていて、それ以外の形だと損金計上できないので注意してください。
役員変更登記の必要性
役員が変更になった時には、法務局で登記を行います。これは会社の基本情報を公的に明らかにするためです。
法務局が会社の役員構成を知らなければ会社の最新の実態を把握できません。企業体制の透明性を維持して公平なビジネス環境を確保するために登記が必要とされています。
ひとり会社の場合には、役員として任期を満了して再度役員として選任されるため、役員変更の手続き必要ないと感じるかもしれません。
しかし、任期満了で退任した役員の再度就任は役員の登記事項の変更であり登記が求められます。
株式会社であれば役員の就任や任期満了、重任から2週間以内に役員変更の登記を行います。
必要な登記をしていないと、100万円以下の過料が科される可能性があるので、速やかに手続をしてください。
登記がされていないからとペナルティを受ければ、金融機関や取引先からの信頼を損ねる可能性もあります。
ひとり会社であっても、会社の信頼性を保つために手続きは確実におこなってください。
よくある質問(FAQ)

会社設立は、手続きも多くわかりにくい部分も少なくありません。ここからは、会社設立時の役員についてよくある質問に回答します。
Q. 会社を設立するだけなら役員は1人でもいい?
前述した通り、株式会社・合同会社ともに役員1人での設立は法律上可能です。役員が1人であっても会社法上の責任や義務は複数人の場合と同じで特別な扱いはありません。
ひとり会社では、複数人で行えば負担が少ない手続きや作業も1人で実施します。
誰かに相談したい時、スケジュールや体力の負担が大きすぎると感じた時には、複数人で設立するか専門家に任せてしまうことも検討してください。
ひとり会社は意思決定が迅速で自分の希望が通りやすいメリットがある一方で信用力や経営判断の幅が狭くなる点が課題です。
状況に応じて複数人役員体制のほうが望ましい場合があるので、置かれた環境を踏まえて検討してみてください。
Q. 親や配偶者を役員にしても問題ない?
複数人を役員にすると考える時に、できるだけ信用できる人物を役員にしたいと考えるのは当然のことです。
その中で信頼できる人物として親や配偶者を役員にする方法があります。
親や配偶者を役員にすることは法的に問題ありません。所得を分散できるので節税効果も期待できます。
ただし、利益相反や業務の公正性確保に配慮は必要です。
家族で経営すると、経営責任や役割分担があいまいになりがちです。契約や議事録でそれぞれが担う役割を定めておくようにしてください。
Q. 報酬ゼロの役員でも登記できる?
役員報酬は、金額の変更などに制限がある一方で役員報酬をゼロとして登記することも認められています。
会社の設立直後は、経営が不安定な場合も多くできるだけビジネスにお金を使うために報酬ゼロを設定することがあります。
法人を設立すると基本的に社会保険に加入することになりますが、役員報酬がゼロであれば社会保険の加入義務もありません。
税金や社会保険料の負担を軽減できるものの、役員個人として国民健康保険や国民年金への加入は必要なのでその負担はあります。
役員報酬がゼロだと会社が計上できる経費が減るため、収益が増加して結果として法人税が増えてしまうことがある点には注意が必要です。
役員報酬の額は、生活資金や税務上の影響も踏まえて決めなければいけません。
会社として支払う税金と役員個人の負担を比較して納税額のバランスが取れた役員報酬に調整してください。
まとめ|会社にとっての「役員」の意味を理解しよう
役員は会社の経営を担う重要な存在であり、人数や任期、報酬の設定は経営基盤に直結しています。
1人で立ち上げたからといって役員も自分だけで進められると単純に考えるのはおすすめできません。
ひとり会社でも将来の拡大や信用力向上を考えると、役員構成を戦略的に計画すべきです。
法的要件を満たすだけでなく、実務面のメリット・デメリットを踏まえて役員人事を行うようにしましょう。
創業手帳(冊子版)は、これから会社設立に動き出す人に向けて役立つ記事を多数掲載しています。役員が必要か、ひとり会社を検討するときにも創業手帳をお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)