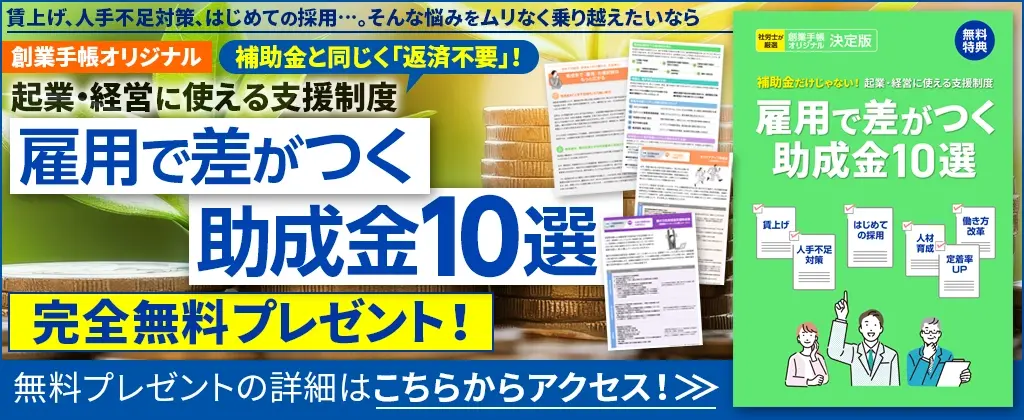従業員の雇用手続きは4ステップ!必要書類やトラブルの対処法も解説
従業員を雇用した時の手続きはスケジュールを立てて進めよう

新しい従業員が増える時、職場での受け入れや仕事の引継ぎなど、やらなければならないことは多くあります。
職場で速やかに職務に従事するためには、従業員の雇用手続きを円滑に進め、新しい仲間が働きやすい環境を整えてください。
従業員の雇用手続きやそのスケジュールについて紹介します。
採用活動だけでなく、その後の社員のスキルアップや正社員化などにも使える「雇用で差がつく助成金10選」を無料でプレゼント中です。社労士が厳選した助成金について、申請の流れや、概要の一覧などを掲載しています。ぜひこの機会にご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
企業が従業員に郵送する雇用手続きの必要書類

会社が新しく従業員を雇用することになった場合、様々な書類を用意する必要があります。
以下では代表的なものを紹介しました。
必要に応じて返信用封筒を添えて、署名捺印の上で返送してもらってください。
採用通知書(内定通知書)
実務において、雇用契約書は作成しても内定通知書は作らない会社もあるでしょう。内定通知書のように採用の決定を応募者に伝える書類は法律で義務化されてはいません。
しかし、電話やメールでの連絡だけでは、聞き間違いや勘違いが起こる可能性もあります。
採用の意思を明確に示して伝えるため、トラブルを避ける目的で多くの企業では内定通知書が使われています。
雇用契約書・労働条件通知書
雇用契約書と労働条件通知書は、雇用主と従業員の間での労働条件の取り決めについてまとめたもので、双方の署名か記名押印をします。
雇用契約書は法的には発行しなくても問題はありません。お互いの認識違いでトラブルが起きることがないように、多くの会社で取り交わされています。
一方で、労働条件通知書は、労働基準法で交付が義務化され、雇用主側の署名または記名押印が求められます。
雇用契約書と労働条件通知書をまとめて、労働条件通知書兼雇用契約書とされる場合もあるので、自社に適した方法で交付してください。
扶養控除等申告書
扶養控除等申告書は、税金や社会保険の手続きに必要です。扶養控除とは、扶養親族がいる場合に税金の控除を受けられる制度。
この申告書の情報をもとにして、毎月の給与から控除する所得税額が決定されます。扶養者がいない場合でも提出が求められます。
健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届
健康保険被扶養者異動届と国民年金第3号被保険者届は、扶養者がいる場合に提出が求められます。社会保険の加入手続きの際に使用します。
入社誓約書
入社誓約書には、就業規則や服務規律などが記載されています。
入社に対する意思確認のための入社承諾書を兼ねている場合もあり、従業員に署名捺印をしてもらいます。
従業員が入社時に提出する雇用手続きの必要書類

入社する時に回収する書類は多くあります。以下では、その中でも主なものを紹介していきます。
雇用保険被保険者証番号
過去に雇用保険に加入していたことがある内定者には、雇用保険被保険者証番号を求めます。
雇用保険被保険者番号は、「4桁-6桁-1桁」で構成される番号です。
雇用保険被保険者証は、基本的に勤めている会社が保管して従業員が退職する時に返却します。
もしも紛失していた場合には、雇用主がハローワークに確認依頼を行うか、従業員が再交付を申請します。
基礎年金番号
基礎年金番号は、社会保険の手続きに必要な番号で「4桁-6桁」で構成されています。
基礎年金番号は年金手帳や基礎年金番号通知書から確認できますが、年金手帳の交付は廃止されたため、現在では交付や再発行は基礎年金番号通知書が発行されています。
給与振込先の口座情報
給与の振込先の口座情報も入社後に必要です。会社で書類を用意してあらかじめ銀行名や口座番号の情報を記入してください。
また、通帳の口座番号がわかるページをコピーする方法も使われています。
個人情報保護に関する誓約書
個人情報保護法の施行などによって、個人情報といった情報管理の重要性が増しています。
従業員が情報を持ち出したり不正利用したりすることがないように、企業の管理や説明が必要です。
入社してから企業の情報管理のルール、情報漏洩時の損害賠償といった内容について認識させた上で同意を得るようにしてください。
マイナンバーカードの写し
マイナンバーは、住民票を持つすべての人に割り当てられた個人番号です。税金や保険の手続きには、マイナンバーが必要となります。
マイナンバーは、マイナンバーカードや個人番号通知カード、住民票から確認できます。
扶養家族がいる場合には、本人だけでなく扶養家族のマイナンバーも必要です。
取得時には必ず利用目的を明らかにするように法律で定められているので注意してください。
源泉徴収票
源泉徴収票は、従業員が1年間にどれだけの収入を得て所得税をいくら支払っているかがわかる書類です。
年末調整を行う時に必要となるため、中途採用をして前の会社と入社する年が重なる時には源泉徴収票の提出を求めます。
従業員の雇用手続きの4ステップ

従業員を雇用するには、多くの書類や届け出が必要です。ここでは、全体としてどのような手順で雇用していくのかを把握していきます。
1.社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続き
従業員が働く時には、社会保険や労働保険の加入手続きを行います。
社会保険は、健康保険と厚生年金保険から構成され、加入条件を満たす場合には資格取得の手続きを行います。
従業員を雇い入れてから5日以内に、健康保険・厚生年金被保険者資格取得届、被扶養者がいれば健康保険被扶養者(異動)届を所轄の年金事務所に提出することが必要です。
社会保険の資格取得手続きが完了すると保険者から健康保険証が送付されるので、届き次第従業員本人に渡してください。
2. 労働保険の加入手続き
労働保険は、労働災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。労働保険それぞれの加入しなければいけないので、忘れることなく手続きしてください。
労災保険
ケガや病気をした時に給付される労災保険、仕事を失った時に給付される雇用保険は従業員が安心して働くために不可欠なものです。
従業員をひとりでも雇用していれば加入が義務づけられています。
ただし、労災保険の手続きは初めて従業員を雇う時だけです。労働者であれば、アルバイトやパートであっても全員が自動加入となります。
雇用保険
雇用保険の手続きは、ハローワークで行います。初めて従業員を雇用する時には、10日以内に雇用保険適用事業所設置届を提出してください。
採用した時には、翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
月末入社の場合のように、提出期限までに余裕がないケースもあるので注意しましょう。
3. 給与支給に向けた税金(所得税・住民税)の手続き
従業員を雇用すると、所得税や住民税の手続きも必要になります。
それぞれを紹介します。
所得税の手続き
所得税は、1月1日~12月31日までに得た所得に対して課せられる税金です。
所得税は、『課税所得金額×税額−税額控除』で計算され、給与所得者の税金に関わる部分なので正確に計算しなければいけません。
所得税は、従業員から提出される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもとにして計算します。
源泉徴収票を不備なく従業員に発行するため、事業者は源泉徴収簿を作成して支払った給与や扶養家族の情報を記録しておきます。
住民税の特別徴収の確認
住民税は、地域に住む住民が地域で必要な費用を分担する目的の税金です。
住民税は、前年の所得に対して課税され、従業員が普通徴収か特別徴収かによって手続きが異なります。
普通徴収は、従業員が個人で手続きして納税する方法です。個人事業主やフリーランスで働く人は、普通徴収です。
特別徴収は、雇用主が従業員に代わって給与から住民税を天引きして納税する方法です。
前の職場で特別徴収を選択していて、入社してから特別徴収を選ぶ場合には給与所得者異動届出書を各市区町村に提出します。
4. 会社で進める総務上の手続き
労働保険や社会保険の手続きには、定められた期限があります。
一方で、社内で進めておく手続きには期限はないため、後回しにしてしまうかもしれません。しかし、従業員がスムーズに働き始めるためには社内の手続きも重要です。
社内で進めておく手続きを紹介します。
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作成
内定者が決まったら、さっそく名簿の作成に取りかかりましょう。
労働者名簿と賃金台帳、出勤簿の法定三帳簿は労働基準法で保管義務が定められています。
それぞれ保管義務期間や記入項目が定められている重要書類なので速やかに作成してください。
制服・備品の準備
入社後すぐに仕事に取りかかるためには、使用する備品や制服は事前に用意しておきます。
制服や作業服は事前にサイズをヒアリングして、入社してすぐに渡せるようにしてください。
また、社員証や名刺のほか、仕事で使う備品類を準備します。配属先が決定しているのであれば、デスクやイス、電話やパソコンなども準備しておくとスムーズです。
メールアドレス・社内システムへの登録
パソコンの設定は、入社してから本人が実施するケースが多いかもしれません。
事前にマニュアルを用意しておくほか、仕事用のメールアドレスやネットワークに必要なIDやパスワードを準備しておきます。
従業員が増えることによって、人事システムや給与計算システムにも変更が生じます。
入力する内容は、氏名や住所、扶養親族といった個人情報です。給与を振り込む銀行情報の登録も忘れずに行います。
従業員の雇用手続きでよくあるトラブルと対処法

従業員は一人ひとり事情が違うため、トラブルが生じることもあります。どういったトラブルが起こるのか対処法とともに紹介します。
保険の手続きが期限までにできなかった
従業員を雇用するには、社内の手続きだけでなく社会保険や雇用保険といった外部とのやり取りも行わなければいけません。
しかし、必要書類が揃わなくて期日を過ぎてしまうケースもあります。
基本的には、期日を過ぎても手続きはできるので、すぐに関係する役所に連絡するか早急に手続きしてください。
特に健康保険は保険証の交付にも関わるので、可能な限り早い対応が望まれます。
雇用保険被保険者証がない・雇用保険被保険者番号が不明
雇用保険被保険者証が見つからない、被保険者番号がわからないといった場合には、被保険者本人が手続きを行います。
雇用保険被保険者証再交付申請書で申請することによって、被保険者証の再交付を受けられます。
年金手帳をなくした
社会保険の手続きには、年金手帳が必要ですが紛失した方もいるかもしれません。
以前は再交付手続きを行っていましたが、2022年に年金手帳が廃止されたため再交付されません。
基礎年金番号通知書の発行を依頼してください。
外国人を初めて雇用した
人手不足から、外国人就労者を雇用するケースは増えています。
外国人は、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められている在留資格の範囲内で就労できます。
雇い入れの際には、在留カードやパスポートで身元や在留資格を確認してください。
海外在住の外国人を日本国内に呼んで雇用する時には、在留資格認定証明書の交付申請や在留資格認定証明書の送付が必要です。
雇い入れてからも外国人雇用状況の届け出をハローワークに提出します。
まとめ・従業員の雇用手続きは期日や規定を理解してスムーズに進めよう
入社に関わる手続きや書類は多岐にわたいるため、混乱してしまったり、必要な処理を忘れてしまったりするリスクがあります。
また、マイナンバーのように提供してもらう方法や取り扱いに注意が必要な書類もあるので、慎重に進めなければいけません。
入社手続きを間違いなく進めることは、新しい従業員からの信頼を獲得するためにも重要です。各種の手続きは、マニュアル化してミスがないようにしてください。
創業手帳(冊子版)では、更に具体的な人事・労務の仕組みやアウトソーシングの利用方法なども解説。他にも資金繰りの方法やオフィス環境の整え方など、起業や経営に必要な情報がこの1冊にまとめられています。無料でお配りしていますので、是非ご活用ください。
雇用全般に活用できる補助金をまとめた、「雇用で差がつく助成金10選」を無料配布中です。詳しくは以下のバナーから!
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。