社内ベンチャーとはいったい何?取組みの意味やメリット、成功するポイントを解説
自社に新しいビジネスモデルを取り入れる社内ベンチャー。起ち上げ方から成功事例までわかりやすく解説します。

自社内に新たな事業のイノベーションを生み出すために、社内ベンチャーと呼ばれる取組みを導入するケースがあります。
社内ベンチャーは、斬新なアイデアを創出し、既存のリソースを利用して自社を成長させたり、社内の凝り固まった風土に新風をもたらしたりすることに有効です。
今回は、社内ベンチャーとはどのようなものか、成功するために必要なポイントなどを交えて解説します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
社内ベンチャーとは何か

まずは、社内ベンチャーの具体的な内容について説明します。
社内ベンチャーの概要について
社内ベンチャーとは、企業内において既存の事業にはない新たなビジネスモデルを創出するために設置する独立した組織を指します。
事業を軌道に乗せている企業では、新規事業に乗り出すリスクを避ける傾向がありますが、新たな挑戦でより多くの利益を上げるために導入されるケースが多いです。
社内ベンチャーは、企業が確立している資金力やノウハウを用いることで、これまでにない事業に乗り出せます。
そして、既存事業に依存しすぎないために、企業内の別組織として稼働する形態を取ります。
社内ベンチャーの目的とは
社内ベンチャーを起ち上げる目的には、具体的に以下のようなものがあります。
新たな方向性で利益を生み出す
長く既存事業を継続している企業では、現状維持のために利益の伸びしろが行き詰っているだけではなく、業務のマンネリが起こっていることが多いです。
このように現状維持を続けていると、市場に大きな変化が起きたときに流れに対応するのが難しく、経営が危ぶまれる事態にもなりかねません。
そこで、新規事業を起ち上げ別ルートで利益を生み出す仕組みを作り、業績向上やリスクを回避することに役立てます。
自社の社風に新しい風を取り入れる
企業が、既存事業に注力し続けマンネリが起こると、業務が単調化し凝り固まってしまいがちです。
この状態では、従業員のモチベーションも上がらず、成長が止まった社風をそのまま引きずってしまいます。
社内ベンチャーの存在は、新規事業によって従来の社風に新しい風を取り入れ、社内に活気を取り戻す効果も期待できます。
さらには、社内ベンチャーの存在により、既存事業との相乗効果で双方の成長も見込めます。
新たな事業を創出できる人材が育つ
社内ベンチャーの担当者は、事業のアイデアを創出して具現化するための思考力、実行力が求められます。さらに、経営ノウハウを身に着けることも重要です。
このような経験により、既存では得られなかった経験やスキルを積めるため、急激に成長を遂げ優秀な人材が育つ要素になりえます。
新事業への有効な投資
特に、大規模な企業では多額の利益を出し資金を増やすものの、資金の有益な活用方法が見いだせず持て余している場合もあります。
そこで、社内ベンチャーを起ち上げて新企業に投資することで、新たな資金の活用法が開けてきます。
さらに、新規事業が成功すれば大きなリターンを得られ、企業の経済状況に潤いをもたらすでしょう。
社内ベンチャーの立ち上げ方

社内ベンチャーは、主に以下の2つの起点から立ち上げられます。
経営者主導で行う
新規事業の展開について、企業の経営者から提案し主導を行う形です(トップダウン)。
このケースでは、新規事業のミッションや目標について経営者が決定し、社内ベンチャーを担当するメンバーは経営者が提示したミッションなどの実現に向けて動きます。
ただし、経営者の意図と市場の動きにずれが生じる可能性もあり、経営者と社内ベンチャーの間では綿密にコミュニケーションを取ることが求められます。
従業員からアイデアを募る
社内ベンチャーの立ち上げにあたり、従業員からアイデアやミッションを募って実行に移す形です(ボトムアップ)。
従業員から集まったアイデアやミッションの中で、実現可能なものや事業として成功できる可能性があるものを経営者が選出し、実際に社内ベンチャーとして実行します。
この形態であれば、実際の市場や現場の状況に即した事業の創出ができ、経営者の同意を得られれば比較的柔軟な事業展開が期待できます。
社内ベンチャーを立ち上げるメリット・デメリット
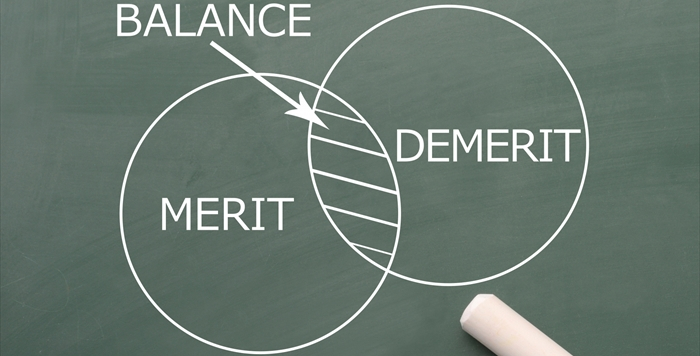
では、社内ベンチャーを立ち上げる際のメリットやデメリットは、どのようなものでしょう。
メリット5つ
1.これまでにない新規事業に挑戦できる
企業にとっては、これまでに生み出せなかった新規事業に乗り出すことができ、新しく利益向上の基盤を作り収益性を上げることが期待できます。
新規事業が軌道に乗れば、既存事業にも好影響をもたらし、相乗効果でさらなる企業の成長が見込めます。
2.自社内に革新的な流れをもたらせる
社内ベンチャーを起ち上げ新たな道を創出することは、企業にとって前向きかつ革新的な試みです。
革新的な事業に乗り出す流れは、社内の風通しをよくして人材の新たな可能性を見出します。
また、既存事業に従事していた従業員のモチベーションを向上させるなどの効果もあります。
3.必要なリソースが揃っていることでより発展できる
社内ベンチャーの事業は、企業の潤沢な資金やノウハウなどのリソースを存分に利用して行えます。つまり、まったくのゼロから始めるよりも事業に着手しやすいです。
また、事業展開に必要なリソースが揃っていれば、挑戦的なアイデアやミッションを実現でき、資金繰りに苦しむことなく飛躍的な発展が可能です。
4.自社がバックについているため信用度が高い
ゼロから起業するベンチャー企業やスタートアップは、実績がないことから社会的信用度を得ることが難しいかもしれません。
その点、社内ベンチャーは大元の企業のネームバリューをバックにつけることができ、社会的信用度を認められ取引き先の開拓や融資などの際に有利になります。
5.人材の成長を促せる
社内ベンチャーのメンバーとなった場合、既存事業での部署では発見されなかった新たな才能を開花できる可能性があり、埋もれていた人材を見出すチャンスになります。
また、自分たちで新たな事業にチャレンジし様々な経験を積むことは、人材の急激な成長やモチベーション向上につながり、ひいては企業への定着率の増加も期待できるでしょう。
デメリット4つ
1.失敗する場合もある
社内ベンチャーは、企業内で起ち上げた組織とはいえ、新しい分野での事業に挑戦するものであるため、もちろん失敗するリスクはついてきます。
もし失敗した場合は、その損失は大元となる企業へ大きな打撃を与えます。
その結果、企業の経営を圧迫し、社内ベンチャーのみならず企業自体も共倒れになる危険性があるかもしれません。
2.他社との競合についていくスピードが求められる
社外で立ち上げられるベンチャー企業やスタートアップのうち、特にスタートアップに関しては革新的な事業で急速な成長を目的としています。
社内ベンチャーで、まったく新しい事業に挑戦する場合、競合するスタートアップの動きについていけないと競り負けてしまうため、迅速な成長が求められます。
3.自社の後ろ盾があるためモチベーションを維持しにくい
起業に失敗すると後がないベンチャー企業やスタートアップと違って、社内ベンチャーは仮に失敗しても、その損失が多大でなければまた大元の企業に戻ることが可能です。
自社の後ろ盾があることは、悪い意味で安心感を与え、競合するベンチャー企業やスタートアップのようなモチベーションを維持しにくい側面もあります。
4.自社の意思決定に従わなければならない
ベンチャー企業やスタートアップの利点は、小規模であるために新規事業への施策に小回りが利き、柔軟性を活用できるところです。
しかし、社内ベンチャーは基本的に大元の企業の管理下に置かれるため、意思決定を上層部にゆだねなければならない事態になると、動きが取りにくくなってしまいます。
社内ベンチャーを成功させるためのポイント

社内ベンチャーを成功させるためには、以下の点に注意しておくと良いです。
従業員が参加しやすい環境を作る
企業側の姿勢として、従業員が積極的に社内ベンチャーに参加できる環境を作ることは課題です。
そのためには、新規事業への後押しをする意向を示し、協力体制をしっかり構築しなければなりません。
また、万が一の事態が起きた場合に備え、担当メンバーへのアフターサポートの体制を整えるなどの施策が求められます。
自社の意思決定を素早く行う
前述のとおり、社外のベンチャー企業やスタートアップと競合する時には、柔軟かつ迅速な意思決定が必要です。
企業の管理下に置かれる社内ベンチャーにおいては、経営者や上層部の介入はできるだけ少なくし、意思決定や人員配置などの権限は担当者に一任することが得策です。
自社リソースの活用を有効に行う
企業は、社内ベンチャーに対して自社の資金やノウハウなどのリソースを積極的に提供し、社内ベンチャーの事業に有効活用させる仕組みを確立させなければなりません。
リスクを恐れてリソースの提供を惜しんでいては、新たな事業の成長を効率的に後押しすることが難しくなります。
自社内の既存事業と切り離す
社内ベンチャーは、あくまで企業内の別組織であり、自社内の既存事業とのつながりを重視しすぎると新規事業への可能性が狭められる危険性もあります。
企業は、既存事業と社内ベンチャーの癒着をできるだけ避け、別の競合組織として双方が成長し合う関係を作り出すのが良いでしょう。
ひとつのチームで検証を行う
社内ベンチャーの担当メンバーをひとつのチームと考え、あくまでチーム内で新規事業における戦略立案と検証、問題点の抽出などを繰り返し行う体制を整えます。
様々な検証を行い、試行錯誤を一緒に経験することは、チーム内の結束を固めるだけではなく、人材のさらなる成長にもつながります。
社内ベンチャー内の仕組みを独立させる
企業内の組織であるとはいえ、社内ベンチャーはひとつの企業です。
そのため、経営の指針を決定する役員制度や経理部門など、会社組織としての仕組みは独立させておくべきです。
このような、会社運営にかかる重要な位置を大元の企業に依存すると、事業のスピード感が失われるだけではなく、各事務処理も混乱をきたす可能性があります。
他のスタートアップ・ベンチャー企業同様ビジョンとモチベーションを持つ
新規事業を行うにあたっては、具体的かつ明確なビジョンを打ち立てることが必須です。
担当メンバーだけで新たな道を切り開いて事業展開するためには、事業の目標となるビジョンを明確にしなければ迷走してしまいます。
これは、社外のスタートアップやベンチャー企業がモチベーションを保つために実践している過程です。
そのため、社内ベンチャーも競合他社と同等のモチベーションと情熱を持つ必要があります。
社内外との人脈を広げる
社内ベンチャーの利点は、大元の企業が後ろ盾になっていることです。
そのため、企業から独立した組織として運営するとしても、有事には企業のサポートを積極的に受けて問題はありません。
さらに、社外の取引き先などにも人脈を広げておけば、多くの人々の支えを受けながら事業を成功に導く道が開けます。
失敗の線引きを明確にする
社内ベンチャーは、企業から独立した組織であるとはいえ、資金などについては、企業と共有していることから、企業内の事業のひとつと捉える側面もあります。
そのため、新規事業が思うように展開できず収益が伸びない場合にも、明確な損失が生まれない限り失敗のラインが見えにくいです。
そのままずるずると事業を続けていると、大元の企業の経営を圧迫する可能性が高いため、失敗とする明確な基準を設定します。
その上で、基準に達したときに速やかに事業を撤退する仕組みを構築しておくべきです。
社内ベンチャーを成功させている事例

こちらからは、実際に社内ベンチャーを成功させた事例について紹介します。
大手企業内における学習アプリの開発・運営
求人広告掲載からITソリューションまで幅広く行っている大手企業では、スマホやタブレットで学習を行えるアプリを開発する社内ベンチャーを起ち上げました。
開発したアプリは、主に受検生を対象としたものであり、個人のみならず学校や塾などでの導入事例も増やしています。
これは、地域的もしくは経済的など、何らかの理由で塾に通うことができない受検生のニーズを的確に突いたものであり、飛躍的な成長を遂げました。
近年では、社会人向けの英会話コンテンツなどもリリースしており、会員数は右肩上がりです。
総合商社内で生まれた飲食店
日本を代表する大手総合商社の中で生まれた社内ベンチャーは、人々の食生活に寄り添う飲食店経営でした。
ただの飲食店ではなく、ストーリー性のあるコンセプトを掲げたスープ専門店であり、スープのある1日が充実したものになるようにとの願いが込められています。
このコンセプトと、軽食としてのスープメニューは、女性を中心とした多くの顧客を呼び込み、事業として急成長を遂げています。
新たなアイデア創出のために整えられた環境
幅広くIT事業を展開している大手企業の中には、社内ベンチャーを数十以上抱えているところがあります。
少人数で複数のチームを作ってアイデアを創出し、経営者や役員が介入しない審査に通過したものはスピーディに事業として発進する仕組みを整えています。
このようにして生まれた社内ベンチャーの中には、ゲーム業界で大きなシェアを占めるチームも存在し、大元の企業が積極的に社内ベンチャーを後押ししている好例です。
インキ製造会社から生まれたフィットネス事業
大手インキ製造会社から、フィットネス事業を全国に拡大させた例もあります。
これら2つの事業はにわかには結び付けにくいものですが、思わぬ発想から社内ベンチャーとして発展しています。
インキ製造に付随して製造していた樹脂が、グラウンドなどの地面・アンツーカーの原材料であったことから、スポーツ関連事業に乗り出すアイデアが創出されました。
そして、フィットネス事業は拡大するだけではなく、多角的な事業を展開しており、大きな成長を遂げて大元の企業から完全独立して上場企業までに成長しています。
まとめ
社内ベンチャーは、自社の既存事業では生まれなかったアイデアをもとに、新たな事業を起こす仕組みとして非常に有益です。
社内ベンチャーを起ち上げるにあたり、メリットとデメリットがそれぞれにあります。
しかし、デメリットに関しては成功のためのポイントを押さえていれば、おおよそ回避できるものです。
自社のさらなる発展のためにも、社内ベンチャーの仕組みを整えましょう。
(編集:創業手帳編集部)





































