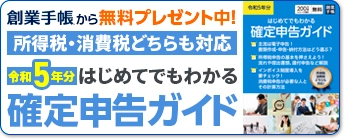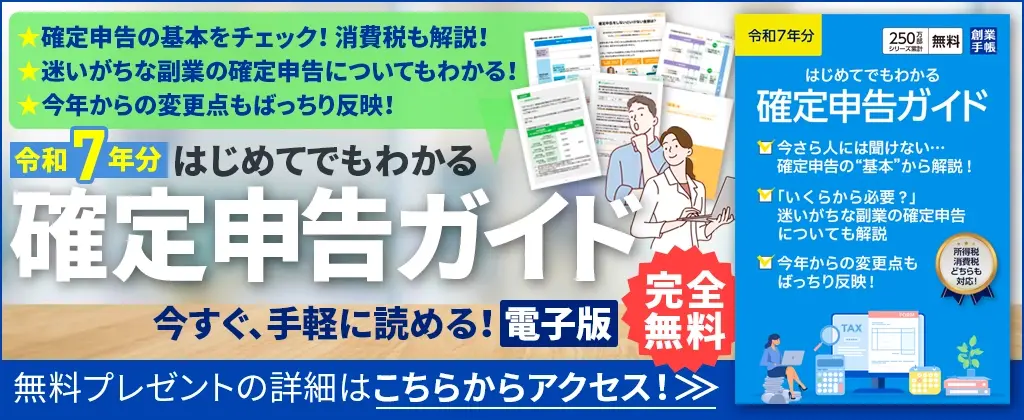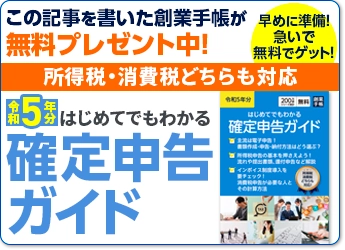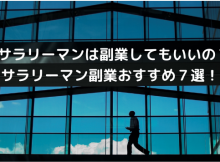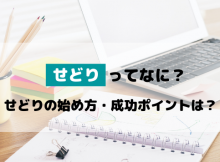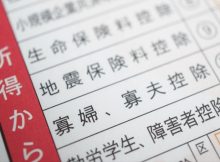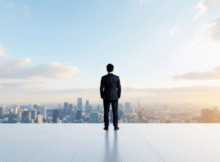副業で社会保険料はどうなる!?増えるケースと増えないケースを紹介。必要な手続きも解説
副業した際に事業主の会社にかかる負担も解説します

近年では働き方が多様化しており、副業を認める会社が増えています。副業の魅力は、本業を続けながら、自分の能力や経験を活かして新しい仕事ができることです。
しかし、副業を行うと社会保険料の負担が増えてしまう可能性がある点に注意が必要です。
また、それによって事業主の会社にどのような影響が出るのかも理解しておくことが求められます。
今回は、副業で社会保険料が増えるケースや、社会保険に加入する際の必要な手続きなどについて詳しく解説します。
創業手帳では、副業に特化して確定申告について解説した「副業確定申告ガイド」を無料でお配りしています。昨今副業をしている人が増えてきていますが、副業されている方の所得額よっては確定申告が必要になるケースもあります。本業のほうで年末調整を対応しているから大丈夫と思われている方、ぜひこちらを一度お読み頂ければと思います。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
副業で社会保険料が増えるケース

副業を始めれば収入を増やせますが、社会保険料の負担が増えるとなると、手取りに影響が出ます。
社会保険料が増えてしまうケースとして、以下の2つが挙げられます。
2ヵ所以上の事業所で働く場合
副業として2ヵ所以上の事業所で働いている場合、社会保険料が増える可能性があります。
社会保険に加入するためには、事業者ごとの加入要件を満たさなければなりません。
副業先の社会保険の加入条件を満たした場合には被保険者になり、保険料を支払う義務が発生します。
この場合、本業と副業先の両方の社会保険に加入し、それぞれで納付することになるので、結果的に社会保険料が増えることになります。
副業の雇用形態がアルバイト・パートといった非正規であっても、要件を満たせば加入義務が発生することに注意が必要です。
副業で会社を設立した場合
副業として自分で会社を設立して報酬を受け取る場合には、社会保険料が増えます。
1人社長での起業であっても、法人の代表者が役員報酬を得る場合は社会保険の加入義務が発生します。
その場合、本業から支給される給与との合計額を按分して決定される社会保険料を支払わなければなりません。
また、従業員を1人でも雇えば、年収によって従業員を社会保険に加入させる必要があります。なお、従業員が支払う社会保険料の半分以上は法人が負担しなければなりません。
そうなれば、経費に負担がかかることに注意が必要です。
副業で社会保険料が増えないケース
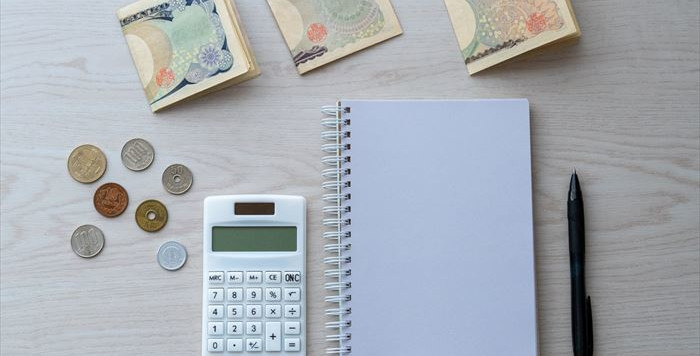
副業を行うと社会保険料が増えるケースがありますが、反対に副業の内容ややり方によっては社会保険料が増えないケースもあります。
社会保険料が増えないケースは以下のとおりです。
副業の収入が事業所得や雑所得の場合
副業の収入が事業所得や雑所得、不動産所得などであった場合、社会保険料が増える心配はありません。
副業として、FXや株式、不動産投資などをするケースもあります。投資は資産運用に該当するため、副業とは少し異なります。
また、投資や不動産の貸付けなどを行って収入を得る場合には社会保険に加入する義務は生じません。
ただし、法人を設立して投資を行うケースであれば話は別です。
法人から役員報酬を得るなど、社会保険の加入義務に当てはまる場合には、社会保険料が増えてしまうことに注意してください。
副業が個人事業の場合
法人化せず個人事業主として開業して、副業をする場合にも社会保険料は増えません。個人事業主は労働者ではなく、新しい社会保険が適用されることがないことが理由です。
現状、社会保険への加入は会社と個人事業主のいずれかとなっています。
本業が会社員であれば、個人事業を行っていても社会保険に加入している状態となります。副業の個人事業の収入に対しては社会保険料がかかりません。
ただし、副業を行うことで所得が増額して、所得税や住民税の負担が増えることはあります。
一定の金額以上の収入があれば、確定申告をして不足分の税金を納めたり、払い過ぎた税金の還付を受けたりする必要があります。
なお、個人事業主が常時5人以上の従業員を雇用する場合、一部業種以外は狭義の社会保険に加入しなければなりません。
また、1人でも従業員を雇用すれば労働保険の加入が必要です。従業員と個人事業主とで社会保険料を折半することになることに注意してください。
副業でいくら稼いだら?社会保険の加入条件

副業を始めたからといって必ず社会保険料が増えるわけではありませんが、2ヵ所以上の事業所に雇用されるケースでは注意が必要です。
労災保険は雇用される全従業員に適用されますが、労災保険以外の社会保険の加入には一定の条件があります。ここからは、社会保険の加入条件を紹介します。
健康保険・介護保険・厚生年金の場合
アルバイト・パートなどの非正規雇用でも、以下の条件のいずれかを満たしていれば、健康保険・介護保険・厚生年金の3つの保険に加入する義務が生じます。
1.1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が正社員の3/4以上
2.以下5つの要件を満たしている場合
-
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤務期間が2カ月以上超えて見込まれている
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生ではない
- 一般被保険者が常時100人以上の企業に務めている
1週間と1カ月の所定労働時間が正社員の3/4以下の場合や、5つの要件のいずれかを満たしていない場合には、社会保険の加入義務はありません。
また、本業以外の事業所に雇われて副業を行っていても、社会保険料が増えることはありません。
雇用保険の場合
雇用保険の加入条件は、健康保険・介護保険・厚生年金の3つの保険とは異なることに注意してください。
-
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 継続して31日以上の雇用が見込まれている
上記2つの条件を満たしていれば、雇用保険に加入できます。ただし、雇用保険の二重加入は認められていません。
雇用保険は「主たる賃金を受ける雇用関係」にのみ加入資格があるため、基本的には本業の勤務先で加入することになります。
副業を行う場合には、二重加入にならないように注意してください。
複数の社会保険に加入する時は自ら手続きをする

副業を行うことで、勤務先の社会保険への加入義務が発生すれば、自分で手続きする必要があります。
ここでは、社会保険加入に必要な手続きと、加入を怠った場合のリスクを紹介します。
加入義務が発生したら年金事務所・事務所センターに届け出る
複数の事業所で健康保険・厚生年金に加入する場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
提出先は、本業となる勤務先を管轄する年金事務所・事務センターや健康保険組合です。
直接窓口に持参するか、郵送や電子申請で届け出を提出することが可能です。副業の勤務先で働き始めてから10日以内に提出するようにしてください。
届け出の用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードすることが可能です。
本業ではない事業所で加入していた社会保険は、資格過失届の提出や健康保険被保険者証の返却を求められることがあります。
事前に年金事務所などに確認をとり、必要な手続きの準備を行ってください。
加入を怠るとペナルティを受ける可能性がある
加入義務が発生したにもかかわらず加入手続きを放置した場合、罰則を受ける可能性があることに注意が必要です。
健康保険法第208条では、事業主が正当な理由なく届け出をしなかった場合や虚偽の届け出をしたなど違反行為があれば、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となることが定められています。
近年では、マイナンバー制度によって、法人番号をもとに社会保険の加入状況を容易に確認できます。
加入手続きを怠ったことが発覚すると勤務先が健康保険法違反とみなされ、罰則の対象になってしまう恐れがあるのです。
ほかにも、健康保険や厚生年金に未加入であることが発覚すれば、最大で2カ月遡って加入義務が発生し、その分の社会保険料を一括納付しなければなりません。
納付にはまとまったお金が必要で、企業側や個人事業主に負担が生じることに注意が必要です。
副業時における社会保険料の計算方法

副業を始める場合の社会保険料は、各事業所の報酬月額を合算した標準報酬月額と保険料率をかけた保険料額に基づき、各事業所で按分することになります。
1カ月あたりの社会保険料は、以下の公式から計算することが可能です。
1カ月あたりの社会保険料=標準報酬月額(2ヵ所以上の事業所の報酬月額の合計)×保険料率
事業所と被保険者で折半した保険料額=1カ月あたりの社会保険料÷2
各事業所での被保険者の負担額=折半した保険料額×各事業所の報酬月額÷各事業所の報酬月額の合算
例えば、厚生年金保険料の報酬月額がA社で25万円、B社で10万円と想定した場合、月額は35万円です。
2024年3月分の東京都の保険料額表を参考にすると、標準月額報酬は34万円(21等級)に該当します。
また、厚生年金の保険料率は18.3%です。上記条件に基づいて計算すると、厚生年金の保険料は以下のようにシミュレーションできます。
1カ月の厚生年金保険料額:34万円×18.3%=6万2,220円
事業所と被保険者で折半した厚生年金保険料額:6万2,220円÷2=3万1,100円
A社の厚生年金保険料の被保険者負担額:3万1,100円×25万円÷35万円=2万2,214円
B社の厚生年金保険料の被保険者負担額:3万1,100円×10万円÷35万円=8,885円
上記の条件では、厚生年金保険料額は6万2,220円となります。実際には事業所と被保険者で折半し、さらに事業所ごとに報酬月額に応じて按分されます。
そのため、被保険者が各事業所で負担する保険料は、A社は2万2,214円、B社では8,885円になる計算です。
健康保険料は、厚生年金保険料をメインとする企業が加入する健康保険の保険料率に置き換えることで、同じように計算できます。
副業時における健康保険証は一枚のみ発行

複数の事業所で働いていても、発行される健康保険証は1枚のみです。複数の事業者のうち「主たる会社」を自分で決めなければなりません。
被保険者が選択した事業所では被保険者資格情報が登録されますが、健康保険証の利用登録をすることでマイナ保険証を利用できるようになります。
例えば、A社が協会けんぽの東京支部に加入していて、B社が協会けんぽの神奈川支部に加入していたとします。
A社を主たる会社と選べば、被保険者の加入先は協会けんぽの東京支部です。
すでに本業で協会けんぽに加入していて、引き続き同じ事業所の健康保険に加入する場合は被保険者整理番号が新しい番号になります。
副業で社会保険料が増えた時の会社の負担は?

副業によって社会保険料が増える場合、自分が働く事業主にはどのような影響が出るのか理解しておく必要があります。
ここでは、社会保険料が増えた際に会社にかかる負担について紹介します。
会社が負担する社会保険料は変わらない
副業によって社会保険料が増えたとしても、会社の負担は大きく変わりません。
副業先が法人であれば、事業所ごとの報酬月額に基づいて本業と副業で合算した社会保険料が算出されます。
さらに会社ごとの報酬月額で按分することにより支払金額が決まり、給料から天引きされる仕組みです。
会社側が負担する社会保険料は変わりませんが、被保険者本人が負担する保険料は増えます。
一方、副業が個人事業であれば社会保険に加入することはなく、会社や本人が負担する社会保険料に変化はありません。
副業をする社員の社会保険の手続き漏れに注意する
副業先の社会保険に加入が必要になった際、手続き漏れに注意が必要です。
2ヵ所以上の事業所で働くと、本業と副業の合算した収入をベースに社会保険料が決まるため、手続きを怠ると会社が負担する社会保険料が本来とは異なり多く支払ってしまう可能性があります。
副業先で社会保険の加入義務が発生しているにもかかわらず未加入の状態であれば、法律違反となり会社のイメージダウンにもつながります。
また、被保険者本人も未払いの社会保険料を最大2年間遡って支払う必要があり、不利益をかぶる可能性が高いです。
これらのリスクを避けるためにも、副業をする際は加入条件を理解し、加入義務が発生した際には適切な手続きを行うようにしてください。
まとめ・副業をする際は社会保険料に注意しよう
副業をすることで収入を増やせますが、労働条件によっては社会保険料が増額する恐れがあります。
社会保険料が増えると副収入の手取りが少なくなるため、損したと感じる人もいるかもしれません。
その場合、加入条件を満たさないように働いたり、個人事業や投資などで収入を得たりするなど、社会保険料が増えない条件で働くように工夫してみてください。
創業手帳では、副業されている方のための確定申告についてまとめた「副業確定申告ガイド」を無料でお配りしています。ぜひこちらもあわせてお読みください
(編集:創業手帳編集部)